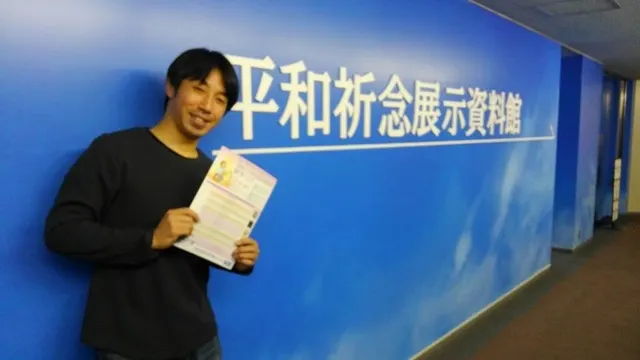20 「沈黙」の「声」──森下高志「映像と音で綴る朗読会 少年志願兵のシベリア体験」を観る
2017.3.20
森下高志の朗読を聞きながら感じたのは、やっぱり「声の力」だった。この「やっぱり」には、ぼくなりの思いがある。
現代詩の世界では、一時、朗読がはやった時期がある。ぼくが知っているだけでも、谷川俊太郎や、吉原幸子や、吉増剛造などが、盛んに自作朗読会をやっていたように思う。しかし、そのころ、そうした流れに反対する詩人たちもいた。確かな記憶ではないが、たぶん、荒川洋治なんかもそのひとりだったような気もする。彼らは、詩の表現は、「声」ではなくて、黙って読まれる「文字」にこそ本質がある、というような意見だったように思う。ぼくは、何となく、そうした意見にかえって新鮮さを感じ、詩人の自作朗読には否定的な気分になっていった。そして、そのことが、「自作朗読」だけではなく、「朗読」そのものへの興味を失わせていったようにも思うのだ。
しかし、一方では、たとえば宮沢賢治の『春と修羅』とか、『青森挽歌』とかは、何かにつけて、ぶつぶつと一人で「朗読」(まあ、音読レベルだが)したり、土方巽が朗読した吉岡実の『僧侶』『聖按摩語彙編』の奇跡的な朗読テープをデジタル化し、何十回と聞いたりもしてきた。
そうした中で、言葉とはいったい何だろうかという疑問が常に頭にあった。(もちろん今もあるわけだが。)
言葉の本質は「音」だ。断じて文字ではない。だから、詩の本質も「声に出された音=朗読」にあるはずだ、というのが、たぶん、「朗読派」の主張だったはずだ。しかし、「声」にしてしまった言葉からは、文字の持つ、特に漢字の持つ、豊かなイメージははぎ取られてしまう。しかも、その「声」によって、あるいは「朗読者」によって、詩の内容、あるいは思想までもが歪められ限定されてしまう。だから、「詩の声化=朗読」は否定されるべきだ、というのが「反朗読派」の言い分だったのではないかと思う。
今なら、そうまとめて、まあ、どっちの言い分もわかるよね、で終わってもいいようなものだが、やはり、この問題は、「朗読」が無条件に賞賛されるべきものではない、という点で、心にとめるべきことなのだ。
森下高志という一人の肉体を持った人間が、少年志願兵として出兵し、はからずも満州へ送られ、その結果シベリアに抑留されることになってしまった今井敬一という人間の手記を、「今井敬一として」朗読する。今回の朗読はそういう構造だったわけだが、それはすでに、普通の「朗読」の概念から逸脱して、「演劇」に足を踏み入れている、いや、すでに「演劇」そのものだと言ってもいいということを意味している。
本を手に持って読んでいるから「朗読」なのではない。森下高志が今井敬一を演じているという構造がはっきりしている限り、それは「演劇」である。たぶん。しかし、今は、「朗読」なのか、「演劇」なのか、などという議論に深入りすまい。とにかく、「ああやっぱり声だよね」「声の力だよなあ」というぼくの感慨は、言葉というものが、その本質、あるいは起源において、「生きた人間から、生きた人間への伝達」にあるということの再発見、いや再確認によるものであるということなのだ。
ぼくの父(大正8年生まれ)もまたシベリア抑留者である。父の「シベリア話」は、幼いころからさんざん聞かされてきたし、いまでも鮮明に記憶にある。そのことを書いていると、終わらないから、やめておくが、さんざん話したとはいっても、おそらく「話した」のは、父の経験のほんの一部に過ぎなかったことは容易に分かる。今回も、資料館に置かれた観覧者のノートをパラパラとみたら、「私の父もシベリア抑留者でしたが、シベリアのことはいっさい話しませんでした。」といった言葉が書き付けられていたのを見た。思い出したくもない、まして話すことなど思いも寄らないという経験を抱え、沈黙のうちに亡くなっていった多くの抑留者がいるのだ。
それでも中には今井敬一さんのように手記を残す方もいる。けれども、その手記も、そのまま本になっているだけなら、ほとんど顧みられることはないだろう。もちろん、多くの人が「読む」だろう。けれども、そこから今井敬一さんの「声」を聞き取ることは容易なことではない。書かれた文字から、「声」を聞き取るのには、想像を絶する困難がある。長い忍耐と、鋭敏な想像力と、豊かな知識が必要だ。だからこそ、「読む」ことを学ぶことは、人間としてもっとも大切な作業なのだ。(昨日見た「炎 アンサンディ」のセリフが頭の中に響いている。「読むこと、書くこと、数えること、話すことを学べ。」というセリフ。)
朗読は(もちろん優れた朗読は、という絶対的な条件付きだが)、その「読む」ことの困難を一気に乗り越えて、直接、ぼくらの生きた心に語りかける。そこには、今井敬一さんの心とは別の、森下高志という人間の心が介入はしているが、それでも、「優れた朗読」は、今井敬一さんの「声」を、今、ここの空間・時間の中に現出させるのだ。
自分の体験を語り続ける「語り部」と呼ばれる方々も多くいる。その方がよほどリアリティにあふれる話をするに違いないと誰もが思うだろう。けれども、果たしてそうだろうか。たとえばぼくの父が「語り部」たりえたろうか。父はもし舞台に立たされたら、何を語り得たろうか。それは父が特別シャイな人間であったからという問題ではなく、どんなに語り部として長く活動された人でも、実は、「語らないこと」を多く抱えているだろうと思うのだ。「語らないこと」「語れないこと」の周囲で、語り部は語る。そうするしかないのだ。それを聞く人は、その「語られなかったこと」をこそ聞き取らなければならない。それは果てしもなく困難なことだ。だからこそ「聞くこと」も学び取られなければならないのだ。
「朗読」は、あるいは「演劇」は、その「語られなかったこと」を、現出させる「技術」だ。「技巧」ではない。ちょっとした「テクニック」ではない。長い訓練と思考を経て、獲得される「技術」、優れた職人のみが有する「技術」なのだ。俳優森下高志の「技術」が十分なものであったかは、専門家ならぬぼくには判断できないけれども、ぼくには、「演じられた声」のなかに、今井敬一さんの「声」が、そして今井敬一さんの「沈黙」が、確かに聞こえた。それだけで、ぼくには十分だ。森下高志自身にとっても、今回の朗読は、これからの大きな糧となったはずだ。
30人ほど入れば満席の客席に、60名もの人が集まり超満員となった。そのうち、20数名はキンダースペースの団員及び関係者だった。このことはキンダースペースという劇団が、いかに暖かい人間関係によって結ばれているか、そして現代の問題にいかに真剣に取り組んでいるかを明白に語るものだったし、その関係者の一端に加われていることの幸せをしみじみと味わった。
たった1回の40分ほどの朗読に、「読む本」の選定と脚本化から、音楽、演出など、すべてキンダーのメンバーが関わり、時間をかけて丁寧に作りあげてきたことが、その後の「打ち上げ」でよく分かった。キンダースペースの皆さんに心からの敬意を表したい。そして、平成の世を直前にして亡くなった父になりかわって、心からのお礼も申し上げたい。