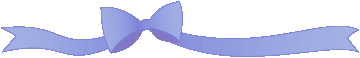「やれやれ、なぜ私がこのようなところまで来なくてはならぬのか。」
クラヴィスは小さくため息をもらした。
ここは主星のとある町の住宅街だった。穏やかな昼下がり、どの家も陽気に誘われて外出しているのか人通りもほとんどなかった。クラヴィスは若草色のシャツに細身の深緑のパンツという目立たぬ格好をしていたが、それでも、時折通りかかる女性の視線は彼の全身にまとわりついた。
彼の前の道は緩やかな上り坂になっていた。そこを若い夫婦と小さな女の子が上っていた。女の子を真ん中に、三人で手をつないで楽しそうに話をしている。女の子のタンポポのような金髪が一歩歩むごとに弾んでいた。
母親らしき人が何を話しかけたのか、女の子は自分の髪に両手を当てて、あわてた様子で後ろを振り向いた。その視線は自分の通ってきた道を遡り、クラヴィスへと行き着いた。クラヴィスとほんの少し視線があい、それは彼の足元へとそれた。クラヴィスもそれに引き寄せられるように自分の足元を見た。そこには赤いシルクのリボンが落ちていた。
クラヴィスの長い指がリボンを拾った。女の子がクラヴィスの元に駈けてくる。両親が笑いながら早く取っておいでと走る女の子を見守っている。女の子がクラヴィスのところで息を切らしながら手を出した。何のこともない光景だった。
坂の途中に立ち止まっていた男女の姿がゆがんだ。
クラヴィスの表情の変化に、女の子はリボンをもらおうと手を出したまま両親の方を向いた。彼女の目にはゆがみ、消えかけた両親の姿が映った。引きつった表情を認めるまもなく、その姿はかき消えた。
「ママ! パパ!」
女の子が叫びながら両親のいた場所に走り寄ろうとしたのをクラヴィスは引き留めた。どこか別の景色が目の前の街並みに重なっている。そこの空間はゆがみ、裂け、あきらかに拡張していた。
「近寄ってはダメだ!」
クラヴィスは片腕でその子を押さえながら、もう片方の掌をその空間に向けた。何かがその掌に集まり、放たれた。
二重になった風景が次第に収縮されていき、やがて、なくなった。そこにいたはずの男女の姿はない。
女の子はクラヴィスの腕を振りきって両親のいた場所へと駆け寄った。
「ママ・・パパ・・」
呼び声が泣き声へと変わっていく。大きな目からぽろぽろと涙がこぼれた。その目が歩み寄ったクラヴィスを見上げた。涙にも曇らない二つのエメラルドがクラヴィスにすがった。
「泣くな・・・」
クラヴィスは子供の前にかがみ込み、手に握ったままの赤いリボンを女の子に見せた。
「結んでやろう。名は何という。」
「・・アンジェリーク・・」
ヒックヒックと泣きじゃくりながらも、女の子は素直にリボンを結ばせた。くるくるとカールした金髪に赤いリボンがよく映えた。
「アンジェリークか・・・よい名だ。私はクラヴィス・・・」
クラヴィスはアンジェリークを軽々と抱き上げた。彼女の涙はクラヴィスのシャツの胸元に染み込んでいった。
さて、どうしたものか・・・
困惑を面に出さないように努めながら、クラヴィスはアンジェリークに安心するようにと微笑みを向けた。
主星の異常が伝えられたのは少し前のことだった。少なからぬ場所で次元の裂け目ができているとのことだった。女王陛下の力の衰えがこんなところにまで現れてきていた。裂け目が広がらぬうちに急いでその一つ一つを塞がないと大変なことになる。守護聖が各地に派遣されていった。
「私も行くのか?」
「当たり前だ。聖地の危機だぞ。私を除けば一番サクリアの強いおまえが行かなくてどうする。事情が許すなら、私が行きたいところだ。
それとも、私の代わりにここにいて守護聖の統括をやってくれるか、クラヴィス。」
「いや・・・それこそお断りだ。」
「ならば職務を全うすることだな。」
目を怒らせて言い放ったジュリアスに、クラヴィスは聞こえぬようにため息をついた。
あちこち出かけるのは性に合わぬ。
だが、その時はこんなことになるとは想像さえしなかった。まさか、女の子を拾うことになるとは。
異常事態は次第に収束に向かっていた。だが、消えたアンジェリークの両親の消息はつかめなかった。クラヴィスは子どものために仮の居を構えた。
「王立研究院は研究員を総動員して二人を探している。もう少し待って欲しい。」
「他には巻き込まれたものはいなかったのか?」
「いない。あの子の両親だけだ。たまたま次元の裂け目が発生したその場所にいたのが不運だった。前代未聞のこととて、果たして二人がどうなっているか・・・」
いつもは歯切れのよいジュリアスが言いよどんだその先はクラヴィスにも見当がついた。運がよければ場所なり時間なりが移るだけで生きているだろう。そこが陛下の力が及ぶ場所であれば、発見できる。だが、万一次元の狭間に落ち込んだとすると・・・。
クラヴィスはあの裂け目を閉じるとき、ほんの一瞬躊躇した。二人を追って裂け目に飛び込もうかという考えが脳裏をよぎったのだ。だが、深まる亀裂と手の中の子どもがその考えを捨てさせた。こうして二人の行方がわからぬまま時が過ぎ、クラヴィスは後悔の念にさいなまれていた。
気を取り直したようにジュリアスは次の言葉を続けた。
「あの子はどうしている?」
「アンジェリークか? 落ち着いた。今リュミエールが相手をしている。」
「あの子が今一人でいるのは我々の責任でもある。できるだけあの子の為によきようにしてやって欲しい。」
「わかっている。・・・ふっ、まかせろ。」
「おまえからそんな言葉を聞くとはな。」
苦笑とともにジュリアスの通信は切れた。
クラヴィスは部屋を出ようと扉を開けた。廊下にはアンジェリークが立っており、その後ろに困った顔をしたリュミエールが控えていた。
「クラヴィス様、申し訳ありません。あちらの部屋で待っているようにと言ったのですが、どうしてもここで待つと・・・。」
「アンジェリーク・・・どうした?」
彼女は何も言わずにクラヴィスの足にしがみついた。そして、そのままリュミエールをにらみつけた。翠の瞳が涙でにじんでいる。
「どうやら私は嫌われてしまったようですね。」
困ったように微笑んだリュミエールをクラヴィスは当惑げに眺めた。
「おまえの方が子供相手には向いていると思ったのだが・・・すまぬ。」
「いえ、そんな。鳥も動物も、クラヴィス様に集まってきます。皆クラヴィス様のお心の温かさを知っているのでしょう。アンジェリークも本能的にそれを感じているのかもしれません。賢い、かわいい子です。」
それでも、リュミエールはアンジェリークを抱き上げたクラヴィスを不思議そうに眺めた。
この話を聖地でしても、誰も信じてくれないかもしれませんね。この子はなんと信じ切った目でクラヴィス様を眺めているのでしょう。そして、クラヴィス様も、なんと穏やかな目で・・・。
リュミエールは一瞬でもうらやましいと思った自分の気持ちを封じ込めた。
「それでは、私はこれで・・・」
「・・・外まで送ろう・・・」
守護聖はまだ主星のあちこちで奮闘していた。一人でも多くの人手がまだ必要だった。アンジェリークがクラヴィスから離れようとしないので、リュミエールがそちらに戻ることになったのだ。
クラヴィスはアンジェリークを抱いたままリュミエールを送るためにテラスから外へ出た。テラスの外には紫陽花が大輪の花を咲かせていた。
薄緑から藤色に染まったその花を背中に、クラヴィスはリュミエールへと別れを告げた。クラヴィスに抱えられたアンジェリークはいつのまにかうたた寝をしていた。その手はクラヴィスの黒髪を握り、離れないという意思表示を暗にしていた。
想像できない風景でありながら、なぜかお似合いな・・・
リュミエールは、紫陽花を背にしアンジェリークを抱いたクラヴィスの様子を胸に刻み込んでいた。聖地で何年か先、リュミエールはその風景を一枚の絵にした。
夕飯をすまし、入浴を終え(手伝いの女性がアンジェリークを入浴させた)、クラヴィスはアンジェリークの寝室と定めた部屋のベッドに彼女を寝かしつけ、居間でカードをくくっていた。彼は何かの気配を感じて振り向いた。扉の所に小さな影がぼんやりと立っていた。
「どうした? 眠れぬのか?」
返事をせぬまま、アンジェリークはクラヴィスへと近づき、その顔をのぞき込みながら長い黒髪の一房をひっぱった。
ふっ・・・さびしいのか・・・無理もない。こんな知らぬ家で両親もいぬ。
クラヴィスは髪を握らせたままアンジェリークを抱き上げると、彼女の寝室へと向かった。
アンジェリークをベッドに下ろし握っていた髪をはなさせると、クラヴィスは椅子をベッドの脇まで持ってきて、彼女の枕元に座った。アンジェリークはまたクラヴィスの髪を握り、枕の上でにっこりと笑った。
「眠るがよい・・・私はここにいる・・・」
明かりを落とした中、クラヴィスの手がアンジェリークの頭に触れ、そっとなでた。その単調な刺激にアンジェリークはすぐに寝息をたて始めた。彼女が眠り込んでもまだ、クラヴィスは彼女を見守っていた。その手にはまだクラヴィスの髪が握られていた。
その翌日、アンジェリークは庭で花を眺めたり、虫を追ったり、それに飽きると絵本を読んだりして過ごした。クラヴィスはいつもその側についていた。クラヴィスの姿が見えなくなるとすぐにアンジェリークの瞳に涙がにじむので、そうせざるをえないのだった。クラヴィスにとっても、アンジェリークの両親の行方という不安を抱えながらも、不思議と穏やかな時間だった。子どもの何にでも興味を示し、刻一刻と変化する表情は見ているだけでおもしろかった。
その夜もアンジェリークはクラヴィスの髪を握ったまま眠りについた。
夜中、聖地からクラヴィスの元に通信が入った。
「あの子の両親が先ほど見つかった。主星の、消えた地点とはかなり離れた場所だったが、次元の裂け目が観測されてすぐにオスカーが向かったため、現れてすぐに保護できた。」
安心したクラヴィスだったが、ジュリアスの言葉の何かが不安を与えた。
「・・・それで、何が問題なのだ?」
ジュリアスはほんの一瞬言葉を選んだ。
「彼らは次元の狭間でかなりの恐怖感を味わったようだ。精神が尋常ではなくなってる。今、オリヴィエに様子を調べさせている。」
「記憶を・・・消せばよい・・・できるだけ深く。」
クラヴィスの瞳が通信機からの明かりを受けてキラリと光った。
「それしかなかろう。できれば使いたくない手段だが仕方あるまい。オリヴィエがうまくやってくれればよいが。」
「ふっ・・・彼は大丈夫だ。
明日の朝までにこちらに両親を戻せるか?」
「たぶんできるだろう。だが、それがどうした?」
「アンジェリークの記憶も封じなくてはならぬ。明日の朝目覚めとともに両親と再会するのが一番無理がないだろう。」
「わかった。オリヴィエに伝えよう。そちらはよろしく頼む。」
通信機からジュリアスのしかめっ面が消えたあとも、クラヴィスは画面に視線を向けたままだった。
アンジェリークから私の記憶を消すのか。さみしくないと言えば嘘になるな。
彼女の無邪気な視線をクラヴィスは思い起こした。そして、そんな自分の感傷を苦笑とともに振り払った。
アンジェリークは自分の部屋で目を覚ました。いつものように寝間着のままベッドの下に脱いであるうさぎのスリッパを履いて台所へと向かった。そこではママがオムレツを焼き、パパがコーヒーを入れていた。いつもの通りの朝だった。
アンジェリークはミルクを飲みながら、その夜に見た夢のことを思い出していた。
「ママ、わたしへんなゆめを見たの。」
「ふーん、どんな夢?」
「わすれちゃった。でも、とってもかなしくって、とってもきもちがよかった。」
手の中に何かがあるような気がして、アンジェリークは自分の掌をながめた。だが、そこには何もなかった。パパがトーストを取ってくれて、彼女は夢を見たこともすっかり忘れてしまった。
「クラヴィス様、お疲れはとれましたか?」
今回の騒動もやっと落ち着き、クラヴィスとリュミエールは闇の邸でくつろいでいた。
「・・・別に・・・私は子どもと遊んでいただけだ・・・」
大変だったでしょうに・・とリュミエールは心の中でつぶやいた。
「アンジェリークはどうしているでしょうね。」
リュミエールは懐かしそうに言った。そして、ためらいがちに続けた。
「あの子の記憶はどうなったのですが?」
クラヴィスはリュミエールにちらりと視線を投げて、それから立ち上がって窓辺へ行き、外を眺めた。
「消した。すっかり消すつもりだった。だが・・・」
「だが・・・?」
リュミエールは不思議な顔をしてクラヴィスを見上げた。
「すっかりは消せなかった。あの幼子の中に私の干渉を跳ね返すところがあったのだ。・・・なぜなのかはわからぬ。もしかしたら・・・いや、まさか・・・」
リュミエールはさらに訊ねようとして思いとどまった。クラヴィスがこのようなときは、たとえリュミエールが聞いても何も教えてくれないのだ。
「いずれにしろ、記憶が残っても夢だと思うだろう。あの年齢だ。すぐ忘れ去る。」
「そうですね。きっと幸せな少女に成長しますよ。」
クラヴィスは黙って外を見ていた。
自分の腕の中で寝ていたアンジェリークの温かさが、まだ残っている気がする。髪を引っ張る腕の力を感じるような気がする。
そんなクラヴィスの心情を察してか、リュミエールは何も言わずにそっとハーブを奏で始めた。
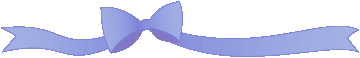
女王試験が始まった。飛行都市に赴いたクラヴィスとリュミエールは、そこであの女の子アンジェリークに再会した。タンポポ頭に赤いリボンそのまま、幼子は少女に変身していた。その翠の瞳は恥ずかしそうに、だがまっすぐにクラヴィスへと向かった。
女王試験はこれから始まる。
〜Fin
あとがきへ
青籃さん画「腕」へ
佳月作「華雪洞」へ
彩雲の本棚へ
「腕」・一枚の絵から―――目次へ