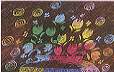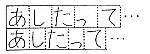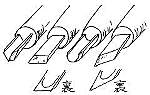> さ < |
さ し す せ そ |
| 細密描写 |
細い線を用いて対象物の細部に至るまで表現した絵画のことを指します。鉛筆やペン,細筆を用いますが,エッチングやドライポイントのような版画では針やニードルを用いて描きます。淡い色を付けて仕上げる淡彩画はまずこの技法で描いてから,透明描法で彩色を行います。 |
| 錯視 |
本来の事実とは異なり,ごまかしによってそうであると錯覚させる視覚の不思議を指します。長さが違ったり,平行であるはずなのに傾いて見えたりする手法を利用して描かれた図です。
これを利用した絵画では,モーリス・エッシャーが有名です。
|
| さっ筆 |
パステルやコンテで描くときに使われます。微妙なグラデーションや,淡い感じやぼかしの効果を表すときにこれを用います。材質は紙でできており,こすることで表現します。
|
| 三原色 |
色の三原色と光の三原色があります。※原色の項を参照のこと。 |
| |
|
> し < |
さ し す せ そ |
| 信楽焼 |
滋賀県の信楽地方(町)で算出する粘土を使ってつくられる陶器のことです。日本六古窯のひとつで,平安時代から今日に至るまで焼かれ続けています。
よく狸の置き物が取り上げられるので,知っている人も多いのではないでしょうか。 |
| じかづけ |
まず作品の中心となる心棒をつくり,その周囲に直接石膏やセメントなどをつけて製作していく彫刻の手法です。
|
| 磁器 |
石の粉(石英;ガラス質)を練って焼成する。陶器よりも高い温度で焼きます。 |
| 色相・色相環 |
色の3要素の一つの呼び名です。色の3原色によって作り出されるだいだいやむらさきといった,色それぞれがもっている雰囲気のことです。手相や人相といえばさまざまな形態があるように,色にもさまざまな特徴があることを指しています。
色相環とは,三原色を使ってつくられています。教科書などに登場する12色相環とは色相を12個使ってつくられています。

※ 絵の具を3つだけ使い(赤・黄・青)実際に作ってみると,早く理解できます。
|
| シルクスクリーン |
孔版の技法のひとつ。スクリーンに絹を張り,そこに感光用の薬品を塗る。それに原画を描いたネガを合わせて焼きつける。絵の部分の感光剤はとれて孔があくため,絹の目が表れる。スキージでインクを刷り込み印刷する。
制作方法としては感光法やブロッキング法,カッティング法などがあります。 |
| 写実主義 |
19世紀の中期に現れた絵画の手法。ありのままに描くことを目的として,誇張も理想化もせずに現実を忠実に表現しようとした。クールベが有名。 |
| シャモット |
粘土を素焼きし,それを細かく砕いたものです。理科の実験で使われる沸騰石というのは,こうやって作られます。 |
| 主調色 |
画面全体の中で広い範囲を占める色はその絵の中心的な色彩となる。 |
| シュパンヌンク |
形が持っている勢いのこと。三角形の鋭角部分はその頂点の方向に強く引っ張られるように感じる。
|
| シュールレアリズム |
日本語では超現実主義と表現されます。人間の心の中に潜む無意識や夢,欲望などに注目し,日常とかけ離れた不合理で幻想的な世界の表現を追求した芸術活動のことです。
大きな影響を与えたのは心理学者のフロイトでした。夢の世界は,普段隠れて見えない潜在意識が見せるものだと考えます。作家たちはこの潜在意識の世界を,様々な表現方法を用いて表現しようとしました。
主な作家にダリやエルンスト,マグリッド,ミロなど。
|
| 純色 |
色の3原色によってつくられる色相。色相環はこれによってつくられる。 |
| 書院造 |
室町時代に発達した建築様式。客間に床の間をつけたり,襖や障子でしきりを入れたりした。もともとは禅宗において書を読むための場所を建築に取り入れたといわれる。 |
| 焼成 |
粘土でつくられた作品を乾燥させ,焼いて硬化させること。これによって耐久性が増し,器などとして利用できる。
窯を利用し,素焼きの場合は800度前後,釉薬をかけた陶器であれば1250度前後,磁器の場合は1300度前後まで高められる。 |
| 障壁画 |
|
| 新印象派(新印象主義) |
感覚的な色彩表現をさらに発展させて,色彩の原理を科学的に追求します。そこで点描という技法を生み出します。色彩は混ぜると済度が低下してしまいます。それを防ぐために小さな点状に色彩を並べ,鑑賞者の視覚上で混色させようと試みます。この場合は加算混合になり,混色しても鮮やかさが落ちません。代表的な作家にスーラ,シニャックがいます。
|
| 心象表現 |
表現活動を大きく二つに分けると絵画や彫塑のように目的となるものを表現するのではなく,純粋に自己の表したいものを造形・表現する分野と,ある目的を持っていて,それに適応させるデザインや工芸などの分野とに分けられます。前者を心象表現といい,後者を適応表現といいます。 |
| 寝殿造 |
平安時代の住宅様式のひとつ。南に神殿を配置し,必要に応じて左右に対の家を建てて,渡り廊下でつながっている。 |
| 心棒 |
彫塑の塑像制作の際に作品の中心となる,芯の部分のこと。木材や針金でつくられる。心棒の周りはシュロ縄で縛り,粘土がつきやすくする。 |
| シンメトリー |
左右や上下など,ある部分を基準として対称となる形態のこと。
<作例> |
| |
|
> す < |
さ し す せ そ |
| 水煙 |
奈良時代の寺院にみられる。防火の象徴としてつくられる。屋根の上にあるものとしては鯱(しゃちほこ)が有名ですが,あれも屋根を水面(波)に見立てて,防火の願いを込めたものです。 |
| 水彩絵の具 |
顔料35%,アラビアゴム5%,グリセリン20%,水20%を練り合わせて作られています。この中には多少の防腐剤が混ぜられており,カビがはえるのを防いでいます。
水彩絵の具には透明水彩絵の具と不透明水彩絵の具があります。
透明水彩絵の具というのは,よく小学校で使われる風景画を描いたり,友達を書いたりするときに使った絵の具で,顔料の粒子が非常に細かく作られているために,水で薄く溶いてもきれいなグラデーションを表現できます。にじみやぼかしの効果も生きてきます。
不透明水彩絵の具というのはポスターカラーなどです。顔料の粒子が大きく,広い範囲を均一な色で仕上げるのに向いています。水は絵の具の粘度(粘りけ)が落ちないように,ほとんど加えずに使います。よく耳たぶの柔らかさだとか,アイスクリームが溶けたときのような,と表現されます。
その他水溶性の絵の具と言えばアクリル絵の具や日本画用の絵の具があります。 |
| 水墨画 |
鎌倉時代に禅宗と共に,中国から日本に渡る。宋,元の時代につくられた水墨画は室町時代の絵画に大きな影響を与える。 |
| 須恵器(すえき) |
飛鳥時代から鎌倉時代にかけてつくられていた焼き物の種類。ろくろで形を整えて素焼きをする。 |
| スキージー |
版画の道具で平たくて幅の広いへら。インクを版の上で押し出し,延ばすために使用する。ゴムやポリウレタン樹脂のような弾力性のある素材によってつくられている。 |
| 数寄屋(すきや)造 |
江戸時代の住宅建築様式のひとつ。桂離宮や修学院離宮が有名。 |
| スクラッチ |
モダンテクニックの一つ。
クレヨンなどで下地に色を付けて最後に上から黒のクレヨンで重ね塗りをする。その後くぎの頭などでひっかいて下地の色を使って絵を描く表現方法。厚紙の表面をひっかいたりする技法もある。
<作例>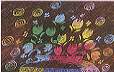 |
| スタンピング |
モダンテクニックの一つ。
版(印)になるものを用意し,それを画面に押してつくる表現技法。
<作例> |
| ステンシル |
薄い金属板や紙を思い通りの形に切り抜き,その部分にインクなどを刷り込む版画の技法。染色などでも使われる。 |
| ステンドグラス |
色ガラスを鉛の棒によって固定し,絵模様を作り出したもの。ゴシック建築の窓に盛んに用いられた。
(教会は天に近づくためにどんどん巨大化していった。建物が大きくなればなるほど室内は暗くなる。そこで室内では火を焚いていたが,より神に近い天の光を美しく感じさせるために,そこに差し込む「明かり取り」という以外の意味を込めて作り出された芸術ともいえる) |
| 砂袋 |
金属工芸に用いられる,板金打ち出しの時に下に敷くもの。 |
| スパッタリング |
モダンテクニックの一つ。
やや水を多めにして溶いた絵の具を金網と歯ブラシを使って霧状にして紙に描く技法。型紙を用いた表現やぼかしの効果が利用できる。機械で製作する場合はエアーブラシという道具がある。
<作例> |
| スペーシング |
レタリングを行う際に,「し」や「く」の様な文字幅の狭いものや,「い」などの文字幅の広いものの間隔をそれぞれの文字幅にあわせて文字の隙間をとって配置することで,文字の種類によって間延びした感じを防ぐ作業のことです。
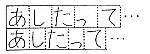
|
| スペースデザイン |
環境デザインとも言います。室内のインテリアデザインに始まり,建築物,公園などの広い空間をデザインする場合にも使われることばです。 |
| 素焼き |
粘土で形を形成した後,完全に乾燥させてから700度前後で焼き上げること。釉薬をかける場合は必ずこれを行った後に本焼きをする。テラコッタは素焼きで制作する。 |
| |
|
> せ < |
さ し す せ そ |
| 青磁器 |
緑青色の施釉を施した陶器,または磁器。 |
| 清色 |
純色に白,または黒を混ぜたときの名称。白は明清色,黒は暗清色と呼ぶ。灰色を混ぜたときは濁色という。 |
| 石版画 |
平版の一種で,リトグラフとも言われる。
無結晶石灰石の表面を平坦によく磨き,その上に石版用のクレヨンやインクで絵を描く。化学作用によって絵を写し取る版画。現在は金属板,すりガラスなどを使うことがある。水と油が反発し合う性質を利用している。 |
| 瀬戸焼 |
日本六古窯のひとつで,愛知県瀬戸市に古くから産する磁土を用いてつくられる陶磁器。「せともの」といわれるように,一般に広く伝わっている。 |
| 施釉(せゆ) |
焼き物をつくる際に,まず素焼きをする。その作品の表面に釉薬をかける作業のこと。この後乾燥させ,それぞれの釉薬に適した温度で焼成する。 |
| 線遠近法 |
※ 透視図法の項を参照のこと。 |
| 千手観音 |
|
| |
|
> そ < |
さ し す せ そ |
| 象嵌(ぞうがん) |
工芸の装飾技法の一つ。
金属や磁器・木材などの工芸品において,同質の材料または他の材料を使って表面に模様や形を嵌入する手法。 |
| 塑像(そぞう) |
彫ってつくる彫像に対して,粘土や石膏など,可塑性のある素材を使ってつくる像のこと。 |
| 染め付け |
磁器などに絵つけをする際,呉須(ごす)<塩化コバルト>を使って青い模様や絵を書き入れることを指す。 |
| |
|
> た < |
た ち つ て と |
| 濁色(だくしょく) |
純色に灰色を混ぜてつくった色の名称。灰色の明度差(明るい灰色から暗い灰色まで様々な段階のもの)や混ぜる割合(10%や70%といった分量)によって彩度が変わる。 |
| ダダイズム |
ダダというのは赤ちゃんが「あーあー(ダーダー)」と発する言葉からきています。この運動は,過去の芸術を否定して新しい価値の創出を試みました。騒々しい音楽やナンセンスな詩などもつくられました。アメリカではデュシャンが日常使われているものに題名をつけて別の意味を持たせます。「レディ・メイド」と呼んで展示しますが,それは先入観を否定し,再発見を促すものでした。
第一次世界大戦により,文明に不信感を持ったものたちが行った破壊的芸術活動。既存のものへの反発精神が中心。特に決まり事を定めず,芸術についての考え方を全て白紙にした状態で,偶然や瞬間的なひらめきに芸術の可能性を探る。このころにモダンテクニックの技法が開発される。
|
| たたきぼかし |
絵の具をたんぽや穂先を切った筆などにつけて,たたきつけながら霧を吹き付けたような効果を出す技法。 |
| たたら板 |
粘土を板状にしたものを「たたら」と呼びます。この板状の粘土を作るために使われる板がたたら板と呼ばれます。まず,粘土の左右に同じ厚みだけ板を積み上げます。その板に針金を当てて同じ厚さの粘土板を制作します。板づくりの作品のために使われます。 |
| 脱乾漆(だっかんしつ) |
※ 乾漆の項を参照のこと。 |
| タッチ |
絵の具を使用する際,筆をどのように活用するかで絵の雰囲気が変わる。荒々しく塗りつけたり,繊細に動かして細密描写をしたりする際に表れる筆触のこと。個性や心情の表現によって様々な方法が採られる。ゴッホはタッチが強いので有名。 |
| タピストリー |
手織の壁掛けで室内装飾に用いられる。様々な技法を用いて織られる。シンプルなものから豪華で複雑な図柄までさまざま。 |
| タブロー |
フランス語。エチュード(習作)やデッサンに対して作品として完成された絵画を指す。 |
| 濃絵(だみえ) |
桃山時代になると,室町時代から続いていた水墨画に対して,岩絵の具を使い豪華な絵が描かれた。
特に障壁画でその才能を発揮した画家が数多く誕生した。当時,水墨画に対してこう呼ばれた。 |
| 淡彩画 |
鉛筆や墨などで線がきした作品に,水彩絵の具を用いて薄くあっさりと塗ったもの。重色やにじみの効果を利用する。 |
| |
|
> ち < |
た ち つ て と |
| 地山 |
人物彫刻など,たっている足下の地面に当たる部分のこと。この部分も作品の一部であり,その大きさや形,厚みなどは作品全体のイメージを考えてつくられている。 |
| 抽象主義 |
20世紀に生まれた,写実的ではない芸術を表します。実物をありのままに表現せずに,線や色,形の組み合わせによって表現しています。 |
| 超現実主義 |
※ シュールレアリズムの項を参照のこと。 |
| 彫刻刀 |
木彫作品を制作するときに使う刃物です。印刀(切り出し),三角刀,平刀,丸刀などがあり,印刀には右利き用と左利き用とがあります。持ち方の基本を学んで作業をしないと,指を突くなどのけがをしますので注意が必要です。
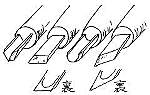
※ 左から三角刀,平刀,丸刀,切り出し,です。 |
| 頂相(ちんそう) |
禅僧の肖像画のことです。鎌倉時代以降に数多く描かれました。 |
| 沈金 |
漆工芸の技法の一つです。漆面に針で模様を彫り,そこに金箔を置いて綿で押し込みます。そうすると金色の線ができあがります。室町時代以来行われてきた技法で,石川県の輪島塗が有名です。 |
| |
|
> つ < |
た ち つ て と |
| つくりえ |
平安時代に描かれた,岩絵の具を用いた濃彩画。源氏物語絵巻など。 |
| つけたて |
※ 没骨描(もっこつびょう)の項を参照のこと。 |
| |
|
> て < |
た ち つ て と |
| デカルコマニー |
モダンテクニックの一つ。
紙を2つに折り,その間に絵の具をつけて押しつけたりこすったりした後で開くと,絵の具が広がったり混ざり合って意図しない形や色調が生まれる。これをもとに発想したり(心理学テストにも用いられます),作品を製作したりします。
<作例> |
| テクスチュア |
素材の表面のこと。ざらざら,つるつるといった地肌の質感を指す。 |
| 鉄線描法 |
奈良時代前期に描かれた技法。ピアノ線のように強い筆感に特徴がある。 |
| デッサン |
じっくりと対象を見つめ,濃淡や質感を正確に面で表す。 |
| ディテール |
全体に対して細部のことを指す。 |
| 適応表現 |
※ 心象表現の項を参照のこと。 |
| 手びねり |
陶芸の製作方法の一つ。
粘土をひも状にしてつくったり,粘土の塊を指で押し広げながらつくったりする。ろくろや型を使ってつくる方法に対して自然な味わいのある作品に仕上がる。 |
| デフォルメ |
デフォルメーション。実際の形から必要な要素を抽出し,強調して表現する方法。 |
| ディペーズマン |
あり得ないものが,あり得ない場所に存在するという不思議な空間を意識して製作し,奇異な雰囲気を作り出すこと。シュールレアリズムの技法で,転置とも呼ばれる。 |
| テラコッタ |
焼き物の一種で,中をくりぬき空洞にしてある,素焼きのものを指す。古代ギリシャの時代からつくられる。本来は焼いた土という意味。 |
| 手ろくろ |
手びねりで陶芸作品を作るときの道具です。この台を回しながら形を整えます。また,絵付けや施釉,高台を削るときにも使います。 |
| 点描画 |
線や面を使わず,筆に付けた色を点状に並べて描く技法。
これは混色をさけて,彩度を低下させずに見る人の目の中で混ざり合って見えるように工夫した。
近くで見ると色が分解されて表現されているのがわかる作品もある。スーラやシニャックなどが有名。 |
| テンペラ |
油絵の具の登場まで,ヨーロッパの絵画材料だった。顔料を黄身やいちぢくの汁などで溶いて描く。白身は金箔などを張りつける接着剤として用いた。乾燥が早くかさかさした表面になるため,樹脂やワニスを塗って表面を保護した。 |
| |
|
> と < |
た ち つ て と |
| 陶器 |
粘土をよく練って形成し,焼成して作り出します。縄文時代では野焼きと言って,平地で薪などを積み上げて焼きましたが,時代が進むと窯をつくって効率よく焼くことを考え出します。素焼きと本焼きがあり,本焼きでは1250度ぐらいまで窯の温度を上げます。 |
| どうさ紙 |
|
| 透視図法 |
線遠近法で奥行きや立体感を表す場合に使われる図法です。消失点と目の高さ(水平線)が作図の基本になります。だんだんと遠くなるに従って物体を小さく描くことができるために見た感じの遠近感を表現することができます。1点透視図法,2点透視図法,3点透視図法がありますが,中学生では2点透視図法までを練習することが多いようです。 |
| 動勢 |
モダンテクニックの一つ。
ムーブメントともいう。作品全体における動きを指す。 |
| ドリス様式 |
古代ギリシャの時代で,ドーリス人の勢力が強かった頃に作られた建築様式です。ギリシャ建築の中で最も簡素で,力強い表現が特徴です。 |
| トーン |
調子,という意味です。画面全体の色の感じを指したり,明暗を表現する際に使われます。 |
| 土偶 |
先史時代に作られた土の人形です。呪術的な意味を持っているといわれています。 |
| 土佐派 |
|
| 凸版 |
版画の一種。
木版画のように彫刻刀で彫り,凸部にインクを付けてばれんで刷りとる方法や,厚紙を切り,台詞に張り付けてつくる方法など様々な技法がある。 |
| どべ |
粘土に水を加え,柔らかく泥状にしたものをいいます。粘土と粘土を接着するときに使います。この「どべ」は,接着する粘土と同じ材質のもので作ります。 |
| ドライポイント |
凹版画の技法のひとつ。
塩ビ板などにニードルを使ってひっかき傷をつくり,凹部にインクをつけてエッチングプレス機で刷るとる。エッチングと違い薬品を使わないので手軽に製作できる。 |
| ドリッピング |
モダンテクニックのひとつ。
水分の多い絵の具やインクを紙の上にたらし,口やストローで強く吹いたり紙を傾けたりしてできる偶然できる形を利用する技法。
<作例> |
| 鳥の子 |
きめが細かく地肌の美しい紙。よく学校で掲示物を作るときに使う大きな紙がこれですね。 |
| ドルメン |
|
| トレース(転写) |
原図版の上に薄い紙をのせて写し取ることです。トレーシングペーパーという半透明の紙に写し取ることが多いですが,ライトボックスの上に原図版を置き,下から光を当ててケント紙などの厚手の紙に写し取ることもできます。 |
| |
|