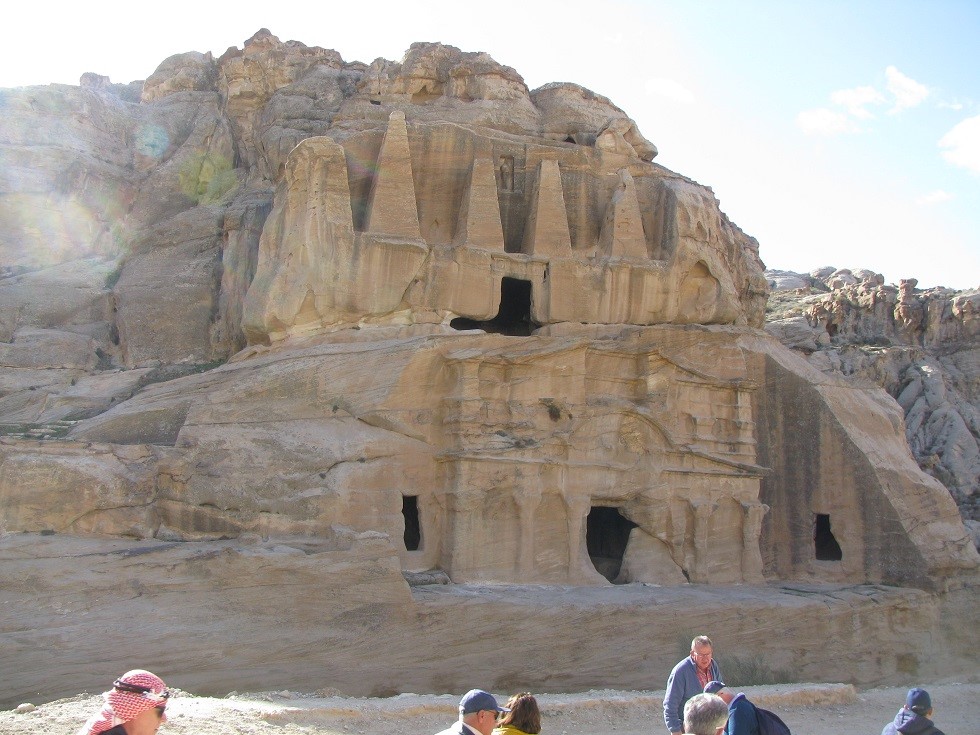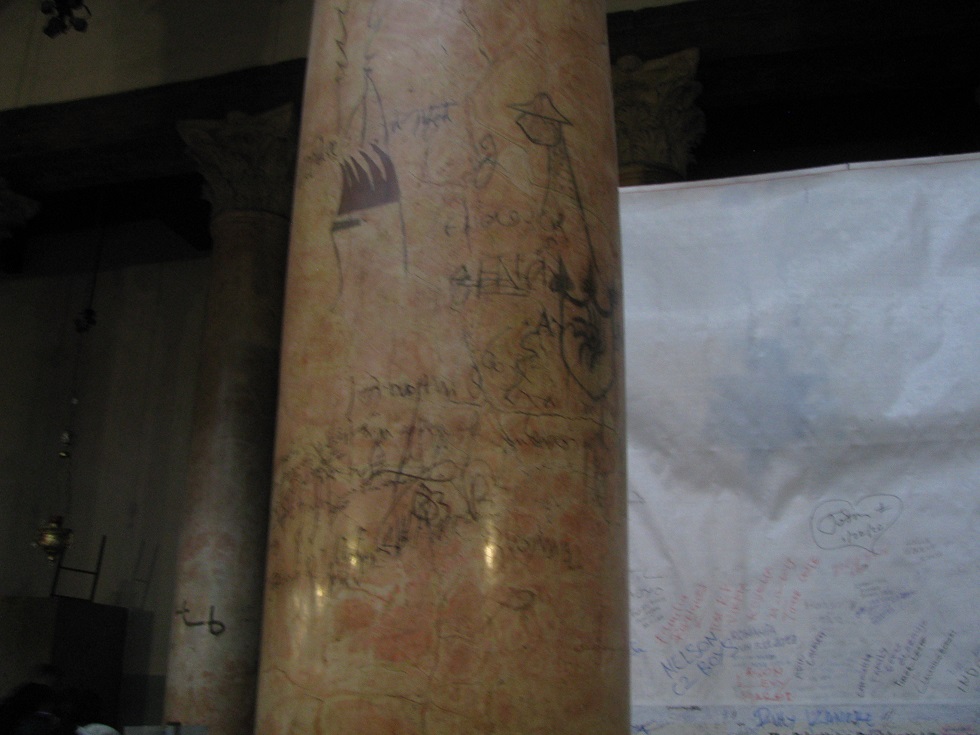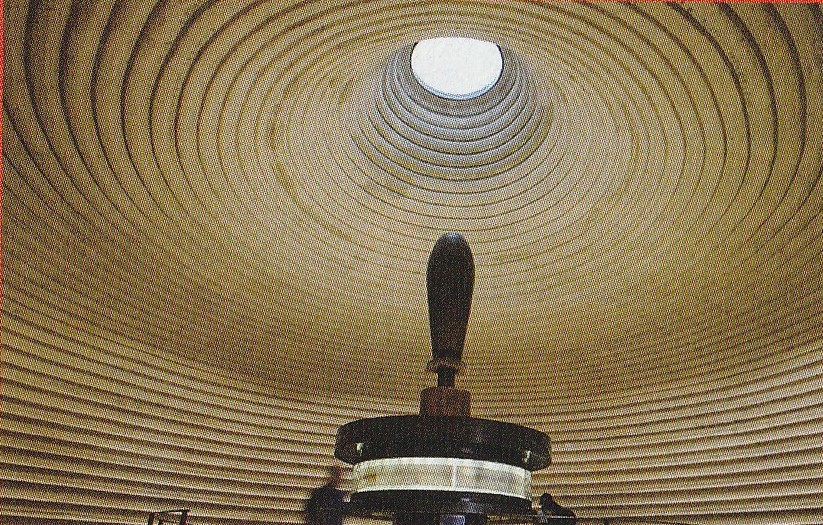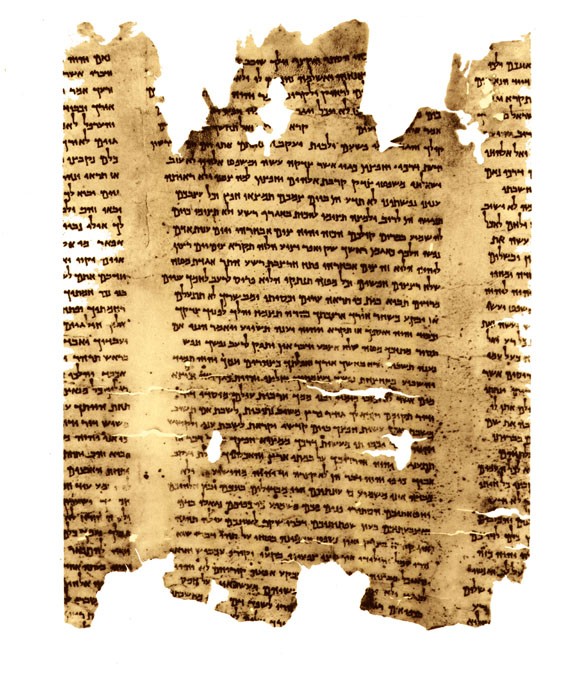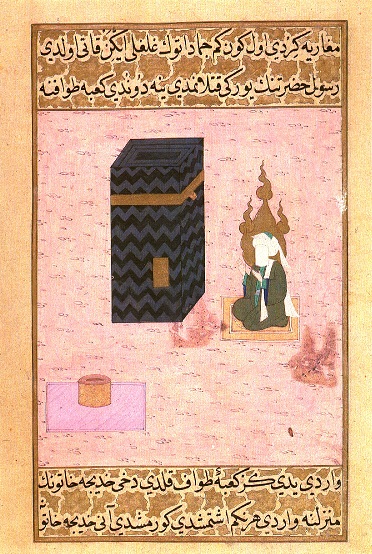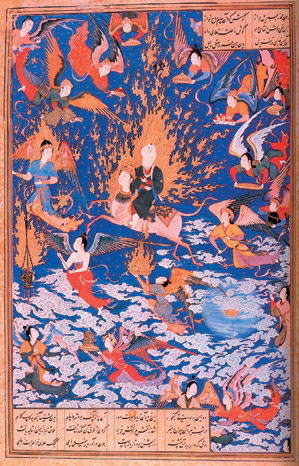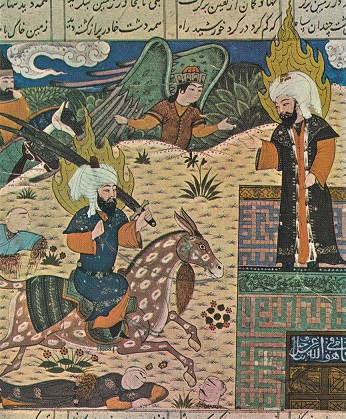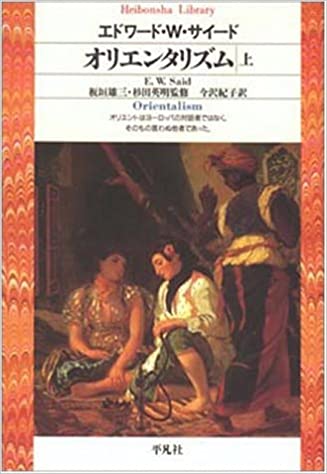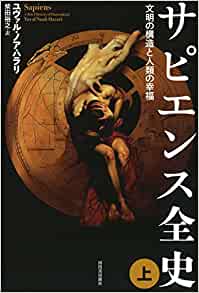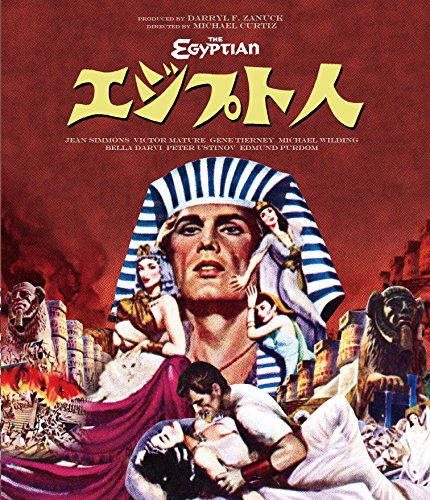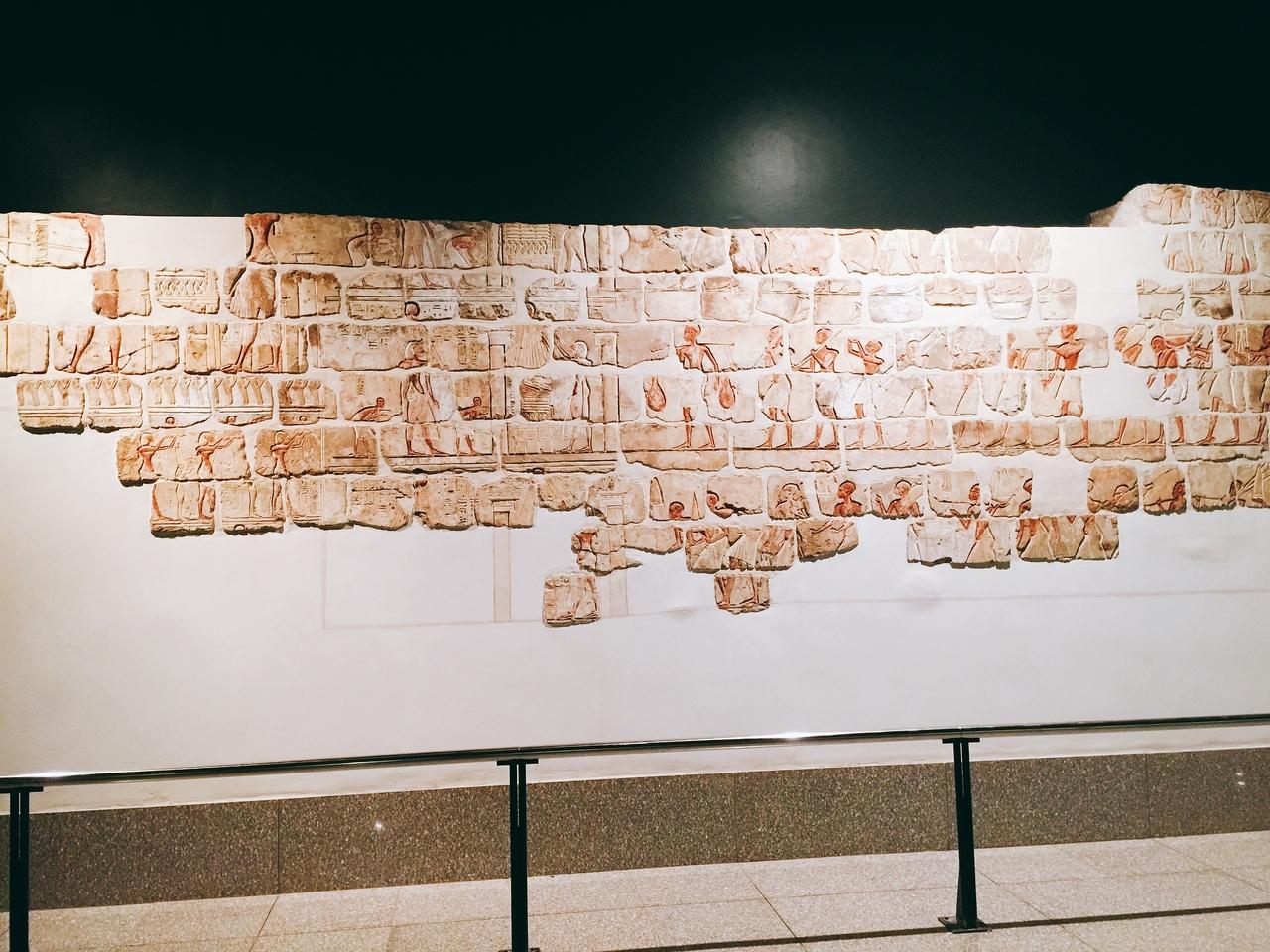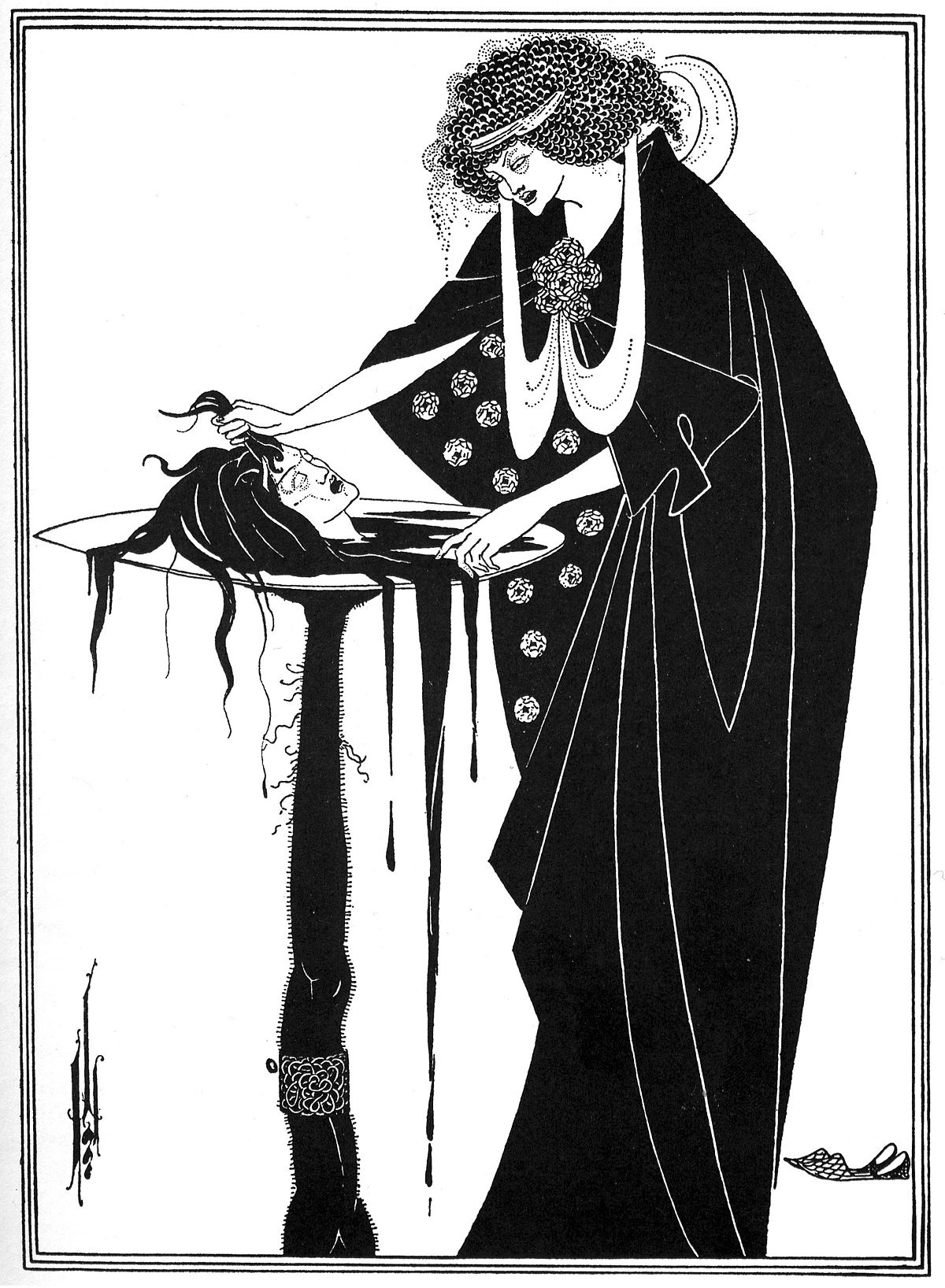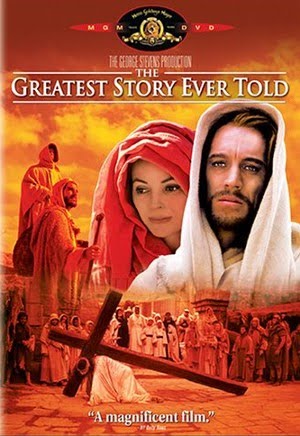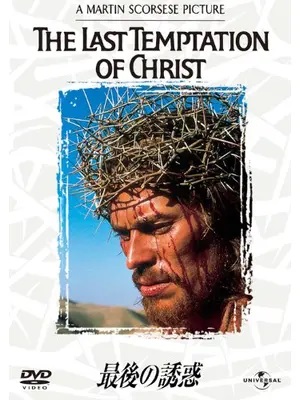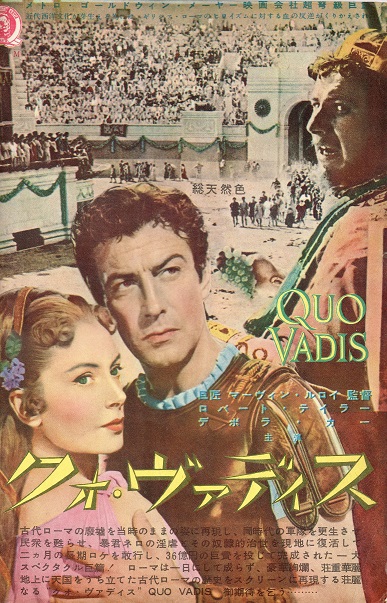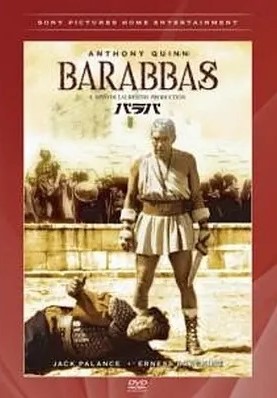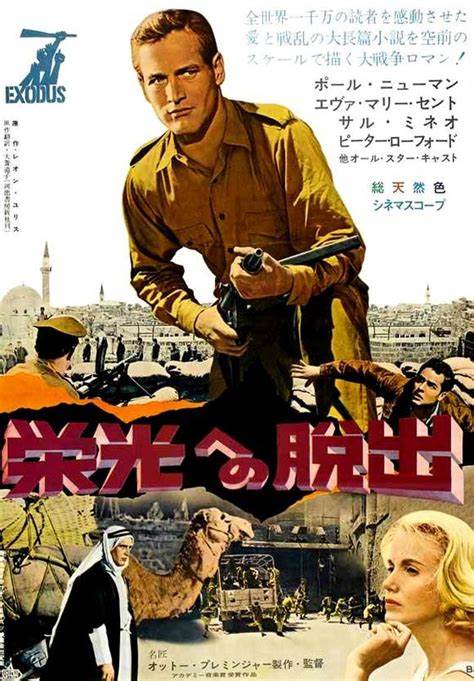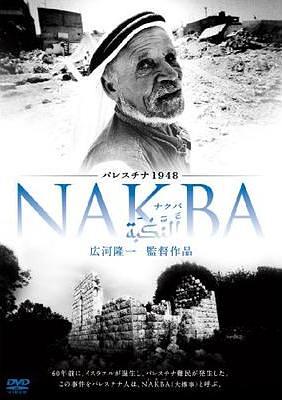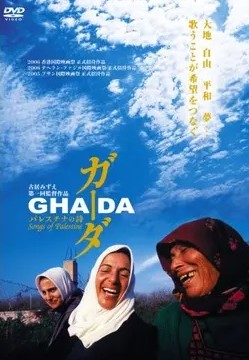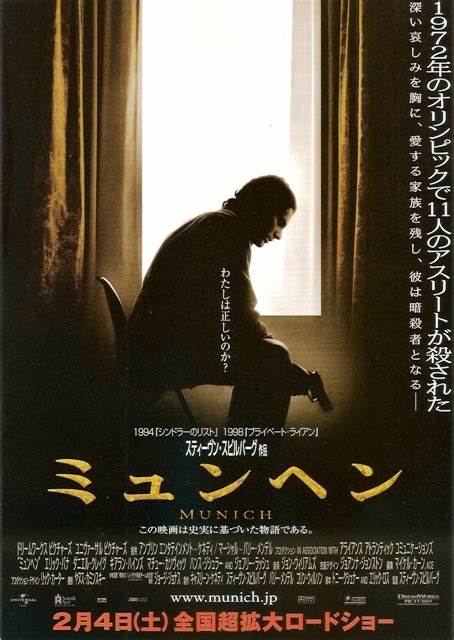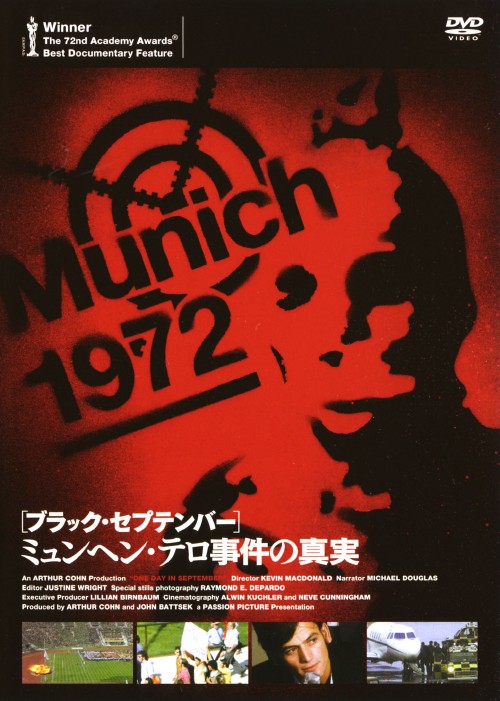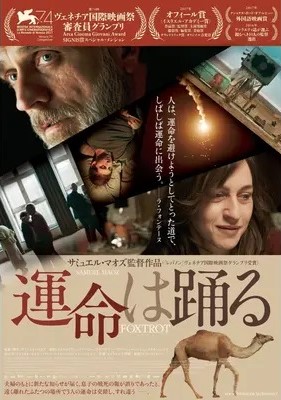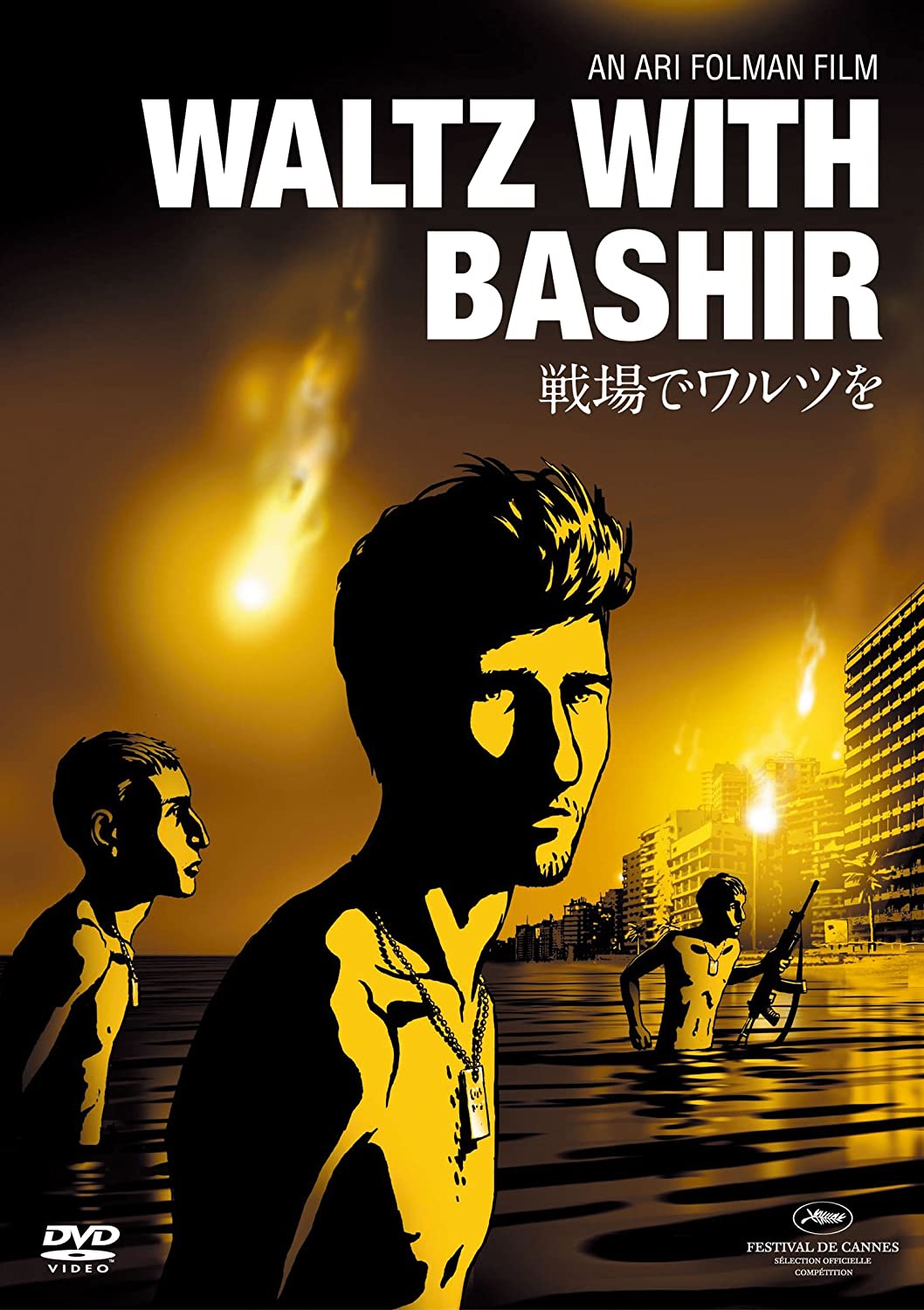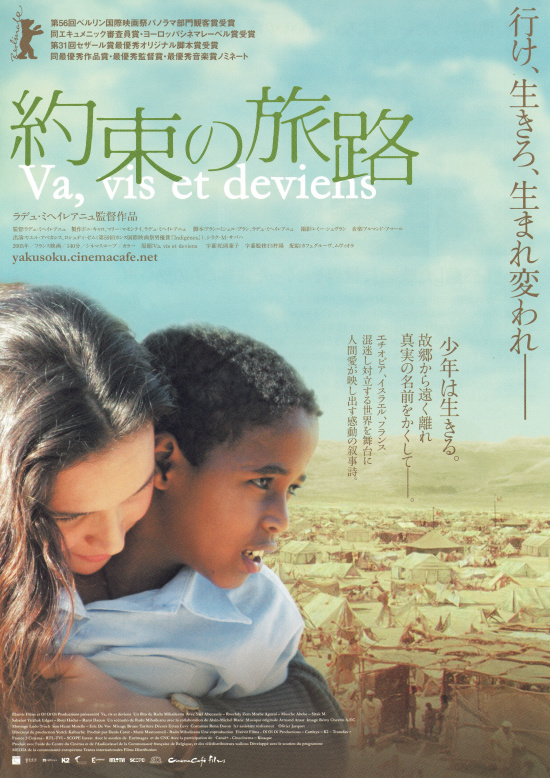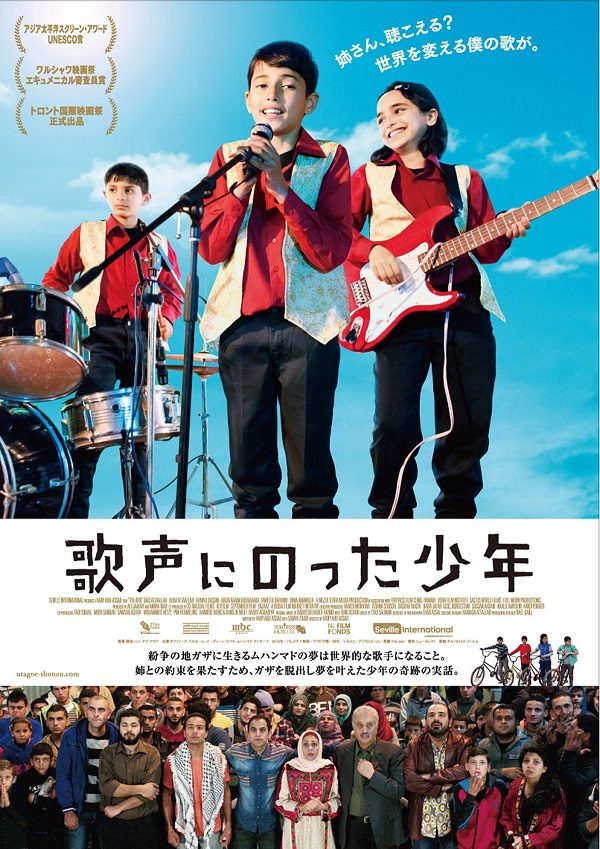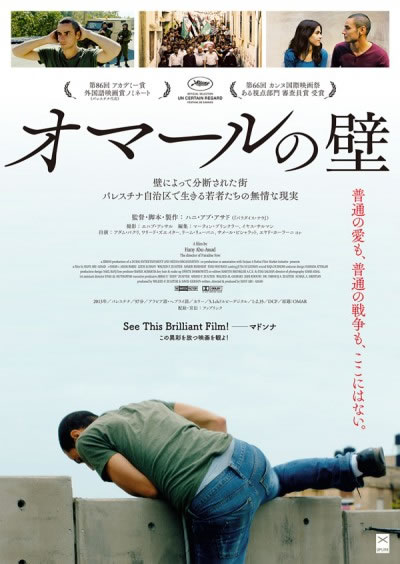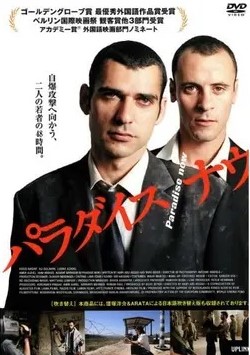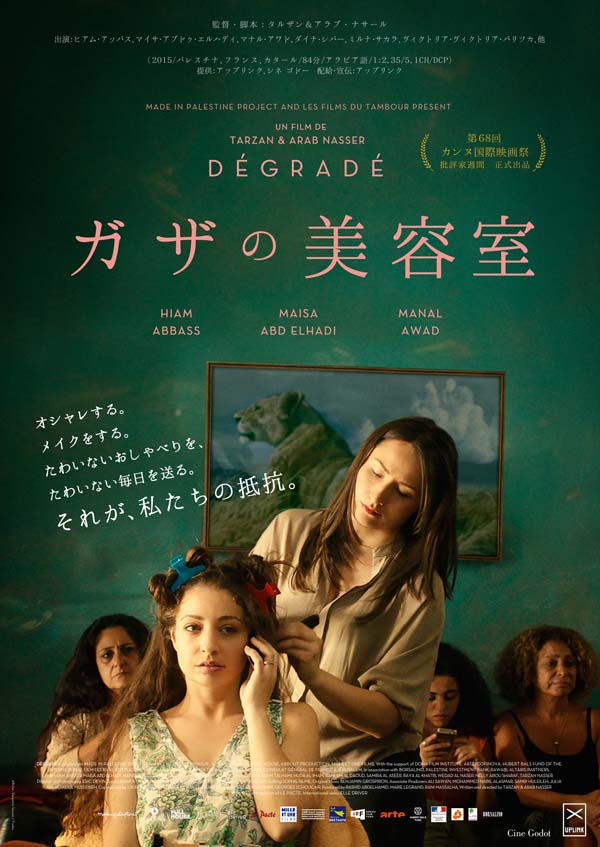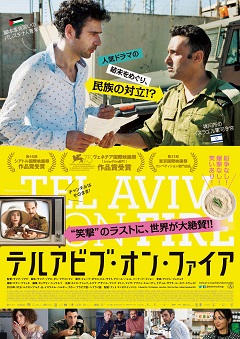�����_���E�C�X���G�����s
�c���V�I�j�X�g�Ƃ��Ĉ�_���̒n�����܂悤�c
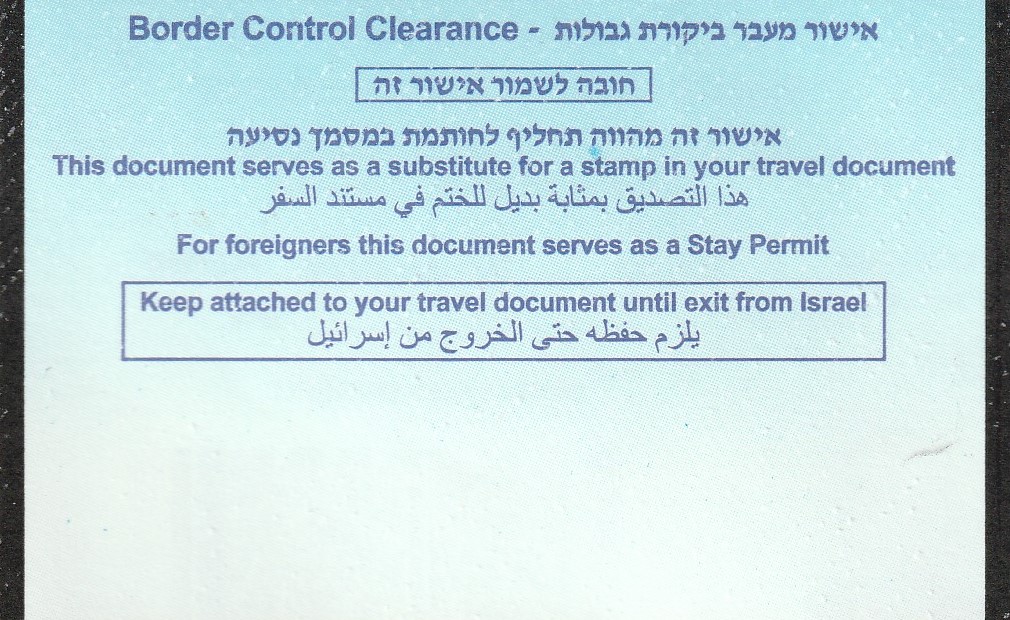
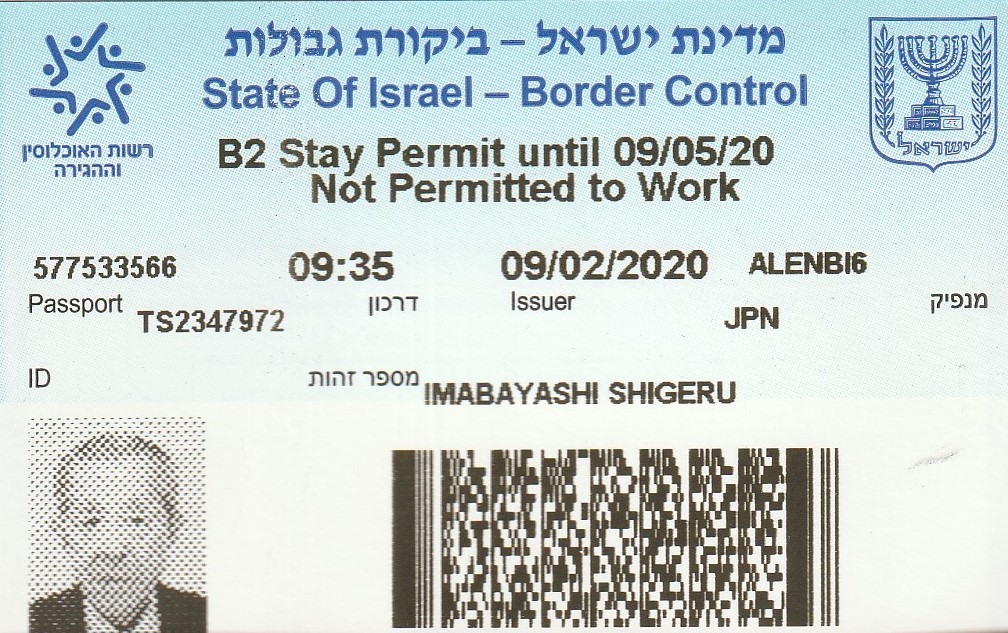 �@2020�N2��5������12���ɂ����āA�����_���ƃC�X���G���𗷂��܂����B��N���A���������s�Ŕ��������V�^�R���i�E�E�C���X���A�܂����E�I�Ɋg�U����ȑO�́A���b�N�_�E�����O�A���ˍۂ̂悤�Ȏ����ł��B�C�X���G�����痷�s�Ђɑ��A���N���ɒ����֗��s�����҂̓������֎~����A�Ƃ����ʒm���o����Ă����悤�ł��B�A����������A�C�X���G���͓��{���s�҂̓������֎~���܂����B���s����A��������A�V�^�E�C���X������قǂ̊����͂������Ă��悤�Ƃ́A�}�l�̎��ɂ͍l�����y�ʂ��Ƃł����B
�@2020�N2��5������12���ɂ����āA�����_���ƃC�X���G���𗷂��܂����B��N���A���������s�Ŕ��������V�^�R���i�E�E�C���X���A�܂����E�I�Ɋg�U����ȑO�́A���b�N�_�E�����O�A���ˍۂ̂悤�Ȏ����ł��B�C�X���G�����痷�s�Ђɑ��A���N���ɒ����֗��s�����҂̓������֎~����A�Ƃ����ʒm���o����Ă����悤�ł��B�A����������A�C�X���G���͓��{���s�҂̓������֎~���܂����B���s����A��������A�V�^�E�C���X������قǂ̊����͂������Ă��悤�Ƃ́A�}�l�̎��ɂ͍l�����y�ʂ��Ƃł����B
�@��藷�s�Ђ̃p�b�P�[�W�ł�����A�������Ղ𗷂��邱�ƂɂȂ�܂��B�ٔ�����������ɂ́A�Ȃ邾���G��Ȃ��ł��܂��悤�Ƃ��闷�ł�����܂��B�����_���̎�s�A���}���́A��`���p�ƒ��H�����A�C�X���G���ł͎�s�ł���e���A�r�u�ɂ͗������܂���B����ł��A����܂ł̌o���ɂ͂Ȃ��ْ����ɂ܂�āA��_���̒n�𗷂��܂����B
�@�@���ɂ͕Ό��������Ȃ��悤�A�l�I�ɂ͓w�߂Ă��܂����B���O�����̕����k�ŁA���_�_�҂ł��B�m���|���ł�����܂��B�l���݂ɁA�i�`�X�̃��_���l�s�E�ɂ͋���������o���܂��B�����������ɁA���݂̃C�X���G���̍s���ɂ́A�[���{����o���܂��B�S��I�ɂ͔��V�I�j�X�g�A�e�p���X�`�i�ł��B���̂悤�Ȑl�Ԃ��A�Z�����̒n�𗷂��܂����B
�i���т��ѐ��������p���Ă��܂����A�̂Ȃ���̕���Ȃ��ݐ[���A������͗p���Ă��܂���B������Ǔ_��K�X�}�����A���㉼�������ɉ��߂܂����B�j
�����_���@
�y�g�����

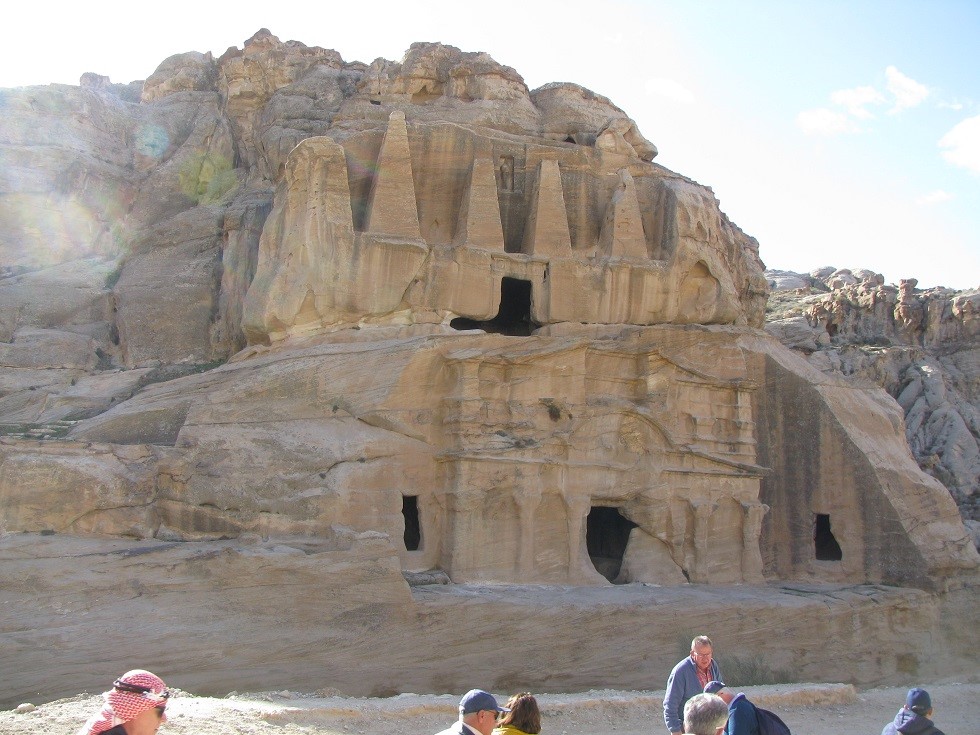 �@�V�[�N�ƌĂ���R�̗ڂ�1.2�L�����[�g���قǂ̉�L���`������B��ǂ́A�ł������Ƃ����100���[�g���ɂ��y�сA���͋����Ƃ����3���[�g���قǂ����Ȃ��B���R�����ݏo������Ղ̉�L�ł���B�藧�����R�̗��e�ɂ́A���̍������炢�̈ʒu�ɐ��H�����܂�Ă���B�����n�тɎ��܂�~��J�͓S�C���ƂȂ�B���̉�L���A���̓S�C�������o�������̂ł���B2018�N11���A�ό��q�����H�̏�ɑޔ������f���ɋ������L��������B�Ñ�l�́A�����r�i�_���j������āA�M�d�ȉJ�𗘗p�����B��ǂɂ͐_�a�̃t�@�T�[�h�̂悤�Ȓ��肱�݂�����������B
�@�V�[�N�ƌĂ���R�̗ڂ�1.2�L�����[�g���قǂ̉�L���`������B��ǂ́A�ł������Ƃ����100���[�g���ɂ��y�сA���͋����Ƃ����3���[�g���قǂ����Ȃ��B���R�����ݏo������Ղ̉�L�ł���B�藧�����R�̗��e�ɂ́A���̍������炢�̈ʒu�ɐ��H�����܂�Ă���B�����n�тɎ��܂�~��J�͓S�C���ƂȂ�B���̉�L���A���̓S�C�������o�������̂ł���B2018�N11���A�ό��q�����H�̏�ɑޔ������f���ɋ������L��������B�Ñ�l�́A�����r�i�_���j������āA�M�d�ȉJ�𗘗p�����B��ǂɂ͐_�a�̃t�@�T�[�h�̂悤�Ȓ��肱�݂�����������B


 �@����������ꂽ����A���R�Ƃ��Ċ�O���J���A�藧������ǂɒ��肱�܂ꂽ�������o������B�G���E�n�Y�l�ł���B
�@����������ꂽ����A���R�Ƃ��Ċ�O���J���A�藧������ǂɒ��肱�܂ꂽ�������o������B�G���E�n�Y�l�ł���B
�@���������Ԍ��Տ��l�ɂƂ��āA�����_���̊�R�͑傫�ȏ�Q���������B���ׂ̍����R�̉�L�͒n���C�֒ʂ���ߓ��ƂȂ�B��L�̔����́A�����ɋ��Z���镔�����ɁA�v��m��Ȃ��ɉh�������炵���B
�@�y�g���̈�Ղ́A���̒n���x�z�����i�o�e�A���̉h�����܂ɓ`����B
�@���Ƃ��Ƃ��̒n�ɂ́A�����ɂ��o�ꂷ��G�h�������Z��ł����B�G�h���Ƃ́A�C�T�N�̎q�G�T�E���Z�n���Ӗ�����B�M���V�A�ƃA�W�A�A�q�b�^�C�g�i���g���R�j�ƃG�W�v�g�̈ʒu�W���C���[�W����ƁA���̒n�������ʂ���Ղ̏\���H�ł��������Ƃ��悭�����ł���B�G�h�����ɂƂ��Đ��ɏZ�ރ��_�����͌��H�̎x�z���𑈂��������肾�����B�\���������̎���A�G�h�����̓��_�����ɔs����H�̎x�z���������B�������̃��_�������A�I���O587�N�A�o�r���j�A�ɐ��������B������u�o�r�����̕ߎ��v�ƌĂ�鎞��ł���B���_�������A�ꋎ��ꂽ��A�G�h���̐l�X�����̒n�ɖ߂��Ă������A�債�����͂ł͂Ȃ������炵���B


 �@�i�o�e�A���͂��Ƃ��ƗV�q���������B���݂̃����_����C�X���G���암�ɏZ�݁A�r�̕��q������̏P�����炵�̗ƂƂ��Ă����B�l���̑����ɔ����A�ނ�̓y�g�����Z�̒n�ɑI�B���_�������o�r���j�A�֘A�ꋎ���A�G�h�����̐��͂��܂��ł��Ă��Ȃ��^�C�~���O���i�o�e�A���ɍK�������B
�@�i�o�e�A���͂��Ƃ��ƗV�q���������B���݂̃����_����C�X���G���암�ɏZ�݁A�r�̕��q������̏P�����炵�̗ƂƂ��Ă����B�l���̑����ɔ����A�ނ�̓y�g�����Z�̒n�ɑI�B���_�������o�r���j�A�֘A�ꋎ���A�G�h�����̐��͂��܂��ł��Ă��Ȃ��^�C�~���O���i�o�e�A���ɍK�������B
�@�ʏ���̗v�n�Ɉʒu����y�g���́A�����s�s�Ƃ��Ĕɉh�����B����ȕx�Ŕނ�͈�剤����z���グ���B�G�h���l�́A�ۉ��Ȃ��i�o�e�A���ɋz�����ꂽ�Ƃ݂���B
�@�I���O1�A2���I���i�o�e�A���̉�������ł���B�����ł͂��������A�����͖���I�œz������Ȃ������炵���B�V�[�N�i��L�j�̃_����Ղ������悤�ɁA�����n�тł���Ȃ�����_�Ƃ��s���Ă����B���������̕x�́A�V�����[�}�̐����~��������B106�N�A��s�y�g���̓��[�}�R�ɍU������A���[�}�̈�B�s�A���B�A���r�A�Ƃ��Ďx�z�����Ɏ������B




 �@���̌�����炭�͌��Փs�s�Ƃ��ċ@�\�����B�������������[�g�́A�����̎v�f���z���ĕϓ�����B�y�g���o�R�̌��H���A����ɓ�k��̃��[�g�ւƈړ������B�p���~���o�R�̗��H�ƍg�C�𗘗p�����C�ニ�[�g�ł���B
�@���̌�����炭�͌��Փs�s�Ƃ��ċ@�\�����B�������������[�g�́A�����̎v�f���z���ĕϓ�����B�y�g���o�R�̌��H���A����ɓ�k��̃��[�g�ւƈړ������B�p���~���o�R�̗��H�ƍg�C�𗘗p�����C�ニ�[�g�ł���B
�@���H�̕ω���x�d�Ȃ�n�k�Ȃǂ��e�����āA�I��4���I���i�o�e�A�����͖ŖS����B���������ɂ̓L���X�g��������Ă��A7���I�ɂ̓C�X�������k�̎x�z���ɓ���B12���I�A�\���R����ǂ�z�������A�ނ炪�P�ނ������Ƃ́A�V�q�̖��x�h�E�B�����Z�ނ����̖Y���ꂽ�n��ƂȂ����B�i�o�e�A�������܂ǂ̕����Ɋ܂܂��̂����R�Ƃ��Ȃ��B
�@�قƂ�ǂ̌Ñ㕔���������ł������悤�ɁA�ނ�̏@���̓A�j�~�Y�����甭�W�������_���������B�Ƃ��ɑc�搒�q�̔O�������A�G���E�n�Y�l����_�������B�G���E�n�Y�l�Ƃ͕a���Ӗ�����B�t�@�T�[�h�㕔�̚�ɕ��B����Ă���̂ł́A�Ɣ����҂��v�����̂ł���B�������ȂǂȂ������B���z�l���̓w���j�Y�������̉e����F�Z���c���Ă���B�I���O1���I�����2���I�ɍ�肾���ꂽ�B�����͓���֎~�B�f��u�C���f�B�E�W���[���Y�Ō�̐���v�ɏo�Ă���悤�ȉ��s���͂Ȃ��炵���B�n����������A�܂������͏I����Ă��Ȃ��B



 �@�y�g���ł͉�L�i�V�[�N�j�ƃG���E�n�Y�l�����܂�ɂ��L�������A����͈�Ղ̂����ꕔ�ɉ߂��Ȃ��B�G���E�n�Y�l���̊�R�̌��Ԃ���Ɩ~�n��̑�n���L����B�����ɂ͐��̌͂ꂽ�삪����B�����̊R�ɂ͗�_�����������荞�܂�Ă���B�������ʂ̓��[�}�鍑�̋{�a�l���ɍ������Ă���B���~�`�����ʂ肪�c���Ă���B�����ɂ��Ɣ��@���ꂽ�����̐��͂��悻800�A����500�ȏオ����Ƃ����B�c�搒�q�̏@�����������Ƃ���Ղ͕����B
�@�y�g���ł͉�L�i�V�[�N�j�ƃG���E�n�Y�l�����܂�ɂ��L�������A����͈�Ղ̂����ꕔ�ɉ߂��Ȃ��B�G���E�n�Y�l���̊�R�̌��Ԃ���Ɩ~�n��̑�n���L����B�����ɂ͐��̌͂ꂽ�삪����B�����̊R�ɂ͗�_�����������荞�܂�Ă���B�������ʂ̓��[�}�鍑�̋{�a�l���ɍ������Ă���B���~�`�����ʂ肪�c���Ă���B�����ɂ��Ɣ��@���ꂽ�����̐��͂��悻800�A����500�ȏオ����Ƃ����B�c�搒�q�̏@�����������Ƃ���Ղ͕����B

 �@�~�n��̑�n���߂���ƎR���ɓ���B1���ԂقǓo�����Ƃ���ɁA�C���@�ƌĂ��G�h�E�f�B����Ղ�����B�G���E�n�Y�l��菭����A1�`2���I�ɍ��ꂽ��_�ł���B�G���E�n�Y�l�̂悤�Ȓ��L���ւ͂Ȃ����A���z�l���͍������Ă���B�\���R����A�ꎞ���C���m���Z��ł����B���̗̂R���͂��̂�����ɂ���B
�@�~�n��̑�n���߂���ƎR���ɓ���B1���ԂقǓo�����Ƃ���ɁA�C���@�ƌĂ��G�h�E�f�B����Ղ�����B�G���E�n�Y�l��菭����A1�`2���I�ɍ��ꂽ��_�ł���B�G���E�n�Y�l�̂悤�Ȓ��L���ւ͂Ȃ����A���z�l���͍������Ă���B�\���R����A�ꎞ���C���m���Z��ł����B���̗̂R���͂��̂�����ɂ���B
�@���[�[�̌Z�A�����̕�Ƃ����W���o���E�n���[���́A����ɓk��6���ԂقǗ��ꂽ�R���ɂ���A���R�p�b�P�[�W�̃c�A�[�s���ɂ͊܂܂�Ă��Ȃ��B
�@���܁A�y�g���̈�Ղ�ڂ̑O�ɂ���ƁA���̑��݂��̂��̂��A�l�X�̋L��������������Ă����Ƃ͐M���������B�����������́A1812�N�A�X�C�X�l���n���E���[�g���B�q�E�u���N�n���g���y�g����ՂƂ��ďЉ��܂ŁA�n���̗V�q���ȊO�m��l���Ȃ��A�Y�ꋎ��ꂽ��Ղ������B�@
�l�{�R
�@�C������āA���[�Z������G�W�v�g�̖��������G�W�v�g��E�o����B�����̒��ł��A�����Ƃ����I�ȃV�[���ł���B
�@�l�{�R�̓��[�Z�I���̒n�Ƃ���Ă���B�����ɂ��ƁA���[�Z�̓��_���̖��𗦂��ăG�W�v�g���o�����A���Ɩ��̗����n�J�i���ւ͂Ȃ��Ȃ����B�ł��Ȃ������B����60���l�i�u�o�G�W�v�g�L�v12�F37�j�̃��_���̖����A40�N�ԃV�i�C���������܂�����ƁA�����ɂ͋L�q����Ă��邪�A���Ԃ̐����͂�������\���̈ꂮ�炢���A�����Ə��Ȃ������̂ł͂Ȃ����낤���B����ɂ��Ă���l���ł���A�����N���ł���B
�@���O�����̕����k�Ŗ��_�_�҂̂킽���ɂ́A�f��u�\���v�i1957�N�j����������Ƃ��Ă͕�����₷���B�����̓��_���l�̌o�T�ł���A�������͂����ނ˂Ȃ�������ɂ����B�����ł́A�G�W�v�g�̃t�@���I�i�����ł̓p���j�������ł���B�ē̓Z�V���E�a�E�f�~���B�傪����ȃX�y�N�^�N���f��ӂƂ����B�����������ނɂ����u�T���\���ƃf�����v�i1950�N�j���ނ̎�ɂȂ�B���҂Ƃ��A�N�w�I�Ȑ[�݂ȂǑS���Ȃ��B
�@�������A�Ȃ����_���l���G�W�v�g�ɏZ�݁A�z��̂悤�ȋ����ɒu����Ă��������ŏ��ɓ��ɓ���Ă����Ȃ��ƁA�G�W�v�g�ɑ��ĕs�������낤�B�����u�n���L�v37�͈ȍ~�ɂ��̋L�q������A���̑}�b�Łu�n���L�v�͏I���B
�@�A�u���n���̑����R�u�͎q��R�������B�ނ͒x�����܂ꂽ���Z�t��M�������B���i�����Z�킽���́A�r��Ń��Z�t�̈ߕ����͂����A���ɓ˂����Ƃ��B�ߕ��ɎR�r�̌������A���Z�t�͖�b�ɏP���Ď��ƁA�����R�u�ɕ���B���Z�t�͒ʂ肩�����������ɋ~����邪�A�ނ�̓��Z�t���G�W�v�g�֔������Ă��܂��B
�@���܂��܂ȋ������z�������Z�t�́A�����f�ŃG�W�v�g���̐M����B�t�@���I�̌���������A7�N�����L��ƁA���̌��7�N�̋����\�����A�L��̂������ɐH�Ƃ��\���ɒ�����悤�i������B�t�@���I�̓��Z�t�Ɏ{���C�����B�����f�̒ʂ�A�L��̌�勥�삪7�N���������A�G�W�v�g�͒��������p���č�������ɕx�܂��邱�Ƃɐ��������B�ނ̓t�@���I�Ɏ����n�ʂɂ܂ŏ��߂�B


 �@�J�i���̒n������Ɍ������A���Z�t�̌Z�킽�����G�W�v�g�ւ���Ă����B���Z�t�͌Z�킽���������A�����R�u�������悤���߂�B���R�u�́A�G�W�v�g�֍s���ׂ����ǂ�����_�ɖ₤�B�n���L46�͂̋L�q�����̂܂܋L���B�c��͐_�Ȃ�A���̕��̐_�Ȃ�B�G�W�v�g�ɂ����邱�Ƃ����Ȃ���B���ޙ|�ɂē���傢�Ȃ鍑���ƂȂ���B����Ƌ��ɃG�W�v�g�։���ׂ��B�����Ȃ炸�����̂ڂ�ׂ��i3-4�j�B
�@�J�i���̒n������Ɍ������A���Z�t�̌Z�킽�����G�W�v�g�ւ���Ă����B���Z�t�͌Z�킽���������A�����R�u�������悤���߂�B���R�u�́A�G�W�v�g�֍s���ׂ����ǂ�����_�ɖ₤�B�n���L46�͂̋L�q�����̂܂܋L���B�c��͐_�Ȃ�A���̕��̐_�Ȃ�B�G�W�v�g�ɂ����邱�Ƃ����Ȃ���B���ޙ|�ɂē���傢�Ȃ鍑���ƂȂ���B����Ƌ��ɃG�W�v�g�։���ׂ��B�����Ȃ炸�����̂ڂ�ׂ��i3-4�j�B
�@���Z�t�͎w���͂ɕx���͂���l���������B�g�[�}�X�E�}���͔ނ̐��U�����ƂɁu���Z�t�Ƃ��̌Z��v�i�}�����[�A�]���s�b�E�����ߖ�j���������B���M���@�Ƀi�`�v�z�ւ̔������������ƌ����Ă��邪�A���Z�t�̐l�ƂȂ�ւ̋������A�����ɂ��̑咷�҂����������̂��낤�B
�@���������Z�t�����Ƀt�@���I���ς��A���_���l�ւ̑Ή����ς��B�����āA���_���̖��͗B��_����ȂɐM���A�ւ荂���A���͂ƗZ�����悤�Ƃ��Ȃ��B�ٖ����Ƃ��Ĕ��Q����Ă��d���̂Ȃ��v�f�𑽕��Ɏ����Ă���B�����āA���Z�t�̎l���ɐ��܂ꂽ�̂����[�Z�������B


 �@���_�����̃��[�_�[�ƂȂ������[�Z�́A�t�@���I�Əo���̌�������B�����ȘJ���͂��K�v�ȃt�@���I�͋��ۂ���B���[�Z�͐������̊�Ղ������āA�t�@���I����������B���_���̖��ւ̊�Ղ̓G�W�v�g�ɂƂ��Ă̍Ж�ł���B�\�Ԗڂ̍Ж�ł��������B�S�ẲƂ́A�l�ł���ƒ{�ł���A���q���E���Ƃ������̂������B���̂Ƃ��A���_���̖��́A����ɗr�̌���h��A�_�̓{�肩�瓦���ڈ�Ƃ����B���̊�Ղ��j���߉z�Ղ́A���_���̎O��j�Ղ̈�ł���B�_�̓{����߂��z�������Ƃ��j���Ă���B
�@���_�����̃��[�_�[�ƂȂ������[�Z�́A�t�@���I�Əo���̌�������B�����ȘJ���͂��K�v�ȃt�@���I�͋��ۂ���B���[�Z�͐������̊�Ղ������āA�t�@���I����������B���_���̖��ւ̊�Ղ̓G�W�v�g�ɂƂ��Ă̍Ж�ł���B�\�Ԗڂ̍Ж�ł��������B�S�ẲƂ́A�l�ł���ƒ{�ł���A���q���E���Ƃ������̂������B���̂Ƃ��A���_���̖��́A����ɗr�̌���h��A�_�̓{�肩�瓦���ڈ�Ƃ����B���̊�Ղ��j���߉z�Ղ́A���_���̎O��j�Ղ̈�ł���B�_�̓{����߂��z�������Ƃ��j���Ă���B
�@���[�Z�́A�_�����R�u�ɗ^�������t�u�����Ȃ炸�����̂ڂ�ׂ��v�ɏ]���A���_���̖��𗦂��ăG�W�v�g���o���B�t�@���I�̒ǐՂ�������̂�������Ȃ����A�J�i���̒n�֒H�蒅���܂Œ����N����v�����B�����ɂ́A���Z�t�̕����R�u��Z�킽�����A�G�W�v�g�֗���̂ɒ����N����v�����Ƃ͏�����Ă��Ȃ��B����̂͊y���������A�A��̂ɂ͎��Ԃ����������ƂȂ�ƁA���w�u�Ƃ����v�݂����ʼn����B������ƍl����̂́A�������_�_�҂�����Ɗ��ق��Ă��炢�����B
�@�G�W�v�g�̗��j�ɓK��������ƁA���_���l���������������̂́A�I���O1730�N���`1580�N���̃q�N�\�X�������Ƃ����B���[�Z�̃G�W�v�g�E�o�́A��19���������Z�X�i�݈ʁA�O1279-1213�j�̎���ɑ�������B�G�W�v�g�̎��鏊�ɋ���Ȓ������c���������~�̋������ł���B�G�W�v�g���ɂ̓��_���l���S�̋L�^����Ȃ��B�����Z�X�ɂƂ��Ė��_�Șb�ł͂Ȃ�����L�^���Ȃ������\�����Ȃ��͂Ȃ��B���������j�Ƃ����́A�����ɋL�q�����悤�ȑ�E�o�����ʂ����Ă������̂��ǂ����Ƌ^���������Ă���B


 �@���[�Z���V�i�C�R�Ő_����^����ꂽ�Ƃ����\���́A�u�o�G�W�v�g�L�v20�͂ɋL�q����Ă���B
�@���[�Z���V�i�C�R�Ő_����^����ꂽ�Ƃ����\���́A�u�o�G�W�v�g�L�v20�͂ɋL�q����Ă���B
�@1.��̊O���������_�Ƃ��ׂ��炸�A2.�����ނׂ��炸�A3.�_�̖����݂���Ɍ��ɂ����ׂ��炸�A4.�������������ĉ��̋Ɩ������Ȃ��ׂ��炸�A5.������h���A6.�E���Ȃ���A7.��������Ȃ���A8.���ނȂ���A9.���ς̏؋�������Ȃ���A10.�אl�̏��L���Â�Ȃ���A������ł���B
�@�_�����[�Z�ɏ\����^�����̂́A�G�W�v�g���o�Ă���O�����Ƃ������������ł���B�Ս��Ȉړ��̗��ŁA�Q�O�̋K���͊ɂ�ł���B���[�Z�ɂ́A���ׂ��Œ���̉����𑁂������Ɏ����K�v���������ƍl���Ă������낤�B
�@���X�̋������z���A���[�Z�̓J�i���̒n��������Ƃ���܂Ń��_���̖����Ă����B�������_�́A���[�Z�����̒n�֓��邱�Ƃ������Ȃ������B�u�\���L�v�ɂ́c�����ăG�z�o����Ɍ�����������͉䂪�A�u���n���A�C�T�N�A���R�u�ɂނ����V����̎q���ɂ�������ƌ����Đ������肵�n�͐��Ȃ�B��Ȃ����ĔV��ڂɊς邱�Ƃ����ށB�R�Ǔ��͔ޙ|�֍ς�䂭���Ƃ��i34�F4�j�B
�@����ɍl����A���[�Z�̎����������܂ł������Ƃ������ƂɂȂ�B���ȗ��̓r��A���[�Z�͖��炩�ɁA���x���_�̖��߂ɏ������B�G�z�o�͎�������i�[���_���ƌ����Ă���B���[�Z�̔��R���A�_�������Ȃ������Ƃ�����������B���̕������ʂ�B�����Ď��́A�u�ς�䂭���Ƃ��v�ƍ�����ꂽ�Ƃ��̃��[�Z�̐S���Ɏv����y����B
�@��p�҂̓��V���A�ł���B�l�{�R�̒��ォ�烂�[�Z�́A�V�����w���҂ɗ������ăJ�m���̒n��������s�����������B
�@�u�\���L�v�̓��[�Z�̍Ō�����̂悤�ɋL���B
�@�c�z���̔@���G�z�o�̖l���[�Z�̓G�z�o�̌��̂��Ƃ����A�u�̒n�Ɏ���B�i�����j�����܂ł��̕��m��l�Ȃ��B���[�Z�͂��̎����鎞�S��\�Ȃ肵���A���̖ڂ��܂܂����̋C�͂͐������肫�i34�F5-7�j�B
�}�_�o�@�c���W���[�W����



 �@���W���[�W����̓M���V�A�����̋���ŁA���[�}�鍑�������ɕ�����Ɍ��Ă��Ă���B����6���I�ɍ��ꂽ���U�C�N���c���Ă���B�Ñ�̏���n�}�A�ό��ē��ł���B�����̃p���X�`�i�̒n�}�����U�C�N�ŕ`����A���C��G���T�����̎s�X�n�����ʂł���B�Ƃ�킯�A�����拳��傫���`����A4���I�Ƀ��[�}�鍑���L���X�g�������Ə@���Ƃ��ĊԂ��Ȃ������́A�@���I�M���Ԃ��f�i������B
�@���W���[�W����̓M���V�A�����̋���ŁA���[�}�鍑�������ɕ�����Ɍ��Ă��Ă���B����6���I�ɍ��ꂽ���U�C�N���c���Ă���B�Ñ�̏���n�}�A�ό��ē��ł���B�����̃p���X�`�i�̒n�}�����U�C�N�ŕ`����A���C��G���T�����̎s�X�n�����ʂł���B�Ƃ�킯�A�����拳��傫���`����A4���I�Ƀ��[�}�鍑���L���X�g�������Ə@���Ƃ��ĊԂ��Ȃ������́A�@���I�M���Ԃ��f�i������B
�@�p�b�P�[�W�E�c�A�[�̖��ŁA�����_���ŖK�₵���̂́A���C���܂߂ĎO�����ł���B��藷�s�ЂƂ��ẮA�L���X�g���M�҂₻�̃V���p�A�������͒P�Ƀy�g���ό��ړI�����̗��s�q��ΏۂƂ��ĖK����I�肷��̂��낤�B�����_���̎�s�A���}���ɂ́A�A�r���H�ɗ�������������ŁA���ト���_���������Ƃ͌����Ȃ��B
�A���n�x�z�ƃ����_���a��
�@���݂̒����e���̍������́A���������A��ɃC�M���X�ƃt�����X���A���n�x�z����ɏ���Ɉ��������̂ł���B����E����ʂ̊p�x���猩��A�A���n���L���ł���C�M���X��t�����X�A�A�����J�ȂǂƁA�V���ɐA���n�����l����ڎw���V�K�Q�����h�C�c���тɓ��{�Ƃ̑����ł��������B�I��͓����ɐA���n��`�̕���ւƂȂ������B�h�C�c�Ɠ��{�ɁA�A���n����Ƃ��������ȖړI���������Ƃ͌����Ȃ����A���j�I�ϊ��̈����������������͉ʂ������B
 �@�A���n�x�z�̓S���́A�c��������ȁA�������ē�������A�ł���B�c�������Ɨ��^�����A�����҂͍ł����ꂽ�B������@���̈Ⴂ���A�����̊�ƂȂ�B�A���n�x�z�ȑO�́A�B���������a�ȋ�����Ԃ��A�@�卑�̈ӌ��łƂ��Ƃ��������ڂւƕω�����B���̌X���́A���ɒ�����A�t���J�ŕ\�ʉ������B����A�W�A�����́A�A���n�x�z���n�܂�ȑO����A�ꉞ���ƂƂ��Ă̑̍ق𐮂��Ă����B�N���҂͎x�z�҂���Ȃ�����Ύ����肽�B������A�t���J�́A�G�W�v�g��y���V���i�C�����j�������āA�ʂł͂Ȃ��_���x�z�̒P�ʂ������B���ʂ��������́u�ꑰ�v�ӎ��ł���B�ꑰ�̒����A�x�z�P�ʂł���_�̃��[�_�[�������B�قƂ�ǂ��C�X�������̍��Ƃ͂����Ă��A�X���j�h�ƃV�[�A�h�����͂𑈂��Ă���B�u�������ē�������v�̐��A����Ȃ�Η���������B�C���N��V���A�̂悤�ɁA�@���ł͏����h�ɑ����郊�[�_�[���ꍑ���x�z�����ꍇ�A�����͈�w��������B�A���n�����̈��e���͂��܂��ɔ��������Ďc���Ă���B
�@�A���n�x�z�̓S���́A�c��������ȁA�������ē�������A�ł���B�c�������Ɨ��^�����A�����҂͍ł����ꂽ�B������@���̈Ⴂ���A�����̊�ƂȂ�B�A���n�x�z�ȑO�́A�B���������a�ȋ�����Ԃ��A�@�卑�̈ӌ��łƂ��Ƃ��������ڂւƕω�����B���̌X���́A���ɒ�����A�t���J�ŕ\�ʉ������B����A�W�A�����́A�A���n�x�z���n�܂�ȑO����A�ꉞ���ƂƂ��Ă̑̍ق𐮂��Ă����B�N���҂͎x�z�҂���Ȃ�����Ύ����肽�B������A�t���J�́A�G�W�v�g��y���V���i�C�����j�������āA�ʂł͂Ȃ��_���x�z�̒P�ʂ������B���ʂ��������́u�ꑰ�v�ӎ��ł���B�ꑰ�̒����A�x�z�P�ʂł���_�̃��[�_�[�������B�قƂ�ǂ��C�X�������̍��Ƃ͂����Ă��A�X���j�h�ƃV�[�A�h�����͂𑈂��Ă���B�u�������ē�������v�̐��A����Ȃ�Η���������B�C���N��V���A�̂悤�ɁA�@���ł͏����h�ɑ����郊�[�_�[���ꍑ���x�z�����ꍇ�A�����͈�w��������B�A���n�����̈��e���͂��܂��ɔ��������Ďc���Ă���B
�@�A���n��������₩�ɍ��������Ⴊ�Ȃ��킯�ł��Ȃ��B�A���u���A�M�́A���̎����ɂ₩�ȘA�M���`�����Ă���B���̎Ȃ���̂������������Ε������ł���B�������傫��������ƂȂ�B�Ζ������͌��͎҂�����B�T�E�W�A���r�A�̂悤�Ɏ�v�t���͉��q��������߂�B


 �@���������́A�A���n����ɒǂ����܂�Ă��A���̉e���͂��c�����Ƃ��܂��܂ɉ���B�����͊W�@�卑�̗͊W�Ő��������ꂽ�B���̉ߒ��ŁA�N���h���͑��݂����ꂽ�B�Ɨ���̃��[�_�[�̑I���ɂ��A���@�卑�̈Ӑ}�������Ɍ����B�V���[�_�[�����̈Ӑ}�ɓY��Ȃ����Ƃ�����B�ꍇ�ɂ���ẮA���Δh�̃N�[�f�^�[���x��������������B���̉��̏X�����́A�l�Ԃ̐�������M�������Ȃ�قǂ����܂����B�@�卑�P�ތ�A�����͓ƍَ҂ƂȂ�A�ꑰ�ŕx��Ɛ肵���B
�@���������́A�A���n����ɒǂ����܂�Ă��A���̉e���͂��c�����Ƃ��܂��܂ɉ���B�����͊W�@�卑�̗͊W�Ő��������ꂽ�B���̉ߒ��ŁA�N���h���͑��݂����ꂽ�B�Ɨ���̃��[�_�[�̑I���ɂ��A���@�卑�̈Ӑ}�������Ɍ����B�V���[�_�[�����̈Ӑ}�ɓY��Ȃ����Ƃ�����B�ꍇ�ɂ���ẮA���Δh�̃N�[�f�^�[���x��������������B���̉��̏X�����́A�l�Ԃ̐�������M�������Ȃ�قǂ����܂����B�@�卑�P�ތ�A�����͓ƍَ҂ƂȂ�A�ꑰ�ŕx��Ɛ肵���B
�@�Ɨ���̂��܂��Ȃ��������������������B�C�X�������iISIS)�̂悤�ȉߌ��h�ɁA���Ă��Ă����܂�錄��������B
�@���݂̒����̍����̎傽��v���́A��ꎟ���E��풆�̃C�M���X��O���Ɍ�������B
�@1914�N6��28���A�Z���r�A�̈�N���I�[�X�g���A�̍c�ʌp���҂��ÎE�����B���̎����Ƀh�C�c�ƃ��V�A���ߕq�ɔ������đ�푈�ւƔ��W�����B�����̑唼���x�z���Ă����I�X�}���E�g���R�́A�I�[�X�g���A�A�h�C�c���ɂ����B���V�A���ɂ����C�M���X�́A�܂��X�G�Y�^�͂̌��v����邽�߁A�G�W�v�g�����S�ȕی썑�Ƃ����B���̌�A�C�M���X�͖����ɖ�������A������B
�@1915�N�A�t�Z�C���E�}�N�}�t�H������ŁA���b�J�̑���t�Z�C���E�C�u���E�A���[�ɑ��A��ꎟ����̓Ɨ�������B1916�N�A�p���ԂŁA�T�C�N�X�E�s�R���肪���ꂽ�B�I�X�}���E�g���R����D����������y���A�p���ŕ�������Ƃ����閧����ł���B���̋���ɂ́A��Ƀ��V�A��������Ă���B����͖��炩�ɁA�t�Z�C���ɑ��ĂȂ��ꂽ�Ɩ�������B�����āA���݂̒��������ő�̗v���ƂȂ�o���t�H�A�錾���A1917�N�ɏo�����B���̐錾�ŁA�C�M���X�̓��_�������ɑ��A���ɏ�������Ƃ��������t���ł͂��邪�A�p���X�`�i�̒n�Ƀ��_���l���Ƃ���������Ɩ����B�푈�p���ɑ���̎�����K�v�Ƃ����ꂵ����̐錾�ł���B�����A�I�X�}���E�g���R�������āA�����ɂ͍��Ƃ炵�����݂͂Ȃ��B�푈�ɏ�������������Ƃ͉��Ƃł��Ȃ�Ƃ����v�����C�M���X�ɂ������B�����̃C�M���X�́A���z�̒��܂ʒ鍑�Ƃ���ꂽ�B���̘��肪�����ӔC�ȓ�O����O���������B

 �@���b�J�̑����t�Z�C���E�C�u���E�A���[�́A�C�X�������̎n�c���n���}�h�̌��������n�[�V���Ƃ̓���ł��������B���q�̈�l�t�@�C�T�����A�A���r�A�l������g�D���āA1920�N�A�_�}�X�J�X�ɓ��邵���B�V���A�ƃp���X�`�i���̂����ނ́A�t�@�C�T���ꐢ�Ƃ��ĉ��ʂɂ����B���̌o�܂́A�f��u�A���r�A���������X�v�i1962�N�j�ɂ��`����Ă���B
�@���b�J�̑����t�Z�C���E�C�u���E�A���[�́A�C�X�������̎n�c���n���}�h�̌��������n�[�V���Ƃ̓���ł��������B���q�̈�l�t�@�C�T�����A�A���r�A�l������g�D���āA1920�N�A�_�}�X�J�X�ɓ��邵���B�V���A�ƃp���X�`�i���̂����ނ́A�t�@�C�T���ꐢ�Ƃ��ĉ��ʂɂ����B���̌o�܂́A�f��u�A���r�A���������X�v�i1962�N�j�ɂ��`����Ă���B
�@�T�C�N�X�E�s�R����Ɋ�Â��A�t�����X���V���A�ƃ��o�m������ɓ��ꂽ�B�t�����X�́A�A���n�������ז��ȃt�@�C�T���ꐢ��Ǖ������B���R�����^������������B1936�N�A���a���Ƃ��Ď�����F�߂�ꂽ���A���S�ȓƗ�����ɂ����̂͑����i1946�N�j�ł���B
�@�����_���̌����́A���̉Q���ɐ��܂ꂽ�B1921�N3���A�t�Z�C���̕ʂ̑��q�A�u�h�D�b���[�́A�A���}���ɐi������̂����B�C�M���X�̓p���X�`�i�̒n���ɕ����A�����_���쓌�ݒn����A�u�h�D�b���[�̗̓y�Ƃ��ĔF�߂��B�u�g�����X�E�����_�����v�̒a���ł���B���ꂪ���݂̃����_���E�n�V�~�e�����̌��`�ƂȂ����B



 �@�Ζ������Ɍb�܂�Ȃ������_���́A�R���I�ɋ���ȃC�X���G���̗��Ƃ��āA�@���ɐ����čs���ׂ�����S���Ă���B�����푈�ł̓A���u���̈���Ƃ��ăC�X���G���Ɛ킢�A�O�x�s�ꂽ�i��l���ɂ͎Q�킵�Ă��Ȃ��j�B�����̃p���X�`�i����������A���܂ł͐l����70%�ȏ���߂�BPLO�i�p���X�`�i����@�\�j�̓����_���Œa�������B�p�ݐ푈�ł̓C���N�x���ɉ�����B2011�N�Ɏn�܂����u�A���u�̏t�v�^���ŁA���̃V���A�������ԂƂȂ�A�����̓�����Ă����B���݂̐l����970���l�����A30%�͔��_�����Ђ��Ƃ����iWikipedia�j�B
�@�Ζ������Ɍb�܂�Ȃ������_���́A�R���I�ɋ���ȃC�X���G���̗��Ƃ��āA�@���ɐ����čs���ׂ�����S���Ă���B�����푈�ł̓A���u���̈���Ƃ��ăC�X���G���Ɛ킢�A�O�x�s�ꂽ�i��l���ɂ͎Q�킵�Ă��Ȃ��j�B�����̃p���X�`�i����������A���܂ł͐l����70%�ȏ���߂�BPLO�i�p���X�`�i����@�\�j�̓����_���Œa�������B�p�ݐ푈�ł̓C���N�x���ɉ�����B2011�N�Ɏn�܂����u�A���u�̏t�v�^���ŁA���̃V���A�������ԂƂȂ�A�����̓�����Ă����B���݂̐l����970���l�����A30%�͔��_�����Ђ��Ƃ����iWikipedia�j�B


 �@���݁A�C�X���G���ƍ������������̍��́A�G�W�v�g�ƃ����_���݂̓̂ł���B�G�W�v�g�́A1967�N�̑�O�������푈�ŃV�i�C���������������A���̕Ԋ҂������ɁA1979�N�������J�����B�����_�����C�X���G���Ƃ̕��a�������̂�1994�N�ł���B�푈��Ԃ��������܂܂ł́A�����_���k�J���A���ݒn����C�X���G���ɒD�����ꂩ�˂Ȃ��B��ނ��J���������ł���B���������邩��ƌ����āA���C�X���G��������̒��������ɔ�ׂĊ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�p�ݐ푈�ŃC���N���x�������̂��A����ɔ��C�X���G����������������Ƃ݂ĊԈႢ�Ȃ��B
�@���݁A�C�X���G���ƍ������������̍��́A�G�W�v�g�ƃ����_���݂̓̂ł���B�G�W�v�g�́A1967�N�̑�O�������푈�ŃV�i�C���������������A���̕Ԋ҂������ɁA1979�N�������J�����B�����_�����C�X���G���Ƃ̕��a�������̂�1994�N�ł���B�푈��Ԃ��������܂܂ł́A�����_���k�J���A���ݒn����C�X���G���ɒD�����ꂩ�˂Ȃ��B��ނ��J���������ł���B���������邩��ƌ����āA���C�X���G��������̒��������ɔ�ׂĊ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�p�ݐ푈�ŃC���N���x�������̂��A����ɔ��C�X���G����������������Ƃ݂ĊԈႢ�Ȃ��B
�C�X���G��
�x�c���w��
�@�C�X���G���̓��_���l�̍����Ƃ��̍��̕ێ�I�w���҂����͎咣����B�C�X���G�����Ђ����p���X�`�i�l�����邪�A���̑��݂͂قƂ�ǖ�������Ă���B�����ɑ����̃L���X�g������i�����A�V���A�����j��X�N�����邪�A��{�I�ɂ̓��_�����̍��ł���B���݂ł͖��_�_�҂������Ă��Ă�����̂́A�����̐߁X�ɉe�����郆�_�������͂��Ă��Ȃ��B�H���֊����命���̐l�тƂ�����Ă���B���n�K�C�h�̌��t�����ƁA44%�͍D������A32%�͍��Ə@���Ƃ��Ă̑��d�h�A24%�͓`���Ŏ��h���Ƃ����B���̂����A�������h�̓��_���l���l����11%���߂Ă���B

 �@�C�X���G���́A1967�N�̑�O�������푈�ŒD������������_���쐼�ݒn��Ɠ��G���T�����A�S�����������킪���̂Ƃ��ē������Ă���B�����`�Ԃ�ABC�̎O�ɕ������BA�n��͍s���A�����Ƃ��Ƀp���X�`�i�������{�BB�n��̍s���̓p���X�`�i�A�����̓C�X���G���BC�n��͍s���A�����Ƃ��ɃC�X���G���B�Ƃ͂������̂́A���P�ʂ̍s���敪�ł݂�ƁA�C�X���G�����s���E�����Ƃ������Ă���n�悪�����B
�@�C�X���G���́A1967�N�̑�O�������푈�ŒD������������_���쐼�ݒn��Ɠ��G���T�����A�S�����������킪���̂Ƃ��ē������Ă���B�����`�Ԃ�ABC�̎O�ɕ������BA�n��͍s���A�����Ƃ��Ƀp���X�`�i�������{�BB�n��̍s���̓p���X�`�i�A�����̓C�X���G���BC�n��͍s���A�����Ƃ��ɃC�X���G���B�Ƃ͂������̂́A���P�ʂ̍s���敪�ł݂�ƁA�C�X���G�����s���E�����Ƃ������Ă���n�悪�����B
�@�����Ɏ��グ���x�c���w�����A�s�s������A�n�悾���A���P�ʂŌ���Ƒ唼��B�AC�̋敪�ɓ���B�O���̃L���X�g���k������̂悤�Ȋό��q�́A�قƂ�ǐ����Ȃ��x�c���w���֓���邪�A�C�X���G���̐l�тƂɂ͐��{�̋����K�v�ƂȂ�B�U������Đg�����v�������\�������邩�炾�ƌ����B�������A�s�s�̎��͈͂������������ǂɈ͂܂�Ă���B

 �@���_�����̌o�T�́A��ʓI�Ɍ����Ƃ���̋����ł���B�L���X�g���k�ɂ́A����E�V��̓�̐��T�����邪�A���_�����k�ɐV��͂Ȃ��B�_����^����ꂽ�Ƃ���鐹�T������݂̂ł���B���ɏd�v�������̂��A�g�[���i���@�j�ƌ����郂�[�Z���ł���B���Ȃ킿�A�u�n���L�v�u�o�G�W�v�g�L�v�u���r�L�v�u�����I���v�u�\���L�v�̌��ł���B
�@���_�����̌o�T�́A��ʓI�Ɍ����Ƃ���̋����ł���B�L���X�g���k�ɂ́A����E�V��̓�̐��T�����邪�A���_�����k�ɐV��͂Ȃ��B�_����^����ꂽ�Ƃ���鐹�T������݂̂ł���B���ɏd�v�������̂��A�g�[���i���@�j�ƌ����郂�[�Z���ł���B���Ȃ킿�A�u�n���L�v�u�o�G�W�v�g�L�v�u���r�L�v�u�����I���v�u�\���L�v�̌��ł���B
�@�u�n���L�v�ł́A�_�G�z�o�̓V�n�n���A�A�_���ƃG�o�i�C�u�j�A�Z��E���̃J�C���ƃA�x���A���̒��ŗL���ȃ\�h���ƃS�����A�m�A�̕��M�A�o�x���̓��A�A�u���n���ƃC�T�N�����ՁA�����ȃ��Z�t�ƃ��_�����̃G�W�v�g�ڏZ�Ȃǂ̑}�b�������B�u�o�G�W�v�g�L�v����u�\���L�v�܂ł̎l���́A�G�W�v�g��E�o�������[�Z�̈�s���J�i���̒n�֎���܂ł̋���`���B
�@���_�����k�ɂƂ��āA�C�G�X���a�̒n�x�c���w���͂��قǏd�v�Ȓn�ł͂Ȃ��B�C�G�X�͋~����Ƃ͔F�߂��Ă��Ȃ��B�C�X���G�����A�x�c���w����A�n��̂܂܂ɂ��Ă���̂́A�@����̏d�v�������قǂł��Ȃ����炾�낤�B�G���T�����̂悤�ɁA���_�����ɂƂ��ďd�v�Ȓn��ł���A�����̎v�f�Ȃǖ������Ă킪���̂Ƃ��Ă��锤�ł���B
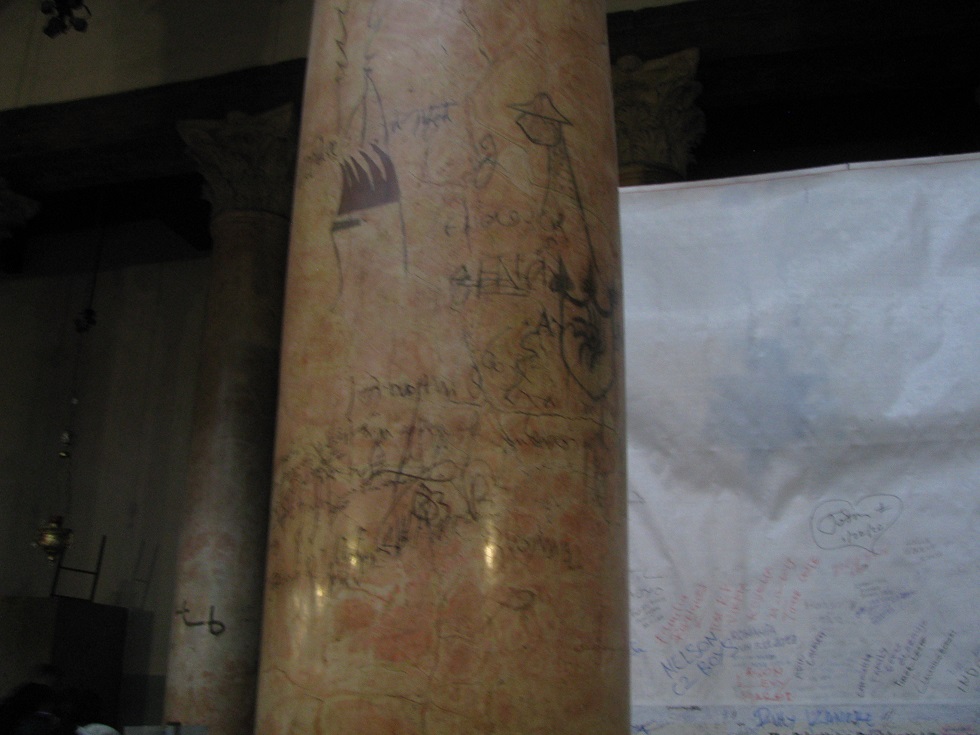


 �@����ɏo�Ă���x�c���w���ŋL���ɂ���̂́u���c�L�v�ŁA�{�A�Y�ƈٖM�̏����c�Ƃ̈��������B����̂Ȃ��ł��A�w�܂�̐S���܂�}�b�ŁA�ނ�̑\�����_�r�f�ƂȂ�B
�@����ɏo�Ă���x�c���w���ŋL���ɂ���̂́u���c�L�v�ŁA�{�A�Y�ƈٖM�̏����c�Ƃ̈��������B����̂Ȃ��ł��A�w�܂�̐S���܂�}�b�ŁA�ނ�̑\�����_�r�f�ƂȂ�B
�@�Ñネ�[�}�鍑�́A�قڎO���I�ɂ킽���ăL���X�g���𔗊Q�����������A�M�҂͑��������������B���ɁA�K�����E�X�邪311�N�Ɋ��e�߂��o���A313�N�ɂ́A�R���X�^���e�B�k�X��Ɠ����҃��L�j�E�X���A�L���X�g�������F����u�~���m���߁v���o���Ɏ������B�������A���̒i�K�ł́A���̂��ׂĂ̏@���ƂƂ��Ɍ��F���ꂽ�����ɉ߂��Ȃ��B�R���X�^���e�B�k�X��́A�L���X�g���ɉ��@�����ŏ��̍c��ƂȂ����B�����̍c��ɕ�������Ă����鍑���ē��ꂵ�A��Ɍ��V�@������̏̍���^�����Ă���B�R���X�^���`�m�[�v���i���C�X�^���u�[���j�����݂����c��ł�����B

 �@380�N�A�e�I�h�V�E�X�邪�L���X�g�������[�}�鍑�̍����Ɛ錾�A392�N�ɂ̓L���X�g���ȊO�̏@���ւ̐M���֎~���ꂽ�B�����ł͂��߂āA�L���X�g�������[�}�鍑�B��̏@���ƂȂ����̂ł���B
�@380�N�A�e�I�h�V�E�X�邪�L���X�g�������[�}�鍑�̍����Ɛ錾�A392�N�ɂ̓L���X�g���ȊO�̏@���ւ̐M���֎~���ꂽ�B�����ł͂��߂āA�L���X�g�������[�}�鍑�B��̏@���ƂȂ����̂ł���B
�@���a����́A�C�G�X���a�̒n�ƐM�����Ă���B���[�}�c��R���X�^���e�B�k�X�̕�w���i�̍��]�ŁA325�N�ɍc�邪���Ă��B�ނ̉��@�́A�_�̌[�����Đ퓬�ɏ��������̂����������ƌ����Ă��邪�A��w���i�̉e�������������̂��낤�B�x�c���w����G���T�����Ɏc�鑽���̐��n�́A���̑唼���w���i�����肵�Ă���B

 �@�C�G�X�̒a����V���ɂ��ǂ�ƁA�i�U���ɏZ�ރ��Z�t�ƃ}���A�́A�l�������̂��߃x�c���w���֗����Ƃ���B�����ł́c�}�����������āA���q�����ݔV��z�ɕ�݂Ĕn���ɉ炳������B���ɂɂ���|�Ȃ��肵�̂Ȃ�i�u���J�������v2�F7-8�j�B���_�_�҂ł���킽���ɂ́A���̂悤�ȏꏊ���A�O�S�N�ȏ���o������œ���ł�����̂��ƁA���v���Ă��܂��B�M�͂ǂ�Ȃ��Ƃł��\�ɂ���B���̂��Ƃ��A�킽���͖Y��Ă���B
�@�C�G�X�̒a����V���ɂ��ǂ�ƁA�i�U���ɏZ�ރ��Z�t�ƃ}���A�́A�l�������̂��߃x�c���w���֗����Ƃ���B�����ł́c�}�����������āA���q�����ݔV��z�ɕ�݂Ĕn���ɉ炳������B���ɂɂ���|�Ȃ��肵�̂Ȃ�i�u���J�������v2�F7-8�j�B���_�_�҂ł���킽���ɂ́A���̂悤�ȏꏊ���A�O�S�N�ȏ���o������œ���ł�����̂��ƁA���v���Ă��܂��B�M�͂ǂ�Ȃ��Ƃł��\�ɂ���B���̂��Ƃ��A�킽���͖Y��Ă���B
�@�C�G�X�̒a���ɂ��ẮA����u�C�U�����v�c���Ƃߛs�݂Ďq�����܂�A���̖����C���}�k�G�����i���ׂ��i7�F14�j�A�ɗa������Ă���Ƃ���B

 �@�����}�b���C�X�������ɂ�����B�V��u���n�l�������v���`����C�G�X�̌��t�c��ꕃ�ɐ����A���͑��ɏ�����������āA�i���ɓ���Ƙ�ɋ��炵�ߋ����ׂ��B����͐^���̌��Ȃ�A���͂�����邱�Ɣ\�킸�A����������A�܂��m��ʂɗR��B�Ȃ�͔V��m��B�ނ͓���Ƙ�ɋ���A�܂�����̒��ɋ������ׂ���Ȃ�B��Ȃ���₵�Čǎ��Ƃ͂����A����ɗ�����Ȃ�i14�F16-18�j�B���́u�^���̌��v�����n���}�h���Ƃ����B������u�R�[�����v�i�䓛�r�F��A��g���Ɂj�ŗ��t����ƁA
�@�����}�b���C�X�������ɂ�����B�V��u���n�l�������v���`����C�G�X�̌��t�c��ꕃ�ɐ����A���͑��ɏ�����������āA�i���ɓ���Ƙ�ɋ��炵�ߋ����ׂ��B����͐^���̌��Ȃ�A���͂�����邱�Ɣ\�킸�A����������A�܂��m��ʂɗR��B�Ȃ�͔V��m��B�ނ͓���Ƙ�ɋ���A�܂�����̒��ɋ������ׂ���Ȃ�B��Ȃ���₵�Čǎ��Ƃ͂����A����ɗ�����Ȃ�i14�F16-18�j�B���́u�^���̌��v�����n���}�h���Ƃ����B������u�R�[�����v�i�䓛�r�F��A��g���Ɂj�ŗ��t����ƁA
�c�}�������i�}�����j�̎q�C�[�T�[�i�C�G�X�j���������������̂��ƁA�u����A�C�X���G���̎q���A�킵�̓A�b���[�Ɍ��킳��Ă��O�����̂��Ƃɗ������́B�킵���O�Ɂi�[�����ꂽ�j���@���m���A���킵�̌�Ɉ�l�̎g�k�������Ƃ������������M��`���ɗ������́B���́i�g�k�j�̖��̓A�t�}�h�i�A�t�}�h Ahmad �̓}�z���b�g�̌��� Muhammad �Ƃقړ��`�B�j�v�Ɓi61.�u���v6�j�B
�@���_�_�҂ɂ́A�ǂ�������Еt���ɖZ�����ƁA���X���܂��������Ȃ�B
�i�����ł̃J�b�R���̌��t�́A��҂��ǎ҂̗����������邽�߂ɕ⑫�������́B�R�[������114�̏͂���Ȃ�B�Ȍ�A�R�[���������p����ꍇ�́A�ŏ��ɏ͔ԍ��A�薼�A�Â��ċ�ԍ���\�L����B�Ȃ��A�̓��n���}�h��ʏ̂̃}�z���b�g�ƕ\�L���Ă���A���p���͌����ʂ�}�z���b�g�Ƃ���B�j
�@2019�N12��2���t����AP�ʐM�́A�o�`�J���ɕۑ�����Ă����n���̔j�Ђ��A�x�c���w���֕Ԃ��ꂽ�ƕ����B�ؕЂ́A�ؗ�ɑ������ꂽ�e��ɔ[�߂��Ă���B1400�N�O�A���̒n���烍�[�}���c�֑���ꂽ���̂��ƌ����B�t�ǂ݂���A�ؕЂ��������ꂽ�̂̓C�G�X���a��A6�`7���I��Ƃ������ƂɂȂ�B�M�͕s�\���\�ɂ���B�@
�G���T����
����
�@�_�r�f����\�������̎���i�O1000�`�O900�N���j���A�Ñ�C�X���G���̉������������B�C�X���G������̉��T�E���̐Ղ��p�����̂̓_�r�f�ł���B�ނɂ́A�������̈�b���c��B���N����A�y���V�e�̋��l�S���A�e���A�����œ|�����B���l�b�T���X���A�~�P�����W�F���������ł���������ɕ\�������B����ɏ��钤���͂Ȃ��B
�@�_�r�f�́A��勭���A�G�W�v�g�ƃA�b�V���A�̐��ނɏ悶�āA�G�W�v�g�������烆�[�t���e�X��ɐڂ���L��ȗ̈�𐪕������B����ŁA�E�����̍ȃo�e�V�o�̓�������p�����ė~���Ƃ������₩�Ȃ�ʃG�s�\�[�h������B�E�����͔ނ̔z���̕����������B�ނ́A�E��������Ŏ��ɒǂ����A���S�l�ƂȂ����o�e�V�o���ȂɌ}�����ꂽ�B���R�_��������B�_�r�f�̎q�A�u�T�����́A���ɔw���Ă��т��є������N�������B�_�r�f�͑��q�Ɛ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��H�ڂɊׂ�B�A�u�T�����̓_�r�f�̕����ɎE�����B�������_�r�f�́A�c�킪�q�A�u�T������A�킪�q�A�킪�q�A�u�T������A�Ă����ɑ��Ď��ɂ������̂��A�A�u�T�����A�킪�q��킪�q��i�u�T���G���㏑�v18�F33�j�A�ƒQ���B
�@�_���͑����B�ނƃo�e�V�o�̍ŏ��̎q�͑��������B���ƋQ�[���C�X���G�����P�����B�������_�́A�[�����������_�r�f�������B
 �@�G���T�����������̎�s�ƒ�߂��̂̓_�r�f�ł���B�ނƃo�e�V�o�Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ�\���������A���̉��ƂȂ�B�Ⴂ����̔ނ͌����Ō����ȉ��������B�u�I����v�ɂ́A
�@�G���T�����������̎�s�ƒ�߂��̂̓_�r�f�ł���B�ނƃo�e�V�o�Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ�\���������A���̉��ƂȂ�B�Ⴂ����̔ނ͌����Ō����ȉ��������B�u�I����v�ɂ́A
�@�c�G�z�o��̖��Ƀ\�������Ɍ��ꋋ����A�_�������܂�����͉䉽������o���ׂ����B�i�����A�\�������́A�_�ɏj�����ꂽ���������ɓ������ׂ����ƁA�G�z�o�ɂЂ�����肤�j�����ʂ�S��l���o���ē��̖���摂��߁A������đP���ʂ邱�Ƃ����߂��܂��A�N�����̍��쑽������摂����Ƃ�Ɓi3�F5-9�j�B�c�Ƃ���B����́A�Ȃ̕x�Ⓑ���ł͂Ȃ��A�����K���ɂ���q�b�����߂��B�_�G�z�o�́A���̂悤�ȃ\�����������ł��B
�@�����Ĕނ́A�G���T�����ɑs��Ȑ_�a��z���B�u�I����v��6�͂ɂ͂��̃X�P�[�����L�q����Ă��邪�A�L���r�g�Ƃ����P�ʂȂ̂ł킩��ɂ����B���[�g���@�ɂȂ����ƁA�����悻��10���[�g���A����15���[�g���A���s��30���[�g���قǂ炵���B���z�ɂ�7�N��v�����B����őN�₩�ɏ����A�������ɂ͌_��̔����^�э��܂ꂽ�B�_��̔��i���C�j�ɂ́A���[�Z���V�i�C�R���玝���A�����Ƃ����Δ��[�߂��Ă���B
�@�\�������̐_�a�́A�O587�N�o�r���j�A�ɔj�ꂽ�̂ŁA���_�a�ƌĂ�Ă���B
�@�\�������͌o�ςɂ����邭�A���Ղō���x�܂����B���܂��G�W�v�g����}���A�a�����ێ������B�ނ̉b�q�̗�Ƃ��āA��l�̏�����l�̎q���߂����đ����剪�ق��̂悤�Șb������B�������A�^�����̂͑剪�ق��̕��ł���B�L���ȃV�o�̏����Ƃ̑}�b�́A�����u�I����v��10�́A�u���u�����v��9�͂Ɍ���Ă���B�c�V�o�̏����\�������̕������y�ѓ������ă\�����������݂�Ɓi�����j�A�\�������̒m�炸���ē������鎖�͖��肫�i�u���u�����v9�F1-2�j�B�����j���Ƃ��Ă̌𗬂̘b�͐����ɂ͂Ȃ��B
�@�����ɉb�q�ɖ������\�������ƌ����ǂ��l�̎q�ł���B�h�s���ɂ߂������̔ɉh�ɁA�ނ̐S�͊ɂ݂�������B�u�I����v��11�͂ɂ́A�c�\���������A�p���i�t�@���I�j�̏��̑��ɑ����̊O���̕w������B�i�����j�G�z�o�\�Đ����̍����ɂ��ăC�X���G���̎q���Ɍ����������炭�A�����͔ޓ��ƌ���ׂ��炸�A�i�����j�ޓ��K�������̐S��]���Ĕޓ��̐_�X�ɏ]�킵�߂�ƁB������Ƀ\�������ޓ��������ė��ꂴ�肫�B�ށA�܌��厵�S�A�l�O�S�l����i11�F1-3�j�A�Ƃ���B�l�͑����ƍl���Ă������낤�B���͂̍��X�Ƃ̗Z�a��}��ړI���������ɈႢ�Ȃ����A����ɂ��Ă��ُ�Ȑ����ł���B�h�̖��ɓM�ꋝ�y�ɒ^�����ƌ����Ă��d�����Ȃ��B��ꋉ�̕����l�������ނ́A�K�R�I�ɑ��̏@���ɂ����e�������B�܂⑤���ɂً͈��k�����������B�@���S�̋������_���̐l�тƂɁA���ւ̋^�O���������̂����R�ƌ����悤�B�ؗ�Ȑ_�a�≤�{�̌��݂́A�l�X�ɏd�ł��ۂ����ʂƂȂ����B�����̕s���͕��B�����āA���Ƃ̔j�]�̓\�������̎���ɖK�ꂽ�B
�@�ނ̎q���n�x�A���̎���A�C�X���G�������͓�k�ɕ����B��̃��_�����̓G���T��������s�Ƃ��A�k�̃C�X���G�������̓T�}���A����s�ƒ�߂��B�I���O930�N���̂��Ƃł���B���Ĕe���𑈂��A�Ƃ��ɑ̗͂������B�k�̃C�X���G�������͑O722�N�A�A�b�V���A�ɖłڂ��ꂽ�B���_�����̓A�b�V���A��G�W�v�g�ɕ�������`�ő����������A�O597�N�ƑO586�N�̓�x�ɂ킽���āA�o�r���j�A�ɐ������ꂽ�B�o�r���j�A�̉��̓l�u�J�h�l�U���ł���B���_�����̓G�W�v�g�ƌ���Ńo�r���j�A�ɑR���悤�Ƃ����B�l�u�J�h�l�U���͂���������Ȃ������B�G���T�����͉��サ�A�\�����������Ă��_�a�͓O��I�ɔj�ꂽ�B�x�z�҂�_�������̓o�r���j�A�ɘA�s���ꂽ�B������o�r�����̕ߎ��Ƃ����B�������U���Ӗ�����f�B�A�X�|���Ƃ������t�́A�؋���ɂ��g���邪�A�啶���Ŏn�܂�
Diaspora �Ə������ꍇ�́A�C�X���G���E�p���X�`�i�̊O�ŕ�炷���_���l�W�c���w���ŗL�����ƂȂ�B
�@�o�r���j�A�̔ɉh�͒Z�������B�O538�N�A�y���V���ɂ���Ėłڂ����B���_���̐l�тƂ͋A���������ꂽ���̂́A�����܂ł��y���V���̎x�z���ɂ���Ƃ��������̂��Ƃ������B�����Ƃ��A���R�ӎv�Ŏc�������҂����������B�f�B�A�X�|���Ƃ������t����z������قǁA���S�n�̈�����炵�ł͂Ȃ������炵���B�u�_�j�G���L�v�ɂ́A�a���҃_�j�G�����o�r���j�A�{��ŏd���p����ꂽ���Ƃ��L�q����Ă���B
�@�A���������_���l�����̓[���o�x���̎w���̂��ƁA�_�a���Č������Ղ��s�����i�u�G�Y�����v3�F2-3�j�B�y���V�����_���C�I�X�ꐢ�����A�O515�N�̂��ƂƂ����B�y�g���Ƀi�o�e�A������Z���n�߂�����ɑ������邾�낤�B


 �@�o�r�����ߎ��̈�l�A�l�w�~�A�̓y���V���{��ō����n�ʂɂ���A��ꎟ�A���������ꂽ�Ƃ��ɂ͎c���g�������B�G���T�����̏�ǂ��j�ꂽ�܂܂��ƒm�����ނ́A�y���V�����ɋA�����肢�o���B�A���^�N�Z���N�Z�X�ꐢ�͂��̊肢������A�ނƂ��ċA���������B�ނ́A���܂��܂ȏ�Q���������A52���ŏ�ǂ��C�������i�u�l�w�~���L�v6�F15�j�B�܂��A����5��14�ɂ́A12�N�̊ԁA�������Z������Ƃ��Ă̕�V�����Ȃ������Əq�ׂ��Ă���A��قnjȂɌ������l�������̂��낤�B
�@�o�r�����ߎ��̈�l�A�l�w�~�A�̓y���V���{��ō����n�ʂɂ���A��ꎟ�A���������ꂽ�Ƃ��ɂ͎c���g�������B�G���T�����̏�ǂ��j�ꂽ�܂܂��ƒm�����ނ́A�y���V�����ɋA�����肢�o���B�A���^�N�Z���N�Z�X�ꐢ�͂��̊肢������A�ނƂ��ċA���������B�ނ́A���܂��܂ȏ�Q���������A52���ŏ�ǂ��C�������i�u�l�w�~���L�v6�F15�j�B�܂��A����5��14�ɂ́A12�N�̊ԁA�������Z������Ƃ��Ă̕�V�����Ȃ������Əq�ׂ��Ă���A��قnjȂɌ������l�������̂��낤�B
�@�u�G�Y�����v��7�͂ɂ́A�G�Y���̎w���̂��ƁA��x�ڂ̏W�c�A�����s��ꂽ�ƋL�^����Ă���i7�F13�j�B�O458�N�ɑ�������B���̓�l�̌��i�Ȏw���҃l�w�~�A�ƃG�Y���̎���A���_���̍��̂�����A���_�����̍�������܂����B���_�������ȊO�Ƃ̌������ւ����i�u�G�Y�����v9�F11-12�j���ƂŁA���_�������̓Ǝ������f�B�A�X�|���̍Œ��ɂ����Ă��ێ����ꂽ�B����̃C�X���G���ɂ܂ő傫�ȉe�����c�����ƌ�����B�����Ƃ����_�_�҂̂킽���́A�u���c�L�v�ɓo�ꂷ�郋�c�͈ٖM�l�������ł͂Ȃ����Ɩ������o���Ă��܂��̂����c�B
�@�����̃y���V���́A�G�W�v�g�����̂����͂��֎����A�Ő}�̓M���V�A�����ɂ܂ŋy�B�ĎO�ɂ킽���đ�R��h���������A�X�p���^�̊拭�Ȓ�R�Ő����ɂ͎���Ȃ������B���̕��̂悤�ɁA�O333�N�A�A���N�T���h���X�剤���y���V���𐪕������B�p���X�`�i�̒n���A�M���V�A�̎x�z���ɓ������B�A���N�T���h���X�剤�̎���A�z���̏��R�����́A�e�n�Ńw���j�Y���F�̋���������z�����B�Z���E�R�X���i�V���A�j�ƃv�g���}�C�I�X���i�G�W�v�g�j���A�p���X�`�i�̒n�������Ďx�z���𑈂����B�O198�N�A�Z���E�R�X�������̒n�̎x�z�����m�����A�����Ɍ����������B�Z���E�R�X���́A�y���V���ƈقȂ�@���ɂ͕s���e�������B�w���j�Y���������V���A�̉����́A���_���̐l�тƂɃG���T�����_�a�łً̈����q�i�M���V�A�̐_�X�j�����v�����B
�@�Z���E�R�X���ւ̔��������߂����_���̐l�тƂ́A�Վi�}�J�o�C�Ƃ̃}�^�e�B�A�Ƃ��̑��q�����𒆐S�ɁA�O167�N�A�������N�������B�}�^�e�B�A�̎�����퓬�͌p�����A�O164�N�ɃG���T�����_�a��D���B�����đO143�N�A���ɃZ���E�R�X���̉e����E���āA�}�J�o�C�Ƃɂ��x�z���m�������B�o�r���j�A�ɐ�������Ĉȗ��A�l�S�N�ȏ�̔N�����₵�Ă悤�₭�Ɨ��������B�}�^�e�B�A�̑]�c���̖����Ƃ��ăn�X�������Ƃ����B
�@���{�̏��X�ň�ʓI�ɔ����Ă��鐹���ɂ́A���̃C�X���G���ɂƂ��Čւ炵���͂��̋L�^���܂܂�Ă��Ȃ��B�u�}�J�o�C�L�v�̈������A�J�g���b�N�ƃv���e�X�^���g�ł͈قȂ�B�v���e�X�^���g�ł͊O�T�Ƃ���iWikipedia�j�A�J�g���b�N����ŗp���鐹���ł͐��T�����ł���B��O���ɂ́A���̌o�܂��������邵���Ȃ��B
�@�n�X�������̎����������͂Ȃ��B�V�������a�����[�}�����͂��}���ɐL���Ă��Ă����B�O63�N�A�|���y�C�E�X���V���A�̃Z���E�R�X����łڂ��B�n�X�������́A���[�}�̃V���A���B�̈ꕔ�Ƃ��āA������x�̎�����F�߂��Ȃ��琶���c��B���a�����[�}�́A�J�G�T�����ÎE���ꂽ��A�N���I�p�g��Ƃ̈��ɓM�ꂽ�A���g�j�E�X���A�N�e�B�E���̊C��Ŕs��A�A�E�O�X�g�D�X���ŏI�̏����҂ƂȂ�B�A�E�O�X�g�D�X�͏���c��ƂȂ�A���a�����[�}�͒鍑�ƂȂ����B�c��͎���_�i�������̂��P��ƂȂ����B
�@�n�X�������̕����̈�l�w���f���A�����ɏ悶�ăn�X��������|���A�O37�N�w���f�����n�܂����B�Ƃ͂����A�����܂ł����[�}�̌�돂�������Ă̂��Ƃł���B�ނ́A��ɑ��q�����Ƌ�ʂ��邽�ߑ剤�Ə̂���ꂽ���A���̖��ɂӂ��킵���Ɛт��������킯�ł͂Ȃ��B�ނ́A�����ȃ��_���l�ł͂Ȃ������B�n�X�������̕P�}���A���l��܂Ɍ}���A����̐��������m�������B�ȋ^�S�ɖ������w���f�́A�s�v�ƂȂ����n�X�������̐l�X�����X�ɎE�Q���čs�����B�����āA�O4�N�A���悻70�i���N���s���j�Ō��܂݂�̐��U���I�����B
�@�ނ̋ƐтƂ��ẮA�G���T�����̐_�a��{�a�̑���z��������ׂ����낤�B�{�a�͔��Ηv�ǂƉ����Ă����B���z���ꂽ�_�a�́A�\�������̂���ƑΔ䂵�āA���_�a�ƌĂ��B���̑s�킳�́A���[�}�鍑�̓��O�Ɍ��`���ꂽ�B�f�B�A�X�|���̃��_���l�݂̂Ȃ炸�A�_���l�܂ŃG���T������K�ꂽ�Ƃ����B
�@���z�ɂ͕��X�Ȃ�ʊS���������炵���B�����̖����������v�Ǔs�s�w���f�B�I�����v�ǃ}�T�_�ȂǁA�܂̍Ԍ��{�a���\�z���Ă���B���̂����A���J�[�E�B���̍Ԃ͔ނ̎q�w���f�E�A���e�B�p�X������҃��n�l��H�����ꏊ�ł͂Ȃ����Ɛ��肳��Ă���B
�@���[�}�鍑�́A���_�����̏̍����w���f�̑��q�����ɗ^�����A�����������B�G���T�����A�T�}���A�n�����w���f�E�A���P���I�X�A�y�����ƃK���������w���f�E�A���e�B�p�X�A�S�����ƃ����_���쓌�݂��w���f�E�t�B���b�|�X�����ꂼ�ꓝ�������B���̌ネ�[�}�́A�G���T�����A�T�}���A�n�������߂�A���P���I�X���A�����\�͂Ɍ�����Ƃ��č~�i�����B�G���T�����A�T�}���A�n���̓��[�}�����ړ����ƂȂ��ăC�G�X�̎�����}����B
�@�V���ɓo�ꂷ��w���f�́A�c���s�E�̃w���f�剤�ƁA���̑��q�̈�l�A�y�����A�K�����������߂�w���f�E�A���e�B�p�X�̓�l�ł���B
�V��
�C�G�X�̎���
�@�V���ɂ��A�C�G�X���x�c���w���Ő��܂ꂽ�Ƃ��A���̔��m�������w���f����K�˂Ă����B�u���_���̉��Ƃ��Đ��܂ꂽ���͉����ɂ�����̂��v�Ƃ������m�����̌��t�ɁA�w���f�͎����̒n�ʂ��������҂��N���Ƌ^�O������A���m�����ɋA�r�{��֗������悤���B���m�����́A�Ӑ}�I�ɕʂ̓���ʂ��ċA�����B
�@�c�����Ƀw���f�A���m�������ς��ꂽ��ƌ��āA�r������������A�l�����킵�A���m�����ɗR��ďڍׂɂ��������v��A�x�c���w���y�і}�Ă���粂̒n���Ȃ��Έȉ��̒j�̎������Ƃ��Ƃ��E����i�u�}�^�C�������v2�F16�j�B
�@�����ɓo�ꂷ��c�s�ȉ��́A�w���f�剤�ł���B�������̗c���E�Q�ɂ͔ᔻ�I����������B�}�^�C�`�ȊO�̕������ɂ͂��̂悤�ȋL�q���Ȃ��A���̈�ʓI�ȗ��j���ɂ��L�^���Ȃ��B�������ɗc���E�����������Ƃ��Ă��A�����̃x�c���w���̐l���͂�������300�l���x�ŁA���ۂɎE���ꂽ�c���̐��́A�ǂ�Ȃɑ������ς����Ă�20�`30�l���x�ł͂Ȃ����iWikipedia�j�A�Ƃ����^��ł���B
�@����̓C�G�X�̒a������n�܂�B�ȑO��Before Christ = BC,�Ȍ��Anno Domini
= AD �i���e����Łu��炪��̔N�v�j�ƋL���B�w���f�剤�͑O4�N�Ɏ���ł���A�����ɍl����C�G�X���a�������Ƃ��ɂ͐����Ă��Ȃ����ƂɂȂ�B��������A�C�G�X�̒a���͑O5�N���A6�N���낤�Ƃ��������o�Ă���B
�@�v����ɁA��ٍ��m���A�c���s�E���A�ڂ����炽�Ăċᖡ����K�v�͂Ȃ��B�C�G�X�Ƃ����l�����݂��A���̑�n����݁A��������������Ƃ��d�v���Ǝv�����@���Ȃ��̂��낤���B

 �@�V���ɂ͎l�̕�����������B���̂�������A�a���Ȍ㕟��������n�߂�܂ł́A���悻30�N�Ԃɂ��Ă̋L�q���܂��ƂɖR�����B�u���J�������v�ɁA12�Ύ��̃C�G�X�̐_���Ԃ肪�A�킸���Ɍ���Ă���ɉ߂��Ȃ��B�L�q�ɏ]���ƁA�C�G�X�̗��e�͂킪�q���������A�T�����������A�G���T�����̋{�a�ɂ����Ƃ��������B�C�G�X�͋��t�Ɩⓚ���Ă����B��͌����B�c�u���̕��Ɖ�ƗJ���Đq�˂���v�B�C�G�X�������܂��B�u���̂���q�˂��邩�A��͂킪���̉Ƃɋ���ׂ���m��ʂ��v�i2�F48-49�j�B���e�Ƃ��A�C�G�X�̓����̐^�̈Ӗ������Ȃ������A�Ƃ���B
�@�V���ɂ͎l�̕�����������B���̂�������A�a���Ȍ㕟��������n�߂�܂ł́A���悻30�N�Ԃɂ��Ă̋L�q���܂��ƂɖR�����B�u���J�������v�ɁA12�Ύ��̃C�G�X�̐_���Ԃ肪�A�킸���Ɍ���Ă���ɉ߂��Ȃ��B�L�q�ɏ]���ƁA�C�G�X�̗��e�͂킪�q���������A�T�����������A�G���T�����̋{�a�ɂ����Ƃ��������B�C�G�X�͋��t�Ɩⓚ���Ă����B��͌����B�c�u���̕��Ɖ�ƗJ���Đq�˂���v�B�C�G�X�������܂��B�u���̂���q�˂��邩�A��͂킪���̉Ƃɋ���ׂ���m��ʂ��v�i2�F48-49�j�B���e�Ƃ��A�C�G�X�̓����̐^�̈Ӗ������Ȃ������A�Ƃ���B
�@�ނ̐����̐߁X����A����Ɋւ�����X�Ȃ�ʒm�������������Ƃ͐���ł��邪�A�ނ��ǂ��ŏC�Ƃ����̂��F�ڂ킩��Ȃ��B���F�[�_�Ɏ�������������A����ȂƂ��납��A�C���h�C�Ɛ��܂ł���B
�@���̋̂����ŁA�C�G�X�a���̎��ɗ���d�v�ȑ}�b�́A����҃��n�l�̊����̋L�q�ƂȂ�A���R�T�������o�ꂷ��B�������A�����ɂ́A�u�}�^�C�������v14�͂�u�}���R�������v��6�͂Ƀw���f���̖��Ƃ��ēo�ꂷ��݂̂ŁA�ޏ��̖��O�͑��̔N��L����m�肳�ꂽ���̂ł���B
�@�w���f�剤�̑��q�̈�l�A�w���f�E�A���e�B�p�X�̓y�����ƃK�������̗̎傾�����B�]���āA�ނ�����҃��n�l�����ɓ������͂˂��̂̓y�����ɋ߂����J�[�E�B���̍Ԍ��{�a�ƍl�����Ă���B�����̓����_���쓌�݂Ɉʒu���A�c�O�Ȃ��獡��̗��̖K��n�ɂ͊܂܂�Ă��Ȃ��B
�@�C�G�X���A�G���T�����ɓ��邵���Ƃ��A���Ă��Č}�����l�X�́A�~���傪���ꂽ�Ǝv�����B�ނ��a�҂��������A���҂�h�点��ȂǁA���X�̊�Ղ��s�������Ƃ����`���ɓ`����Ă����B
�@�c�C�G�X�{�ɓ���A���̓��Ȃ�}�Ă̔�������҂𐋂������A���ւ���҂��i�E����҂̍��|��|���āi�u�}�^�C�������v21�F12�j�A�c�Ƃ����p��ڂ̓�����ɂ����l�X���������Ȃ��͂����Ȃ��B
�@�������C�G�X�́A�G���T��������̑O�ɁA��q�����Ɍ������Ă��������Ă���B�c���͋~����L���X�g�ł���A�G���T�����ɍs���A���V�E�Վi���E�w�҂��葽���̋����A���E����A�O���ڂ��S��i�u�}�^�C�������v16�F21�j�A�ƍ����Ă���B���̂��ƂO�͒m��Ȃ��B
�@�C�G�X�̕ϗe�ɂ��Ắu�}�^�C�������v��17�́A�u�}���R�������v��9�́A�u���J�������v��9�͂ɋL�q������B���炪�L���X�g�ł��莀�̓������ł��邱�Ƃ������Ă���8������߂��Ă���B�u���J�������v�ɂ��c�y�e���A���n�l�A���R�u�𗦂���A�F���ƂĎR�ɓo�苋���B�����ċF�苋���قǂɁA���̏��A���̈ߔ����Ȃ�ċP����B����A��l�̐l����ăC�G�X�Ƌ��Ɍ��B����̓��[�Z�ƃG�����ƂɂāA�h���̂����Ɍ��͂�A�C�G�X�̃G���T�����ɂĐ�����Ƃ�������̂��Ƃ���������Ȃ�i9�F28-31�j�B�o�`�J���ɂ��郉�t�@�G���̊G���A�����ɂ��̊�Ղ�\�����Ă���B
�@����Ǝ����_��̌����A�C�X�������̌o�T�u�R�[�����v��17�́u��̗��v�ɂ���B

 �@�c�����Ȃ�Ɩܑ̂Ȃ����L����Ƃ��A�i�A�b���[�j�͂��̖l�i�}�z���b�g�j��A��Ė�i��j������A���Ȃ��q���i���b�J�̐_�a�j����A���́A���i�A�b���[�j�ɂ��������߂�ꂽ���u�̗�q���i�G���T�����̐_�a�j�܂ŗ����āA���̐_����ڂ̂�����q�܂��悤�Ƃ��������B�܂��ƂɎ������A�S�Ă�������������_�B
�@�c�����Ȃ�Ɩܑ̂Ȃ����L����Ƃ��A�i�A�b���[�j�͂��̖l�i�}�z���b�g�j��A��Ė�i��j������A���Ȃ��q���i���b�J�̐_�a�j����A���́A���i�A�b���[�j�ɂ��������߂�ꂽ���u�̗�q���i�G���T�����̐_�a�j�܂ŗ����āA���̐_����ڂ̂�����q�܂��悤�Ƃ��������B�܂��ƂɎ������A�S�Ă�������������_�B
�@���̃G���T�����̐_�a�Ƃ����̂��A�_�a�̋u�ɂ����̃h�[���ł���B�C�X�������k�ȊO����ł��Ȃ��B��т̓C�X���G���R�̎x�z���ɂ���A���R�ȎQ�q��]�ރC�X�������k�Ƃ̊Ԃł����������₦�Ȃ��B�����̗��s�͈��S���̃p�b�P�[�W�ł���B��̃h�[����A���E�A�N�T�[���@�́A�I���[�u�R�̓W�]�䂩��]���������������B

 �@���k�łȂ��҂ɂƂ��āA�_�a���珤�l������ǂ������D�u����C�G�X�ƁA�ڂɑł���ď\���ˏ�Ŏ��ʂ݂��߂ȃC�G�X�Ƃ̊u����͂��܂�ɂ��傫���B���Ȃ����Ƌ^��������Ă��܂��B���ׂẮA����ɏ����ꂽ�a���̍Č����Ƃ����̂����A�M������ȑO�Ɂu�T���v�̂ł���B�������A�������邱�ƂƐM���邱�Ƃɂ͓V�n�قǂ̊J��������Ƃ͕S�����m�ł͂��邪�c�B
�@���k�łȂ��҂ɂƂ��āA�_�a���珤�l������ǂ������D�u����C�G�X�ƁA�ڂɑł���ď\���ˏ�Ŏ��ʂ݂��߂ȃC�G�X�Ƃ̊u����͂��܂�ɂ��傫���B���Ȃ����Ƌ^��������Ă��܂��B���ׂẮA����ɏ����ꂽ�a���̍Č����Ƃ����̂����A�M������ȑO�Ɂu�T���v�̂ł���B�������A�������邱�ƂƐM���邱�Ƃɂ͓V�n�قǂ̊J��������Ƃ͕S�����m�ł͂��邪�c�B
�@���l������_�a����ǂ��o���Ƃ����X�����o��������C�G�X�́A���_�̎�����ŕ߂炦���ٔ��ɂ�������B���̂Ƃ����[�}�鍑���_�����s���g�ƃw���f���Ƃ̊ԂŁA�ӔC����̂���肪����B���̃w���f�́A����҃��n�l�̎���͂˂��w���f�E�A���e�B�p�X�ł���B�y�����A�K�������̓����҂ł���ނ́A���܂��܂��̂Ƃ��G���T�����ɑ؍݂��Ă����B�����邱�Ƃ̂Ȃ��������Ɏc�����B
�@�G���T�����ł́A�C�G�X���\���˂�w�����ĕ����S���S�_�ւ̓��E���B�A�E�h�����[�T�i�߂��݂̓��j��H���āA�����拳��Ɍw�ł��B�C�G�X�̋ꂵ�݂�Ǒ̌����鏄��s�ł���B
�C�G�X�v��
�@���[�}�c��R���X�^���e�B�k�X���̕�w���i���A����̗��ŃG���T�������������Ƃ��A�\���˂��A�S���S�_�̋u�Ɠ��肵�ċ�������Ă��B4���I�̂��Ƃł���B�u���̂��̂�����ŕ����Ă���B

 �@�L���X�g���ɂ͑����̏@�h������A�e�h�������拳��̊Ǘ����𑈂��Ă����B���قɓ������I�X�}���E�g���R�́A1852�N�u�X�e�C�^�X�E�N�I�i����ێ��j�v�̒��߂��o�����B���݂Ɏ����Ă��A����������̖���J���̂̓��X�����̏��N�ƌ��܂��Ă���B�C�X�������k�ɂ�钇�قƂ����̂��A���݂̂Ƃ��Ƃ��������������݂�Ƃ����b�̂悤�Ɏv����B���ꂪ����ɂ��Č��ł��Ȃ����̂��낤���B
�@�L���X�g���ɂ͑����̏@�h������A�e�h�������拳��̊Ǘ����𑈂��Ă����B���قɓ������I�X�}���E�g���R�́A1852�N�u�X�e�C�^�X�E�N�I�i����ێ��j�v�̒��߂��o�����B���݂Ɏ����Ă��A����������̖���J���̂̓��X�����̏��N�ƌ��܂��Ă���B�C�X�������k�ɂ�钇�قƂ����̂��A���݂̂Ƃ��Ƃ��������������݂�Ƃ����b�̂悤�Ɏv����B���ꂪ����ɂ��Č��ł��Ȃ����̂��낤���B
�@�w���f�剤���z�����{�a����ǂ��j�ꂽ�̂�70�N�A���_���l�ɂ�锽���i��ꎟ���_���푈�j�����[�ł���B�e�B�g�D�X�����郍�[�}�R��������������A�_�a��O��I�ɔj���B�����R�̈ꕔ�̓}�T�_�̍Ԃɓ���A73�N�ɋʍӂ���܂Ő킢�������B�e�B�g�D�X�͌�ɍc��ƂȂ�B
�@
 ���[�}�鍑��������܌���̎O�ԖځA�c��n�h���A�k�X�͔p�ЂƂȂ����G���T���������z�����B���̈ꕔ���J���h�Ƃ��Ďc���Ă���B�ނ̓��[�}�̉��K��^���邱�ƂŁA���_�����������_���悤�Ƃ����B���������̎��݂͖��c�Ɏ��s����B�o���E�R�N�o�����郆�_��������R��132�N�A���[�}���R���P�����ăG���T�������̂����B�o���E�R�N�o�͌��̖����V�����Ƃ����B������~����i���V�A�j�Ə̂����B�o���E�R�N�o�i���̎q�j�̖��́A�u�����L���v24��17�A�u���R�u����ӂ̐����ł�v�ɗR������B2�N���z���铝���̊ԁA���s����������L�O����d�݂𒒑������B���͂ȃ��[�}�R���s�X��͋�肾�����B���ǃn�h���A�k�X��͑�R�𑗂荞��Ŕ��������������Ȃ��B��������ł����邽�ߐ_�a���s�X�n���ł������Ȃ������B�o���E�R�N�o�͐펀�����B���[�}�鍑�́A���B���_���Ƃ��Ă����������A���B�V���A�E�p���X�`�i�Ɖ��߂��B���_���̓G�Ύ҃y���V�e�l�̖��ɗR������B�����Ă��̖��̂́A���݂̃p���X�`�i�Ɍq�����Ă���B
���[�}�鍑��������܌���̎O�ԖځA�c��n�h���A�k�X�͔p�ЂƂȂ����G���T���������z�����B���̈ꕔ���J���h�Ƃ��Ďc���Ă���B�ނ̓��[�}�̉��K��^���邱�ƂŁA���_�����������_���悤�Ƃ����B���������̎��݂͖��c�Ɏ��s����B�o���E�R�N�o�����郆�_��������R��132�N�A���[�}���R���P�����ăG���T�������̂����B�o���E�R�N�o�͌��̖����V�����Ƃ����B������~����i���V�A�j�Ə̂����B�o���E�R�N�o�i���̎q�j�̖��́A�u�����L���v24��17�A�u���R�u����ӂ̐����ł�v�ɗR������B2�N���z���铝���̊ԁA���s����������L�O����d�݂𒒑������B���͂ȃ��[�}�R���s�X��͋�肾�����B���ǃn�h���A�k�X��͑�R�𑗂荞��Ŕ��������������Ȃ��B��������ł����邽�ߐ_�a���s�X�n���ł������Ȃ������B�o���E�R�N�o�͐펀�����B���[�}�鍑�́A���B���_���Ƃ��Ă����������A���B�V���A�E�p���X�`�i�Ɖ��߂��B���_���̓G�Ύ҃y���V�e�l�̖��ɗR������B�����Ă��̖��̂́A���݂̃p���X�`�i�Ɍq�����Ă���B
�@�}���O���b�g�E�����X�i���́u�n�h���A�k�X��̉�z�v�i���c�q���q��A�����Ёj�́A���̂Ƃ��̃��[�}�c��̋�Y�������ɕ\�����Ă���B
�@�c�B��̐_�̊T�O�̋������E�̂����ɁA������^�������Ƃ��Ƃ��Ƃ����߁A�������邱�Ƃɂ���āA���ׂĂ��܂����_��̑��l���J����������������������́A�C�X���G���������đ��Ɉ���Ȃ��B�C�X���G���ȊO�̂����Ȃ�_���A���̐��q�҂ɁA�ق��̍Ւd�ɋF��҂ւ̌y�̂Ƒ����𐁂����݂͂��Ȃ������B���ꂾ���炱���Ȃ�����킽���́A�C�X���G��������̖����Ɗ���̏@�������a�ɋ����ł���A���̒��Ɠ����悤�Ȓ��ɂ����������B���M�Ə펯�Ƃ̑����ɂ����ď펯�������Ƃ͂߂����ɂȂ��Ƃ����������킽���͖Y��Ă����̂ł���B�i�����j�ے肷�ׂ����Ȃ��\�\���̃��_������͂킽���̎���̈�������B
�@70�N�̔��������Ɠ��l�A�O�ꂵ���j�Č����ꂽ�B�n�h���A�k�X��ɂ͉������A���_�������ɂ͉��O���c�������ƂȂ����B
�@�_�a���j�ꂽ���߁A�_�a�ՋV���S�̃��_�����͏I�����B���_�����k�̃G���T������������͋֎~���ꂽ�B��N�Ɉ�������̗������肪�����ꂽ�̂́A�u�~���m���߁v���o���ꂽ4���I�ȍ~�̂��Ƃł���B�w���f�剤���z�����_�a�́A���ǂ������c���Ă����B���_�����k�͂����ŋF���������B�����͌�ɒQ���̕ǂƌĂ��悤�ɂȂ����B

 �@5���I�A���̒n�Ɏc�������_���̐l�тƂ͏����h�ɂȂ��Ă����B�����̃��_���l�����́A���V�A���܂ރ��[���b�p�S��ɗ��U�����B�ނ�͐^�̈Ӗ��ł̃f�B�A�X�|���A�S���̖��ƂȂ����B���U��ł́A��Ƀ}�C�m���e�B�i�����h�j�������B�L���X�g���Љ�ł́A�C�G�X���E���������Ƃ��Ĕ��Q�̑ΏۂƂȂ����B�����������ɒ������ނ�͂��ԂƂ��������т��B����ɏ����ꂽ�u�I�ꂽ���v�Ƃ��Ă̌ւ�����������A���Ȃ��Ƃ��ŋ߂܂ł̓��_���Ƃ��Ă̖����̌��������ɕۂ��������B
�@5���I�A���̒n�Ɏc�������_���̐l�тƂ͏����h�ɂȂ��Ă����B�����̃��_���l�����́A���V�A���܂ރ��[���b�p�S��ɗ��U�����B�ނ�͐^�̈Ӗ��ł̃f�B�A�X�|���A�S���̖��ƂȂ����B���U��ł́A��Ƀ}�C�m���e�B�i�����h�j�������B�L���X�g���Љ�ł́A�C�G�X���E���������Ƃ��Ĕ��Q�̑ΏۂƂȂ����B�����������ɒ������ނ�͂��ԂƂ��������т��B����ɏ����ꂽ�u�I�ꂽ���v�Ƃ��Ă̌ւ�����������A���Ȃ��Ƃ��ŋ߂܂ł̓��_���Ƃ��Ă̖����̌��������ɕۂ��������B
�@�C�X�������̖u���́A�u�E��ɃR�[�����A����Ɍ��v�̂��Ƃ킴�ʂ�A�����Ƃ����Ԃɒ�������A�t���J���[�܂ł��C�X�������������B�����̒����́A���̑��������_���̍��X�������B�@�c���n���}�h�Ƃ��̈ꑰ�́A���_���̍��X�͂Ő��e�������A�ʂ����Ă�����@���푈�ƌĂ�ł悢���̂��ǂ����A�˘f�����o����B���͊g��̎傽��v���͌��Ղɂ������B�C�X�������́A�������瑼�@���Ɋ��e�������B�L���X�g���k�́A�]�߂G���T�������炪�\�������B
�@���������c���́A��������C�X�������k�̎肩��D�҂���悤�L���X�g�����̍��������ɌĂт������B11���I�A�\���R�����̒n�𐪕��A�G���T�������������������B����������̓L���X�g���k�̂��߂̉���ł���A���_�������̂��߂ł͂Ȃ������B�����āA�̐S�̃G���T�����\���R��1187�N�A�T���f�B���i�T���[�t�b�f�B�[���j������R�ɔs��A�������̂��̂�1291�N�ɏ��ł����B
�@���@���Ɋ��e�������C�X�������́A����ɃL���X�g���Ɛ�s�ɑΗ�����悤�ɂȂ����B�����Ɍ��Ă��A�@���Η���������̂́A���̎��_�ł��A������20���I�̃A�t�K���푈�Ȍ���L���X�g�������ł���B
�@�\���R�̈ȑO���Ȍ���A���_�������͑����̚��O�ɂ������B1947�N�ɍ��A���������c��ʂ��܂ŁA���̒n�����_�������̂��̂ł��������Ƃ͂Ȃ��B
�@�G���T�������s�X�́A1981�N���E��Y�ɓo�^����Ă���B�\�����̓����_���ł���B�C�X���G���ł͂Ȃ��B���_�����k�����̒n�Ɏ��R�ɏo����ł���悤�ɂȂ����̂́A1967�N�̒����푈�ȍ~�ł���B���̐�̍s�ׂ́A�����̍�����@�Ƃ��Ă���B
�G���R
�@�C�X���G���ό��̓x�c���w���ƃG���T���������������̂����A�����_���֔�����ʊւ̓s����A�킸������̎��ԃG���R�ɗ�����邱�Ƃ��o�����B�����I�ɂ�A�n��ɑ����A�s���E�����Ƃ��Ƀp���X�`�i�������{���ӔC�������Ă���B�����Ɍb�܂ꂽ���̒n�͎����������\�Ɏv����B�������ɓ��Ɩ��̗����n�ł���B�v���Ȃ����A�p���X�`�i�̐l�тƂ̕\������₩�Ɍ������B�Ƃ͂����A�����_���̂̌k�J���܂߁A�C�X���G���͌Վ�ἁX�Ɖ䂪���̂ɂ��ׂ��_���Ă���B�p���X�`�i������Ƃ���̂́A�A���u�̑�`�Ɛ��E���_�ł���B
�@���[�Z�̓l�{�R�̒��ォ��A�J�i���̒n���������_���̐l�тƂ����������B�ނ炪����������̓G���R�������B

 �@�����ɂ��ƁA�_�G�z�o�́A����������̗������C�܂ŃA�u���n���̎q���ɗ^����Ɩ��Ă���B�����������ɂ͐�Z�̖����������B�̒n�ł͂����Ă����l�ł͂Ȃ��B���R�u���ꑰ�������A��ăG�W�v�g�֓n���Ĉȗ��A���R�̂��ƂȂ��瑼�������ڂ�Z��ł����̂ł���B�u���V���A�L�v��3��10�ɂ��A�J�i���l�A�w�e�l�A�q�r�l�A�y���W�l�A�M���K�V�l�A�A�����l�A�G�u���l�Ƃ������ƂɂȂ�B�G���R�̉��́A�X�̎��͂���ǂň͂ݎ����ł߂Ă����B
�@�����ɂ��ƁA�_�G�z�o�́A����������̗������C�܂ŃA�u���n���̎q���ɗ^����Ɩ��Ă���B�����������ɂ͐�Z�̖����������B�̒n�ł͂����Ă����l�ł͂Ȃ��B���R�u���ꑰ�������A��ăG�W�v�g�֓n���Ĉȗ��A���R�̂��ƂȂ��瑼�������ڂ�Z��ł����̂ł���B�u���V���A�L�v��3��10�ɂ��A�J�i���l�A�w�e�l�A�q�r�l�A�y���W�l�A�M���K�V�l�A�A�����l�A�G�u���l�Ƃ������ƂɂȂ�B�G���R�̉��́A�X�̎��͂���ǂň͂ݎ����ł߂Ă����B
�@���[�Z�ɑ����ă��_���̐l�тƂ𗦂��郈�V���A�ɁA�_�̂�����������B�w���ʂ�A�_��̟C��S�i�l�j���Ń����_����܂Ői�ނƁA���̗��ꂪ�~�܂�₷�₷�Ɠn�͂ł����B�M�҂łȂ��҂́A���̂悤�Ȋ�b���o�Ă��邽�тɔ��ɑ������^�O������B�u�T���v�̂ł���B��Ղ͂��ꂾ���Ɏ~�܂�Ȃ��B�����ɏ]���ƁA
�@�c����R�l�݂ȗW��ㅂ�ėW�̎��͂��ꎟ�܂��ׂ��B��Z���̊Ԃ����ׂ�B�Վi�����l���̂��̃��x���̚h�ڂ��������ւğC�ɐ旧�ׂ��B�����đ掵���ɂ͓��玵���W���߂���Վi���h�ڂ𐁂��Ȃ炷�ׂ��B�i�����j���݂ȑ�ɌĂ͂�^�Ԃׂ��B�R�����̗W�̐Ί_���ꂨ����B���݂Ȓ��ɐi�݂čU�߂̂ڂ�ׂ��i�u���V���A�L�v6�F2-5�j�B
�@�_��̟C��S���Ƃ����s�ׂ́A���{�̂��_�`�S���̂悤�Ȃ��̂��낤�B�ւ��Ȃ���͂킽�������ł͂Ȃ����ɂ�����ƌ����āA���̊�Ղ�n�k�̂������낤�Ƃ����l������B
�@���V���A�����郆�_���̐l�тƂ́A���ꂽ��ǂ��z���ăG���R�𐪕������B���l��́u�W�F���R�̐킢�v�͂��̊�Ղ��̂��ĔM���B�����āA���l��̂����тɎv���̂́A���l�z�ꂽ���ɃL���X�g�������������l�����̋U�P�ł���B�C�G�X�̐��������t�̐��X�ƌȂ̍s�ׂƂ̖������A�z�ꏊ�L�҂����͌�邱�Ƃ��Ȃ������̂��낤���B�����g�U�P�̉�̂悤�Ȑl�Ԃ�����A�ɂ��قnj��߂�����������B

 �@�G���R�̖k���ɂ��т����R��������u�U�f�̎R�v�ł���B�C�G�X�������̗U�f�ɂ��炳�ꂽ�R�Ƃ����B�u�}�^�C�������v��4�͂��ȗ��ɋL���ƁA�C�G�X�͌��ɓ�����čr��Ɏ���B40���Ԃ̒f�H�s�ŋQ���Ă���B�����������B�����_�̎q�Ȃ���̐��p���ɕς���B�C�G�X�͓�����B�u�l�̐�����̓p���݂̂ɂ��炸�v�B�����̓C�G�X�s�̋{�̒���ɗ������A��э~���A�_����g���ɖ����ď�����͂����A�ƌ����B�C�G�X�͓�����B�u��Ȃ���̐_�����ނׂ��炸�v�B�����ŁA�����͐��̂������̍��ƁA���̉h�������A�������q��������S���^���悤�A�ƗU�f����B�C�G�X�͓�����B�u�T�^����A�ނ��B�w��Ȃ���̐_��q���A�����V�Ɏd����ׂ��x�ƋL����Ă���v�B�s�ꂽ�����͋���c�Ƃ����o�܂��d�X���������B
�@�G���R�̖k���ɂ��т����R��������u�U�f�̎R�v�ł���B�C�G�X�������̗U�f�ɂ��炳�ꂽ�R�Ƃ����B�u�}�^�C�������v��4�͂��ȗ��ɋL���ƁA�C�G�X�͌��ɓ�����čr��Ɏ���B40���Ԃ̒f�H�s�ŋQ���Ă���B�����������B�����_�̎q�Ȃ���̐��p���ɕς���B�C�G�X�͓�����B�u�l�̐�����̓p���݂̂ɂ��炸�v�B�����̓C�G�X�s�̋{�̒���ɗ������A��э~���A�_����g���ɖ����ď�����͂����A�ƌ����B�C�G�X�͓�����B�u��Ȃ���̐_�����ނׂ��炸�v�B�����ŁA�����͐��̂������̍��ƁA���̉h�������A�������q��������S���^���悤�A�ƗU�f����B�C�G�X�͓�����B�u�T�^����A�ނ��B�w��Ȃ���̐_��q���A�����V�Ɏd����ׂ��x�ƋL����Ă���v�B�s�ꂽ�����͋���c�Ƃ����o�܂��d�X���������B
�@�����ɂ������b������B�߉ނ������̉��Ō����J���T��ɓ������Ƃ��A�ґz��W���邽�߈����}�[���́A�܂���n�߂ɔ������Z�ɒ������O�l�̖��𑗂荞�B�߉ނ͗U�f�ɋ����Ȃ��B���낵���`���̉��������Ɏ߉ނ��P�킹�����A�Ȃ����߂Â����Ƃ��o���Ȃ������B��₠��Ƃ����镐����~�点�A���͂��Èłŕ��������߉ނ͓����Ȃ��B�Ō�ɁA�}�[�����g����ȉ~�Ղ�U�肩�����Č������čs�����A�~�Ղ͉ԗւƂȂ��Ă��܂��B�}�[���͔s�k��F�߁A�߉ނ͌����J�����c�B
�@�@���w���҂��_�i������čs���ɂ�A�K������������b�����܂��B���Ȃ݂ɒj���̔鏊�Ƀ}���Ƃ������A�ꌹ�͂��̈����}�[���ɗR������B
�@�U�f�̎R�̒����ɂ̓M���V�A������̏C���@������B���Ԃɐ��ꂽ�����́A���X�g�������y�Y���X�̍L�ꂩ�牓�]�����݂̂ł���B���̓X�́u�U�f�̎R�v�Ƃ������O�������B
���̗��̏I��
�@�l���̏I�����ɓ������҂ɂƂ��āA����̗��́A���͂Ō����s���I�b�h��ł悤�ȈӖ������������Ă����B���ꂩ���A�C�O���s���ł����Ƃ��Ă��A����قǂ̏d�݂������Ƃ͂Ȃ����낤�B�@����C�X���G���ɂ��āA������v���Ă��邱�Ƃ������A�˂Ă݂�B�璷�ȓ_�́A�V��̐��ȂƂ��e�͊肢�����B
�������ꂱ��
�����ƌÎ��L
�@���Ȃ��Ƃ��I���O550�N���ɏ����ꂽ�Ƃ���鋌�����A���{�ŌÂƂ͌����Ă�8���I�ɏ����ꂽ�Î��L�Ɣ�ׂ�ȂǁA�s�����r�������Ƃ��������ɈႢ�Ȃ��B�����A���ꂼ��̎��M���@�Ɠ��e�Ɏ��ʂ����_���Ȃ��킯�ł��Ȃ��B
�@�����ōł��d�v�������̂́A���[�Z���ƌĂ��u�n���L�v�u�o�G�W�v�g�L�v�u���r�L�v�u�����L�v�u�\���L�v�ł���B�����̓g�[���i���@�j�ƌĂ�A���[�Z���������Ƃ���Ă���B�����������҂����́A���[�Z�����o�r���j�A�ߎ����ɕҎ[���ꂽ�ł��낤�Ƃ��Ă���B�o�r���j�A�ɖłڂ���A�����������������A���������̃A�C�f���e�B�e�B�[���������悤�ƁA�×�����`���_�b�E�`���������ɂ܂Ƃ߂��̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B
�@�Î��L�������ꂽ�̂�712�N�i�a��5�N�j�ł���B�B�c����̋L�������Ƃɑ����������Ҏ[���A�����V�c�Ɍ��サ���B�B�c����́A���܂ł������L�̌�蕔�̂悤�ȑ��݂������̂��낤�B���j�̕Ҏ[�𖽂����͓̂V���V�c�ł���B663�N�i�V�q2�N�j�����]�̐킢�ŁA���{�͓��E�V���̘A���R�Ɋ��s�����B�������N�͎O������ŁA���͂ł͍���킪���͂������B���͐V���Ƒg��ō����ɔ������B�����ɂƂ��āA�����̐��[�Ɉʒu����S�ς͎ז��҂������B���E�V���̘A���R�͕S�ς��U�߂��B�S�ς͓��{�Ɏx�������߂��B
�@�����̓��{�ɂ́A�܂����Ƃ������Ƃ����ӎ������������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�����A�V���A�S�ς̐l�тƂ͒��N�C����n���Ď��R�ɉ������Ă����B���{�ɋ������n���l�����������B�Ƃ�킯�A�S�ς͓��{�c���Ƃ̌��т������������B���N�C���͍����ł͂Ȃ������̂ł���B
�@�����]�̐킢�ɔs�ꂽ���{�́A���E�V���A���R�̏P�������ꂽ�B���ɕ{�̖k�ɐ����R���z�����B���A�Δn�ɔh�����ꂽ�h�l�̉̂����t�W�ɏW�^����Ă���B���̂Ƃ����߂āA���{�͍��ƂƂ������̂��ӎ������B�V�q�V�c�̐Ղ��p�����V���V�c�́A���{�Ƃ������݂m�ɂ��ׂ����j�̕Ҏ[�𖽂����B�������{�́A�C�X���G���̂悤�ɍ����������Ƃ͂Ȃ��������A����j���Ҏ[�̓��@�������Ƃ���͎��ʂ��Ă���B
�@����Ȃ鋤�ʓ_�́A����ȍ��ɗאڂ��Ă���Ƃ����n���I���ł���B���{�Ō����Β����A�C�X���G���ł̓G�W�v�g�̑��݂��傫���B��������j�̐[���A�Â��͔�r���悤���Ȃ��B������ׂ悤�ɂ����͗�R�Ƃ��Ă���B���߂Ă��܂茩���̂��Ȃ����x�Ɍ`�𐮂��悤�Ƃ���w�͂��A�_�b��̐l���⏉���V�c�����̎����Ɍ��ꂽ�B
�@�V���Ƃ��č~�Ղ����玌|���̎����́u�v�����v�Ƃ����L�^����Ă��Ȃ����A���̎q�R�K�F�̕ʖ��Œm������q��X�茩����580�܂Ő������B���̑�����V�c�_����137�܂Ő������B�ނ���15�㉞�_130�܂ŁA11�l�̓V�c���S���z����B����10�㐒�_��168�܂Ő������Ƃ���B���ʂƂ��āA�_���V�c���ʂ����N�Ƃ�����{�̋I�N�͐�����660�N�����B2020�N���݂̍c�I��2680�N�ł���i�V�c�̖v�N�͌Î��L�Ɠ��{���I�ł͑��Ⴗ�邪�A�����ł͌Î��L�ɏ]�����j�B
�@����ɓo�ꂷ��l�X�́A����ɓV���w�I�ɒ����ł���B�A�_��930�A�m�A950�A�m�A�̎q�Z���A�Z���̌n��A�u���n�������܂�邪�A���̂�����̓o��l���݂͂�900�A800���z����B�m�A����10��ڂ̃A�u���n�����炪�A�l�Ƃ��Ă̗��j���Ɖ��肵�Ă��A���̔ނ�175�A�C�T�N180�A���Z�t110�A���[�Z120�ƈُ�ȔN��L�^����Ă���B
�@�G�f���̉��͖L�`�ȃi�C���쉈�݂��C���[�W���Ă���Ƃ�����������B�Ȃ��ݐ[������q���́A�V��_�z���X������L���̏��_�C�V�X�����f�����ƌ�����B���������̉e�����ɂ��������{�Ɠ��l�A�������͂���ȏ�Ƀ��_�������ƃG�W�v�g�Ƃ̊W�͐[���B
�@����͌����܂ł��Ȃ���_���ł���B���E�͐_�G�z�o�ɂ���đn���A�A�_�����l�ނ̑c�ƂȂ�B�A�_���ȑO�ɐl�Ԃ����݂��Ă��Ă͓s���������B���ꂾ���N��̃T�o��ǂ�ł����A������G�W�v�g�̗��j���Â��Ƃ��A�A�_������A�u���n���Ɏ���܂ł̒N�����G�W�v�g�����̑c�悾�Ɛ����ł���B�����́A�o�x���̓��̑}�b�ɐ������������Ă���B�c���̂ɑ����̓o�x���i�����j�ƌĂ�B���̓G�z�o�ޙ|�ɑS�n�̌����������܂Ђ��ɗR�ĂȂ�B�ޙ|���G�z�o�ޓ���S�n�̕\�ɎU�炵���܂ւ�i�u�n���L�v11�F9�j�B����L�q�҂̋�S�̂قǂ��@������B
�@����ƌ����A�V��ƌ����A��������_�Ƃ̌_����Ӗ�����B�_�ƌ_������ԂȂǁA���_���̐��E�ɏZ�ގ҂ɂ͋y�т����Ȃ������ł���B�Î��L�ɂ��̂悤�ȍV�Ԃ�͂Ȃ��B���̓_�A���҂͍��{�I�ɈقȂ�B
�@�L���X�g�������[�}�𒆐S�ɕ��y����܂ŁA��_���̓}�C�i�[�ȏ@���������B���͂͂��ׂđ��_���������B�@�����A�j�~�Y�����甭�W�������̂ł���ΕK�R�I�ɑ��_���ƂȂ�B
�@��_���̒a���ɂ��ẮA�W�[�N�����g�E�t���C�g�́u���[�Z�ƈ�_���v�i�n�ӓN�v��A�����܊w�|���Ɂj���Q�l�ɂȂ�B���_���͂̑n�n�҃t���C�g�́A1938�N�A�i�`�X�̃I�[�X�g���A�N�U��ă����h���֖S�������B���ł�82�ɂȂ��Ă����B�u���[�Z�ƈ�_���v�Ɓu���_���͊T���v�i�����j�������A1939�N83�Ő����������B
 �@�ނ͈�_�����G�W�v�g���C�N�i�g���̑��z�_�A�e���M����n�܂����Ƃ���B�C�N�i�g���̐������̓A�����z�e�v�l���A�ʖ��A�N�G���A�e���Ƃ����B���炭��Ƃ���Ă������A�c�^���J�[�����̕��Ƃ����B�c�^���J�[�����͓����c�^���J�[�g���Ƃ������O�������B�A�g���_�̖��������Ɉ��p����Ă���B���C�N�i�g���̎��S��A�G�W�v�g�̓A�����_�𒆐S�Ƃ��鑽�_���ɖ߂����B�c�^���J�[�g���̓c�^���J�[�����Ɩ��O�����߂��i���߂�����ꂽ�j�B
�@�ނ͈�_�����G�W�v�g���C�N�i�g���̑��z�_�A�e���M����n�܂����Ƃ���B�C�N�i�g���̐������̓A�����z�e�v�l���A�ʖ��A�N�G���A�e���Ƃ����B���炭��Ƃ���Ă������A�c�^���J�[�����̕��Ƃ����B�c�^���J�[�����͓����c�^���J�[�g���Ƃ������O�������B�A�g���_�̖��������Ɉ��p����Ă���B���C�N�i�g���̎��S��A�G�W�v�g�̓A�����_�𒆐S�Ƃ��鑽�_���ɖ߂����B�c�^���J�[�g���̓c�^���J�[�����Ɩ��O�����߂��i���߂�����ꂽ�j�B
�@�t���C�g�̐��́A���[�Z���C�N�i�g���̑��q�������������Ƃ����B���[�Z�����_���l�ł͂Ȃ��\�����������Ă���B�C�N�i�g���̎��S��A���_���ɖ߂����G�W�v�g�Ɏ��]���A���_�����O�Ɉ�_�����������B�ނ̏�������p����B
�@�c�ނ̓��_���������_�̑I���ł��邱�Ƃ�ۏ��Ĕނ�̎����̔O�����߁A�ޓ��ʂ��A�ނ�ɑ��������痣�E���邱�Ƃ��`���Â����B�i�����j���_���l��n�������̂̓��[�Z�Ƃ����Ƃ̒j�ł������A�Ɗ����Č����Ă��悩�낤�Ǝv���B���_�������́A���̋��x�Ȑ����͂��A�܂������ɁA�̂���g�Ɏ��܂��Ȃ��g�Ɏ����Ă�����͂̓G���S�̂قƂ�ǂ��ׂĂ��A���[�Z�Ƃ����j����Ƃ����̂��B
�@�����ăt���C�g�́A�C�N�i�g���̈�_�����u�������ꂽ���ۉ��̍��݂ւ̔��𐬂��������v�ƌ����A�L���X�g�����A�u���e�̏@���v����u���q�̏@���v�ɕϖe�������ƂŁu���_�������o��߂����_���̍��݂��ێ��ł��Ȃ������v�Ɛ�̂Ă�B
�@�u�}�^�C�������v�̖`���́A�A�u���n���Ɏn�܂�C�G�X�Ɏ��錌����Ԃ�B�u���J�������v��3�͂ł͋t�ɃC�G�X����k���ăA�_���Ɏ��錌����������Ă���B���̌����̂Ȃ��ɁA���[�Z�͊܂܂�Ă��Ȃ��B�A�u���n���̌n���ł͂Ȃ��a���҂������ƍl������ޘb�����A�Ђ���Ƃ�����t���C�g�̂����ʂ�A���_���l�ł͂Ȃ������̂�������Ȃ��B��������h����́A����n���Ȃƈ�ɕt����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����c�B
�@�ŏ�����������ɂ����Ƃ��A�����ł��������厖�Ȃ̂��Ɗ�قɊ������B�V�c�ƂɎ��Ă���Ǝv�����B�V�c�Ƃ́A26��p�̂ɋ^�O�͂�����̂́A�_���Ɏn�܂�ߘa�Ɏ���܂ŁA���X�ƈ�̌������ێ�����Ă����B

 �@���_�_�҂̎v�l�͂܂��Ƃɉ��˂ł���B�}��������ٍ��m�Őg���������̂ł���A�A�u���n�����畃���Z�t�܂łȂ��錌���́A�C�G�X�ɓ`���Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�����ɖ����͂Ȃ��̂��B����ɂ���Đg���������̂�����A�_�̎q�Ȃ̂��ƌ��������܂ł����A�����ł���A�t�Ɍ������~�X�L�^����K�v�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�@���_�_�҂̎v�l�͂܂��Ƃɉ��˂ł���B�}��������ٍ��m�Őg���������̂ł���A�A�u���n�����畃���Z�t�܂łȂ��錌���́A�C�G�X�ɓ`���Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�����ɖ����͂Ȃ��̂��B����ɂ���Đg���������̂�����A�_�̎q�Ȃ̂��ƌ��������܂ł����A�����ł���A�t�Ɍ������~�X�L�^����K�v�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�@�ȏ�́A�����Đ������Ȃ߂悤�Ə������킯�ł͂Ȃ��B�_�b���Ƃ����炩�ɎƂ߂Ă����悢�b�ł���B�����Ɏg���Ă��錾�t�͐��E�ŌÂƂ����킯�ł͂Ȃ��B���̂��Ƃ͂��łɏؖ�����Ă���B���������E�ɂ́A�����͐_�̌��t�ňꌾ�����͂Ȃ��Ƃ��鋶�M�҂����Ȃ��Ȃ��B�A�����J�̃o�C�u���E�x���g�ƌĂ��암���B�ɂ��̌X���������B�f��u���̈�Y�v�i1960�N�j�́A�i���_�����������Z���t���߂���ٔ���`�����B���̎����́A��Ƀ����L�[�ٔ��ƌĂꂽ�B�ḗu���ɂāv�̃X�^�����[�E�N���C�}�[�B�f��̑�́A�u⼌��v�c���̂�̉Ƃ����邵�ނ���͕̂������ď��L�Ƃ���i11�F29�j������p����Ă���B
�@�u�b�V���i�q�j�哝�̂̓N���G�[�V���j�Y�����w�Z�ŋ����Ă͂ǂ����Ɣ��������B������Y�Ƃ����哝�̂������B�l�Ԃ͐_�ɂ���đn��ꂽ�Ƃ���N���G�[�V���j�Y���́A�C���e���W�F���g�E�f�U�C���Ɠ��Ӌ`�ƍl���Ă����B�i���_�̔ے�ł���B
�@�C�X�������k�ɂ����M�҂�����B2015�N1���p���ŁA���n���}�h�̕��h����f�ڂ����V�������[�E�G�u�h���̕ҏW���A��ƂȂ�12�l���E���ꂽ�B���{�ł͂��łɖY�ꋎ���Ă��邪�A�T���}���E���V���f�B�u�����̎��v�̖|��ҁi�\����j���A1991�N�ɎE�Q����Ă���B�Ɛl�͕߂܂��Ă��Ȃ��B���l�̏@���S��`�����ׂ��ł͂Ȃ����A�E�l�Ȃǂ͋��C�̍����ł���B
�@�����āA�v�[�`���哝�̂�g�����v�哝�̂ȂǁA�ƂĂ��h�i�ȐM�҂Ƃ͎v���Ȃ��悤�Ȑl�����A�����̎x���邽�߂����̖ړI�ŁA�M�S�[�����ȑԓx��������̂ɂ������̑���v��������B
�\�������̉b�q
�@�u�I���v��u���u���v�ɂ́A�\�������������ɉb�q�ɖ����Ă��������~�X�q�ׂ��Ă���B�����A��̓I�ȗ�͑剪�ق����炢�����Ȃ��B
�@�\�������̉b�q��m��ɂ́u�`���̏��v��ǂނׂ��Ȃ̂��낤�B�����̈�ʓI�Ȕz��ł́A�u⼌��v�u�`���̏��v�u��́v�̏������A��������\���������������Ƃ����B���e���珇����ǂ��ƁA�N���Ɂu��́v�ň����r���A�s�N���ɒq�b�̏��u⼌��v���܂Ƃ߁A�ӔN�ɁA���ׂĂ͋��Ɓu�`���̏��v�������c�����A�Ǝv����B
�@�u��́v�́A�j���̗��̉̂ł���A�����̂Ȃ��ł����X�^�j��ƌ�����B�����ً��k�ɂƂ��ẮA�ق��ƐS�a�ޏ͂ł�����B�u⼌��v�͏@�����炵���i�������ԁB�s�M�S�҂����Ƃ���͂ł���B
�@�u�`���̏��v�͍ŋ߁u�R�w���g�̌��t�v�Ƃ���邱�Ƃ������B�R�w���g�Ƃ́u�W�߂�ҁv���Ӗ�����B�ŏ����̏͂�ǂƂ��A�����̋����ɂ悭���Ă��ċ��������Ƃ��v���o���B
�@�c�_�r�f�̎q�G���T�����̉��`���҂̌��t�B�`���Ҍ�����̋�A��̋�Ȃ�ƁA�s�ċ�Ȃ�A���̉��ɐl�̘J���Ĉׂ��Ƃ���̏��̓���͂��̐g�ɉ��̉v�������B���͋��萢�͗���B�n�͉i�v�ɑ��Ȃ�B���͏o�œ��͓��薒���̏o�ł����ɚb���䂭�Ȃ�i1�F1-5�j�B�c���̉��ɂ͐V�����҂��炴��Ȃ�i1�F9�j�B�c��S��ᶂ��Ēq�b��m���Ƃ��A���ςƋ�s��m���Ƃ����肵���A�����܂�����߂炤��@���Ȃ������B�v�q�b������Ε��������B�m���𑝂��҂͗J���𑝂��i1�F17-18�j�B�c�����Ɏ�����A���ʂ�Ɏ�����A�A����Ɏ�����i3�F2�j�B�c��͗P���鐶�҂������Ɏ��ɂ��鎀�҂����čK�Ȃ�Ƃ��B�܂����̓�҂����K�Ȃ�͖������ɂ��炸���ē��̉��ɍs���鈫����������҂Ȃ�i4�F2-3�j�B�c����D�ގ҂͋�ɖO�����Ɩ����B�L�x�Ȃ�Ƃ��D�ގ҂͓���Ƃ��날�炸�A���܂���Ȃ�i5�F10�j�B�c�l�̚施��N�ɔ{����Ƃ�������ւ��ɂ͂��炸�B�F�ꏊ�ɉ����ɂ��炸��i6�F6�j�B�c�O���̌��_����ċ��������Ƒ����B�R��ǐl�ɉ��̉v������i6�F11�j�B�c����̉��ɋ�Ȃ鎖�̂����Ȃ�����ς���B�����`�l�ɂ��Ĉ��l�̑����ׂ����ɑ����҂���B���l�ɂ��ċ`�l�̑����ׂ����ɑ����҂���B������营���܂���Ȃ�i8�F14�j�B�c����̉��Ɉ�̊��������������B���͌N������҂�肢�Â�ߌ�Ɏ�����B���Ȃ킿�����Ȃ�ҍ����ʂɒu����M���Ҕڂ����ɍ���i10�F5-6�j�B�c�����Đo�͖{�̔@���ɓy�ɋA��썰�͂�������_�ɂ�����ׂ��B�`���҉]���A��̋�Ȃ邩�ȊF��Ȃ�i12�F7-8�j�B
�@�u�`���̏��v���{���Ƀ\�������ɂ���ď����ꂽ���̂��ǂ����Ƌ^�������҂����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�\���������������Ƃ���A���悻�O10���I���̒���Ƃ������ƂɂȂ�B�٘_�����邱�Ƃ�F�߂������ŁA��͂肱�̏͂̓\�������̔ӔN�̎v���������\���Ă���Ǝv�������B
�@�����ɐS���ӂ����N���A���~�ɓM�ꂽ�s�N�����o�āA�[���}�����ɐZ���ꂽ�ނ̘V�N���Ɏv����y����B�\�������قǂ̌��҂ɂȂ�ƁA�����^���ɓ��B�����Ǝv���Ă��A���̓��ɂ͋^�������������Ƃ��낤�B���̌J��Ԃ������ƔނɒQ���������̂ł͂Ȃ����낤���B�^���_�Ɋׂ����悤�ɂ��v����B
�@�����u�`���̏��v�́u��v�́A�����̐����u��v�Ƃ͔����ɈႤ�悤�ȋC������B�u��v�̉p���
vanity �ƂȂ��Ă���B�ʎ�S�o�́u��v�� emptiness �Ɩ��̂���Ԃ̂悤�ł���B��͋�ł��A�u�`���̏��v�́u��v�́A�_�̂Ȃ��l���́u��v���ƌ����Ă���悤�Ɏv���B����͍ŏI12�͂̌��тɂ���c���̑S铂̋A���鏊���ׂ��A�]���_���ꂻ�̐��������B���͏��̐l�̖{������B�_�͈�̍s�ׂȂ�тɈ�̉B�ꂽ�鎖��P���Ƃ��ɐR�����܂��Ȃ�i13-14�j�B����́A�͂����ɓ������ĂƂ��Ă����M�����Ƃ͎v���Ȃ��B��͂�A�����́u��v�Ƃ͈قȂ�B
�@�ŋ߂̌����������悤�ɁA�\���������̐l�������c�������̂ł͂Ȃ���������Ȃ��B�������A�u⼌��v�����̂ɂ����l�����́u�`���̏��v���������Ƒz�肷��ƁA��w�l���̋������ɐg���ꂻ���Ȏv���Ɏ���B�����āu�`���̏��v�����邱�Ƃɂ���āA�\�������Ƃ����l�́A�l�ԂƂ��Ă̎コ���܂߂����݂������ł���悤�Ɏv���B
�V��̔��
�@���_�����̎w���҂����́A���̋������L�߂悤�ƈӐ}�������Ƃ͂Ȃ��B�����܂ł��ꖯ���̏@���ŗǂ��Ƃ����B�I�ꂽ���͂����݂̂Ƃ����ϔO�ɌŎ������B���_�����ł͋~����͂܂�����Ă��Ȃ��B
�@�L���X�g���́A���_��������o�����Ȃ���z���ɔM�S�������B�y�e����p�E�������[�}�ɑ_�����߂��Ƃ��A����͐��E�@���ւ̑����ƂȂ����B�����A���[�}�͐��E�̒��S�������B�C���h�⒆���͓Ǝ��̕������������Ă������A�G���T�������猩������͉����ً��������B

 �@�ȉ��́A���_�_�҂̎����ł���B
�@�ȉ��́A���_�_�҂̎����ł���B
�@�\��g�k�̂����A��Ԃ̃C���e�����������_�́A�C�G�X���~���傾�ƐM���Ă����B�G���T�����̐_�a���珤�l������ǂ��o�����Ƃ��A�_�̍������������Ɗ��삵���B�Ƃ��낪�C�G�X�́A���Ɋ��҂���s�����N�����Ȃ��B���]�����ނ́A�C�G�X���������Ƃ���B�ߕ߂���A�ٔ��ɂ�������悤�Ȃ��ƂɂȂ�A�_��������_�j����̂ł͂Ȃ����A�_�̎q�Ƃ��Đ^�̈Ќ�������̂ł͂Ȃ����A�Ɗ��҂����B�ނ͋��30���Ŗ������A�C�G�X��ߕ߂������B�Ƃ��낪�C�G�X�͈�ؒ�R�����A�\���˂ɉ˂���ꂽ�B���_�͐�]���A��݂𓊂��̂āA���݂��Ď��B
�@�y�e�����͂��߂Ƃ���g�k�������A���_���l�A�C�G�X�������������܂Ŋ�Ղ��N����Ɗ��҂��Ă����B�����������N���Ȃ������B�������A��������V�����@�����A���_�����̐���z���Ēa�������B
 �@���߂������C�G�X�̎��Ƃ����T�O����b�ƂȂ�B���V�A��������ߋ��ɑk���Ď�ٍ��m�A�a���A�O���m�Ȃǂ̈�A�̐_�b���n�肾���ꂽ�B�����͂����炭�A�C�G�X�̎����ǂ̂悤�ɉ��߂��A�M�k�����ɂǂ��������邩�Ƃ����Ƃ��납��n�܂����ɈႢ�Ȃ��B�_�i������A�s�����ȏ������ق����V��������K�v�Ƃ��Ȃ��B
�@���߂������C�G�X�̎��Ƃ����T�O����b�ƂȂ�B���V�A��������ߋ��ɑk���Ď�ٍ��m�A�a���A�O���m�Ȃǂ̈�A�̐_�b���n�肾���ꂽ�B�����͂����炭�A�C�G�X�̎����ǂ̂悤�ɉ��߂��A�M�k�����ɂǂ��������邩�Ƃ����Ƃ��납��n�܂����ɈႢ�Ȃ��B�_�i������A�s�����ȏ������ق����V��������K�v�Ƃ��Ȃ��B
�@�����炭�A�g�k�������܂��ŏ��ɂ������Ƃ́A����̂Ȃ�����A�C�G�X�̎�������ł��镶�͂�T���o�����Ƃł͂Ȃ��������낤���B�R��̐��P���玀�Ɏ���܂ŁA�C�G�X�̋����ƍs�����A���ׂĐ_��������ꂽ�̎����������Ɛ�������K�v���������B
�@�~����Ƃ����C���[�W���炷��A�ނ��ق��҂�����葁������ł͍���B���𗝗R�Â���K�v��������B�C�G�X���~����Ɛ_��������A���Ƃł������͂��B����ɂ̓��_�������琔�i�̔�K�v�ƂȂ�B�c���ꂽ�g�k��������L�҂����͂���������ɐ����������A�Ɛ��@����B�s�h�̂�����͊ÂĎ�B
�@�߉ނ�E�q���l�A�C�G�X�ɂ����炪�����c�������̂͂Ȃ��B�ނ�̎���A��q�������W�܂��Ďt�̌��t��Ҏ[�����B���ꂪ�}�^�C�A�}���R�A���J�A���n�l�̕������ƂȂ����B�z��������`����g�k�s�`�A�Ō�ɗa���߂������n�l�َ��^�������ĐV��̌`���ł܂����B

 �@�L���X�g�������E�@���Ɏ������ő�̍v���҂̓p�E���ł���B�ނ̓C�G�X�̒���q�ł͂Ȃ��B�ނ��딗�Q���鑤�ɂ����l���ł���B�g���R�̃^���\�X�̗T���ȉƂɐ��܂�A�M�S�ȃ��_�����k�������B���[�}�̎s���������G���[�g�ł��������B�ނ̓G���T��������_�}�X�J�X�������r��ŁA���Ɍ�����A�ӖڂƂȂ����B�u�g�k�s�`�v�ɏ]���i�����ł̓w�u���C��T�E���ƂȂ��Ă���j�B
�@�L���X�g�������E�@���Ɏ������ő�̍v���҂̓p�E���ł���B�ނ̓C�G�X�̒���q�ł͂Ȃ��B�ނ��딗�Q���鑤�ɂ����l���ł���B�g���R�̃^���\�X�̗T���ȉƂɐ��܂�A�M�S�ȃ��_�����k�������B���[�}�̎s���������G���[�g�ł��������B�ނ̓G���T��������_�}�X�J�X�������r��ŁA���Ɍ�����A�ӖڂƂȂ����B�u�g�k�s�`�v�ɏ]���i�����ł̓w�u���C��T�E���ƂȂ��Ă���j�B
�@�c����n�ɓ|��āu�T�E���A�T�E���A������𔗊Q���邩�v�Ƃ������������B�ނ����u���A�Ȃ͒N���v�B�������܂��u���͓������Q����C�G�X�Ȃ�v�i9�F4-5�j�B
�@�C�G�X�́A�M�҃A�i�j�A�ɁA�p�E���̂��Ƃ֍s�����ނ̏�ɒu���A�Ɩ�����B�A�i�j�A�́u�p�E���͔��Q�҂Ȃ̂ɂȂ�������̂��v�Ɩ₤�B�C�G�X�́A�������I�킾�Ɠ�����B�A�i�j�A���p�E���̏�Ɏ��u���Ɣނ̊�j����̂悤�Ȃ��̂������čĂь�����悤�ɂȂ����B��S�����p�E���͐�����A�M�S�ȕz���҂ƂȂ�B
�@�u�g�k�s�`�v��ǂތ���A�p�E���͏d�v�l���Ƃ��Ă������ɕz���ɐ�O�����悤�Ɍ����邪�A�y�e����ق��̒�q�����Ƃ̊W�͂��Ȃ������̂��������ɈႢ�Ȃ��B�y�e���ɂ̓C�G�X�̈�Ԓ�q���Ƃ����ւ肪����B�C�G�X���璼�ږ�����ꂽ�Ǝ咣����p�E�����A�ق��̒���q�����������ȒP�ɒ��Ԃɓ��ꂽ�Ƃ͎v���Ȃ��B�K�R�I�ɔނ̓A�i�g���A�A�M���V�A�A���[�}�ւƕz�����邱�ƂɂȂ�B���̌��ʂ��ꉞ�̐��ʂ��グ�A����q����������Ɉ�ڂ�u����������Ȃ��Ȃ����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����B

 �@�p�E���ƃo���i�o���ŏ��̕z���������I���A�G���T�����ɖ߂����Ƃ���ő���ڂ̎g�k��c���J�����B�o���i�o�̓p�E���̋����ɋ����A�����𓊂��ď��������ݗ������L�͎҂ł���B�g�k��c�Ŗ��ƂȂ����̂́A���_�������L�̊���ł���B�ٖM�l�֕z������ɓ������āA����̗L������Q�ƂȂ����B�p�E���́A�M�҂ƂȂ�̂Ɋ���͕K�v�Ȃ��Ƃ��闧��ł���B�ĂсA�u�g�k�s�`�v����p�E���̌��t�����p����B
�@�p�E���ƃo���i�o���ŏ��̕z���������I���A�G���T�����ɖ߂����Ƃ���ő���ڂ̎g�k��c���J�����B�o���i�o�̓p�E���̋����ɋ����A�����𓊂��ď��������ݗ������L�͎҂ł���B�g�k��c�Ŗ��ƂȂ����̂́A���_�������L�̊���ł���B�ٖM�l�֕z������ɓ������āA����̗L������Q�ƂȂ����B�p�E���́A�M�҂ƂȂ�̂Ɋ���͕K�v�Ȃ��Ƃ��闧��ł���B�ĂсA�u�g�k�s�`�v����p�E���̌��t�����p����B
�@�c�u�Z�킽����A����̒m�邲�Ƃ��A�v�����O�ɐ_�́A�Ȃ�̒������I�сA�킪�����ٖM�l�ɕ����̌��t�����A�V��M�����߂�Ƃ�������B�l�̐S��m�肽�܂��_�́A���Ɠ������A�ޓ��ɂ������^����暂��Ȃ��A���M�ɂ��Ĕނ�̐S������߁A���Ɣނ�Ƃ̊ԂɊu��u�����킴�肫�B�i�����j���̋~������ނ�Ƌς�����C�G�X�̉��b�ɗR�邱�Ƃ����͐M���v�i15�F7-11�j�B
�@�ނ̗͋������t�ɉ�O�͒��ق����ƋL����Ă���B����̎g�k��c��49�N�̂��Ƃ������B
�@���_���l�L���X�g���k�ƁA�ٖM�l�L���X�g���k�Ƃ̘_���͂��̌���������B�������A70�N�̃G���T�����ח��ȗ��A�g�k�����̊����͍��O�ٖ̈M�l�����ւƔ�d���ڂ��čs�����B
�@���_�_�҂Ƃ��ẮA�C�X���G���Ƃ��������̈ꏬ���̗��j���A�����������E�̗��j�ł��邩�̂悤�ɍ��o���������p�Ɋ��Q����B���p�ƌ����Ă͐��E�@���Ɏ��炾�Ƃ���A���ƌ����Ă������B
�@�o�`�J���̋��c��������T���E�s�G�g���吹���́A�c�u��͂܂����ɍ����A���̓y�e���Ȃ�A�䂱�̔ւ̏�ɉ䂪��������Ă�B�i�����j���V���̌�����ɗ^����i�u�}�^�C�������v16�F18-19�j�A�Ƃ����C�G�X�̌��t�Ɋ�Â��B�y�e���̋���ł���B���̐����̑O�ɁA�V���̌������y�e���ƁA������p�E���́A��̒����������Ă���B�L���X�g�������E�@���ƂȂ�ߒ��ŁA�p�E���̉ʂ����������������ɑ傫�����������A�����̔z�u��������Ă���B
������^


 �@�����ւ̋^�O�������Ă��܂������A�����͂܂��Ƃɖ��͂ɖ����Ă���B���Z����A���ꋳ�t���u�������w�𗝉����悤�Ǝv���Ȃ�A������ǂ�ł����ׂ��c�v�ƌ������B�Ö{���Ŕ������������A���܂��苖�ɂ���B��݂����ɓǂ݂͂��߂����̂́A�����肱�������B�}�b�͏d�����邵�A��b���o�Ă��邽�тɋ^���������B������u�T���v�̂ł���B
�@�����ւ̋^�O�������Ă��܂������A�����͂܂��Ƃɖ��͂ɖ����Ă���B���Z����A���ꋳ�t���u�������w�𗝉����悤�Ǝv���Ȃ�A������ǂ�ł����ׂ��c�v�ƌ������B�Ö{���Ŕ������������A���܂��苖�ɂ���B��݂����ɓǂ݂͂��߂����̂́A�����肱�������B�}�b�͏d�����邵�A��b���o�Ă��邽�тɋ^���������B������u�T���v�̂ł���B
�@�����ɂ́A�A�u���n�����䂪�q�C�T�N���E���Ɩ�����ꂽ��i�u�n���L�v22�́j�A�`�l���u���������Ȃ���������i�u���u�L�v�j�ȂǁA���܂ł���̕�����Ȃ��͂����X����B����ł��A��g�Ƃ��ēǂ߂A�ւƃG�o�i�C�u�j�̒q�b�̉ʎ���m�A�̕��D�A�o�x���̓��ȂǁA�����ɕx�ޑ}�b������B�l�тƂ��o�x���̓������Ă悤�Ƃ���O�܂ł́c�S�n�͈�̌����̉��݂̂Ȃ肫�i�u�n���L�v11�F1�j�Ƃ���B����������ƁA�o�x���̓����Ăэ�肩�˂Ȃ��l�ނ̈�l�Ƃ��āA�@�������Ђ��ς����ꂽ�悤�ȋC���ɂȂ�B
�@�_�Ƃ����T�O�ɂ��ċ����[���\��������B���[�Z�����_���̖����~���Ɛ_�ɖ�����ꂽ�Ƃ��A�_�ɖ₢������B�C�X���G���̐l�X�����ɁA�_�̖��͉��Ƃ������Ɩ₤���Ƃ��A�ǂ�������悢���ƁB�_�G�z�o�͓�����B�c�w��͗L��č݂�҂Ȃ�B���������܂�����́A�������C�X���G���̎q���ɂ����ׂ��B��L�Ƃ����ҁA����Ȃ�Ɍ��킵���܂��x�Ɓi�u�o�G�W�v�g�L�v3�F14�j�B�u���n�l�َ��^�v�ɂ́c�����܂��A�̂��܂��A�カ���苋����Ȃ�S�\�̐_���������w��̓A���p�Ȃ�A�I���K�Ȃ�x�i1�F8�j�Ƃ���B�_�́u�L��č݂�ҁv�ɂ��āu���߂ł���I��v���ƌ����Ƃ��Ă���B
�@���{�ɂ͕������痈���i���⌿�����X����B�����ɂ������ɗR���������t�����X����B���̐��͓��{�ȏゾ�낤�B�����l�̖��O���A�����͐����ɗR�����Ă���B
�@���f���ꂽ���t�������A�˂Ă݂�B

 �@�_�A������ƌ������܂�����Ό����肫�i�u�n���L�v1�F3�j�͐_�b�̎n�܂�̌��t�Ƃ��ė͋����B�����Ă��̌��t�́A�V��u���n�l�������v�`���́A�c�����Ɍ�����A���͐_�Ƙ�ɂ���A���͐_�Ȃ肫�B���̌��͑����ɐ_�ƂƂ��ɍ݂�A�݂̕�����ɗR��Đ���A���肽�镨�Ɉ�Ƃ��ĔV�ɂ��Ő��肽��͂Ȃ��B�V�ɐ�������B���̐����͐l�̌��Ȃ肫�B���͈ÈłɏƂ�B�����ĈÍ��͔V����炴�肫�i1�F1-5�j�B�ւƂȂ���B�����Ɏg���錾
Word �́A�M���V�A�ꐹ���� Logos �̉p�Ƃ����i�u�p�ꐹ���̌��t�v�D�ˉp�v�A��g�V���j�B�P�Ȃ錾��ł͂Ȃ��A�����̈Ӗ������B���{�ɂ�����Ƃ����\��������B�������ɐl�ԂƂ��Ă̗����́A���t����Ƃ��납��n�܂����̂�������Ȃ��B�����āA�u���n�l�������v�ɂ������̓C�G�X�̓������������Ă���B
�@�_�A������ƌ������܂�����Ό����肫�i�u�n���L�v1�F3�j�͐_�b�̎n�܂�̌��t�Ƃ��ė͋����B�����Ă��̌��t�́A�V��u���n�l�������v�`���́A�c�����Ɍ�����A���͐_�Ƙ�ɂ���A���͐_�Ȃ肫�B���̌��͑����ɐ_�ƂƂ��ɍ݂�A�݂̕�����ɗR��Đ���A���肽�镨�Ɉ�Ƃ��ĔV�ɂ��Ő��肽��͂Ȃ��B�V�ɐ�������B���̐����͐l�̌��Ȃ肫�B���͈ÈłɏƂ�B�����ĈÍ��͔V����炴�肫�i1�F1-5�j�B�ւƂȂ���B�����Ɏg���錾
Word �́A�M���V�A�ꐹ���� Logos �̉p�Ƃ����i�u�p�ꐹ���̌��t�v�D�ˉp�v�A��g�V���j�B�P�Ȃ錾��ł͂Ȃ��A�����̈Ӗ������B���{�ɂ�����Ƃ����\��������B�������ɐl�ԂƂ��Ă̗����́A���t����Ƃ��납��n�܂����̂�������Ȃ��B�����āA�u���n�l�������v�ɂ������̓C�G�X�̓������������Ă���B
�@���͐o�Ȃ�ΐo�ɋA��ׂ��i�u�n���L�v3�F19�j�́A�_���A�_����y����n�������ƂɗR�����A�u���u�L�v�́c�䗇�ɂĕ�̑ق��o����B�����ɂĔޏ��ɋA���i1�F21�j�B�ɑΉ�����B
�@�V��̃C�G�X�̌��t�͐[���Ŕ������B�Ƃ��ɒp�������ė������ނ��Ƃ�����B�������A�}�l�̓����ŁA����Ȏꏟ�Ȏv���������Y��Ă��܂��̂����c�B
�@�����}�f�Ȏ��́A�������q��栂���A�S�C�̂����̈�C�̖�����r�̔�g���A�܂��悭�����ł��Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝ��⎩�����Ă���B
�@��̕S���͔@���ɂ��Ĉ�����v���A�J�����A�a������Ȃ�B�R��lj����ɍ����A�h���ɂ߂���\���������ɁA���̕������̉Ԃ̈�ɂ��y�����肫�i�u�}�^�C�������v6�F28-29�j�B����v������B�������A���炸�A�[�����q���Ȃ��B�R��ɐ_�͔V��{�������i�u���J�������v12�F24�j�B�ς͌�����A��̒��͚˂���A�R��ǐl�̎q�͖����鏊�Ȃ��i�u�}�^�C�������v8�F20�j�A�Ȃǂ͓��A���������ɔ�g�Ƃ��ėp���Ă���B
�@�Ȃ�̒��A�߂Ȃ��҂܂��āi�u���n�l�������v8�F7�j�A�͌������B����J�C�U���̕��̓J�C�U���ɁA�_�̕��͐_�ɔ[�߂�i�u�}�^�C�������v22�F21�j�A�͐��Ƒ��̌��E�������Ė����ł���B
�@���߂�A�R��Η^������B�q�˂�A����Ό��o����B���@���A����ΊJ�����i�u�}�^�C�������v7�F7�j�A�͈ӋC�j�r�����Ƃ��̎x���ƂȂ�B
�@���ׂČ����Ƃ�҂͌��ɂĖS�Ԃ�Ȃ�i�u�}�^�C�������v26�F52�j�A�͐��̌��͎҂������ׂĂɑ��肽���B
�@�D�ꂽ�@���ɂ͂ǂ������ʂ������̂�����B�������������łЂ��ƁA�R��Ζ}�Đl�Ɉׂ���Ǝv�����Ƃ́A�l�ɂ������̔@������i�u�}�^�C�������v7�F12�A�u���J�������v6�F31�j�A���w���ƋL�ڂ���Ă���B���̂��悻�ܕS�N�O�A�E�q�́A�Ȃ̗~�����鏊�͐l�Ɏ{�����Ɩ܂�i�u�_��V�߁v�畣12�A�F��N�l��A�u�k�Њw�p���Ɂj�ƌ������B

 �@�l�������̉E�̖j�������A������������i�u�}�^�C�������v5�F39�A�u���J�������v6�F29�j�͎ߑ��́A���݂ɕ�ɉ��݂��ȂĂ����Ȃ�A���ɉ��݂̑��ނ��Ƃ��Ȃ��B���݂����ĂĂ������ށi�u�^���̌��t�_���}�p�_�v1�F5�A��������A��g���Ɂj��A�V�q�u�����o63�v�́A���݂ɕ���ɓ����ȂĂ��i�u�V�q�v���J����A�u�k�Њw�p���Ɂj�ɋ��ʂ���B�E�q�́A�����ȂĂ����ɕ�B�����Ȃĉ��݂ɕA�����Ȃē��ɕ��i�u�_��V�߁v����14�j�ƌ������B��҉F��N�l�́u���v�����������Ɖ����Ă���B���̖��Ɋւ������A�̑�ȏ펯�l�������E�q�ɂ́A�ߑ���V�q�قǂ̐ꖡ���Ȃ��B
�@�l�������̉E�̖j�������A������������i�u�}�^�C�������v5�F39�A�u���J�������v6�F29�j�͎ߑ��́A���݂ɕ�ɉ��݂��ȂĂ����Ȃ�A���ɉ��݂̑��ނ��Ƃ��Ȃ��B���݂����ĂĂ������ށi�u�^���̌��t�_���}�p�_�v1�F5�A��������A��g���Ɂj��A�V�q�u�����o63�v�́A���݂ɕ���ɓ����ȂĂ��i�u�V�q�v���J����A�u�k�Њw�p���Ɂj�ɋ��ʂ���B�E�q�́A�����ȂĂ����ɕ�B�����Ȃĉ��݂ɕA�����Ȃē��ɕ��i�u�_��V�߁v����14�j�ƌ������B��҉F��N�l�́u���v�����������Ɖ����Ă���B���̖��Ɋւ������A�̑�ȏ펯�l�������E�q�ɂ́A�ߑ���V�q�قǂ̐ꖡ���Ȃ��B
�@�V��ɖ�������̂́A�Ƃ��ɃC�G�X�̐l�ԂƂ��Ă̓�������������Ƃ���ɂ���B
�@�Ō�̔ӎ`���I�����C�G�X�́A�Q�b�Z�}�l�̉��ɒ�q�������c���A�Ƃ��ɐi��ŋF��B�ނ͎���̉^����\�m���Ă���B��q�����́A�C�G�X�̋ꂵ�݂��@���邱�ƂȂ��A������������Ă��܂��B�C�G�X�͋F��B�c�w�킪����A�������ׂ����̎�t������߂����点�����B����lj䂪�ӂ̘ԂɂƂɂ͂��炸�A��ӂ̂܂܂Ɉׂ������x�i�u�}�^�C�������v26�F39�j�B�u���J�������v�ɂ́A�c�C�G�X�߂ݔ���A���悢��ɋF�苋���A���͒n��ɗ��錌�̎��̔@���i22�F44�j�B�Ƃ���B

 �@����ɕ������́A�\���˂Ɋ|����ꂽ�C�G�X�̍Ō�̌��t���L�^����B�c�O������A�C�G�X�吺�ɋ��тāw�G���A�G���A���}�A�T�o�N�^�j�x�ƌ��������B�킪�_�A�킪�_�A�Ȃ�������ċ������Ƃ̈ӂȂ�i�u�}�^�C�������v27�F46�j�B�u�}���R�������v�̋L�q���قړ��l�����A�u���J�������v�́A�c�w����A�킪������ɂ䂾�ʁx�z�������đ��₦���܂��i23�F46�j�A�ƊȌ��ɋL���݂̂ł���B�u���n�l�������v�́c�C�G�X�݂̎��̏I�肽���m��ā[�[�����̑S��������ׂɁ[�[�w��ꊉ���x�ƌ��������B�����Ɏ_���������̖�������킠��A���̕������̂ӂ��݂���C�Ȃ��q�\�v�ɒ����ăC�G�X�̌��ɍ������B�C�G�X���̕������������Č㌾�������B�w���L��ʁx�B���Ɏ������ė���킽�������i19�F28-30�j�A�ƋL�q����B�u�����̑S��������ׂɁv�̉ӏ��́A�u���сv22��19�́c�킪�͂͂��킫�ē���̂������̂��Ƃ��A�킪��͊{�ɂЂ�����B�Ȃ������̐o�ɂӂ���������c�ɗR������炵���B
�@����ɕ������́A�\���˂Ɋ|����ꂽ�C�G�X�̍Ō�̌��t���L�^����B�c�O������A�C�G�X�吺�ɋ��тāw�G���A�G���A���}�A�T�o�N�^�j�x�ƌ��������B�킪�_�A�킪�_�A�Ȃ�������ċ������Ƃ̈ӂȂ�i�u�}�^�C�������v27�F46�j�B�u�}���R�������v�̋L�q���قړ��l�����A�u���J�������v�́A�c�w����A�킪������ɂ䂾�ʁx�z�������đ��₦���܂��i23�F46�j�A�ƊȌ��ɋL���݂̂ł���B�u���n�l�������v�́c�C�G�X�݂̎��̏I�肽���m��ā[�[�����̑S��������ׂɁ[�[�w��ꊉ���x�ƌ��������B�����Ɏ_���������̖�������킠��A���̕������̂ӂ��݂���C�Ȃ��q�\�v�ɒ����ăC�G�X�̌��ɍ������B�C�G�X���̕������������Č㌾�������B�w���L��ʁx�B���Ɏ������ė���킽�������i19�F28-30�j�A�ƋL�q����B�u�����̑S��������ׂɁv�̉ӏ��́A�u���сv22��19�́c�킪�͂͂��킫�ē���̂������̂��Ƃ��A�킪��͊{�ɂЂ�����B�Ȃ������̐o�ɂӂ���������c�ɗR������炵���B
�@���_�_�҂Ƃ��ẮA�w��ꊉ���x�w�G���A�G���A���}�A�T�o�N�^�j�A�킪�_�A�킪�_�A�Ȃ�������ċ������x�w���L��ʁx�Ƃ��������ŃC�G�X�̓������悤�ȋC������B�����āw����A�킪������ɂ䂾�ʁx�̋L�q���Ȃ���A�������͏@�����Ƃ��Đ������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���B�u�}�^�C�������v�́c�C�G�X�Ăё吺�ɌĂ��đ��₦���܂��i27�F50�j�A�Əq�ׁA�Ō�̌��t���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������L���Ă��Ȃ��B
 �@���̊��𗬂��āw���̎�t������߂����点�����x�ƋF��A�w�킪�_�A�킪�_�A�Ȃ�������ċ������x�Ƌ��ԃC�G�X�ɁA�킽���͐M�̂���Ȃ��ɊW�Ȃ��[����𐂂��B�����āA�����̌��t�́A�C�G�X�̐_�i����j�Q����̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���B���̕|��ɋ��ނ��ƂȂ��A������Ə����c�����������L�҂����ɂ��A���l�Ɏ�𐂂��B
�@���̊��𗬂��āw���̎�t������߂����点�����x�ƋF��A�w�킪�_�A�킪�_�A�Ȃ�������ċ������x�Ƌ��ԃC�G�X�ɁA�킽���͐M�̂���Ȃ��ɊW�Ȃ��[����𐂂��B�����āA�����̌��t�́A�C�G�X�̐_�i����j�Q����̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���B���̕|��ɋ��ނ��ƂȂ��A������Ə����c�����������L�҂����ɂ��A���l�Ɏ�𐂂��B
�@���̍��̍Ō�ɁA���n�l������������p����B�c����_�͂��̓Ǝq�������قǂɐ�������������B�i�����j�_���̎q�𐢂Ɍ��킵���܂���́A����R����ׂɂ��炸�A�ނɂ��Đ��̋~����ׂȂ�B�i3�F16-17�j�B
�@�L���X�g���M�҂ɂƂ��āA���̌��t�قǐS�̋Ր��ɐG�����̂͂Ȃ����낤�B�s�K�ɂ��āA���͂����ł͂Ȃ����B
���C�����A�i�O�E�n�}�f�B����
�@1947�N�A�܂��C�X���G���Ƃ������͒a�����Ă��Ȃ��B�r�����̃x�h�E�B���̏��N���A�Q�ꂩ��͂��ꂽ�q���M��T���Ă����B���C���ݖk�����̒f�R�̒��قǂɁA���A�̂悤�ȓ������������������B�q���M����������ł��Ȃ����ƁA���N�͏��𓊂����B�₪�����悤�ȉ��������B�R���悶�o���Ĕ`�������N�́A�����ƕ��f�Ă��̚�ɋ������B���C�����̔����͂��̂悤�ɁA�������߂��Č����B�Ă̏���������悤�Ƃ����s���l�����������Ƃ����ʂ̐�������B
�@�������c���ꂽ���A�́A���v��11�ӏ��������B���@��Ƃ́A�C�X���G���Ɨ��ɔ��������푈�ɂ��т��ђ��f��]�V�Ȃ����ꂽ���A���܃C�X���G�������قɕۑ��W������Ă���B
�@�����̂قƂ�ǂ͗r�玆�ŁA�G��{���{���ɂȂ�قNJ������Ă����B���݃K���X�ɋ��܂�ĕۑ�����Ă��邪�A�܂��J���s�\�Ȃ��̂�����B���̊����ɂȂ������̂́A�_�����Ђǂ��A�̂�����Ő��ď��Ђɕ����čL�����Ƃ����B
�@���_�����ɂ͖ʔ������K���������B�Â��Ďg���Ȃ��Ȃ����ʖ{�́A�葱����Ŕp������Ă����B���̂��ߌÂ�����̎ʖ{�͑��݂��Ȃ��B�K���ɂ��āA�V�����ʖ{�����ꍇ�A�����ċL���ɗ����ď�����Ă͂Ȃ炸�A�K�����ƂȂ�ʖ{�̒ʂ�ɏ������Ƃƒ�߂��Ă����B
�@���̂��ߌ��ݎg���Ă��鋌�����A���ƂȂ�ʖ{�͈ӊO�ƐV�����B10���I�̎ʖ{�u�}�\���{���v�ł���B�}�\���Ƃ̓w�u���C��Łu�`���̓`�B�v���Ӗ�����iWikipedia�j�B
�@1902�N�AW�DL�D�i�b�V���i�����l�Êw����鏑�j���A�G�W�v�g�ŌÕ�������ꖇ�̃p�s���X���w�������B����͌�2���I���ɏ����ꂽ�����ʖ{�̒f�Ђ������B��Ƀi�b�V���E�p�s���X�ƌĂ��悤�ɂȂ�B��������̓w�u���C����24�s�̒f�Ђɉ߂��Ȃ��B
�@���̂悤�Ȕw�i��m��ƁA�I���O��ɏ����ꂽ�Ƃ���鎀�C�����̔������A�����ɑ傫�Ȕ������ĂыN���������z���ɓ�Ȃ��B
�@�������ꂽ���C�����̑啔���́A�}�\���{���̓`���ɑ����Ă����B10���I�̎ʖ{���A�I���O��̎��C�����ɂ���ė����ꂽ���ƂɂȂ�B����͓����ɁA�ʖ{���X�V����ۂ̊��K�������Ɏ���Ă������Ƃ������Ă����B�����ɔ[�߂��Ă��Ȃ��@���I�����̑��݂́A���T�Ҏ[���������������Ƃ��������Ă���B����ɋ����[���̂́A�������ɔ[�߂ĕۊǂ�������ȏ@�������̂̊����L�^�A������A70�N�̐_�a����ȑO�̂��̂��܂܂�Ă������Ƃł���B�C�G�X�Ǝg�k�����̊������A������x���@��������̂ł��������B
�@�m�������@���g�D�ɂƂ��āA�V���������͂Ƃ����荢�f�������B���`�̕ύX��]�V�Ȃ������\��������B�������V���ƃC�X���G���͊��}���ׂ������ƂƂ炦���B����̃A�C�f���e�B�e�B�[���������A�����ӎ������g�ł���ƍl�����̂ł���B����ȏ@�������̂̊����L�^�́A�C�X���G���ɂƂ��āA�����͂����Ă������Ė��f�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�������A�o�`�J���̋��c���ɂƂ��āA�ʂ����Ċ��}���ׂ����̂��������낤���B

 �@�C�X���G�������ق̊O�ς́A�������ꂽ����̊W���C���[�W�����ʂ˂��^�����Ă���B�O��ɂ�50����1�ɏk�����ꂽ���_�a����̃G���T�����̐��I�Ȗ͌^���W������Ă���B
�@�C�X���G�������ق̊O�ς́A�������ꂽ����̊W���C���[�W�����ʂ˂��^�����Ă���B�O��ɂ�50����1�ɏk�����ꂽ���_�a����̃G���T�����̐��I�Ȗ͌^���W������Ă���B
�@���������C�y�́A�Ñ�̈�Ղ╶�������ɂ܂Ŏc���Ă����B1945�N�A�G�W�v�g�̃i�O�E�n�}�f�B���ŁA�A���u�l�_�v���y���������@��o�����B��ɂ͔�ŒԂ���ꂽ�R�f�b�N�X�i���q��̎ʖ{�j��12����8���̒f�Ђ������Ă����B�������ꂽ�������Ƃ��ăi�O�E�n�}�f�B�����Ƃ����B�����̓��N�\�[�����璼�������Ŗ�60�q�k�Ɉʒu����B
�@�ʖ{�͂��̒n��̏C���m�����̂��������Ă������̂炵���B�㕔�g�D���琳�T�ł͂Ȃ�������p���Ȃ��悤�w�����A�B�������̂ł͂Ȃ����Ƒz�肳��Ă���B�ʖ{�̎��M��B���̎�����3�`4���I�Ƃ���Ă��Ĉ٘_�͂Ȃ��B�ʖ{�̑唼�̓O�m�[�V�X��`�h�̕����ŁA���c������ْ[�Ƃ���Ă���B���ł��ł��L���Ȃ��̂��u�g�}�X�������v�Ɓu���_�������v�ł���B�O�m�[�V�X��`�́A1���I����4���I�ɂ����Ēn���C���E�ň��̐��͂��������@���v�z�������B�O�m�[�V�X�Ƃ̓M���V�A��Łu�F���A�m���v���Ӗ����AWikipedia �ɂ��A���Ȃ̖{���Ɛ^�̐_�ɂ��Ă̔F���ɓ��B���邱�Ƃ����߂�v�z�A�Ƃ���B�䗬�ɍl����A�m�I�ɐ_�̑��݂�Njy����Ƃ������Ƃ��낤�B�˂��l�߂�߂�قǁA�L���X�g���{������͂ݏo���Ă��܂��B�ْ[�Ƃ��ꂽ�̂��K�R�ƌ�����B
�@�u�g�}�X�ɂ�镟�����v�i�r�䌣��A�u�k�Њw�p���Ɂj�ɓo�ꂷ��C�G�X�́A���R�̂��ƂȂ���A�V��̎l�̕������Ɣ����ɈقȂ�B�Ⴆ�A
�@�c�C�G�X���������u�������Ȃ��������҂����Ȃ������Ɂw����A�䍑�͓V�ɂ���x�ƌ����Ȃ�A�V�̒������Ȃ�����������Ɂi�䍑�ցj����ł��낤�B�ނ炪���Ȃ������ɁA�w����͊C�ɂ���x�ƌ����Ȃ�A�������Ȃ���������Ɂi�䍑�ցj����ł��낤�B�����ł͂Ȃ��āA�䍑�͂��Ȃ������̑����ɂ���B�i�����j�������A���Ȃ����������Ȃ��������g��m��Ȃ��Ȃ�A���Ȃ������͕n���ɂ���A�����Ă��Ȃ������͕n���ł���v�i3�j�Ƃ�����߂́A�O�m�[�V�X�i�F���A�m���j���咣����h�́A���`�̓������悭���킵�Ă���B�����V��̂Ȃ��ŁA�C�G�X����q�����ɂ��̂悤�ɋF��Ƌ������c�V�ɂ��܂����̕���A�肭�͌䖼�̐��߂����B�䍑�̗�����Ƃ��B��ӂ̓V�̂��Ƃ��A�n�ɂ��s���Ƃ��i�u�}�^�C�������v�i6�F9-10�j�A�u���J�������v�i11�F2-4�j�A�Ƃ͂�����Ȃ��B���c���Ƃ��Ă��A���Ƃ���g�ł���Ƃ͌����Ă��A���⋛����ɓV���֍s���Ă��܂��Ă͍��邾�낤�B���̂ق��ɂ��A
�@�c�V�����E�y�e�����ނ�Ɍ������A�w�}���n���i�}�O�_���̃}���A�j�͎������̂��Ƃ��狎���������悢�B�������͖��ɒl���Ȃ�����ł���x�B�C�G�X���������A�w����A���͔ޏ����i�V���j�����ł��낤�x�i114�j�B���̂悤�Ɍ�����ƁA�y�e�����C�G�X���̒�q�Ƃ��鋳�c���ɂƂ��Ď����̂ł͂Ȃ����낤���B
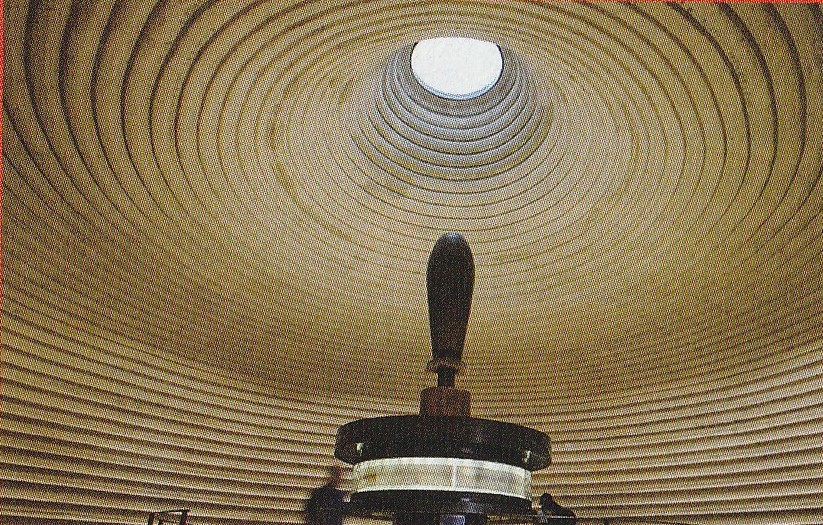
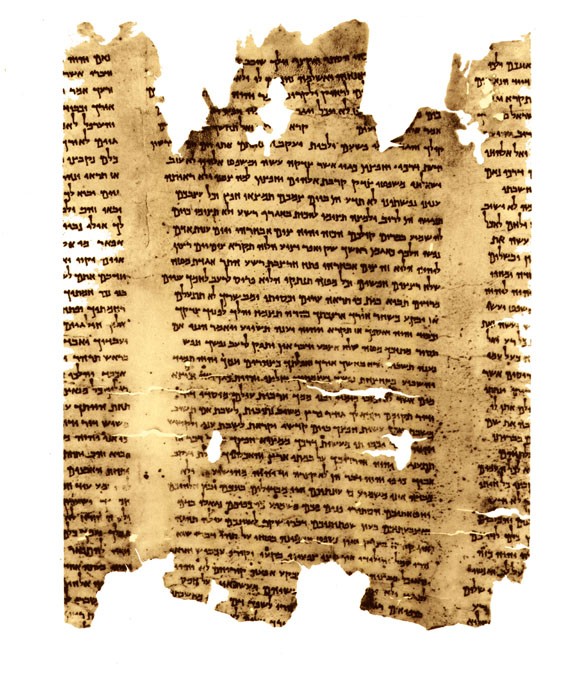 �@�u���_�������v�͂���Ɏh���I�ł���B�C�G�X���ł��悭���������҂̓��_���Ƃ���B�G���[�k�E�y�C�Q���X�A�J�����EL�E�L���O�����u���_�������̓�������v�i�R�`�F�v�A�V�ƍv��A�͏o���[�V�Ёj�́A150�N��̂��鎞���Ɂu���_�������v�͎��M����A���҂͕s�����Əq�ׂĂ���B���������݂��Ď����_���g���������͂����Ȃ��B���̏��ɂ́A�������u���_�������v���̂��̂����^����Ă���B����ɂ��ƁA���_�͎��E�����̂ł͂Ȃ��A���Ԃ̒�q�����̐Αł��ɂ���ĎE���ꂽ�Ƃ���B�L���X�g���k�ɂ�郆�_�̎����������A���_���̍Վi���◥�@�w�҂������A���[�}�鍑�̔��Q�ғ��l�O��I�ɔ���B�ْ[�Ƃ���Ă��d�����Ȃ��ߌ����ł���B
�@�u���_�������v�͂���Ɏh���I�ł���B�C�G�X���ł��悭���������҂̓��_���Ƃ���B�G���[�k�E�y�C�Q���X�A�J�����EL�E�L���O�����u���_�������̓�������v�i�R�`�F�v�A�V�ƍv��A�͏o���[�V�Ёj�́A150�N��̂��鎞���Ɂu���_�������v�͎��M����A���҂͕s�����Əq�ׂĂ���B���������݂��Ď����_���g���������͂����Ȃ��B���̏��ɂ́A�������u���_�������v���̂��̂����^����Ă���B����ɂ��ƁA���_�͎��E�����̂ł͂Ȃ��A���Ԃ̒�q�����̐Αł��ɂ���ĎE���ꂽ�Ƃ���B�L���X�g���k�ɂ�郆�_�̎����������A���_���̍Վi���◥�@�w�҂������A���[�}�鍑�̔��Q�ғ��l�O��I�ɔ���B�ْ[�Ƃ���Ă��d�����Ȃ��ߌ����ł���B
�@���c���̓i�O�E�n�}�f�B�����̔������ɗ͍T���߂Ɉ������B�w�ҊԂ̘_��ɂ��Q�����Ȃ������B���N�̗��j�������`��ύX��������̂ł͂Ȃ��Ƃ����B�M�҂ł͂Ȃ��킽���ɂ́A�Ⴄ�C�G�X��m�邱�ƂŁA���炽�߂Ĕނ̑傫����F���ł���Ǝv���̂����A�L���X�g���{���̏@���҂����ɂƂ��Ă͂������f�Ȕ����������B
�@�V���������̔����́A�C�X���G���ɂ͊�т��A���c���ɂ͍��f�������炵���̂ł���B
�C�X������
�C�X�������̗��r�_
�@�A�u���n���ƍȃT���ɂ́A�N�V���Ă��q�����Ȃ������B�_�́A�A�u���n���ɃJ�i���̒n��^����Ɩ������A�������ׂ��q�����Ȃ��B�T���͕v�ɁA�����n�K���ƌ����q����悤�ɂƊ��߂��B�j�������܂�A�A�u���n���̓C�V�}�G���Ɩ��Â����B���̂Ƃ��A�u���n����86�������i�u�n���L�v16�j�B
�@�A�u���n����99�̂Ƃ��A�_�G�z�o�͔ނɒj�̎q��������ƍ�����B�ނ́A99�̕v��90�̍ȂƂ̊ԂɎq���Ȃǐ��܂��͂����Ȃ��A�ƐS�̒��ŚA���B�_�́A���܂ꂽ�q���C�T�N�Ɩ��Â���悤������B�A�u���n���͏��q�ƂȂ�C�V�}�G���̏�����J���B�_�́A�C�V�}�G���ɂ́u���O�̎q�������߁A��ɔނ̎q���𑝂��ׂ��v�ƍ�����B���͂��̎��܂Ŕނ̖��̓A�u�����������B�Ȍ�A�u���n���i�O���̐l�̕��j�Ɩ��O��ς���悤�ɖ�������B�Ȃ��T���C���������T���ƕς��B���̖��O�̕ύX�ɂ͐������Ȃ��B�u���M�̖��̕�ƂȂ炵�ނׂ��v�Ə�����Ă��邾���ł���B�Ȃ��A����ɂ��Ă������ɋL�q����Ă���i�u�n���L�v17�j�B
�@�_�ɕs�\�͂Ȃ��B��l�͒j����B�A�u���n����100�ɂȂ��Ă����i�u�n���L�v21�j�B
�@���ȃT���Ɏq�����܂��A�n�K���ƃC�V�}�G���̋��ꏊ���Ȃ��Ȃ�B�A�u���n���͐_�̖�M���āA�v�܂ɓ��ꂽ���ƃp�����n�K���ɕ��킹�A��l���Ƃ���o���B�r���f�r������l�́A�p���������s���Đ�����]�݂������B�n�K���́A�킪�q��̉��ɒu���A���ꂽ�Ƃ���ɍ����ċ����B�킪�q�̎���ōs���̂�����ɔE�тȂ������̂ł���B�_�͓�l�̋��������Ƃǂ���B�n�K���̎��ɐ_�̐��������B

 �@�c�N�ē����������V����̎�ɕ����ׂ��B��V���Ȃ鍑�ƂȂ���ƁB�_�n�K���̖ڂ��J�����܂�����ΐ��̈䂠������A�i�����j�_�����Ƙ�ɍ݂��B�ސ��ɐ�����D��ɋ���Ďˎ҂ƂȂ�p�����̞D��ɏZ�߃��B����ނ̂��߂ɃG�W�v�g�̍����Ȃ��}������i�u�n���L�v21�F18-21�j�B
�@�c�N�ē����������V����̎�ɕ����ׂ��B��V���Ȃ鍑�ƂȂ���ƁB�_�n�K���̖ڂ��J�����܂�����ΐ��̈䂠������A�i�����j�_�����Ƙ�ɍ݂��B�ސ��ɐ�����D��ɋ���Ďˎ҂ƂȂ�p�����̞D��ɏZ�߃��B����ނ̂��߂ɃG�W�v�g�̍����Ȃ��}������i�u�n���L�v21�F18-21�j�B
�@���̃C�V�}�G�����A���u�����̑c�ƂȂ����A�Ƃ����̂��R�[�����̂Ƃ闧��ł���B�C�X�������Ƃ����ď̂��A�C�V�}�G���ɗR������B�u�R�[�����v�ɓo�ꂷ��l�X���A�����̈Ⴂ�����ŁA�A�u���n���̓C�u���[�q�[���A���[�Z�̓��[�T�[�A�m�A�̓k�[�t�A�}�����̓}�������A�C�G�X�̓C�[�T�[�A��V�g�K�u���G���̓W�u���[���A�T�^���̓V���C�^�[���ƂȂ�B
�@����z������͓̂�����A�R�[�����͑S�������ƌ����Ă����炵���B����̓g���R����_���Ŏ��ɂ����A�U�[���i��q�̌Ăт����j������z�������B�R�[������|���䓛���̉���ɂ��A�R�[�����̌���u�N���A�[���v�͂��Ƃ��Ɠ��u���Ӗ������Ƃ���B
�@�c�����ĉ�烀�[�T�[�ɐ��T�����^���A�ނ̂��Ƃ����X�Ɓi���́j�g�k�����킵�A�i���ł��j�}�������̎q�C�[�T�[�i�}�����̎q�C�G�X�E�L���X�g�j�ɂ͐��X�̐_����^���A������ɂ���āi���ɔނ��j�x�����B�Ƃ��낪����i���_���l�����j�͌Ȃ��C�ɂ���ʁi�[���j���g�����g�k������邽�тɘ��ݕs���̑ԓx�������A�i�����̎g�k�́j������̂��ΉR����Ƃ̂̂���A��������͎̂E�Q�����i2.�u�ċ��v81�j�B
�@���_�������Ɍ[�������������A�s�������܂�Ȃ��̂ŁA����ǂ͂��炽�߂ăC�V�}�G���̎q�����n���}�h�Ɍ[�����������A�Ƃ����̂��C�X�������̗���ł���B
���n���}�h�̐��U
�@�����܂ł��Ȃ��R�[�����̓��n���}�h���_������[�����L�^�������̂ł���B���n���}�h�����������̂ł͂Ȃ��B���̓_�A�����Ƃ͑S���قȂ�B�|��҈䓛���̌��t�����ƁA�u�_������̏�Ԃɓ�������l�̗�I�l�Ԃ��A������Ԃɂ����Č����������t�̏W�听�v�ł���B
�@���n���}�h�͕��ӂ������ƌ�����(Wikipedia)�B�_�̌[���������n���}�h�́A���̌��t���o���Ă����A�ʂ̎҂ɏ����Ƃ点���B�@���ƂƂȂ�O�́A���l�Ƃ��Đ������Ă���A���S�ȕ��ӂł͂Ȃ������Ǝv�������Ȃ��Ƃ����{�l�ł͂Ȃ������̂��낤�B
�@�R�[������ǂނƁA�܂��L�ڂ̏����Ɋ���Ȃ����Ƃɍ��f����B�[�����������ł��Ȃ��B���̕��ꐫ���Ȃ��B�������e�́A���̂Ƃ��ǂ��̏o�����ɑΉ����Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�ނ͖�肪�N�����s�x�A�_�̌[������������ł���B
�@�䓛���̉���ɏ]���āA���n���}�h�̈ꐶ���R�[��������H���Ă݂邱�Ƃɂ���B
�@�ނ�570�N�����b�J�ɐ��܂ꂽ�B����̃N���C�V���Ƃ̈ꑰ�ł͂��������A���܂�ĕ���m�炸�A6�ŕ���������B�c���Ɉ������ꂽ���A�����3�A4�N�Ŏ��ɁA�����̃A�u�[�E�^�[���u�̉��Ő��������B
�@�c�悢���A�ǎ��͌����ĉՂ߂Ă͂Ȃ�ʂ��B����Ɍ����Ď��ɂ��Ă͂Ȃ�ʂ��i93.�u���v9-10�j�B���̏͋�ɂ́A�ނ̑̌������f���Ă���B
�@�₪�ă��n���}�h�̓n�f�B�[�W���Ƃ������S�l�̌o�c������Տ��ЂɌق���B�����Ȑl���ŐM�p���B���l�Ƃ��Ď��т��グ���ނ́A�n�f�B�[�W�����猋����\�����܂��B���n���}�h25�A�n�f�B�[�W����40�ΑO��B�v�������ʍK�^�Ɍb�܂ꂽ���n���}�h�́A15�N�قǁA�����ȓ��X�𑗂����B40�ɂȂ�������A�ނ̐S�ɉ�����������Ȃ��v�������܂ꂽ�B�ǓƂ��ґz�ւ̗~���ɂ����A�Ƃ����胁�b�J�ߍx�̃q���[�R�̓��A�ɂ�����A�֗~�����𑗂����B�ނ͏����ł��т��уV���A��K��Ă����B�����ŁA�L���X�g���C���m�����̐^���Ȑ����ԓx�Ɏh�������̂ł́A�Ɛ��@����Ă���B�����̃��b�J�́A�����ƈ����̋������q�̓s�������B
�@�c�u�i�U���l�v�Ǝ��̂���l�X�i�L���X�g���k�j�B����Ƃ����̂́A�ނ�̒��ɂ͎i�ՂƂ��C���m�Ƃ������҂���R�����āA�݂���ɘ����ȐS���N�������肵�Ȃ����炾�i5�u.�H��v85�j�B
�@����N�̃��}�U���̌��̂����A���A���ґz���Ă��郀�n���}�h�ɁA�ˑR�����R�I�Ȉ��͂��̂����������B����ނ͂����V�g�W�u���[���i�K�u���G���j�̍~�ՂƉ������B�V�g�͔ނ̍A�����Ђ��͂�ŁA�����Ȃ�u�u�߁v�Ɩ������B�u�킽���͓ǂݏ������ł��ʖ��w�̂��́B�킽���ɉ����u�߂܂��傤�v�ƌ����ƁA�V�g�͔ނɐ_�̌��t��`�����B
�@�c�u�߁A�u�n����Ȃ��̌䖼�ɂ����āB���Ƃ��������Ì�����l�Ԃ��Αn��Ȃ������B�v�@�u�߁A�u���̎�͂���Ȃ��L������B�M�����ׂ����������B�l�Ԃɖ��m�Ȃ邱�Ƃ����������v�Ɓi96.�Ì�1-5�j�B
�@�c�������ɁA���肠��ƒn���̔ޕ��ɂ��p��ށi�}�z���b�g�j�͔q�����i81.�u��������v23�j�B���̂Ƃ��A�ނ͓V�g�̎p�������ƐM����B
�@���������ނ͉Ƃɓ����A��A�Ȃ̕G���v������B�Ă����舫��ɂƂ���ꂽ�Ǝv�����̂ł���B��Âȃn�f�B�[�W���́A���ꂪ�_�̗슴�ł���ƐM�����B�v���܂��A�͂Â��A�ނ��A���r�A�̗a���҂ւƐ����������B�����āA�ޏ��͍ŏ��̐M�҂ƂȂ����B
�@�V�@�������������n���}�h���������A�T���ȊK���̃��b�J�̐l�тƂ͔ނ����l�������A�o�����̂ɂ����B����������ɐM�҂̐��������A�����ł��Ȃ��Ȃ�B�V�@���́A�����n���̗B��_���q�������A���b�J�̐l�тƂ��M�����c�`���̐_�X��ے肷��B�R�[�����̎Љ��́A�n�R�l�ɓs���悭�A�������ɂ͋�����������B�Љ��`�I�ł���B����N���C�V�������͂��߂Ƃ��郁�b�J�x�z�w�́A���͂������ĐV�@���������Ԃ����Ƃ����B�V�@���̐M�҂̑����͕n�����K���̐l�тƂł���B�L�͎҂������爳�͂���������ƐM���h�炬�����B���肠�����A�ő�̎x���҃n�f�B�[�W���Əf���A�u�[�E�^�[���u�����ʁB�������������S�̃A���u�Љ�ŁA���n���}�h�͌�돂���������B
�@�l�ʑ^�̂ƂȂ������n���}�h�́A���f�B�i�ւ́o�J�s�p�֓��ݐ�B�����A���f�B�i�ɏZ�ރA���u�l�̓C�G�����n�ŁA�j�U�[�������S�̃��b�J�ɑR�ӎ��������Ă����B�����āA�x�T�ȃ��_���l�������Z�݁A�B��_�̎v�z����قł͂Ȃ����������B
�@�����̃C�X�������́A���_�����k�A�L���X�g���k�𒇊Ԃƍl���Ă����B���[�Z���͎O�@�����ʂ̐��T�ł���B�ނ���A������������A���r�A�̐l�X���א_���k�Ƃ��ēG�������B���ꂪ�A���f�B�i�ւ̑J�s�����߂��ő�̗v���������B
�@�n�f�B�[�W���̕G���v����قǂɋC��Ȗʂ����������n���}�h���������A�ق�10�N�̊ԂɁA�V�@���̃��[�_�[�Ƃ��Ė��ނ̐�������g�ɂ��Ă����B�o�J�s�p�ɂ��Ă��A���s��2�N���O����T�d�ɕz��ł��Ă���B�܂��M�k���ړ�������Ս��������B���O�H��͐������A���f�B�i�̐l�тƂ̓��n���}�h�̈�s�����҂���B�ގ��g�͕��S�̗F�A�A�u�[�E�o�N���Ɠ�l�A�N���C�V�����̌��d�ȊĎ����������ă��f�B�i�֓������B622�N7��16���A���̓����C�X��������N�ƂȂ�B�A�u�[�E�o�N���̓��n���}�h�S����A����̋��c�i�J���t�j�ƂȂ�l�ł���B
�@���̎���̃R�[�����ɂ́A�����̕��ꂪ�A�����ɉɂ��Ȃ��قǏo�Ă���B���̌����́A�܂�ʼnf�������悤�ɋr�F����Ă���B���_���̐l�тƂ̊��S�����Ƃ����̂��낤���B����������B�_���A�u���n���ɁA�T���Ɏq�������܂��ƍ������ӏ��i�u�n���L�v18�͂ɑ����j�ł���B
�@�c�ޏ��͌������B�u�����A��Ȃ��A���̏��Ɏq�������߂܂��傤���B���͂��̒ʂ�̘V�k�A��l�͂��̂悤�Ȗ�ł��̂ɁB���ꂱ����Ȃ͂Ȃ��Ƃ������́v�ƁB����Ɣނ�i�_�̎g���j�́A�u�A�b���[�̌䖽�߂���Ǝv���̂��B�A�b���[�̂��b�݂Əj���Ƃ����O������Ƃ̏�ɂ���܂��悤�ɁB�܂��ƁA�i�A�b���[�j�����͂��Ƃ��M���A�h���ɖ����������ɂ��킵�܂��v�ƍ������i11.�u�t�[�h�v75-76�j�B
�@���f�B�i�ɓ��������n���}�h�́A��@���W�c���A�C�X�����������̂ւƐi��������B�u���̂Ȃ���v�Ɋ�Â����������̂ł͂Ȃ��A���ʂ̍��J�ƁA���ʂ̗��Q�W�Ɋ�Â��L���A���R�ȋ����́A���Ȃ킿�����́u�T���Z���鍑�v�ւƔ��W�����b��ł����Ă��̂ł���B
�@���̓W�J��ǂ��Ƃ��Ȃ������̂́A�ŏ����}�����͂��̃��_���l�����������B��_���̃��_���̐l�тƂ́A���_���̃A���u�l�ƁA�@���I�ɂ͑Η����邪�A�������Ԃł��������B���Ղŕx���l�тƂł���B�C�X�������M�҃O���[�v�̔��W�́A�V���ȏ����G�̏o���������B�G�̓G�͗F�ł���B���_���l�����́A���b�J�̃A���u�l�����Ǝ�����сA�A�ɗz�Ƀ��n���}�h�����̊�����j�Q���n�߂�B�ނ�Ɋւ���R�[�����̌��t�͌������B
�c�������킳���͈̂����̐l�X�̂݁B���Ȃ킿�A�A�b���[�ƌł��_�������ł����Ȃ���A���C�ł����j��A�A�b���[�����ׂƖ������������̂����Ƃ���ɍق����āA�n��Ɉ����Ȃ��l�X�̂݁B������₩��͖S�т̓���H��s���l�X�i2.�u�ċ��v24-25�j�B
�@���n���}�h�̓L�u����ύX�����B�L�u���͋F��̕��p�������B���ׂẴ��X�N�ɂ̓~�t���[�u�Ƃ����_���Ȃ��ڂ݂�����A���b�J�����Ă���B���f�B�i�֑J�s���������A���n���}�h�̓G���T�����Ɍ������ė�q����悤�w�����Ă����B���_���̐l�X�𖡕��Ɉ�������悤�Ƃ��Ă����̂ł���B���_���l���G���Ă����ȏ�A�G���T�����������K�v�͂Ȃ��B�ނ́A���b�J�̐_�a�J�A�o�F��̕��p��ύX�����B�����ɂ͐_���ȍ�������B
�@���Ƃ��Ɛ𗧂āA������u�_�̂��h�v�Ə̂��A���̐������č��J���s�����Ƃ̓A���r�A�����łȂ��A�Ђ낭�Ñ�Z���l�̐��E�S�ʂɌ����錻�ۂł���B���ꂪ�Ƃ��Ɉ����ł��������Ƃ������ł��낤�B���{�̉̊_�A�k���̔���ՂȂǂɂ��ʂ�����̂�����B
�@���n���}�h���L�u���̕��p�����b�J�̐_�a�֕ς����Ƃ��A�����͂܂����_���̑��A�������B���n���}�h���猩��Ί��݂��ׂ������Ȑ��ΐ��q�ł���B�ނ͐_�ɋF��B�����āA���p��ς���Ɠ����ɁA���̊T�O�܂ŕύX���邨��������B
�@�c�ȑO�ɂ��O�i�}�z���b�g�j���̂��Ă����F��̕��p�����i�A�b���[�j�����̂悤�Ɂi�C�G���T�����Ɍ����āj��߂��̂́A����͌����A�{���Ɏg�k�i�}�z���b�g�j�ɂ��ė���l�ƁA�w�������Ă��܂��҂ǂ��Ƃ��͂����茩�����邽�߂̕��ւ������̂��B�i�����j�������Č��Ă���ƁA���O�i�}�z���b�g�j�́i�ǂ����������Ă��F�肵�Ă����̂�������Ȃ��Ȃ��āj�������낫��댩�Ă���B�悵�A����Ȃ炱���ł��O�ɂ����S�̂����悤�ȕ��p�����߂Ă�낤�B�悢���A���O�̊�Ȃ��q���i���b�J�̐_�a�j�̕��Ɍ�����i2.�u�ċ��v138-139�j�B
�@�c����A����C�u���[�q�[���i�A�u���n���j�̐M�ɏ]����B�ނ����͏����Ȃ�M�̐l�������B�������q�̂₩��ł͂Ȃ������i3.�u�C�����[����Ɓv89�j�B
�@�c�܂����i�A�b���[�j�����a�i���b�J�̃J�A�o�j�l�̊҂藈��ꏊ�ƒ�߁A���S�n��ɒ�߂����̂��ƁB�u����C�u���[�q���̗����i�J�A�o���ɂ��鐹�A�����ɃA�u���n�������������Ƃ����B�w�A�u���n���̑��Ձx���c���Ă���B�_���ȍ��Ƃ͕ʂ̐��j���F���̏ꏊ�Ƃ���v�Ɓi2.�u�ċ��v119�j�B
�@�A�u���n���̐��Ɍ������ċF��A�����ꏊ�ɂ��鐹�Ȃ鍕���A����Ĉ�_���̐M�̋���ǂ���ƂȂ�B
�@���n���}�h�ɂƂ��āA�s���̗ǂ��������ɁA�s���̗ǂ��_�����������悤�Ɏv����B�ٌ삷��킯�ł͂Ȃ����A�ނ̗���ɗ����čl���Ă݂����B����������Ƃ��A������ӂ܂ł��̉�������l����B��S�s���ɐ_�ɋF��B������ԂƂȂ����Ƃ��A�������Ђ�߂��B�܂��ɂ��ꂪ�_�̌[�����ƁA�ނ͐M����B�����āA�s���Ɉڂ��B
�@�C�X�������k�̊Ԃł́A�J�A�o�̓A�_���ƃC�u���_�ɖ������č�����_�a�ŁA�m�A�̎����^���Ŏ���ꂽ���A���̌�A�A�u���n���ƃC�V�}�G�����Ăь��������A�Ƃ����`��������B�������A�����ɂ��̂悤�ȋL�q�͂Ȃ��B
 �@�㐢�Ɏ���ƁA���Ȃ鍕�̓��n���}�h���������Ƃ����`�������܂��B�n�f�B�[�X�i���n���}�h�̌��s��j�ɂ́A���n���}�h�̌��t�Ƃ��āA���͔ނ��������Ƃ��A�����i�Ō�̐R���j�̓��ɂ́A���ɖڂ���������A����ɐG�ꂽ���Ƃ̂���҂ٌ̕������A�Ƃ�������|�̋L�^������iWikipedia�A�C�u���E�C�X�n�[�N�u�a���ғ`�v�j�B
�@�㐢�Ɏ���ƁA���Ȃ鍕�̓��n���}�h���������Ƃ����`�������܂��B�n�f�B�[�X�i���n���}�h�̌��s��j�ɂ́A���n���}�h�̌��t�Ƃ��āA���͔ނ��������Ƃ��A�����i�Ō�̐R���j�̓��ɂ́A���ɖڂ���������A����ɐG�ꂽ���Ƃ̂���҂ٌ̕������A�Ƃ�������|�̋L�^������iWikipedia�A�C�u���E�C�X�n�[�N�u�a���ғ`�v�j�B
�@�L�u���̕ύX�̓��_������L���X�g������̌��ʂ��Ӗ������B���n���}�h�́A�u�����Ȃ�M�̐l�v�ƃA�u���n�����^����B�J�A�o�̑n�n�ҁi�Č��ҁj�����A���n���}�h����������c��ł���A�C�X�������̉��c�ƂȂ邨�����Ƃ���B���_�����ł��L���X�g���ł��Ȃ��A�C�X�����������^�̈�_���ł���Ƃ����Ɨ��錾�������B�����I�ȈӖ��ŁA���n���}�h�̌��f�̑����Ɛ��m���͌����Ƃ����ق��͂Ȃ��B
�@�J�A�o���C�X�������̒��S�_�ƌ��߂����n���}�h�́A�U���ɓ]����B�J�A�o�̂��郁�b�J�͋w�G�N���C�V�����̎蒆�ɂ���B�C�X�������k�̎�Ɏ��߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�_�̂�����������B
�@�c����A�a���҂�A�M�҂�������肽�ĂĐ킢�Ɍ����킹��B����A�E�ϋ����҂���\�l������A��S�l�͏[���ł���������B�������炪�S�l������A���M�҂̐�l���炢�[���ł���������i8.�u�험�i�v66�j�B��ϗE�܂������A����E��풆�̌R���̐��_�_���v���o�����āA���܂肢���C�����ł͓ǂ߂Ȃ��B
�@�c�����A�i�l�����́j�_�������������Ȃ�A���_���k�͌�������A�E���Ă��܂����悢�B�Ђ������A�ǂ����݁A������Ƃ���ɕ�����u���đҕ�����i9.�u�����v5�j�B
�@���n���}�h�͂��Ƃ��Ə��l����������A���Ղɐ�����N���C�V�����̎�_���悭�m���Ă����B���ڃ��b�J���U�߂�̂ł͂Ȃ��A������҂��������ė��D�����p��������B�Q������ł���B�_�����̃^�u�[��j���đ叟���������߂��B�^�u�[��j���Ă悢�̂��Ƃ������ɐ_�̂�����������B
�@�c�_�����ɂ��āA���̊��Ԓ��ɐ푈���邱�Ƃ͂ǂ����Ƃ݂�Ȃ����O�i�}�z���b�g�j�ɐu���ɗ��邱�Ƃł��낤�B���������邪�悢�B�_�����ɐ�����肷��̂͏d���i�߁j���B�������A�A�b���[�̓����痣�E���A�A�b���[��b�J�̐��a�ɑ��ĕs�h�ȑԓx�����A���������O�������o�����肷�邱�Ƃ̕����A�A�b���[�̌�ڂ��猩��A�����Əd���߂ɂȂ�B�i�M��́j����͎E�l�������Əd���߂��A�Ɓi2.�u�ċ��v214�j�B
�@������������ł͂Ȃ��B�E�t�h�̍���ł͑�s�k���i���Ă���B
�@�c�i���̎��j����݂͂ȑ��l�̂��ƂȂǍ\���������ɓق�����o���čs�����i���f�B�i�Ɍ����ē������j�A�g�k�i�}�z���b�g�j����ԓa��ɗ����Ă���Ȃɓ��������ł����̂Ɂi3.�u�C�����[����Ɓv147�j�B
�@�c���O�i�}�z���b�g�j�����̎҂ǂ��i�}�z���b�g�Ƌ��ɐ�������A�S���Ƃ�����Γ��h�����������l�X�j�ɗD�����ԓx��������̂����́A�����Č���A�b���[�̂��b�݂ł������B�������O�������ƉՍ��ȑԓx����������S���d�������肵����A�ނ�͂��肶��ɂȂ��Ă��O�̂܂�肩�瓦���������ł��낤����B�܁A�Ƃ������ނ�̂��Ƃ͎͂��Ă�邪�悢�B�i�����j�܂��A�b���[���ɐM������邱�ƁB�A�b���[�̕��ł��䎩���ɗ�����ė���҂͍D���������v���ɂȂ�i3.�u�C�����[����Ɓv153�j�B
�@�c�A�b���[�̌�ׂ߂ɎE���ꂽ�l�����������Ď����̂Ǝv���Ă͂Ȃ�Ȃ����B�ނ�͗��h�ɐ_�l�̂��T�Ő����Ă���A���ł��[���ɑՂ��āi3.�u�C�����[����Ɓv163�j�B
�@�����̂�����������A�����ȒɎ�ł��������Ƃ����@�ł���B
�@�C�X������5�N�A���n���}�h�ɍő�̊�@���K���B���f�B�i�ɏZ�ݓ�Ȃ������_���l�����́A�k���̃n�C�o���ɏW�����A�d���˂����B�l���̃��_���l�����ɌĂт����ċ������A����Ƀ��b�J�̃N���C�V�����̌R���A�k�A���r�A�̏������A����ɃG�`�I�s�A�̗b���R�܂ʼn�����������R��g�D�����B���w�����̓N���C�V��������I�ꂽ�B
�@��R�����f�B�i�ɔ������B�����ɖ����A�����炢���A���n���}�h�ɏ��`�����X�͖��������B�M�҂����ɂ����h������B�����o�����҂����������B
�@�c����A���O�����M�k�̎ҁA�A�b���[�̎������������b�݂������N�������悢�A���O�����̂Ƃ���֑�R���U�ߊė������̂��ƁA�i�����j�܂��Ƃɂ��̎������A�M�҂݂͂Ȏ��B���A���̐����䂷�Ԃ�ꂽ���̂ł������B����M�҂ǂ���A�S�ɕa���������A�����A�u�A�b���[�Ǝg�k�̖݂͂�Ȃł���߂��������v�Ȃǂƌ����o�������̂��ƁB�i�����j����ł����i�G�R���j�l�����狭���ɐN�����ė��āA���̏�Ŕ��t�i�}�z���b�g�ɔw���ăC�X�����������Ă�j��v�����ꂽ��A�ނ�͕��C�ł���Ă̂��A�w��ǂȂ���S�O�����Ȃ��������Ƃł��낤�B���̂����A�����Ă�����͌����܂���ƑO�X����ł��A�b���[�Ɍ_�Ă������̂��B�A�b���[�Ƃ̌_��ɂ��ẮA���܂ɕK���u�₳��悤���i33.�u���������v9-15�j�B
�@���n���}�h�̓��f�B�i�̎��͂ɐ[���L�������@���āA�ď邷����ɏo���B���܂ł͒��������Ȃ��h�q���A�A���r�A�ł͏��߂Ă̎��݂������B�����R�͍U�߂����݁A�k�ɓ��X���߂��������A����H�Ƃ��Ȃ��Ȃ�B�����R�͈݂͂������A���ꂼ��̋��_�A���Ă��܂����B��R�ł͂��������A���F�͉G���̏O�������B�����Ƃ��R�[�����͎��̂悤�ɋL���B
�@�c���̎����i�A�b���[�j�ނ�Ɍ������đ啗�𐁂��N���A���O�����ɂ������Ȃ��R���i�V�g�̑�R�j�𑗂����ł͂Ȃ����i33.�u���������v9�j�B
�@�c�ނ�i�G�R�j���E�����͓̂���ł͂Ȃ��B�A�b���[���E���������̂��B�ˎE�����̂͂��O�i���n���b�g�j�ł��A���͂��O���ˎE�����̂ł͂Ȃ��B�A�b���[���ˎE���������̂��i8.�u�험�i�v17�j�B
�@���̐����ŁA���n���}�h�̓A���r�A�ł��ЂƂ��ǂ̐l���ƒN�����F�߂鑶�݂ƂȂ����B���N�A�C�X������6�N�_�����A�ނ͌R��Ґ����ă��b�J�֏�荞�����Ƃ����B�ǂ�قǂ̌R�����������͕s�������A�ƂĂ����b�J�𐪕��ł���قǂ̑�R�ł͂Ȃ������Ǝv����B���b�J�ɋ߂��t�_�C�r�[�A�ŁA��s�̐i�H��j�����ƃ��b�J�R���o�Ă����B�����Ń��n���}�h�̐����͂����̂������B���҂̊Ԃŋ��肪���ꂽ�B�t�_�C�r�[�A����Ƃ����B���e�́A����͂��̂܂܈����Ԃ��A���N�͎O���Ԃ����N���C�V�����̓��b�J����ޏo���C�X�������k�ɃJ�A�o�_�a�̎Q�w�������A���������n���}�h�̓��b�J�ɉi�Z���邱�ƂȂ����f�B�i�֖߂�A�Ƃ��������̂ł���B�ꌩ��C�Ɏv���邪�A�J�A�o���C�X�������̐_�a�ł�����ƔF�߂����������͑傫���B
�@�c����A�����ɋP�����������i�t�_�C�r�[�A����̐������w���j��^�������i48.�u�����v1�j�B
�@�c���x���c�����i���b�J�֏�荞�����Ƃ������n���b�g�R�ɎQ�����Ȃ������j�x�h�E�B���ǂ��́i�Ăɑ��Ⴕ�Đ킢���Ȃ��A�a�����肪���ꂽ�̂ŁA����Ăă}�z���b�g�̂��@�����Ƃ�o�����j�u�Ȃɂ�����Y�̂��Ƃ�Ƒ��̂��ƂŎ��t�ł����̂ŁB�܁A��낵�����������˂����܂��v�ƌ����Ă���ɈႢ�Ȃ��B�S�ɂ��Ȃ����Ƃ���Ō��������̂��ƁB���������Ă�邪�悢�A�i�����j�u����A����A�A�b���[�͂��O�����̂��Ă��邱�Ƃ͉����牽�܂Ō䑶�m�B�{���͂��O�����A�g�k�i�}�z���b�g�j��M�҂����i���x�����ɏo���l�X�j��������x�ƍĂщƑ��̂��ƂɊ҂��ė��܂��Ǝv���Ă����̂ł��낤�B�i�����j�܂��ƂɁA�悭�悭����łȂ����A���O��́v�Ɓi48.�u�����v11-12�j�B
�@�C�X������8�N�A����630�N�A�ނ͔O�肩�Ȃ��āA���a���Ƀ��b�J�ɓ���A�_�a�J�A�o�̌���v�����A���ʓ����ɒ�������t�o���_���͂��ߖ����̋�������[���o�ɒ@�����킵���B�U�����鑽�_���̎c�[��O�ɂ��Ĕނ́A�Q�W�����M�k�����Ɂu���܂�ً�����͏I������v�Ɛ錾�����B
�@���̂Ƃ��̓��n���}�h������ɏ]���āA���T�ԂŃ��b�J�����������A�吨�͌������ƌ����Ă����B�C�X�������́A���E�@���ւƕ��ݎn�߂��̂ł���B
�@�C�X������10�N�A���n���}�h�̓��b�J�ɐ����̏�����s�����B���ꂪ�ނ̍ŏ��ōŌ�̏���ƂȂ����B���̔N��6��8���A���ȃA�[�C�V���̋��ɕ�����ĐÂ��ɑ�������������B�@
�R�[�������ꂱ��
�@�u�R�[�����v��|���䓛�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u�{���́w�R�[�����x�̌����ł���B�i�����j����̓��{��̘b�����t�ł́A�����̖苿���悤�ȁA�����Ăǂ��ƂȂ����d�ŁA���Ƃ���Ƒ����ł�������A���̎�������o�������Ȃ��Ɩl�͎v�����v�B�܂����̂ق��Ɂu�_���}�z���b�g�ɒ��ژb�������Ď�X�l�X�Ȃ��Ƃ�Ƃ�Œ���A����ΐ_�l�̓Ƃ�ŋ��݂����Ȃ��̂�����A��������������Č���̕����K���Ǝv���鑤�ʂ��傢�ɂ���킯�Ȃ̂ł���B�v�Əq�ׂĂ���B�����ēǎ҂ɁA�u�v���X�E�A���t�@�Ƃ��āA���̑��d����z�����ɂ����Ȃ��āv���炢�����Ɗ�]���Ă���B�킽�����g�A�����̐����ɖ���������Ȃ��ł���̂�����A��҂̃W�����}�ɑ傢�ɋ�������B

 �@�O���Ń��n���}�h�̐��U�ƁA�R�[�����̏͋����s�I�ɗ��Ă݂��B���ۂ̃R�[����114�͂͂��ׂāA
�@�O���Ń��n���}�h�̐��U�ƁA�R�[�����̏͋����s�I�ɗ��Ă݂��B���ۂ̃R�[����114�͂͂��ׂāA
�@�c���ߐ[���������܂˂��A�b���[�̌䖼�ɂ����āc�A�Ƃ������t�Ŏn�܂�B�قƂ�ǂ̏͂��A�_�̈̑傳�̎^���A�����ƒ����̕����Ő�߂��Ă���B�Ⴆ�A
�@�c�܂������̓��ɂȂ��Č��邪�����A�A�b���[�ɂ��Ă�������ʂ��ƌ����ӂ炵�Ă����҂ǂ��́A�݂Ȋ��^�����ɂ���Ă��܂��B�W���n���i���i�Q�w�i�^�n���j�̒��ɐ��ӋC�Ȏ҂ǂ���e���Ȃ��Ȃ��킯�ł͂���܂����i39�u.�Q��Ȃ��l�X�v61�j�B
�@�c���ꂼ����B�ꖳ��̌�_�A�A�b���[�B�ڂɌ����鐢�E���A�ڂɌ����ʐ��E���Ƃ��ɒm���������B����Ԃ����A���߂Ԃ�����_�B�i�����j�����ܑ̂Ȃ��A���ꑽ���A�l�X���Ƃ��ɕ��ׂ�i�א_�ǂ��j�Ƃ͔�r�ɂȂ�ʍ��݂ɂ��܂���_�ɂ��킵�܂��ɁB�i�����j�V�ɂ�����́A�n�ɂ�����́A���ׂĐ������炩�Ɏ^�������B��������Ȃ��̑�A����Ȃ�������_��i59.�u�Ǖ��v22-24�j�A�Ƃ�������ł���B
�@���`��A�L���X�g���Ƃ̊W�͂܂��Ƃɔ����ł���B�C�G�X���~����Ƃ͔F�߂Ȃ����̂́A�̑�ȗa���҂Ƃ��Ď�舵���Ă���B
�@�c�ނ�i���_�����k�j�͐M�ɔw���}�������i�}�����j�ɂ��Ă���ςȂ��킲�Ƃ��������B������肩�u�킵��͋~����A�_�̎g�k�A�}�������̎q�C�[�T�[�i�C�G�X�j���E�������v�Ȃǂƌ����B�ǂ����ĎE������̂��A�ǂ����ď\���˂Ɋ|��������̂��B�������̂悤�Ɍ����������̂��ƁB�i�����j�ނ�͒f���Ĕށi�C�G�X�j���E���͂��Ȃ������B�A�b���[���䎩���̂��T�Ɉ����グ�������̂���B�A�b���[�͖����̔\�͂ƒm�b�����������i4.�u���v155-158�j�B�C�X�������ł́A�C�G�X���\���˂Ɋ|�����Ď����Ƃ��A���_���l�̉R���Ƃ��Ĕے肷��B�C�G�X�ł͂Ȃ��ăC�G�X�Ɏ����j���E���ꂽ�ɂ����Ȃ��A�Ƃ���B���������V�͔F�߂Ă���B



 �@�c�}�������̑��q�͂����̃A�b���[�̎g�k�ł���ɂ����ʁB�܂��i�A�b���[�j���}�������ɑ����ꂽ�䌾�t�ł���A�i�A�b���[�j���甭������͂ɂ����ʁi�_�ł��Ȃ����A�u�_�̓Ƃ�q�v�ł��Ȃ��j�B�i�����j�����āu�O�v�Ȃǂƌ����Ă͂Ȃ�ʂ��i�O�ʈ�̂̔ے�j�B�i�����j�A�b���[�͂����Ƃ�̐_�ɂ܂��܂����B�����ܑ̂Ȃ��A�_�ɑ��q������Ƃ͉������i4.�u���v169�j�B�C�X�������ł́A���n���}�h�������܂ł��l�Ԃł���Ƃ��A�_�i���͂��Ȃ��B�C�G�X�����l���Ƃ��闧��ň�т���B
�@�c�}�������̑��q�͂����̃A�b���[�̎g�k�ł���ɂ����ʁB�܂��i�A�b���[�j���}�������ɑ����ꂽ�䌾�t�ł���A�i�A�b���[�j���甭������͂ɂ����ʁi�_�ł��Ȃ����A�u�_�̓Ƃ�q�v�ł��Ȃ��j�B�i�����j�����āu�O�v�Ȃǂƌ����Ă͂Ȃ�ʂ��i�O�ʈ�̂̔ے�j�B�i�����j�A�b���[�͂����Ƃ�̐_�ɂ܂��܂����B�����ܑ̂Ȃ��A�_�ɑ��q������Ƃ͉������i4.�u���v169�j�B�C�X�������ł́A���n���}�h�������܂ł��l�Ԃł���Ƃ��A�_�i���͂��Ȃ��B�C�G�X�����l���Ƃ��闧��ň�т���B
�@�R�[�����͓O�ꂵ�Ēj���̏@���i���j�ł���B�������A�������A���A�j���d���̏@���ł��邱�ƂɈႢ�͂Ȃ����A����ł��R�[�����قǂł͂Ȃ��B���j�I�Ɍ����ΐV�����A�C�G�X�̎��ォ��ق�6���I��ɐ��܂ꂽ�@�����A�ł����������ʂ��Ă���B
�@�c�A�b���[�͂��Ƃ��ƒj�Ɓi���j�Ƃ̊ԂɗD��������ɂȂ����̂����A�܂��i�����ɕK�v�ȁj���͒j���o���̂�����A���̓_�Œj�̕������̏�ɗ��ׂ����́B�i�����j���R�I�ɂȂ肻���ȐS�z�̂��鏗�i�����j�͂悭�@���A�i����ł��ʖڂȂ�j�Q���ɒǂ�����āi���炵�߁A����������Ȃ��ꍇ�́j�ŝ�����������悢�B�����A����Ō������Ƃ������悤�Ȃ�A����ȏ�̂��Ƃ����悤�Ƃ��Ă͂Ȃ�ʁB�A�b���[�͂��ƍ����A���Ƃ��̑�ɂ��킵�܂��i4.�u���v38�j�B
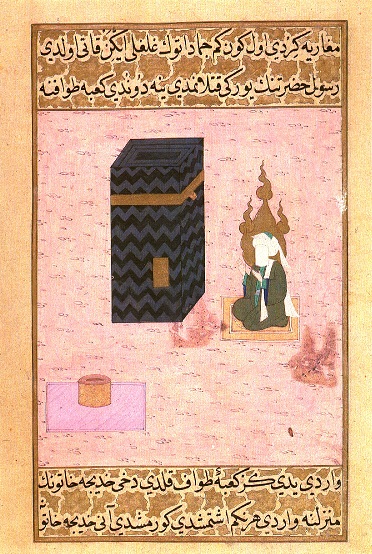 �@��v���Ȃɂ��ẮA
�@��v���Ȃɂ��ẮA
�@�c�N���C�ɓ����������߂Ƃ邪�悢�A��l�Ȃ�A�O�l�Ȃ�A�l�l�Ȃ�B���������i�Ȃ������Ắj�����ɂł��Ȃ��悤�Ȃ�Έ�l�����ɂ��Ă������A�����Ȃ����O�����̉E�肪���L���Ă�����́i���z����w���j�����ʼn䖝���Ă����i4.�u���v3�j�B
�@���n���}�h���g�́AWikipedia �ɂ���12�l�̍Ȃ������Ƃ����B�ً��k�Ƃ̐킢�ő����̖��S�l���o���B���̋~�ςƂ����ʂ��������炵�����A���ʂɃA�b���[�ɂ����������̂��낤�B
�@�����̑̂��`���[�h����u���J�ɂ��ẮA
�@�c���ꂩ�珗�̐M�҂Ɍ����Ă����A�T�݂Ԃ����ڂ������āA�A���͑厖�Ɏ���Ă����A�O���ɏo�Ă��镔���͂��������Ȃ����A���̂ق��̔������Ƃ���͐l�Ɍ����ʂ悤�B���ɂ͕��������Ԃ���悤�i24.�u����v31�j�B
�@�c����A�a���ҁA���O�̍Ȃ����ɂ��A�������ɂ��A�܂���ʐM�k�̏������ɂ��A�i�l�O�ɏo�鎞�́j�K�����߂Łi�����瑫�܂Łj�����ۂ�̂��݂���ōs���悤�\������i33.�u���������v59�j�B�ƃA�b���[���X�̎w��������B
�@�f�H�ɂ��Ă�
�@�c����M�k�̎҂�A�f�H������̎��˂Ȃ�ʋK���ł��邼�A������O�̎���̐l�X�̏ꍇ�Ɠ����悤�ɁB�i���̋K�����悭���j�����Ƃ��O�����ɂ��{���ɐ_���ꂩ�����ދC�������o���Ă��悤�i2.�u�ċ��v179�j�B
�@�c�f�H�̖�A���炪�Ȃƌ���邱�Ƃ͋����Ă�낤���B�i�����j�H�����悵�A���ނ��悵�A�₪���t���̌��肳�����߂āA�����ƍ����̋�ʂ��͂�������悤�ɂȂ鎞�܂ŁB�������A���̎���������A�܂��i���́j��ɂȂ�܂ł�������ƒf�H�����̂����i2.�u�ċ��v183�j�B
 �@�H���̋֊��ɂ��ẮA
�@�H���̋֊��ɂ��ẮA
�@�c�A�b���[������ɋւ��������H���Ƃ����A�����A���A�̓��A���ꂩ��i�j�鎞�Ɂj�A�b���[�ȊO�̖���������ꂽ���́i�ِ_�ɕ�����ꂽ���́j�̂݁B�i�����j��ނȂ��i�H�ׂ��j�ꍇ�ɂ́A�ʂɍ߂ɂȂ�͂��ʁB�܂��ƂɃA�b���[�͂悭�߂���邵���������B�܂��ƂɎ��߂̐S�ӂ��������i2.�u�ċ��v168�j�B
�@�����ēV���ɂ��ẮA
�@�c�����i�y���j�ł͐��I���قǂ悭�������u���܂��B�T���T�r�[���ƌĂԂ������i�V���j�̐�i�̐��j�ŁB���ނ����Ă܂�邨���������͉i���̎�l�A�i���̔��������Ɓj�������ʂ܂��U�炵���^�삩�Ƃ܂�������B�����������A�i�^�́j�K���A�̑�Ȃ�_�̍��Ƃ͂����Ȃ���̂��Ƃ��݂���鎖�ł��낤�i76.�u�l�ԁv17-20�j�B�����ɏo�Ă���T���T�r�[���͐�̐��ŁA�����ł͂Ȃ��̂��낤���A����ȋ^�₪�N���B
�@�c�i�A�b���[�̓}�z���b�g�ɒ��ڌ���������j�����M������A���P�s���Ȃ��l�X�Ɍ����Ă͊�т̉��M�������m�炵�Ă�邪�悢���B�ނ�͂₪���D�X�Ɖ͐������Ή��ɕ����ł��낤���Ƃ��B���́i�Ή��́j�ʎ�����X�̗ƂƂ��ċ�����i�����j���C�̍Ȃ����Ă����A�����ɂ������ĉi���ɏZ�܂��ł��낤���i2.�u�ċ��v23�j�B
�@���C�̍ȂƂ́A�ÃA���r�A�̓`���ŁA�V��̊y���ɏZ�ނƂ����_���t�[���̂��ƁB�C�X�������̓`���ɂ��ƁA�M�҂͎���y���ɓ���Ɠ����ɔޏ���Ɍ}�����A�n��ɂ����ă��}�U�[�����ɒf�H�������̐��ƁA�P�����s�����������ޏ���Ɗ��������邱�Ƃ��������B�������ޏ���͉i���ɏ����ł���Ƃ����B
�@�R�[�����ɂ́A�����Ɍ��ꂽ�}�b���p�ɂɏo�Ă���B�������A���ӂƌ����郀�n���}�h��������ǂ�ł����Ƃ͎v���Ȃ��B���p�̎d�������ꕗ�ŁA�����炭�J�ԂɌ����G�s�\�[�h�����w��Ŋo���Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�����̒m���l�����́A�T�˃R�[�����ɔے�I�������B���̑�\�i�Ƃ��āA�����ł̓p�X�J���ɓo�ꂵ�Ă��炨���B�u�l�Ԃ͍l���鈯�ł���v�Ɩ������c�����p�X�J���i1623-1662�j�́A�ƂĂ��Ȃ��}���`�l�Ԃ������B���w�ҁA�����w�ҁA�L���X�g���_�w�҂����ēN�w�҂ŁA���ꂼ��̕���ōۗ������Ɛт��c���Ă���B�c�O�Ȃ��ƂɒZ���ŁA�킸��39�N���������Ă��Ȃ��B�u�p���Z�i�ґz�^�j�v�i���E���w��n13�u�f�J���g�A�p�X�J���v���Q�M�O��A�}�����[�j�͎��̂悤�ɏq�ׂ�c�l�Ԃ͎��R�̂����ōł��ア��s�̈��ɂ����Ȃ��B����������͍l���鈯�ł���B�i�����j�����̂����鑸���͎v�l�̂����ɑ�����i347�j�B��Ԃɂ���āA�F���͎����݁A��̓_�Ƃ��Ď���ۂށB�v�l�ɂ���Ď��͉F�����ށi348�j�B
�@���̂悤�ɍl�����l���A�C�X���������ǂ̂悤�Ɍ��Ă����̂��낤���B�u�p���Z�v����̈��p�𑱂���B
�@�c���Ђ������Ȃ��}�z���b�g�B����䂦�ɂ����A�ނ̗��R�͌��͓I�ł���˂Ȃ�Ȃ������̂ł��낤�B�Ƃ����̂��A�ނ̗��R�͂��ꎩ�g�̗͂����������Ȃ���������ł���B�^�ł́A�ނ͉��ƌ��������H�@�M���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�ƌ����������ł���i595�j�B�i�u���Ђ������Ȃ��v�Ƃ����̂́A�u�\���҂��A��ւ��A�ؐl�������Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ł���B�������j
�@�c�}�z���b�g�̂����ɂ���B���Ȃ��́A�����_��I�ȈӖ��ɎƂ�ꂻ���Ȃ��̂ɂ���Ăł͂Ȃ��B�ނ���A�����ɂ��閾�ĂȂ��́A���Ȃ킿�ނ̂����V���₻�̑��̂��̂ɂ���āA�ނf���Ă��炢�����B�}�z���b�g�����ׂ����̂ł���̂́A���̓_�ɂ����Ăł���B���������킯�ŁA�ނ̖��Ăȓ_�����ׂ����̂�����A�ނ̞B���ȓ_��_��Ɖ�����̂͐����łȂ��i598�j�B
�@�c�C�G�X�E�L���X�g�ƃ}�z���b�g�Ƃ̍��فB�}�z���b�g�A�\������Ȃ������B�C�G�X�E�L���X�g�A�\�����ꂽ�B�^�}�z���b�g�A�E���B�C�G�X�E�L���X�g�A���̐M�҂��E�����悤�ɂ���B�^�}�z���b�g�A�ǂނ��Ƃ��ւ���B�g�k�����A�ǂނ��Ƃ𖽂���B�^�v����ɁA���҂͂������������Ă���̂ŁA�}�z���b�g���l�ԓI�ɐ������铹��I�Ƃ���A�C�G�X�E�L���X�g�͐l�ԓI�ɔj�ł��铹��I���ƂɂȂ�B�����āA�u�}�z���b�g�����������̂�����A�C�G�X�E�L���X�g���A���R�A�����������v�ƌ��_�������ɁA�u�}�z���b�g�����������̂�����A�C�G�X�E�L���X�g�͔j�ł���̂����R�������v�ƌ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��i599�j�B
�@�R�[�������@�����Ƃ��đ�����A�킽�����p�X�J���̈ӌ��ɂقړ��ӂ���B���n���}�h�́A�V���[�}���ł���Ɠ����Ɍ��o���������ƁA�R�l�������B���̍l���ɗ��ĂA�ނ̓A���N�T���_�[�剤��J�G�T���ȏ�̐l���������ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B
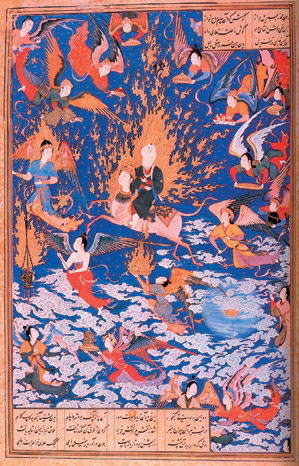 �@�C�X��������ᔻ����Ɣ��������낵���B�������A�p�X�J���͎l���I���O�̒m�̋��l�ł���B�ނ́A�u�p���Z�v�Ɂu�N���I�p�g���̕@�A���ꂪ���������Ⴉ������A��n�̑S�\�ʂ͕ς���Ă����ł��낤�i162�j�v�Ƃ��u�l�͈ӎ����Ĉ����ׂ��Ƃ��قǁA���S�ɂ܂������ɂ�����ׂ����Ƃ͂Ȃ��i895�j�v�Ȃǂ̖�������c�����l�ł�����B�t�@�g����A������@���w���҂ɂ����ڂ��ڂ������邾�낤�B
�@�C�X��������ᔻ����Ɣ��������낵���B�������A�p�X�J���͎l���I���O�̒m�̋��l�ł���B�ނ́A�u�p���Z�v�Ɂu�N���I�p�g���̕@�A���ꂪ���������Ⴉ������A��n�̑S�\�ʂ͕ς���Ă����ł��낤�i162�j�v�Ƃ��u�l�͈ӎ����Ĉ����ׂ��Ƃ��قǁA���S�ɂ܂������ɂ�����ׂ����Ƃ͂Ȃ��i895�j�v�Ȃǂ̖�������c�����l�ł�����B�t�@�g����A������@���w���҂ɂ����ڂ��ڂ������邾�낤�B
�@�Ō�ɁA�I�}���E�n�C���[���u���o�C���[�g�v�i��A���엺��A��g���Ɂj�̎��i88�j�ł��̍���������B�ނ�11���I�y���V���̓V���w�ҁA���w�҂����Ď����悭�����l���̒B�l�ł���B���n���}�h���猩��A�s�M�̓k�ƌ������ƂɂȂ邩���m��Ȃ����c�B
�@�@�V���ɂ͂���Ȃɔ������V��������̂��H
�@�@���̐�▨�̒r�����ӂ�Ă���Ƃ����̂��H
�@�@���̐��̗��Ɣ����i���܂����j��I�����
�@�@�V��������ς肻��Ȃ��̂ɂ����Ȃ��̂��H
�X���j�h�ƃV�[�A�h
�@�C�X�������̐M�҂́A�S���E�Ŗ�18���l����ƌ����Ă���B�X���j�h���命���ŁA�V�[�A�h��10�`15���ɉ߂��Ȃ��B�����h�̃V�[�A�h�́A���̂قƂ�ǂ��C�����ɏW�����Ă��邪�A�אڂ���C���N�ł�65%���߂�B2003�N�A�u�b�V���i�q�j�哝�̂��C���N�ɐN�U�����Ƃ��A���҂���A�݂��݂��C�����Ɍ���Ă��悤�Ȃ��̂��Ɨ���ꂽ�B�X���j�h�̃t�Z�C���哝�̂�|���A�V�[�A�h�̑����C���N�́A�K�R�I�ɃC�����ւƌX���B���݂̏́A���҂̌����ɋ߂Â�����B
�@���E�I�Ɍ���Έ��|�I�ɃX���j�h�������悤�Ɍ�����B�������A�ő�̃C�X���������ƌ�����C���h�l�V�A��A�t���J�嗤�̃C�X�������k�����O����ƁA�����ł̔䗦�͂قڝh�R���Ă���B�o�[���[����A�[���o�C�W������60%�ȏ�A���o�m���ł�45%���V�[�A�h����߂�B
�@�ǂ̏@���ł������悤�Ȍ��ۂ����A�@�c�����㕪�n�܂�B�����ł��A���`��̍��ق���A���Ə�����i����j�ɕʂꂽ�B�L���X�g���́A�J�g���b�N�̗͂����|�I���������A���c���̕��s���������āA16���I�ȍ~�v���e�X�^���g�^�����k���𒆐S�ɍL�܂����B
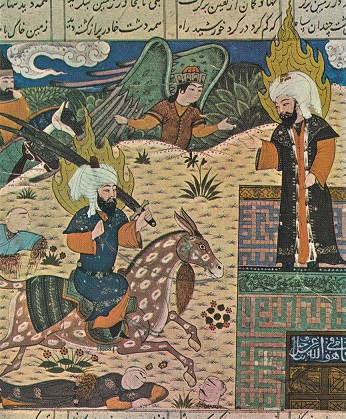 �@�C�X�������́A���������c�����ŕ����B�V�[�A�h�̓��n���}�h�̏]��ŁA�ނ̖��̕v�ł�����A���[����p�҂ƂȂ�A���̌��������܂��ɑ����Ă���B�u�V�[�A�v�̓A���r�A��Łu�A���[�̓}�h�v���Ӗ�����B
�@�C�X�������́A���������c�����ŕ����B�V�[�A�h�̓��n���}�h�̏]��ŁA�ނ̖��̕v�ł�����A���[����p�҂ƂȂ�A���̌��������܂��ɑ����Ă���B�u�V�[�A�v�̓A���r�A��Łu�A���[�̓}�h�v���Ӗ�����B
�@�X���j�h�i�X���i�h�j�́A���������c�����d�����ăX�^�[�g�����B�\���҃��n���}�h�́u���s�v�A�A���r�A��Łu�X���i�v���ꌹ�Ƃ���B�u�X���i�ɏ]���l�v���Ӗ�����u�X���j�[�v�����ݑ����g���Ă���B�C�X���������̂̍ō��w���҂��J���t�Ƃ����B����̃J���t�́A���n���}�h�����b�J���烁�f�B�i�ցu�J�s�v�����ہA�s�������ɂ����A�u�[�E�o�N���ł���B���̌�A�����ɂ�����x�z�I�ȉ����A�Ⴆ�E�}�C�����A�A�b�o�[�X���A�I�X�}�����̉����J���t�������p���ŗ����B1922�N�A�I�X�}�������ŖS���A1924�N�V���g���R�̌����҃A�^�`�����N�ɂ���āA�J���t�����̂��̂��p�~���ꂽ�B�Ō�̃J���t�́A�I�X�}�����̉��A�u�f�������W�h�ł���iWikipedia�j�B
�@�A�����J�̓C���N�̃t�Z�C���哝�̂�|�������A���̎c�}�̓C���N�k���Ɍ��W���A�C�X�������iIS�j�����������B�ނ�̓C�X����������`���咣���A������J���t�Ə̂����B�J���t��ʂ��D�@�ɃC�X�������k�̋����悤�Ƃ����B
�@���܂ł̓C�X�������̐��͂������̐����������Ă��邪�A�ߌ��h�͊e���ɎU�݂���B�X���j�h�ɑ�����M�҂́A���͑������̂̃J�g���b�N�̋��c���̂悤�ȓ���g�D�������Ȃ��B�n�悩�R�~���j�e�B�̏@���w���ҁA�C�}�[���̎w���ɏ]���B���n���}�h�̋����ɒ����ł���ׂ��Ƃ����ߌ��Ȍ������A���Ă��Ďx���₷���B�C�܂܂Ƀt�@�g���Ƃ����w�����j��A�����邪�A���ꂪ���Y�鍐���Ӗ����邱�Ƃ������B�A�t�K�j�X�^���ł́A�X���j�h���V�[�A�h�̃��X�N���P������B�p�L�X�^���ł͖��_�E�l�i�ً��k�Ƃ̌������肤�q�����E���j���₦�Ȃ��B�����āA�C�X�������̂悤�ȁA�܂������̑g�D���J���t�����̂���B���h�ɂ��ꂼ��ߌ��h������A���h���@�k�ƌ���B�����C�X�������k�ł���ɂ��S��炸�c�B
�@�V�[�A�h�̓C�����𒆐S�Ɉ�̂܂Ƃ܂�������A���̕��Ƃ̂悤�ȃ��o�m���̃q�Y�{���A�C�G�����̃t�[�V�̂悤�ȑ��݂��A�n��̕s����v�������o���Ă���B����́A���`�̖��ł͖����A�������͂̑����ɏ@�������p����Ă���ɉ߂��Ȃ��B���C�o���W�ɂ���T�E�W�A���r�A�ƃC�����A�����ăC�X���G���̑��݂���������������B
�@�����A�j���[�X����킷�C�X�������k�Ԃ̃g���u���́A�命���̃C�X�������k�ɂƂ��Ė��f�疜�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ𗝉����Ă����ׂ����낤�B���h�Ƃ��命���́A���a�I�ő��@���ɂ����e�ł���B�g�����v�哝�̂͏A�C���X�C�X�������k�𑄋ʂɂ��������A����͖��m�ƕΌ��̂Ȃ�������������B
����C�X���G��
���Ƃ��Ă̖��O

 �@�C�X���G���Ƃ��������͐����ɗR������B�A�u���n���̑����R�u������l�Ɨ͔�ׂ������B�p�͂̂悤�Ȃ��̂��낤�B���������Ȃ��B���̐l�����R�u�̐����ɐG�ꂽ�B�����Ƃ͌Ҋ߂̂��Ƃł���B�Ăї͔�ׂ�����ƃ��R�u�̍����O�ꂽ�B���������R�u�͕����Ă��Ȃ��B�邪�����āA���̐l�͕ʂ�������悤�Ƃ���B���R�u�́A�����ɏj����^����܂ōs��������̂��Ƃ����B�n���L32�͂ɏ]���B�c���l��������͓��̖��͏d�ă��R�u�ƂƂȂ��ׂ��炸�B�C�X���G���ƂƂȂ��ׂ��B���͓��A�_�Ɛl�Ƃɗ͂����炻���ď�������Ȃ�ƁB�i�����j�z�Ĕޓ��̂��Â鎞�Ƀy�j�G���i�_�̖ʁj���߂����肵���A��鏂̂��ߕ��s�͂��ǂ炴�肫�B���̂ɃC�X���G���̎q���́A�����Ɏ���܂�鏂̋���H�킸�B���ސl�����R�u��鏂̋��ɐG����ɂ��ĂȂ�i28-32�j�B
�@�C�X���G���Ƃ��������͐����ɗR������B�A�u���n���̑����R�u������l�Ɨ͔�ׂ������B�p�͂̂悤�Ȃ��̂��낤�B���������Ȃ��B���̐l�����R�u�̐����ɐG�ꂽ�B�����Ƃ͌Ҋ߂̂��Ƃł���B�Ăї͔�ׂ�����ƃ��R�u�̍����O�ꂽ�B���������R�u�͕����Ă��Ȃ��B�邪�����āA���̐l�͕ʂ�������悤�Ƃ���B���R�u�́A�����ɏj����^����܂ōs��������̂��Ƃ����B�n���L32�͂ɏ]���B�c���l��������͓��̖��͏d�ă��R�u�ƂƂȂ��ׂ��炸�B�C�X���G���ƂƂȂ��ׂ��B���͓��A�_�Ɛl�Ƃɗ͂����炻���ď�������Ȃ�ƁB�i�����j�z�Ĕޓ��̂��Â鎞�Ƀy�j�G���i�_�̖ʁj���߂����肵���A��鏂̂��ߕ��s�͂��ǂ炴�肫�B���̂ɃC�X���G���̎q���́A�����Ɏ���܂�鏂̋���H�킸�B���ސl�����R�u��鏂̋��ɐG����ɂ��ĂȂ�i28-32�j�B
�@ ����l�Ƃ����̂͐_�������Ƃ����A�����������Ȃ�悤�ȑ}�b�ł���B���R�u��傫�������悤�Ƃ��āA�_���������Ȃ��Ă��܂��Ă���B�S�[�M�����͂��̑}�b���ނɁA�u���R�u�ƓV�g�̐킢�v��`�����B�ނȂ�̔��f�ŁA���R�u���͔�ׂ����Ă���̂͐_�ł͂Ȃ��A���̉��̃����N�A�V�g�ł���B
����l�Ƃ����̂͐_�������Ƃ����A�����������Ȃ�悤�ȑ}�b�ł���B���R�u��傫�������悤�Ƃ��āA�_���������Ȃ��Ă��܂��Ă���B�S�[�M�����͂��̑}�b���ނɁA�u���R�u�ƓV�g�̐킢�v��`�����B�ނȂ�̔��f�ŁA���R�u���͔�ׂ����Ă���̂͐_�ł͂Ȃ��A���̉��̃����N�A�V�g�ł���B
�@���R�u�͑o�����������B�Z�ɂ�����G�T�E�͖쐶���������B�����炭�r�͂ł̓��R�u��苭��������������Ȃ��B�����G�T�E���_�Ɨ͔�ׂ����Ă�����Ƒz������ƁA���̑}�b�̉���������ɑ����B
�@������ɂ��Ă��u�C�X���G���ƂƂȂ��ׂ��v�Ƃ������t���A���݂̍����̗R���ł���B
���Ǝ���
�@�C�M���X�̎O����O���ɂ��Ắu�A���n�x�z�ƃ����_���a���v�̍��ŐG�ꂽ�B���݂̒��������̗��R�̑啔���́A�C�X���G���������������Ă���B
�@1917�N�̃o���t�H�A�錾���A�C�M���X���{�͂��قǏd�v�����Ă��Ȃ������B���_���l���Ƃ���������C�ȂǂȂ������B�����A���r�A�������A���u�l�̂��̂Ƃ����t�Z�C���E�}�N�}�t�H������Ɉᔽ����B�A���u���̔����͕K���ł���B�������V�I�j�X�g���͐^���������B�p���X�`�i�ւ̃��_���l�̈ڏZ�����X�ɑ����A���n�l�Ƃ̊Ԃ��a瀂������n�߂Ă����B����E���̖u���́A���̖���s����ȏ�Ԃ̂܂܁A�I�グ�ɂ��Ă��܂����B
�@�i�`�ɂ�郆�_���l�s�E�́A�S���E���������������A���Ƀ��[���b�p�̐l�X�ɋ�����ӂ̔O����������B�ǂ̍�������܂ŁA���Ȃ��炸���_���l�𔗊Q���Ă�������ł���B���̎v�����A���_���l�̖]�ނ��ƂȂ�A���X�̖����͕����˂Ȃ�ʂƂ����f�n�B
�@�������e������~�o���ꂽ�l�X��A���[���b�p�e�n����̈ڏZ��]�҂����X�ƃp���X�`�i�̒n��ڎw�����B�ނ�́A���n�A���u�l�ƕ������N�����������ł͂Ȃ��B�ϔC�����̃C�M���X�����ǂ��o���ɂ��������B��i�̓e���ł���B
�@���M���ׂ��e���������A1947�N7��22���̃L���O�E�f�C���B�b�h�E�z�e�����j�����ł���B����91���A������46���Ƃ����ߎS�Ȍ��ʂB���̃z�e���́A�ϔC���������A�C�M���X�R�w�ߕ��Ȃǂ����p���A�e���g�D�̒����@�ւ��������B������������߂��C�M���X�́A�������A�Ɋۓ��������B
�@���A��1947�N11��29���A�p���X�`�i�������c���̑������B���_���l�̍������[���b�p�̒��ɑn�o����̂ł���A���͋N���Ȃ��������Ƃ��낤�B�������A�V�I�j�X�g�́A���̈Ăł͖������Ȃ��B
�@�������c�̎�ȓ��e�́A�p���X�`�i�̒n�ɃA���u�ƃ��_���l�̍���n�o���A�G���T��������ʓs�s�i���A�̐M�������j�Ƃ��邱�ƁA�C�M���X�̈ϔC�����̏I����1948�N8��1���܂łƂ��邱�ƁA�Ȃǂł���B�̑����ʂ́A�^��33�A����13�A����10�A����1�������B�������G�W�v�g���܂ޒ��������͖Ҕ��������B���������́A���������̈ӌ����y�������B�܂��A���n�x�z����̗]�C���c���Ă����B�������̌��c�́A�̑ォ����킪�n�܂������߁A���������ł͎����Ɏ����Ă��Ȃ��Ƃ����B
�@�����O�A1948�N4��9���ɋN�����f�B���E���V�[�����A�p���X�`�i�Z���s�E�����ɐG��Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��BWikipedia
�ɂ��ƁA�s�E���ꂽ�l�X��107�l����120�l�Ƃ���Ă���B������A�X�Ȃ锗�Q�����ꂽ���\���l�̃A���u�l���G�W�v�g����_���ɓ��ꂽ�B���̋��|���́A�C�X���G�����v��I�ɐ��������̂ł���B�A���u�n�̑��X�ŁA���K�͂̋s�E��C�v�𑱂��A���������Z���������u�ڑ��v�������Ƃ��ؖ�����Ă���B�ƂȂ����n��ɂ̓��_���l�������Z�݁A�y�n���Y�͔ނ�̂��̂ƂȂ����B�C�X���G�����{�́A��̋A�҂�F�߂Ă��Ȃ��B�p���X�`�i�̐l�X�͂��̎������i�N�o�iNAKBA�^��S���j�ƌĂԁB
�푈�s�ׂɂ��̓y�g��
�@�p���X�`�i��肩�瑁�������o�������C�M���X�́A1948�N5��15�����Ȃ��ĈϔC�������I������Ɛ������o�����B���̑O��5��14���A�C�X���G���͌�����錾����B�A���u�����͒����ɁA�C�X���G���ɐ��z�������B��ꎟ�����푈�ł���B�A���u�����̎Q�퍑�́A�G�W�v�g�A�V���A�A�C���N�A���o�m���A�g�����X�����_���A�T�E�W�A���r�A�A�C�G�����A�����b�R�A�X�[�_���ł���B�a������̃C�X���G���́A���́A����Ƃ��Ɏ�̂ŋ���������ꂽ�B
�@���������́A���������̔����������ăC�X���G�������𐄐i�����ȏ�A�a����������̃C�X���G���������Ă�킯�ɂ͂����Ȃ������B����x�����C�X���G���͔������A��펞�ɂ͌��ݑ����̍��X�ɔF�߂��Ă���̓y���l�������B
�@1949�N�C�X���G���́A���ۘA���ւ̉������F�߂�ꂽ�B���̑������A���������̙�ӂ̔O�̗��Ԃ��ł��낤�B
�@�����푈�͎l�x�N���Ă���B1956�N�̑�́A�X�G�Y�^�͂̊Ǘ������߂��鑈���ŁA�C�X���G���̓C�M���X��t�����X�ɕ֏悷��`�Ő푈�ɎQ�������B���v�̗���Ƃ����̂ł���B���̑����̓A�����J�ɂ�钇��ŁA�G�W�v�g�ɊǗ������m�肵���B�����A�C�M���X��t�����X�͂܂��A���n����̖�������߂Ă��Ȃ������B�A�����J�̕����펯�I�������B����̗����F�����Ă����B
�@�����_���֓��ꂽ�p���X�`�i�̐l�X�́A�p���X�`�i����@�\���������A�A���u�����̔閧���̉����āA�C�X���G�����ł̃e���������n�߂��B�Ȃ��ł��A�ł��ߌ��ȕ����g�D���u�����㌎�v�������B
�@��O�������푈�́A1967�N�C�X���G�����搧�U���ŏ����������߂��B�Z���ԂŏI���A6���Ԑ푈�ƌĂ��B�Q�퍑�́A�A���u�A�����a���A�G�W�v�g�A�V���A�A�����_���A�C���N�ł���B���̂Ƃ��ɃC�X���G������̂������G���T�����A�����_���쐼�ݒn��A�S���������ȂǁA���܂����ۓI�ɂ̓C�X���G���̂Ƃ��ĔF�߂��Ă��Ȃ��B
�@���n��I�ɂ́A�O���Ǝl���̒����푈�̊ԂɁA�~�����w���E�I�����s�b�N�������N���Ă���B�p���X�`�i�����g�D�u�����㌎�v��8�����A�C�X���G���I�肽����l���Ɏ��A�G�W�v�g�̃J�C���ւ̒E�o����}�����B��`���ŏe����ƂȂ�A�e�����X�g�����͎��������B���҂́A�C�X���G��11���A�x�@��1���A�u�����㌎�v5���ł���B�c��3���͑ߕ߂��ꂽ���A�Â����t�g�n���U�q��n�C�W���b�N�����ʼn�����ꂽ�B�e���͔����ׂ������A�u�����㌎�v���́A���E���悤�₭�p���X�`�i�̒�R�^����F�������A����I�������Ƃ��Ă���B
�@���{�ɂ����҂������B1972�N5��30���A���{���O�A�������m�A���c���V��3�����A�e���A�r�u��`�ŗ��ˎ������N�������B����26���A������73���Ƃ�����S���ł���B�����ƈ��c�͎ˎE����A���{�͑ߕ߂��ꂽ�B�C�X���G���͔ނ��I�g�Y�ɏ��������A�ߗ������Ń��o�m���ֈړ��A�����S����F�߂��Ă��܂��������Ă���B1947�N���܂ꂾ����A73�ɂȂ��Ă���B
�@1973�N�ɋN������l�������푈�̎Q�퍑�́A�G�W�v�g�ƃV���A�ł���B���̂Ƃ��͕s�ӑł���H�����C�X���G������킵�A��̒n���ꕔ�����Ē�킵�Ă���B
�@�l���ɂ킽��푈�̎Q�퍑���L�����̂ɂ͈Ӗ�������B�C�����̖����ǂ��ɂ��Ȃ��B���݃C�X���G�����ł��G�����Ă���C�����́A�����I�������葱���Ă����B
�@����E���I�������A�C�������x�z���Ă����̂̓p�[�����B�i�p�t�����B�j���ł���B�����I�Ɏx������Ă������n���}�h�E���T�b�f�O�́A1951�N�A�C�M���X�n�A���O���E�C���j�A���Ζ���Ђ̃C�������L����}�����B�A�����JCIA�ƃC�M���X�閧����Ö�A�C�����R�������ăN�[�f�^�[�����s�������B���T�b�f�O�͎��r�A�����Ɍ��͂��W�����錋�ʂB
�@�����p�[�����B�̎x�z�́A1979�N�̃C�����E�C�X���[���v���ɂ���ďI���B�ƍِF�̋��������͍�������x������Ȃ������B�����ĉ������������ꂽ�̂́A�������ɂ߂���炵�Ԃ肾�����B�v����A�S�����������z���C�j�t���A�����A�@�������@�������茠���������I�ȍ��ƂƂȂ����B�C�����͔��ĐF�����߂��B�e�w�����ŃA�����J��g�ِl���������N�����B

 �@�C�����ƒ����푈���I�[�o�[���b�v������ƁA���T�b�f�O���オ�A��ꎟ�ɑ�������B�����̃C�����́A�e�C�X���G���Ƃ͍s���Ȃ��܂ł��A�G���͂��Ă��Ȃ��B��O�������푈�ŁA�C�X���G��������������搧�U�������Ƃ��A�C�����͐e�ẴV���[�i�c��j�x�z�̎���ŁA�C�X���G���̍U���Ώۂł͂Ȃ������B
�@�C�����ƒ����푈���I�[�o�[���b�v������ƁA���T�b�f�O���オ�A��ꎟ�ɑ�������B�����̃C�����́A�e�C�X���G���Ƃ͍s���Ȃ��܂ł��A�G���͂��Ă��Ȃ��B��O�������푈�ŁA�C�X���G��������������搧�U�������Ƃ��A�C�����͐e�ẴV���[�i�c��j�x�z�̎���ŁA�C�X���G���̍U���Ώۂł͂Ȃ������B
�@�A�����J�̗v�炴�銱���A�C�������C�X���G���̓V�G�ɂ��Ă��܂����B
�@�C�X���G�����A�����̋��Ђɕq���Ȃ̂͗����ł���B�������x�d�Ȃ鍑�ۖ@�K�����͋����������B1981�N�ɂ̓C���N�̌��q�F���A2007�N�ɂ̓V���A�̌��q�F�������B����������ۖ@�ᔽ�̉z�������ł���B���A���ۗ��̓C�X���G�����c���̌��������A�A�����J�����ی��������B���̂ق��A�J�_�t�B����̃��r�A�⌻�݂̃C�����ɑ��A���q�F�������������Ƌ����������Ă����B
�@��O�������푈�Ŏx�z�n����L�����C�X���G���́A���A���c�����A��̒n�ւ̓��A���g�債�Ă���B�A�����J�͋��ی��ŃC�X���G�������Â���B�B��̗�O�́A2016�N12��24���ɋN�����B���A�ɂ�����C�X���G�����A�n���c�ɁA����܂ŏ�ɋ��ی����s�g���Ă����A�����J���A�I�o�}�哝�̂̎w���Ŋ��������̂ł���B�������̎��_�ŁA�����哝�̂����a�}�̃g�����v�Ɍ��肵�Ă���A�I�o�}�哝�̂̌��f�́A�����哝�̂̎��~�߂ɂ��Ȃ�Ȃ������B
�@���݂̃C�X���G���́A�������Ă����E�͋����`��������ƍl���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B���N���̊ԁA���Q���ꑱ���Ă������_���l�����́A���������̎v�����ʂ�̂��Ƃ�����Ă悢�͂����ƍl���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B���������Q���Ă����̂́A���V�A���܂߂����������ŁA������A�W�A�ł͂Ȃ��B���̐����������A���܂ł͉䖝���������A��Ԃ������������Ɣ��Ȃ��Ă���悤�Ɏv����B��O�́A�g�����v�哝�̂Ƃ��̎�芪�������ł���B
�@�g�����v�哝�̖̂\���͎~�܂�Ȃ��B�I�o�}�哝�̎���A�A�����J�A�C�M���X�A�t�����X�A�h�C�c�A���V�A�A�����̌܂����ƃC�����Ƃ̊ԂŊj���ӂ����������B�C�����̊j�J���𐧖�ړI�ł���B�C�X���G���͂��̍��ӂ����������B�E�����Z�k�𐧌����Ă��A���������j���e�������A�C�X���G���ւ̋��ЂƂȂ�A�Ƃ����̂����Η��R�ł���B�C�X���G���̌������g�����v�哝�̂́A����I�ɂ��̍��ӂ��痣�E���C�����Ɍo�ϐ��ق��ۂ����B�C�����̊j�J����j�~����ƍ��ꂵ�����A�������ăC�����̃E�����Z�k�����������A�����Ԃ̊W�����������������ł���B
�@�C�����Ƃ̊j���ӂ̈Ӌ`���l����O�ɁA�j�g�U�h�~���̋U�P������ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�A�����J�A�C�M���X�A�t�����X�A���V�A�A�����̌܂����ȊO�A�j����������Ȃ��Ƃ����s�����ȏ��ł���B����ɂ́A���łɊj��������C���h�ƃp�L�X�^���͉������Ă��Ȃ��B�k���N�͗��E�����B�����ăC�X���G�����������ł͂Ȃ��B�C�X���G���͔۔F���m������Ă��Ȃ����A�j����������Ă��邱�Ƃ͌��R�̔閧�ƂȂ��Ă���B
�@���̏��̋U�P���́A�j�ۗL���������̊j�����ۗL�����܂܂ŁA��ۗL���̊j����J�����֎~���悤�Ƃ���Ƃ���ɂ���B�����܂ł���ۗL���̗ǎ��Ɉˑ����邾���́A�����͂Ɍ��������ƌ��킴��Ȃ��B�S���E���j�����������Ȃ�����A���̋U�P���͏��ł��Ȃ��B
�@�C�����Ƃ̊j���ӂ́A�j�g�U�h�~���̋U�P����F������j�ۗL�����A�ǂ����C�����̊j�J���𐧌��ł��邩�ƒq�b���i�����������̎Y���ł���B�g�����v�哝�̂ɂ́A���̔F���������Ă���B�����āA�C�������C�X���G���̋��Ђł���Ƃ���A�C�����ɂƂ��ăC�X���G�������Ђł���Ƃ����F�����A�C�X���G���ɂ͌����Ă���B
�@1996�N�ɍ��A�ō̑����ꂽ�j����֎~���́A���̗��s�L�������Ă��鎞�_�ł́A��y�����܂�50�����ɒB���Ă��Ȃ����ߔ������Ă��Ȃ��B�j�ۗL���́A�������ɌŎ������̏��ɔ��ł���B�C�̈�ԂɎ^�����ׂ�������Q�����{�́A�A�����J�̊j�̎P�Ɏ���Ă���Ƃ������R�ŁA�܂���y���Ă��Ȃ��B�j�ۗL���̋U�P�̕Ж_��S���Ă���B���{�l�Ƃ��Ēp������������ł���B
�@����E����A�푈�s�ׂŗ̓y���L���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����s���������ۊԂŐ��������B�ߎS�Ȑ푈����w���P�ł���B����A���̕s�����Ɉᔽ���Ă��鍑�́A�C�X���G���ƃ��V�A�݂̓̂ł���B
�A�p���g�w�C�g
�@�c���o�r�����̉͂̂قƂ�ɂ����A�V�I�����v�����łė܂𗬂��ʁi�����u���сv137�F1�j�́A�f�B�A�X�|���̔߂��݂��r���ċ���łB�������Â�����c�ق�ڂ���ׂ��o�r�����̏���A�Ȃ�����ɍ삵���@�����ɂނ����l�͂����킢�Ȃ�ׂ��B�Ȃ̉d�����Ƃ�Ċ�̂����ɂȂ����҂͍K���Ȃ�ׂ��i��137�F8-9�j�A�͉��O�̕\���Ƃ��Ă������܂����B
�@�����Ă��܁A���Q����Ă���p���X�`�i�̐l�тƂ́A�o�r���j�A���ł͂Ȃ����A�i�`�X�ł��Ȃ��B
�@�A�p���g�w�C�g�i apartheid �j�́A�����Ƃ��u�����Ӗ�����B��A�t���J���a���ɂ����锒�l�Ɣl�����ʂ���l��u��������w���B1948�N�ɗ��@�A�S���E������ꂽ���A���͂Ɏ��s���ꂽ�B��\�͂��т����}���f���哝�̂̋ꓬ�͍�������łB1994�N�S�l��ɂ�鏉�̑��I���ł��ׂĔp�~���ꂽ�B
�@�����Ă��܁A�l�퍷�ʂ��ł���ȍ����C�X���G���ł���B�������_���l�Љ�ł��A���[���b�p��A�����J����̈ڏZ�҂̒n�ʂ��ł������A�����Ń��V�A�n�A�Œ�̓G�`�I�s�A�Ȃǂ̃A�t���J�n�ƁA��R���鍷�ʂ�����B�܂��ăp���X�`�i�l�̐l���Ȃǖ����ɓ������B
�@�p���X�`�i�̖��́A2000�N�ɂ���ԋ��Z���ƁA����ȑO�̋��Z���̑����ł���B�����ɏ�����Ă��邩��ƌ����āA���Z����@���I�Ɏ咣�ł���͂����Ȃ��B2000�N�̋��Z�����D�悵�A���ʂȂǂ������ȂǂȂ��B
�@1947�N�̍��A�ɂ�����p���X�`�i�������c�ɁA�A���u���������������͎̂��ɓ��R�ƌ�����B�p���X�`�i�l�̏Z�ޒn��l�Ƃ݂Ȃ��āA�C�X���G���Ƃ����L���������Ƃ���ɖ���������B�����āA���c�Ă̕����䂪�s�����������B�l����ŃA���u67%���_��33%�ł������ɂ��S��炸�A�ʐϔ�̓A���u43%���_��56%�������B
�@�����O����A�V�I�j�X�g�����͏����̍��y�ƂȂ�ׂ��n�̐l���䗦���A���_���l�ɂƂ��ėL���ɂȂ�悤�A�������߂��炵���B�p���X�`�i�l������ǂ��o���ɂ��������B���ꂪ�����O�̃f�B���E���V�[���������ł���A������̐l�퍷�ʁA�����ƂȂ��Č��ꂽ�B�C�X���G�����l����`�����ɂ�����A����ɏ���U�P�͂Ȃ��B


 �@�X�g���[�g�E�A�[�e�B�X�g�A�o���N�V�[�́A�ŋ߂Ƃ݂ɗL���ɂȂ����B�C�M���X�l�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����A�f�����B���Ă��āA���ꂪ�L���S���W�߂�v���ƂȂ��Ă���B�ނ̊G�́A��ۂŋɂ߂ĕ�����₷���B��ɔ����͂ł��邱�Ƃ��D�܂����B�C�X���G���؍ݒ��A�ނ̊G�������͈̂�x���������A�ނ͊G�̑��ɂ��A�x�c���w���̃z�e���ɏo�����Ă���B�����ǂɖʂ������̃z�e���́A�u���E�꒭�߂̈����z�e���v�Ƃ����̂��L���b�`�t���[�Y�ɂȂ��Ă���B
�@�X�g���[�g�E�A�[�e�B�X�g�A�o���N�V�[�́A�ŋ߂Ƃ݂ɗL���ɂȂ����B�C�M���X�l�ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����A�f�����B���Ă��āA���ꂪ�L���S���W�߂�v���ƂȂ��Ă���B�ނ̊G�́A��ۂŋɂ߂ĕ�����₷���B��ɔ����͂ł��邱�Ƃ��D�܂����B�C�X���G���؍ݒ��A�ނ̊G�������͈̂�x���������A�ނ͊G�̑��ɂ��A�x�c���w���̃z�e���ɏo�����Ă���B�����ǂɖʂ������̃z�e���́A�u���E�꒭�߂̈����z�e���v�Ƃ����̂��L���b�`�t���[�Y�ɂȂ��Ă���B
�@�ގ��g���֗^�����f�悪�u�C�O�W�b�g�E�X���[�E�U�E�M�t�g�V���b�v�v�i2010�N�j�ŁA�ނ̕��ʊ�����������x���@�ł���B�f��̑�́A�ǂ��̔��p�ق┎���ق��A�M�t�g�V���b�v��ʂ�Ȃ��ƊO�ɏo���Ȃ��A�Ɲ������Ă���B
�@�ނ̊G�͕ǂɕ`�����B�ނ͔�����ۂ������B�u����p���X�`�i�͐��E�ň�Ԃł�����č����B�O���t�B�e�B�A�[�e�B�X�g���A�N�e�B�r�e�B�z���f�[���߂����ɂ͐�D�̖ړI�n�ł�����ˁv�i�g�r�[�L�u�o���N�V�[��ꂩ�������E�Ɉ����v���p�o�ŎЁj�B�������ɃC�X���G���́A�O���t�B�e�B�E�A�[�e�B�X�g�ɋ���ȃJ���o�X��������Ă���B
�@����̃C�X���G����m��ɂ́A�l���c���F�u�p���X�`�i�E�i�E�v�i��i�Ёj�������B�u�V�I�j�Y�������_���l�B���`���咣���邠�܂�ɁA�p���X�`�i�ɖ{�����݂��Ă����@���I���e�A�����I�����A�����I�����̂��Ƃ��Ƃ���j���v�Ə����B�u�C�X���G���Ƃ̓��_���l�ɂ��A���n�v�ł���A�u�V�I�j�X�g�����̓��_�����Ƃ͐�Ɋւ������������Ȃ������B�ނ��냈�[���b�p�����ꂽ�����̃G���[�g���Ƃ�ڎw���Ă����v�ƕ��͂��A�A���n���A�p���g�w�C�g�̍ő�̗v���ł���Ǝw�E����B�u�V�i�S�[�O�ɑ��ݓ��ꂽ���Ƃ��Ȃ��҂�60%�ɒB�����v�Ƃ�������̎w�E�ɂ́A�ꂢ�����������Ȃ��B
 �@�u�K�U�ɒn���S��������v�i�݂������[�j�����������^���́A����A���u���w����Ƃ��鋞�s��w��w�@�����ŁA�l�������Ƃł�����B���̏��̒��ŁA��A�t���J�̔��A�p���g�w�C�g�����Ƃ����̌��t���Љ�Ă���B�ނ�́A�C�X���G���ɂ��Ă̔��l���ƂƓ������C�V�Y�����Ŏ悵�A�C�X���G���̐�̂Ɠ����p���X�`�i�l�Ƃ̘A�т�\�����Ă���B���̒������A�t���J�J���g����c�c���E�B���[�E�}�f�B�V���̌��t���L���B
�@�u�K�U�ɒn���S��������v�i�݂������[�j�����������^���́A����A���u���w����Ƃ��鋞�s��w��w�@�����ŁA�l�������Ƃł�����B���̏��̒��ŁA��A�t���J�̔��A�p���g�w�C�g�����Ƃ����̌��t���Љ�Ă���B�ނ�́A�C�X���G���ɂ��Ă̔��l���ƂƓ������C�V�Y�����Ŏ悵�A�C�X���G���̐�̂Ɠ����p���X�`�i�l�Ƃ̘A�т�\�����Ă���B���̒������A�t���J�J���g����c�c���E�B���[�E�}�f�B�V���̌��t���L���B
�@�c�A�p���g�w�C�g�i��A�t���J�ɂ�����j�́A�E�l�A�i��Y�A���H�A�Ǖ��A�v���A��w���A�o���c�[�X�^���i���l�����l�̓y�n��D�����x�j�̌��ݓ��X�ɂ���ē����Â����邪�A�p���X�`�i�l�̐g�ɋN���Ă��邱�ƂɊr�ׂ�A���j���̃s�N�j�b�N�̂悤�Ȃ��̂��B���͎��M�������Ēf������A�C�X���G���̓A�p���g�w�C�g���Ƃł���B
�@�������������ɑ��A�V�I�j�X�g�����́u�����_����`�v�ƃ��b�e����A�������肩����B
�@�u�K�U�ɒn���S��������v�ȂǗ���͂����Ȃ��B���̃��j�[�N�ȑ�����{�́A���z��ǂ��҂̖���`���Ă�܂Ȃ��B
�@�c�����_���삩��n���C�܂ŁA���܁A�C�X���G�����x�z���邻�̓y�n�̏�ŁA���_���l���A���u�l���A�_�̑O�ł����ł���悤�ɁA���R�ŕ����Ȑl�ԂƂȂ�����c�H�@���ꂱ�����A�V�I�j�Y�����ł�����鎖�Ԃ��B�i�����j�����̟B�̓S�i�q���Ȃ��Ȃ����Ƃ��A�K�U�ɒn���S�����邾�낤�A�Ɖ��^���͂��̏�����߂�����B
�e�����X�g
�@�C�X���G���̓p���X�`�i�l���e�����X�g�ĂсA�����ǂ�z���Ă���B���̏X���ǂ́A��O�������푈�ŒD��������A���ۓI�ɂ͔F�߂��Ă��Ȃ������_���쐼�ݒn��[���H�����݁A�s�@�ȓ��A�n��ی삵�Ă���B�������ɁA�����nj���C�X���G�������ɂ�����e���s�ׂ͌��������B�����A�C�X���G���ɁA�p���X�`�i�̃e���s�ׂ���鎑�i������̂��낤���B
 �@�C�M���X���ϔC������f�O���A�������A�Ɋۓ���������ȗv���́A���_���l�ɂ��e���s�ׂ������B���̂����Ⴊ�A�L���O�E�f�C���B�b�h�E�z�e�����j�����ł���B������A�C�X���G���̓��T�h�Ƃ������E�����H��@�ւ�n�݂����B�A���[���`���ɐ������Ă����i�`�X�̃A�C�q�}����߂炦���̂����̋@�ւł���B���T�h�͈ÎE�W�c�ƌ����Ă����B
�@�C�M���X���ϔC������f�O���A�������A�Ɋۓ���������ȗv���́A���_���l�ɂ��e���s�ׂ������B���̂����Ⴊ�A�L���O�E�f�C���B�b�h�E�z�e�����j�����ł���B������A�C�X���G���̓��T�h�Ƃ������E�����H��@�ւ�n�݂����B�A���[���`���ɐ������Ă����i�`�X�̃A�C�q�}����߂炦���̂����̋@�ւł���B���T�h�͈ÎE�W�c�ƌ����Ă����B
�@�~�����w���E�I�����s�b�N�����̐����c��u�����㌎�v�̃����o�[3����ǂ��l�߂ĎE�����B2010�N�A�p���X�`�i�A�n�}�X�R������n�ݎ҃}�t�}�[�h�E�}�u�[�t���A�h�o�C�ňÎE�����B���̂Ƃ��A���T�h�̃����o�[�́A�C�M���X��I�[�X�g�����A�̋U���p�X�|�[�g�ŃA���u���A�M�֓��������B���p���ꂽ���X�̓C�X���G������A�C�M���X�̓C�X���G���O��������l���O�Ǖ������Ƃ����B�����N�A�C�����A�V�����t�H�ȑ�w�����A���E���n�}�f�B�E�����B�ނ͊j����ږ�ł��������B�C�X���G���͒��ق�����Ă��邪�A�p���X�`�i�ȏ�̃e�����Ƃł��邱�Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B
�@�u���T�h�E�t�@�C���v�i�}�C�P���E�o�[���]�E�n�[�^�j�V���E�~�V�������A��쌳����A�n���J���E�m���t�B�N�V�������Ɂj�ɂ́A���T�h�����{���Ă����ÎE�j��s�ׂ̐��X���L�q����Ă���B���҂��������_���l�ł��邾���ɁA���Ȃ̕ق͑S���Ȃ��B�ނ��냆�_���̌Â����Ƃ킴�u���ꂩ���E���ɂ���̂Ȃ�[�[�����������āA���̒j���ɎE���v�ƌȂ̍s�ׂ𐳓������Ă���B
�@2020�N1��3���A�A�����J�̃h���[�����A�C�����̌R���ӔC�҃\���C�}�j�i�ߊ����o�O�_�b�g��`�Ŕ��E�����B�����̍���̗��s�̒��O�ł���B���̂Ƃ������ɃC���N�̃��n���f�B�X���i�ߊ��ق�4�������S���Ă���B�A�����J�ɁA�������e�����X�g���ƂƌĂԎ��i�͂Ȃ��B
���̂��a���A�֗��Ȑ�����
�@���݂̃p���X�`�i�������{�̕�̂ƂȂ����p���X�`�i����@�\�́A�C�X���G�������ɂ���č��O�ɓ��ꂽ�p���X�`�i�̐l�X������������R�g�D�ł���B1964�N�̃A���u�A���ɂ�����A���u��]��c�ŁA���̐ݗ������F���ꂽ�B�O��Ƃ���̂́A�����������Ɨ��U�p���X�`�i�l�̋A�Ҍ��ł���BPalestine
Liberation Organization �̗���PLO�ƌĂꂽ�B
�@���������_���̃A���}���ɋ��_��u���A�C�X���G���֏��K�͂ȉz���e���U�����J��Ԃ����B�C�X���G���́A�Ƃ��ă����_���������B�����_�����{��PLO��ǂ��o������Ȃ��BPLO�͋��_���A���o�m���ֈڂ����B
�@�C�X���G���ƃp���X�`�i�̓�������n�߂�ƁA�ǂ��Ŏn�߂Ăǂ��ŏI����Ă����̂��A�����當����A�˂Ă��I�肪�Ȃ��悤�Ɏv����B����ł�1982�N�̃��o�m���푈�����́A�����ɋL�^���Ă��������B
�@�C�X���G����1979�N�A�G�W�v�g�Ƃ̘a�����������ƂŁA�암�ł̐푈�̋��Ђ��������ꂽ�B���E�́A�C�������C���N�푈��A�t�H�[�N�����h�푈�̍s���ɒ��ڂ��A�p���X�`�i���ւ̊S������Ă����B�C�X���G���́A������D�@�ɁA���o�m����PLO���Ԃ��ɂ��������B����PLO�����Ƃƍl����A��������푈�ƌ����Ă������B
�@1982�N6���APLO�̋��_���������x�C���[�g���APLO���x������V���A��R�ɂ��U�����������B���A�̒�튩���ɂ��S��炸�A8���܂Ő퓬�𑱂��A�x�C���[�g�͊��I�̎R�Ɖ������B����1��9085�l�A������3��302�l�A�ǎ��ƂȂ����q����6000�l�A�Ƃ��������l��60���l�ƋL�^����Ă���i�L�͗���u�p���X�`�i�v��g�V���j�B�ߌ��͂��ꂾ���Ɏ~�܂�Ȃ��B
�@�L���X�g���}�����h�̕����g�D�t�@�����W�X�g�i�t�@�����w�}�j���A�x�C���[�g�x�O�̃p���X�`�i��L�����v���P���A��퓬�����s�E�����B�t�@�����w�}�́A�e�C�X���G���̖����g�D�ł���B���̔ߌ��̔w�i�ɂ́A���I��������̃��o�m���哝�̃A�~�[���E�W�F�}�C�G���ÎE����������B�e�C�X���G���������哝�̂̈ÎE���A�t�@�����w�}��PLO�̔ƍs�Ƒ����A�p���X�`�i�ւ𐾂̕��Ă����B
�@����ԑ������s�E�̎��҂�762�l����3500�l�ƌ����Ă���iWikipedia�j�B�T�u���[�E�V���e�B�[�������ƌ����B���̎����ŁA�C�X���G���͎��O�̉��[�u����炸�A�s�E��ٔF�����Ɣ��ꂽ�B
�@���̌��ʁAPLO�̓`���j�W�A���_���ڂ����B
�@�C���e�B�t�@�[�_�̓A���r�A��ŁA�u�I�N�v�A�u�����v���Ӗ�����B
�@1987�N10��1���A�C�X���G�������K�U�̃W�n�[�h�^���\����7�����E�Q�����B������A���A�҂��p���X�`�i�̏��q�w����w�ォ��e���A12��6���C�X���G�����h�R�̃g���b�N���o���ɏՓ˂��A�p���X�`�i�l��4�����S�����B��L�����v�ł̑��V���\�k�����A�C�X���G�����h�R�ւ̍U���ւƔ��W�����B��ꎟ�C���e�B�t�@�[�_�Ƃ����B�U�������ƌ����Ă��Ή��r������t�萻�̔��e�ł���B�����̎��S�҂��p���X�`�i�ɏo���B12��22���A���A���ۗ��̓W���l�[�u���ᔽ�Ƃ��ăC�X���G�����c���̑������B
�@�A�����J�̋��ی��Ɏ��ꂽ�C�X���G���͎���ɂ߂Ȃ��B1988�N4���APLO�w���҃A�u�[�W�n�[�h���`���j�X�ňÎE�����B���N10���ɂ́A���_���l�ߌ��h���G���T�����̃��X�N���P�����A�����ɏo�����������x�@���A�p���X�`�i�l22�����ˎE�����B
�@���E�̐��_�́A�u�ԂĂň����҂ɗ����������Z���ƁA������ŐV����ŏ��q�q�����܂ߑ|������C�X���G���R�v�ƂƂ炦�A�C�X���G�����ւƌX�����B
�@�@������ɕq��PLO�A���t�@�g�c���́A1988�N11��15���A�p���X�`�i���Ƃ̓Ɨ���錾�����B1947�N�́A���A�ɂ�����p���X�`�i�������c���܂��������Ă��Ȃ��Ƃ��闧��ł���B�G���T��������s�Ƃ��Đ錾�������̂́A�ǂ��ɂ��̓y�̂Ȃ����Ƃ������B
�@�C�c�n�N�E���r���́A1967�N��O�������푈���̃C�X���G���R�Q�d�����ŁA�����������ɓ������R�l�ł���B�ޖ���A�����J��g�ƂȂ�A���̌㐭�E���肵���B�����͍����n�̘J���}�ŁA�J����b���o�ĘJ���}�}��ƂȂ����B���̂���A�C�X���G���ɂ��ω��̉肪�G���Ă����B���V�A����̈ږ����}�����A�����I�����⍶�������Ă����B1974�N�A�ނ̓S���_�E���C���̐Ղ��p���ŎƂȂ����B�����āA�p���X�`�i�Ƃ̘a���̎���������邱�ƂɂȂ�B
�@�A�����J�A�N�����g���哝�̂͒����a���ɗ͂𒍂����B�ނɂ͏����X�L�����_���̉��������Ă܂�邪�A�O��ʂ̋Ɛт͑傫���B�����ȊO�ł��A�{�X�j�A�E�w���c�F�S���B�i�̘a���𐬌������Ă���B
�@�m���E�F�[�̒�����傫���B���ʉ��̌��̏������B�N�����g���哝�̂̎哱�ŁA�C�X���G���ƃp���X�`�i����@�\�Ƃ̊Ԃ̍��ӂ����������B1993�N9��13���A���V���g���Œ����s�����B�I�X�����ӂƂ����B���r���́A�u�a���͗F�ƌ��Ԃ̂ł͂Ȃ��A�G�ƌ��Ԃ��̂��v�ƌ������i�u���r����z�^�v�|�c���q��A�~���g�X�j�B
�@��{�I�ȍ��ӓ��e�́A�@�C�X���G�������ƂƂ��āAPLO���p���X�`�i�̎������{�Ƃ��đ��݂ɏ��F����A�C�X���G���͐�̂����n�悩��b��I�ɓP�ނ��A5�N�ɂ킽���Ď������{�ɂ�鎩����F�߂�B����5�N�̊Ԃɍ���̏ڍׂ����c����A�Ƃ������̂ł���B
�@���̌��ʁA1994�N5������K�U�ƃG���R�̐�s�������n�܂����B�C�X���G���̃��r���A�y���X�O���APLO�̃A���t�@�g�c���̎O�l�̓m�[�x�����a�܂���܂����B
�@1995�N9��24���A�I�X�����ӂ�����Ɏϋl�߂��u�b�莩���g�升�Ӂv�����V���g���Œ��ꂽ�B�u�x�c���w���v�̍��ŐG�ꂽA�AB�AC�̊Ǘ��敪�͂����Ō��肵�Ă���BC�n��͏����p���X�`�i�ֈڊǂ����v�悾�����B�a���͖ڑO�̂悤�Ɏv�����B
�@1995�N11��4���A���r�����ÎE���ꂽ�B�Ɛl�̓C�X���G���g���`�ҁi�J�n�l��`�j�������B���a�ւ̊�]�͓ڍ������B���̌�Β��̌I���E�������Ƃ͏o�ė��Ȃ��B�m�[�x�����a��҂̈�l�V�����E�y���X�͌�ɑ哝�̂ƂȂ������A���łɏ��蕨�ł����Ȃ������B
�@�C�X���G���̑p���X�`�i����͂�茵�����𑝂��A���A�n�͊g�債���B�R����悤�ɃA���u������s������BPLO���\������t�@�^�n�̉����H���ɕs�������n�}�[�X���K�U���x�z���A��R�^�����ߌ��������B���o�m���̃q�Y�{���͉z���U�����J��Ԃ��B
�@2000�N9���A��C���e�B�t�@�[�_���N�����B���������́A�V�������O���i�����A��Ɏj��1000���̕������m�Ƌ��ɁA�A���E�A�N�T���X�N�ɓ��ꂵ�����Ƃɒ[����B�C�X�������k�ɑ��钧���s�ׂ������B���̑�C���e�B�t�@�[�_���܂��A�u�ԂĂň����҂ɗ����������Z���ƁA������ŐV����ő|������C�X���G���R�v�̌J��Ԃ��ɏI������B���|�I�ȕ��͂̍��́A���|�I�Ȏ��Ґ��̍��ƂȂ�B
�@2002�N2���A�T�E�W�A���r�A���A�A���u�A�����\���Ęa���Ă��Ă����B1967�N�̐�̒n����C�X���G�����P�ނ���A���ƂƂ��ď��F����Ƃ������ɑÓ��Ȓ�Ă������B�������A�O���[�g�E�C�X���G����ڎw���V�I�j�X�g�����͈�ڂ��ɂ��Ȃ������B���ꂾ���ł͂Ȃ��A���E���_��}���邩�̂悤�ɁA�e���}�~�𗝗R�ɕ����ǂ̌��݂��J�n�����B�C�X���G�����c�́A��ɃA�����J�����ی��Ŏ�����B�@
�@�V�I�j�X�g���ڎw���O���[�g�E�C�X���G���Ƃ́A�_�r�f��\����������̗̓y�̍Č��ł���B�����ĂȂǁA�ނ�ɂƂ��Ă͖��f�Ȓ�Ăł���B�������O���[�g�E�C�X���G���ȂǁA���������l�̞D��ł���Ƃ������A�������鍑�X������B�����ł���͂����Ȃ��B�ނ�͐����ɏ�����Ă���ƌ����B�����܂ł���ƁA�C�X����������`�҂̋��M�Ɖ���Ⴂ�͂Ȃ��B
�@2003�N4���A�u�b�V���i�q�j�哝�̂́A�C���N�N�U�ɐ旧���āA�C�X���G���E�p���X�`�i�����������悤�ƁA�����Ă����q�Ƃ��郍�[�h�}�b�v�\�����B�C�X���G���ɂƂ��āA���f�Ȓ�Ă��������Ƃ肠�������ق�������B�u�b�V���哝�̖̂{�S�̓C���N�N�U�ɂ���A���[�h�}�b�v�͂���ȏ�i�W���Ȃ������B
�@2004�N�APLO�̃A���t�@�g�c�������������B��p�҂̓}�t���[�h�E�A�b�o�[�X�ł���B�ނ�2011�N9���A�p���X�`�i���ƂƂ��Ă̍��A������\�������B���A�́A2012�N12��1���A�p���X�`�i���u������I�u�U�[�o�[�g�D�v����u������I�u�U�[�o�[���Ɓv�֊i�グ�����B
�@���݃p���X�`�i�����ƂƂ��ĔF�߂Ă��鍑�X��137�����ɏ��B�c�O�Ȃ���A���{�͒��ԓ��肵�Ă��Ȃ��B
�@2014�N�āA�K�U��51���ԕ��������C�X���G���́A�W�F�m�T�C�h�Ƃł��ĂԂׂ��U�������s���A2200�l�ȏ�̃p���X�`�i�l���E�Q�����B
�@2016�N11���̃A�����J�哝�̑I���ŁA��������̗\�z�ǂ���q�����[�E�N�����g�����哝�̂ɓ��I���Ă����Ƃ���B�v�̃r���E�N�����g�����O���ږ�ƂȂ��ăI�X�����ӂ̍Č���ڎw������������Ȃ��B�������A���j�Ɂu�����v�͐������Ȃ��B�g�����v�哝�̂����I���Ĉȗ��A�C�X���G���ƃp���X�`�i�Ƃ̊W�́A��w�ْ����𑝂����B���[�����ł̓q�����[�ɗ�����g�����v�́A����ڂ�ڎw���āA���_�����̎p��������Ȃ��B���_���̎����ƁA�@���F�̋����암���B�̕[�����݂̍j�ł���B
�@2017�N12���A�A�����J�̓G���T�������C�X���G���̎�s�ƔF��A�C�X���G������70���N���L�O���āA2018�N5����g�ق��e���A�r�u����G���T�����ֈړ������B���ۓI�ɂ͔��ꂽ���A�đI�������ɂȂ��g�����v�哝�̂́A���j�I�o�܂⍑�ې��`�Ȃǂɍl�����y�Ȃ��B���R�p���X�`�i�̔����������B���ɃK�U�ł͌������Փ˂��N�����B�ɒ[�Ȏ��Ґ��̕s�ύt�������ƁA���̓C�X���G���ɏW������B�C�X���G���̓X�i�C�p�[�������t�߂ɔz�u���A�f���O���[�v�̑�����_����������B���Ґ��͌��邪�A�����鏭�N�����ɕs��҂������o��B�ԂĂƍŐV����ł́A��Ɍ��ʂ͌����Ă���B
�@�C�X���G���̎́A1996�N�ȗ��l�^�j���t�ł���B�ނ́A���E�Ȃǂ̃X�L�����_���ɋꂵ�݁A�̒n�ʂ������Αi�ǂ���鋰�ꂪ����B�p���X�`�i���d��𑱂��Đ������ێ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�g�����v�哝�̂ƃl�^�j���t�̑g�ݍ��킹�́A�p���X�`�i�ɂƂ��čň��ƌ�����B���A�n�̊g��͖ٔF���ꂽ�B��l�Ƃ��A�a�����c�̓C�X���G���ƃp���X�`�i�̓�ҊԂōs����ׂ��Ǝ咣����B�͂̍����h�R�����҂ł���A���̘_�ɂ�������������B�C�X���G���ƃp���X�`�i�̓�ҊԂł́A�����̌�����ɉ߂��Ȃ��B
�@�g�����v�哝�̖̂����W�����b�h�E�N�V���i�[�́A�哝�̏㋉�ږ�Ƃ��Ē����a���Ă�����Ă���B���_���l�ł���ނ̈ẮA�C�X���G���ɂ����������̂ƂȂ�B�r�W�l�X�}���Ƃ��Ă͋`���ȏ�ł��낤���A���ꂾ���ɋ��K�I�ȉ����Ă����܂�邱�Ƃ��낤�B�a���Ă��s���Y����Ƃ��Ĉ���ꂩ�˂Ȃ��B�p���X�`�i�̌ւ�ȂNJ��S�ɖ��������ĂɂȂ邱�Ƃ��낤�B
�@�l�^�j���t�̃��C�o���Ɩڂ����x�j�[�E�K���c�́A�l�^�j���t�̉��E�͒Njy������̂́A�O���[�g�E�C�X���G����ڎw���H���ł͂��قLjႢ�͂Ȃ��B�����ĂȂǔO���ɂȂ��B
�@�C�X���G���ɂ��ǐS�h�����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�p���X�`�i�l�̓y�n�����グ�����ƂɁA�ǐS�̒ɂ݂������Ă���l�X����������B�������A�命���͎����̗̓y�̈ێ��g���]�ށB�����傫���Ȃ邱�Ƃɔ�����҂Ȃǂ��Ȃ��B
�@�l�^�j���t�́A���E�����Ƃł���B��������O�ɂƂ��āA�Ȃ̗ǐS��ɂ߂邱�ƂȂ��A�������Ƃ�����Ă���鐭���Ƃ������炫��߂ĕ֗��ł͂Ȃ����낤���B�u�֗��Ȑ����Ɓv�ł��邱�Ƃ��A�l�^�j���t�̑��݉��l�ƌ�����B
�@�a���Ă͂Ȃ��̂��B����B1947�N�ɖ߂낤�B���A�ō̌����ꂽ�p���X�`�i�������c���A���܂��Ȃ��A�ł��Ó��ȈĂȂ̂ł���B
�@�p���X�`�i�̒n�ɁA�A���u�ƃ��_���l�̍���n�o���A�G���T��������ʓs�s�i���A�̐M�������j�Ƃ��邱�Ƃ��������c�̍��q�������B������A1967�N��O�������푈�ȑO�̗̓y���Ŏ��s��������B������͏�ɒP���Ŗ��m�ł���B�������A�����Ɏ������ނ����������Ƃ��A�o��̂͗��������Ȃ��B
�]�_�A���w�A�f��Ȃ�
�m�̋��l����
�@�G�h���[�h�E�v�E�T�C�[�h�̓p���X�`�i�n�̃A�����J�l�ŁA�L���X�g���k�������B�R�����r�A��w�ŁA�p���w�Ɣ�r���w�̋�����40�N�ԋ߂��B
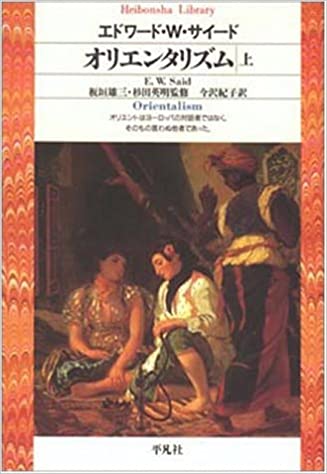 �@�����u�I���G���^���Y���v�i����I�q��A���}�Ѓ��C�u�����[�j�ɂ����āA���̌��t�̎����}���e�B�b�N�ȃC���[�W���A�����̐l�X�����D�z�����琶�܂�Ă����ƓI�m�Ɏw�E�����B�����āA���ꂪ�A���n��`��A�鍑��`�I�Ȗ�]�𐳓�������B�ꖪ�ƂȂ��ė����ƒNjy�����B�����Ă݂�A����ꂪ�����Ɏ��C���[�W�́A�u���镨��v����X�L�[�E�R���T�R�t�́u�V�F�w���U�[�h�v�ł���A�h���N���A��A���O���̊G��ł���B�����̖ڂ�ʂ��Ē��������Ă���B
�@�����u�I���G���^���Y���v�i����I�q��A���}�Ѓ��C�u�����[�j�ɂ����āA���̌��t�̎����}���e�B�b�N�ȃC���[�W���A�����̐l�X�����D�z�����琶�܂�Ă����ƓI�m�Ɏw�E�����B�����āA���ꂪ�A���n��`��A�鍑��`�I�Ȗ�]�𐳓�������B�ꖪ�ƂȂ��ė����ƒNjy�����B�����Ă݂�A����ꂪ�����Ɏ��C���[�W�́A�u���镨��v����X�L�[�E�R���T�R�t�́u�V�F�w���U�[�h�v�ł���A�h���N���A��A���O���̊G��ł���B�����̖ڂ�ʂ��Ē��������Ă���B
�@�T�C�[�h�͂���ɔ��W���āA�I���G���g�ƃI�N�V�f���g�̋�ʂ��s�K�v�Ƃ����B�I�N�V�f���g�́A���e����œ��v�̒n���Ӗ����A�������w�����t�ł���B
�@�u�p���X�`�i�Ƃ͉����v�i���O�V��A��g���㕶�Ɂj��u�y���ƌ��v�i����^�I�q��A�����܊w�|���Ɂj�Ȃǂ������ʂ�A�ނ̓A�����J�ɂ����鐔���Ȃ��p���X�`�i���̘_�q�������B�ނ̓I�X�����ӂɔ��������B�u�ꍑ�Ɖ����v���Ȃ킿�A�A���u�l�ƃ��_���l�����������������V���ȍ������ׂ��Ǝ咣�����B���̂��߁A�A���t�@�g���Ԃ����ƂƂȂ����B�I���G���g�ƃI�N�V�f���g�̋�ʂȂǕs�v�Ǝ咣����ނ炵�����z�_�������B�C���h�Ɨ��̕��K���f�B�[���]�̂́A�q���h�D�[���k�ƃC�X�������k���������������鍑�Ƃ������B�W���i�[�̋��͂Ȕ��ŃC���h�ƃp�L�X�^���̓Ƃ��a�������B�K���f�B�̊肢�͎������Ȃ������B�p���X�`�i�ɂ����āA����ȃV�I�j�X�g�������T�C�[�h�̎咣�ɑg����͂����Ȃ��B���z�_�͖��Ə�����B�ɂ������A�ނ�2003�N67�Ő����������B
�@�C�����ɐ��܂�̃n�~�b�h�E�_�o�V�́A�A�����J�Ŋw�сA���݂̓R�����r�A��w�ŋ������߂Ă���B�T�C�[�h�̌�p�҂Ƃ�������B�u�|�X�g�E�I���G���^���Y���v�i�����M�I�A�{���N��A�^�M�`�A�{�R�����A��i�Ёj�̂Ȃ��ŁA�ނ̓T�C�[�h�́u�I���G���^���Y���v�������]�����A���̘_�������I�l����`�I���n�ɑ����Ă���̂ł͂Ȃ����A�������悤�Ƃ��Ă���Θb�҂������Ɍ����A�C�f�I���M�[�I�Ɏ��ł��Ă���Ǝw�E����B�T�o���^���i��}���ҁj�Ƃ��ẮA���E��Θb�҂ɂ��ׂ��Ǝ�������B
�@�n���`���g���́u�����̏Փˁv��A�t�N���}�́u���j�̏I��v�����グ�A�E�������Ƃɍv�����邾���̌�p�w�҂ƍ��]����B�ɉ��ł��炠��B
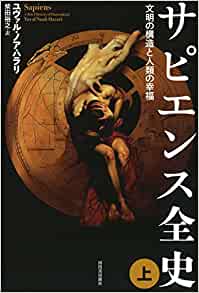 �@�u�T�s�G���X�S�j�v�i�ēc�T�V��A�͏o���[�V�Ёj�̒��҃����@���E�m�A�E�n�����̓C�X���G���l���j�w�҂ł���B�I�b�N�X�t�H�[�h��w�Ɋw�сA�w�u���C��w�ŋ��ڂ��Ƃ�B�ނ͎���_�_�҂ŁA�Q�C�ł��邱�Ƃ��B���Ă��Ȃ��B�܂��̑O�̃��_���Љ������A�����Ă����Ȃ��ނ̐l���ł���B���̏��́A���������ɂ͂����Ȏ�i�Ⴆ���C�I���A�g���A�q���E�A�W���K�[�͂��ׂăq���E���ɓ���j������̂ɁA�l�ނɂ̓z���E�T�s�G���X�������Ȃ��̂��A���̑O�ɑ��݂����l�A���f���^�[���Ƃǂ����Ⴄ�̂��A�Ǝw�E����B�A�t���J�łق��ڂ��ƕ�炵�Ă����z���E�T�s�G���X���A�H���A���̒��_�ɗ����A������z�����̂͂Ȃ����A�Ɩ₢������B
�@�u�T�s�G���X�S�j�v�i�ēc�T�V��A�͏o���[�V�Ёj�̒��҃����@���E�m�A�E�n�����̓C�X���G���l���j�w�҂ł���B�I�b�N�X�t�H�[�h��w�Ɋw�сA�w�u���C��w�ŋ��ڂ��Ƃ�B�ނ͎���_�_�҂ŁA�Q�C�ł��邱�Ƃ��B���Ă��Ȃ��B�܂��̑O�̃��_���Љ������A�����Ă����Ȃ��ނ̐l���ł���B���̏��́A���������ɂ͂����Ȏ�i�Ⴆ���C�I���A�g���A�q���E�A�W���K�[�͂��ׂăq���E���ɓ���j������̂ɁA�l�ނɂ̓z���E�T�s�G���X�������Ȃ��̂��A���̑O�ɑ��݂����l�A���f���^�[���Ƃǂ����Ⴄ�̂��A�Ǝw�E����B�A�t���J�łق��ڂ��ƕ�炵�Ă����z���E�T�s�G���X���A�H���A���̒��_�ɗ����A������z�����̂͂Ȃ����A�Ɩ₢������B
�@����́A�z���E�T�s�G���X�Ɂu���\�v�����\�͂����������炾�A�Ƃ����̂��ނ̓��ł���B�u���\�v���������m��ʐl���m���͂��邱�Ƃ��\�ɂ����B���R���́u���\�v�̒��ɂ͏@�����܂܂��B
�@�����@���E�m�A�E�n�����́u�Q�PLessons�v�i�ēc�T�V��A�͏o���[�V�Ёj�́A����Љ�͂���B�u�_�v�u�i�V���i���Y���v�u�ږ��v�Ȃǂ̖�肪���グ����B�u�������A�G�W�v�g���C�i�S�̑唭���Ɍ�����ꂽ��A�G�W�v�g�l�̓A�b���[�ɋ~�������߂邾�낤���v�Ə����B�ނ̘_�́A�[���Ȗ��̎w�E�Ɏn�܂�A���X�̗��j�I�����Ɣ�r���A�ǂ��炩�ƌ����|�W�e�B�u�Ɍ��_�Â���Ƃ��낪�ʔ����B
�@���̏������p���������̂Ȃ��ɁA�I���_�X�E�n�N�X���[�́u���炵���V���E�v�i�����q�s��A�����Е��Ɂj������B�n�N�X���[�����̃f�X�g�s�A������������̂�1931�N�ł���B�����C�M���X�̃W���[�W�E�I�[�E�F���́u�P�X�W�S�N�v�i�V���N�v��A�n���J�����Ɂj�́A�S�̎�`���Ƃ̃f�X�g�s�A��`���Đl�X���ɂ������B�n�N�X���[�́u���炵���V���E�v�́A����Ɩ\�͂̑���Ɉ��Ɖ��������B���̐��E�͕��a�Ŕɉh���Ă���B���̂ǂ����f�X�g�s�A�Ȃ̂��w�E�͓���B�������A�u�P�X�W�S�N�v�ȏ�Ɉ����̂悤�ȃf�X�g�s�A�Ȃ̂ł���B�u���炵���V���E�v�͖����ւ̊�]�̂Ȃ��l�ԎЉ���������Ă���B�I�[�E�F�����C�[�g���Z�Ŋw��ł�������A�n�N�X���[���ނɃt�����X��������Ă����Ƃ����̂��Ȃɂ�����s�v�c�Ȉ����ł���B
�@�����������m�̋��l�����̏���ǂނƁA�����u�ڂ���v�̎v���ɋ����B�����̒m���̐��ɗ⊾�𗬂��B�܂��ɗ⊾�O�l�̎v���ł���B
�@�����@���E�m�A�E�n�����́A���_���l�ŁA�C�X���G���Ő����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ނ́A���̒����̒��ŁA���Ӑ[���p���X�`�i���������B�u�Q�PLessons�v�̒��ŗB��A�u�C�X���G���l�ƃp���X�`�i�l�̊Ԃ̕��a�������j�ޑ傫�ȏ�Q�̈�́A�C�X���G���l���G���T�����̒�����������Ȃ����Ƃ��B���̒��́w���_�������̉i���̓s�x�ł���A�i���̂��̂Ɋւ��Ă͐�ɑË��ł��Ȃ��A�Ɣނ�͎咣����B�i�����j�w�i���x�͂ǂ�ȂɒZ���Ă�138���N����B�i�����j�G���T�����͂킸��5000�N�O�ɑn�݂���A���_�������͒����Ă�3000�N�̗��j���������Ȃ��B����ł͉i���ƌ������i�͂Ƃ��Ă��Ȃ��v�Əq�ׂĂ��邪�A�����܂ł�����t�̂Ƃ��낾�낤�B
�@��r�����_�ł́A���{����́u���̕����A�̕����A�D�̕����v�iPHP�V���j���悭�܂Ƃ܂��Ă���B��g�͂��ꂼ��A���u�A���[���b�p�A�A�W�A���Ӗ�����B�̕����̃��[���b�p�́A�\�y���_�ƂɌ����Ȃ��B�����ɋ���������H�ƂȂ�B�D�̕����̃A�W�A�͕Ă��Y�o����B���ƕĂł͎x����l���ɍ����o��B�A�W�A�̐l�����x�̍����ɔ��f����B�̕����̃��[���b�p�́A�q�{����Y�ƂɂȂ�B�r�⋍������H�ׂ����ƁA�ʂ̏ꏊ�Ɉړ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɂ͍L���q���n���K�v�ƂȂ�B�K�R�I�Ɋg���`�҂ƂȂ�B
�@���̕����ɏZ�ސl�X�ɂ��āA���{�͉f��u�A���r�A�̃������X�v�����������B�����ɓ������������X���A�ē��̃x���x���l�ƈ�˂̐������ށB������������A�ē��l���ˎE����B�������X���R�c����ƁA�������́u�����͓����l���v�Ɠ�����B�������X�́u�����������B���������l����Ȃ����v�ƍR�c����B�������͓�����u����A���Ȃ��̓Q�X�g���B�Q�X�g�͏��������Ă���v�B
�@�����ɐ�����l�X�́A���ՂŐg�𗧂Ă�B�����Ԃ̃l�b�g���[�N��ʂ��ē`������̍j�ł���B�K�R�I�Ƀ^�t�E�l�S�V�G�[�^�[�ƂȂ�B���̑���Ƃ��Ă͎苭���B
�@���������āA�u�b�V���i�q�j�哝�̂̃C���N�N�U���v���N�����B�ނ̑_���́A�Ζ������̎x�z�ɂ��������A�����I���Ɍ����킯�ɂ��������A�C���N����ʔj��Ɖ��w������������Ă���ƁA�N�U�̗��R�Â��������B�t�Z�C���哝�̂́A�����ے肵�Č��𑱂����B���@�����ۂ����C���N�ɐh��������Ȃ��Ȃ����u�b�V���哝�̂̓C���N�ɍU�ߓ������B�����ɂ͑�ʔj������w������Ȃ������B�C�M���X�̃u���A���A���{�̏�����A�u�b�V���哝�̂ɖӖړI�Ɏ^�����A�ǐ������B���҂Ƃ������ł͂܂��܂��̃��[�_�[���������A�����ʉ������c���Ă��܂����B
�@���̂Ƃ��A�t�Z�C���哝�̂͂܂����𑱂��Ă������ł͂Ȃ��������낤���B�A�����J���A�C�M���X���A���{���A�����̐l�X���^�t�E�l�S�V�G�[�^�[�ł��邱�Ƃ𗝉����Ă��Ȃ������B�搧�U���̔ǂ���ɂ��邩�͖����ł���B
�@�T�C�[�h��_�o�V�̏���ǂ�ŁA�݂������悤�₭�C�X���G���̎��̂𗝉��ł����悤�Ɏv���B�I���G���g�i���m�j�ɑ���I�N�V�f���g�i���m�j�Ƃ����ϓ_���猩��K�v������B�{���A�l�ނɐ��m�����m�������Ă͂Ȃ�Ȃ����A�C�X���G���𗝉�����ɂ́A�ނ�̍l�����ɗ�������Ȃ��B
�@���Ƃ��Ɛ��m���猩��Γ��m�̖������������_���l�́A���N�ɋy�ԃf�B�A�X�|���̖��A���m�̃��_���l�ƂȂ����B���̔ނ炪�A�p���X�`�i�̒n�ɐV����������u�A���n�v���C�X���G���ł���B�l���c���u�p���X�`�i�E�i�E�v�ɏ������A���n�]�X�̎w�E�͐������B���m�ȊO�̒n�悩��̈ڏZ�������_���l�́A���m�n���_���l�̎x�z���ɂ����ĉ����K�w���`������B�A���n���Z���Ƃ̒��ԓI���݂ł���B����Ăɂ����郁�X�e�B�[�\�ɋ߂��B
�@16���I�ȍ~�ɍ��ꂽ�A���n�́A���̂قƂ�ǂ��Ɨ����ʂ������B���ĉ��������_���l�̍�������E�ň�ԐV�����A���n�́A���s������y�����牽���w��ł��Ȃ��B�w�ڂ��Ƃ����Ȃ��B�l�퍷�ʁA�����A�A�p���g�w�C�g�ȂǁA�ނ炪�Ȃ�����قǗ⍓�ɂȂ��̂��A����ƍ��_�������B�����͂��ׂĐ�y�����A�C���h�Ⓦ��A�W�A�A����Ă�A�t���J�ł���ė������Ƃł���B�C�X���G���́A��y���ȏ�ɗ⍓�ɂ�����Č����Ă���ɉ߂��Ȃ��B
���w��f��Ȃ�
���삠�ꂱ��
�@���E�ł��ŌÂƌ����镶�w���A�u�M���K���V���������v�i����v��A�����܊w�|���Ɂj�ł���B�Ñチ�\�|�^�~�A�ɐ��܂ꂽ���̕���́A�S�y�ɞ��`�����ō��܂ꂽ�B�u���C�����v�͗r�玆�ɏ�����Ă����B�������ĕ��ꗎ�������Ă����B�u�M���K���V���������v�̓D�ɍ��܂ꂽ�����͂͂�����Ǝc���Ă������A�S�����Ȃ������Ȕj�ЂɂȂ��Ă����B�o���o���ɂȂ����D�̔j�Ђ��A�����҂����͋C�̉����Ȃ�悤�ȓw�͂��d�˂āA��̕���ɍ\�����Č���ɓ`���Ă����B�|������v���܂߂āA�������������Ɍg���l�����̓��̒��́A�ǂ̂悤�ȍ\���ɂȂ��Ă���̂��A�����Ƃ��������悤���Ȃ��B
�@���̕���́A�I���O1300�`1200�N���ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�Ƃ���Ă���B���͕s���̒Njy�A�F��A�_�ȂǂŁA�l�Ԃ͐��_�I�ɌÑォ��ʂ����Đi�������̂��ƁA�S�Q�̎v���ɋ����B��^���͋����́u�m�A�̕��M�v�A�M���K���V���ƃG���L�h�D�̊W�̓_�r�f�ƃ��i�^���ɉe����^�����Ƃ����B�������A���_�����k���A�L���X�g���k���F�߂����Ȃ������ł���B
�@���̏��ɂ́A�u�C�V���^���̖��E����v�����^����ĂĂ���B�M���V���_�b�̃A�h�j�X��I���t�F�E�X�̕���ɉe����^�����̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���B�����ɁA���{�_�b�̈ɜQ�����̖��E������v���o������B
�@���{�ł��C�G�X�����ɂ����`�L�⏬���͐���������B�Ȃ��ł��ْ[�̍�́A���c�~�́u�킪�q�L���X�g�v�i�u�k�Е��|���Ɂj�ł��낤�B��M�҂́A��ٍ��m�⏈�����فA���V�Ȃǂɒ�R���o����B���c�~�͏�y�@�̑m���ł��������B���Ƃ���������ψ���A���^���悤�Ƃ����܂����ׂċ��ۂ����B����ȍd�������A�����̔[���ł���A��֕���̂Ȃ��̂Ȃ��C�G�X���������B��_�Ȏ��݂ł���B�ނ̑�\��ł͂Ȃ����A�[����������Ƃ���͑����B
�@�p���X�`�i�̃K�b�T�[���E�J�i�t�@�[�j�[�͗D�ꂽ������]�_�������c�����B�u���z�̒j�����^�n�C�t�@�ɖ߂��āv�i���c���Y�E�z�c���r����A�͏o���[�V�Ёj�ɂ͈ږ��̘b���o�ꂷ��B�C���N�̃o�X������N�E�F�C�g�֖�������}�����O�l���A��^�̋����Ԃ̃^���N�ɉB��ĉz�������݂�B���V���Œ��͏Ă��t���悤�ɔM���B���⏊�̌W���͎G�k�Ȃǂ����āA����Ɏ葱����i�߂Ă���Ȃ��B�^�]�肪�Ԃɖ߂����Ƃ��A�����^���N�̒�����͉��̕��������Ȃ������B�O�l�Ƃ����������Ă����B�Ȃ��^���N�̕ǂ�@���Ȃ������̂��ƁA�^�]��͍����Ɍ������ċ��ԁB�@���Ă��A���⏊�ɂ����^�]��ɕ��������͂����Ȃ��B�u�Ȃ����v�Ƃ����^�]��̋��тŕ���͏I���B
�@���̏�����1962�N�ɏ�����Ă���B���l�Ȏ������A����ɑ����̎��҂��o���Č����ɋN�����B�C�M���X��2019�N11���A���F�g�i���l�Ƃ݂���39�l���A�Ⓚ�g���b�N�̃R���e�i�̒��Œ��������Ă����B�^�]��͉ߎ��v���̍߂ŗL�߂ƂȂ������A�w��̈ł̑g�D�ɂ͑{���̎肪�͂��Ȃ��B
�@1936�N���܂�̃J�i�t�@�[�j�[��12�̂Ƃ��A�f�B���E���V�[���������N���A��Ƃ̓_�}�X�J�X�Ɉړ������B��w���ă_�}�X�J�X��w�Ɋw���A���ނ��Đ��������ɓ������B�p���X�`�i����l������iPFLP�j�̌����X�|�[�N�X�}���Ƃ��Ċ��������BPFLP��PLO�̉����g�D�Ƃ݂Ă������낤�B�ނ͗L�\�ȃX�|�[�N�X�}���������B���w��̐����ɂ���āA�ނ̐����I�����ɑ����̐l�X���S����悤�ɂȂ����B�C�X���G���ɂƂ��āA�ނ̑��݂͋��Ђł����Ȃ��B1972�N7���A���҂��������Ԃɔ�����d�|�����B�ނ�36�ňÎE���ꂽ�B
�@�A���W�F���A���܂�̃��X�~�i�E�J�h���́u�e�����v�i���{�D�q��A���쏑�[�j�̕���̓e���A�r�u�ł���B��l���̈�t�́A�x�h�E�B���n�̃A���u�l�ŁA���l���ăC�X���G���ɋA�������o�������B�ނ͌x�@����Ăяo����A�����̍Ȃ������e���̎��s�Ƃ������ƍ�������B�Ȃ�������Ȃ��e�����X�g�ɂȂ��Ă��܂����̂��A�ނ͍Ȃ̑��Ղ�ǂ��ăC�X���G���ƃp���X�`�i������𗷂���B�A���u�n�C�X���G���l�Ƃ�������́A�A���u�n�A���_���n�o������ٕ��q�Ƃ݂Ȃ��ꂩ�˂Ȃ��c�B
�@���X�~�i�E�J�h����1955�N�ɐ��܂�A�A���W�F���A�̌R�l�i����������m���j�������B�ɂ�������炸�A50�Ńt�����X���Ђ��擾�����B�����̎�l�����l���G�Ȍo���̎�����ł���B�t�����X���́A��������ω����Ă���B�C�X���G�����������A�܍߂̎v���������Đe�C�X���G���������B�����J���ɂ����͂��Ă���B���݂́A�C�X���G���̘������Ɍ��C���������̂��A�����I��������n�߂Ă���B
�@�p���X�`�i�Ɨ��錾�̋N���҃}�t���[�h�E�_���E�B�[�V���́A�p���X�`�i���\���鎍�l�ł���B���{�ł́u�ǂɕ`���v�i�l���c���F��A����R�c�j�Ƃ������W���o�ł���Ă���B�u���̑�n�ɂ����āv�Ƃ�����̎��͂��̂悤�Ɍ����B
�@�@�c���̑�n�ɂ����Ă܂����ɒl������́A
�@�@�@���Ȃ��n�A���ׂĂ̎n�܂�ƏI����i���n�B���ăp���X�`�i�ƌĂ�A�̂��Ƀp���X�`�i�ƌĂ��悤�ɂȂ����B
�@�@�@�킪���݂�A�����킪���݂ł��邩����A���ɐ����鉿�l����B
�@�����ƂȂ����u�ǂɕ`���v�͒��Ҏ��ŁA�M���K���V�����琹���A�R�[�����Ȃǂ�ԗ����Ȃ���A�p���X�`�i�̌��݂�`���o���B��w�Ȏ��ɂ͏����ׂ̏d�����ł���B�C�G�X���r�����ӏ��ł́A
�@�@�c���͕��a�ƐÂ�����^�����Ă����B
�@�@�@�����Ȉꗱ�̔����킽����
�@�@�@�G�Ȃ�Z���{�����낤�B
�@�@�@���̎��͂��܂����Ă��Ȃ��B
�@�C�G�X���������͂��́A�u���܂����Ă��Ȃ��v�Ɣނ̎��͌��B
�@�ނ�PLO���s�ψ�����o�[�������B2008�N67�Ő����������B�p���X�`�i�́A�A���t�@�g�c���Ɏ����œ�l�ڂƂȂ鍑���Ŕނ̌��т��]�����B
�@�C�X���G���̍�Ƃł̓A�u���n���EB�E�C�F�z�V���A�́u�G���T�����̏H�v�i��܉Đ���A�͏o���[�V�Ёj��ǂ�ł���B�u���l�́A�₦�ԂȂ����فv�Ɓu�G���T�����̏H�v�̓�҂����߂��Ă���B�M��܂������l�ƁA�ނ��V���ɓ����Ă��琶�܂ꂽ���q��`�����u���l�́A�₦�ԂȂ����فv����ې[���B���q�ɂ͔]�ɏ�Q�������Đ��܂�Ă����炵���B���Ƃ܂���̎��Ƃŕ��e�̎���m�������q�́A���ɍĂю����������悤�Ƃ���B��������Ȃ获�X�ɁB���́u���������Ȃ��A�N�������Ƃ����v�ƌ����B���q�͕��ɑ����Ď��������n�߂�B�Ђ���Ƃ�����A���̑��q�̓C�X���G�����̂��̂��ے����Ă���̂����m��Ȃ��B
�@�C�F�z�V���A�́A�C�X���G���̗ǐS�I�����Ƃ��������݂炵���B�����̉���ɂ��ƁA2006�N�ɋN�������o�m���̃q�Y�{���Ƃ̐푈�ɍۂ��A�u��킵�Č��ɏ���ڂ����v�ƐV���L�����o�����A�Ƃ����B
�@����ł��Ȃ��A�p���X�`�i���̒���ɔ�ׁA��͂萶�ʂ邢���̂�������B�ǂ��l�߂�ꂽ�x�����̈Ⴂ�������ɂ���B
�f�悠�ꂱ��
���j���̂Ȃ�
�@���Ă����f����A���j�I�ȏ����ɕ��ׂĂ݂�B
 �@�܂��A�W�����E�q���[�X�g�����ē����u�V�n�n���v�i1966�N�j������B�ēs�\�Ȋēƌ���ꂽ�q���[�X�g�������A���ɐ^�ʖڂɍ���Ă���B�j�V�r�ł͂Ȃ��Ƃ��낪�A�t�ɖʔ������������ƂɂȂ����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�܂��A�W�����E�q���[�X�g�����ē����u�V�n�n���v�i1966�N�j������B�ēs�\�Ȋēƌ���ꂽ�q���[�X�g�������A���ɐ^�ʖڂɍ���Ă���B�j�V�r�ł͂Ȃ��Ƃ��낪�A�t�ɖʔ������������ƂɂȂ����̂ł͂Ȃ����낤���B
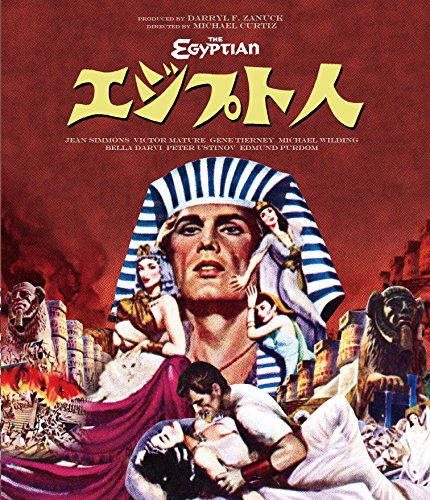
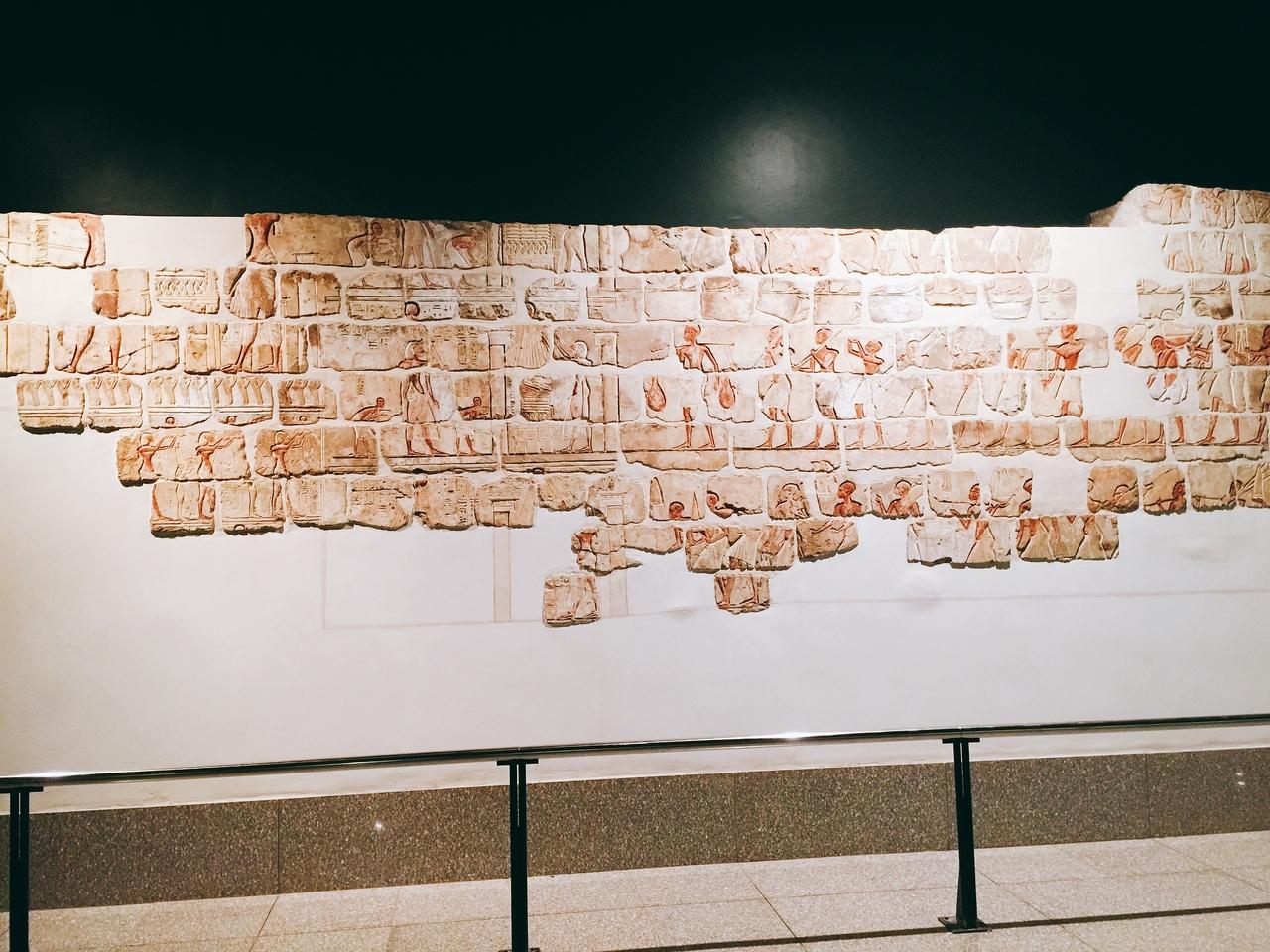 �@��_���̒a���ł́A�u�G�W�v�g�l�v�i1954�N�j�ɃC�N�i�g���i�f��ł̓A�N�i�g���j���o�ꂷ��B���_���������G�W�v�g���A���z�_�A�e���݂̂�M�����_���ɓ������t�@���I�ł���B���ꂪ���_�����̏��߂Ƃ���邪�A����ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�f��ł��A�ނ��닶�C���݂��t�@���I�Ƃ��ĕ`���A���_�����Ƃ͌��т��Ă͂��Ȃ��B�C�N�i�g���̎���A�G�W�v�g�͑��_���ɖ߂�A�ނ̒z�����s�A�P�g�A�e���i���A�}���i�j�͊��S�ɔj�ꂽ�B�ی`�����Œ���ꂽ�ނ̖��͍��Ƃ�ꂽ�B�ȑO�G�W�v�g�𗷍s�����܁A���N�\�[���̔����قŁA�j�ꂽ�_�a�̃����[�t�\�\���U�C�N��ɍČ����ꂽ�̂����Ă���B�C�N�i�g���̒������A���͏��Ȃ����c���Ă��āA�J�C���̃G�W�v�g�l�Êw�����قɓW������Ă���B
�@��_���̒a���ł́A�u�G�W�v�g�l�v�i1954�N�j�ɃC�N�i�g���i�f��ł̓A�N�i�g���j���o�ꂷ��B���_���������G�W�v�g���A���z�_�A�e���݂̂�M�����_���ɓ������t�@���I�ł���B���ꂪ���_�����̏��߂Ƃ���邪�A����ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�f��ł��A�ނ��닶�C���݂��t�@���I�Ƃ��ĕ`���A���_�����Ƃ͌��т��Ă͂��Ȃ��B�C�N�i�g���̎���A�G�W�v�g�͑��_���ɖ߂�A�ނ̒z�����s�A�P�g�A�e���i���A�}���i�j�͊��S�ɔj�ꂽ�B�ی`�����Œ���ꂽ�ނ̖��͍��Ƃ�ꂽ�B�ȑO�G�W�v�g�𗷍s�����܁A���N�\�[���̔����قŁA�j�ꂽ�_�a�̃����[�t�\�\���U�C�N��ɍČ����ꂽ�̂����Ă���B�C�N�i�g���̒������A���͏��Ȃ����c���Ă��āA�J�C���̃G�W�v�g�l�Êw�����قɓW������Ă���B
�@�Z�V���EB�E�f�~���́u�\���v�Ɓu�T���\���ƃf�����v�ɂ��ẮA�����_���̍��ŐG�ꂽ�B
�@����ł́A�u���~�̏\���H�v�i1951�N�j���_�r�f�ƃo�e�V�o�̈��Ƌ�Y��`���B�_�r�f�̓O���S���[�E�y�b�N�A�o�e�V�o�̓X�[�U���E�w�C���[�h���������B
�@�u�\�������ƃV�o�̏����v�i1959�N�j�ł́A�\�������Ƀ����E�u�����i�[�A�����ɃW�[�i�E�����u���W�[�_���������B�ē̓L���O�E���B�_�[�����A�ނƂ��Ă������ł����i�ł͂Ȃ��B
�@�V��ɓ���B�u��̏��T�����v�i1953�N�j�̓��^�E�w�C���[�X��������������B�ޏ��́A����E��풆�A���m�����Ɉ�Ԑl�C�̂������s���i�b�v�K�[���ł���B�����u���W�[�_�Ƃ����A�w�C���[�X�Ƃ����A���F�C�Ŕ��낤�Ƃ����f��́A�T���ďo���������B
�@�ِF��Ƃ��āA�t�������R�̖��_���T�[�A�A�C�[�_�E�S���X������ɃJ�����X�E�T�E�����ē����u�T�����v�i2001�N�j������B�ޏ��̃t�������R�E�_���X�͂������Ɍ�����������B

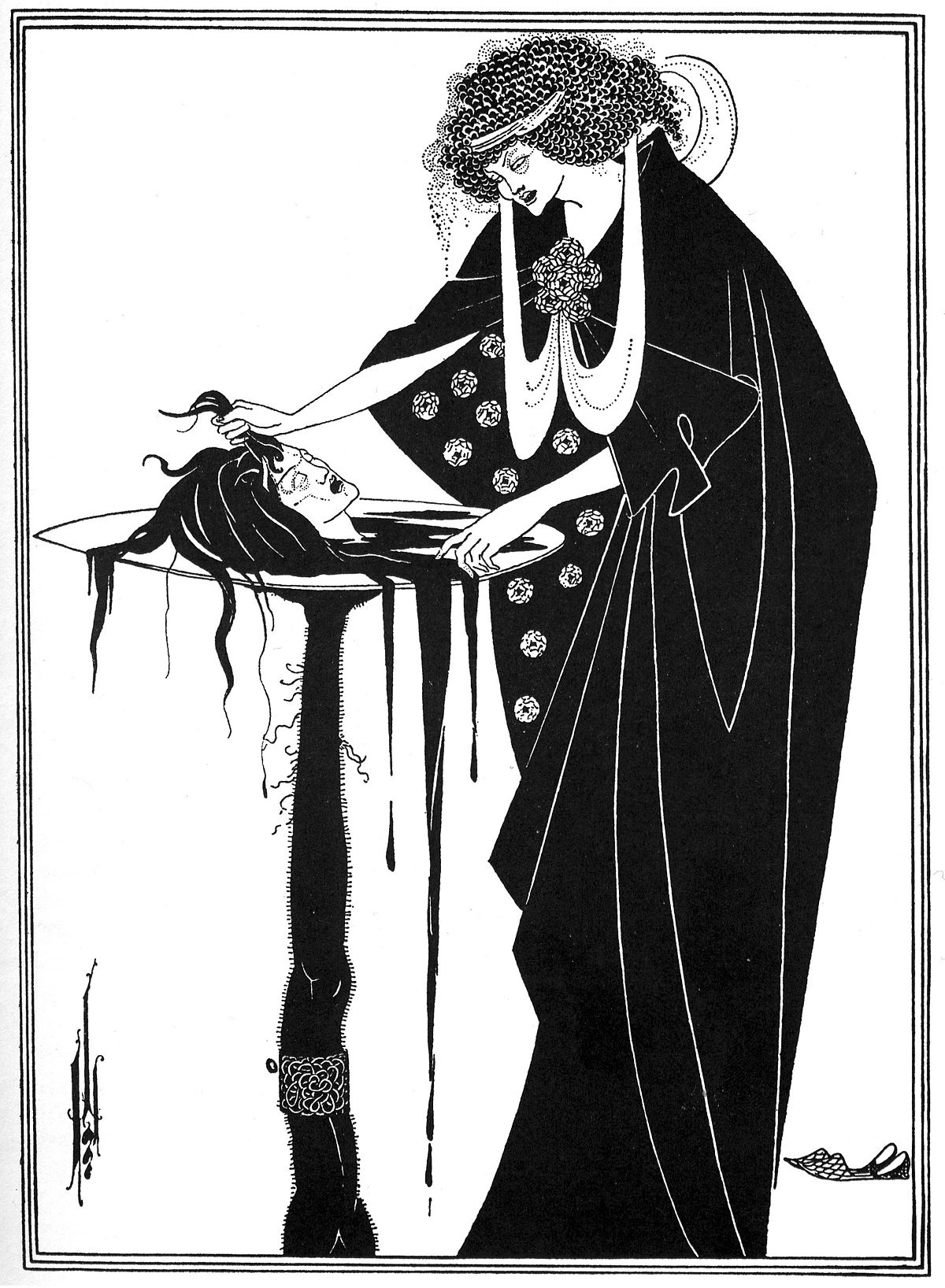 �@������ǂތ���A�T�����́A��ɂ����̂�����āA����҃��n�l�̎�����߂������̏����ɂ����Ȃ��B��N�A�T�������t�@���E�t�@�^���i�^���̏��j�I�ȃC���[�W�ɕς�����̂́A�Ȃ�Ƃ����Ă��I�X�J�[�E���C���h�́u�T�����v�i�����F����A�V�����Ɂj���e�����Ă��悤�B�G��ł́A���C���h�́u�T�����v�ɑ}�G��`�����I�[�u���[�E�r�A�Y���[���A�N��Ȉ�ۂ��c���B�M���X�^�[���E�����[�Ɏ���ƁA�_�̌��Ђւ̒���҂ɏ�����B���y�ł́A���q�����g�E�V���g���E�X���A���C���h�́u�T�����v������Ƃ���I�y�����c�����B
�@������ǂތ���A�T�����́A��ɂ����̂�����āA����҃��n�l�̎�����߂������̏����ɂ����Ȃ��B��N�A�T�������t�@���E�t�@�^���i�^���̏��j�I�ȃC���[�W�ɕς�����̂́A�Ȃ�Ƃ����Ă��I�X�J�[�E���C���h�́u�T�����v�i�����F����A�V�����Ɂj���e�����Ă��悤�B�G��ł́A���C���h�́u�T�����v�ɑ}�G��`�����I�[�u���[�E�r�A�Y���[���A�N��Ȉ�ۂ��c���B�M���X�^�[���E�����[�Ɏ���ƁA�_�̌��Ђւ̒���҂ɏ�����B���y�ł́A���q�����g�E�V���g���E�X���A���C���h�́u�T�����v������Ƃ���I�y�����c�����B
�@�C�G�X��`�������̂ł́A�u�̑�Ȑ��U�̕���v�i1965�N�j�̊����x�������B�ē̓W���[�W�E�X�e�B�[�����X�B�u�z�̂�����ꏊ�v��u�V�F�[���v����������ēł���B�C�G�X�̓X�E�F�[�f���̖��D�}�b�N�X�E�t�H���E�V�h�[���������B���ǁA�f��͐���҂̎u�Ɗē��悾�Ɣ[����������B��ɂ������f��ȂǂƂ͔�r�ɂȂ�Ȃ��B
�@�u�L���O�E�I�u�E�L���O�X�v�i1961�N�j�̊ē̓j�R���X�E���C�B�u��̐l�X�v��u���R�Ȃ����R�v�Ȃǂ�������l�ŁA�n���E�b�h�ł��ِF�ȑ��݂������B�C�G�X���������̂̓A�N�V�����E�X�^�[�̃W�F�t���[�E�n���^�[�B���̃L���X�e�B���O�ɂ͋������ꂽ�B�u�̑�Ȑ��U�̕���v�Ƃ͔�r�ł��Ȃ����A�������̂����i�Ɏd�グ�Ă���B
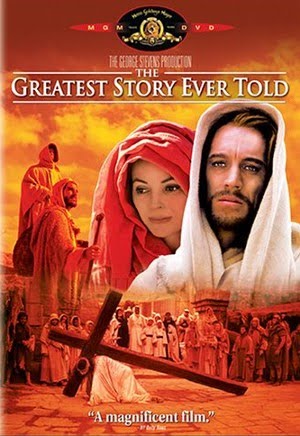
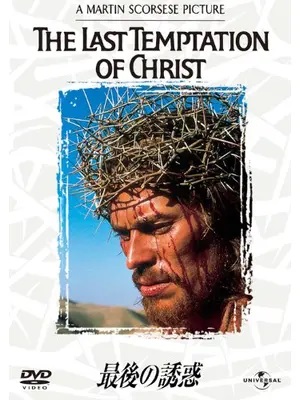 �@�V���߂��̂ł́A�u�Ō�̗U�f�v�i1988�N�j������B�ē̓}�[�e�B���E�X�R�Z�b�V�A�C�G�X���E�B�����E�f�t�H�[���������B�j�R�X�E�J�U���U�L�X�́u�L���X�g�Ō�̂�����݁v�i���ʑ���A�P���Ёj������ɂ��Ă���B
�@�V���߂��̂ł́A�u�Ō�̗U�f�v�i1988�N�j������B�ē̓}�[�e�B���E�X�R�Z�b�V�A�C�G�X���E�B�����E�f�t�H�[���������B�j�R�X�E�J�U���U�L�X�́u�L���X�g�Ō�̂�����݁v�i���ʑ���A�P���Ёj������ɂ��Ă���B
�@�V���߂��鏊�Ȃ́A�\���ˏ�̃C�G�X�ɍŌ�̗U�f���P�����Ƃ���Ƃ���ɂ���B���̗U�f�Ƃ́A�}�O�_���̃}���A��W��A�ޏ��̎���A���U���̎o���}���A�A�}���^�ƌ���A�q�ǂ������Ĉ���ɕ�炷�Ƃ������̂������B���̗U�f�ɑł��������Ƃ��A�ނ͐^�̃��V�A�i�~����j�ƂȂ����c�B�@���F�̋����A�����J�ł́A���̉f��̏�f�ɔ��Ή^�����N�����B
�@�}�[�e�B���E�X�R�Z�b�V�́A�@���ɋ����S�������Ă���炵���B�u�N���h�D���v�i1997�N�j�ŎႫ���̃_���C�E���}��`���A�ŋ߂ł́A��������̌�������ƂɁu���ف@�T�C�����X�v�i2016�N�j��������B��������ŁA�c���_��1971�N�ɉf��ɂ��Ă��邪�A�o���h���̓X�R�Z�b�V�̕����f�R�D��Ă���B�����炭�N���X�`�����������łȂ������A����̗���x�ɉe�����Ă���̂��낤�B
�@�u���߁v�i1953�N�j�́A�\���˂ɂ�����ꂽ�C�G�X�̈߂����Ƃ��Ă��邪�A�����~���肷���āA�������������ɂ͕��}�ȏo���ɏI����Ă���B�剉�̓��`���[�h�E�o�[�g���ƃW�[���E�V�����Y�B�ē͐l��ӂƂ����w�����[�E�R�X�^�B�X�y�N�^�N���ׂ͉��d���������̂�������Ȃ��B
�@�u�o���o�v�i1962�N�j�́A�C�G�X�����Y�ɏ���������Ɏ͖Ƃ��ꂽ�j��`���B�ē̓��`���[�h�E�t���C�V���[�B�E�l���̊ēŁA������Ȃ������70�_���̉f�������B����̓m�[�x���܍�Ƃ̃y�[���E���[�Q���N���B�X�g�B�o���o���A���\�j�[�E�N�C�����������B
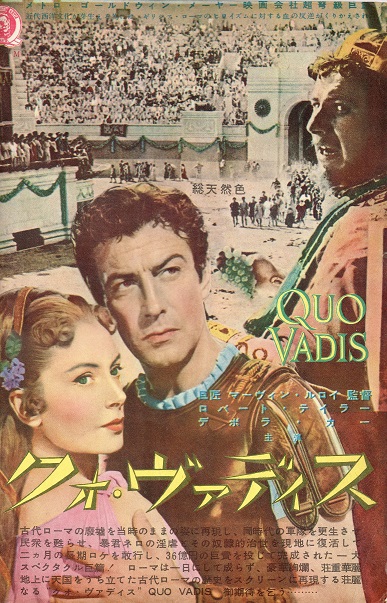
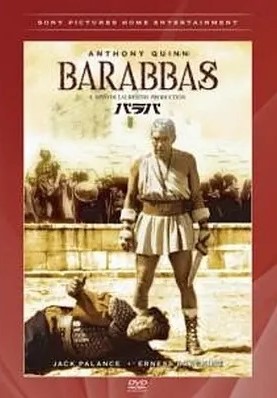
 �@�u�N�H�E���@�f�B�X�v�i1952�N�j�́A���[�}�鍑�A�c��l���̃L���X�g���k���Q��`���B����̓w�����N�E�V�F���L�F���B�`�B���̐l���m�[�x�����w�܂��Ƃ��Ă���B�薼�̓��e����Łu���A�����ɂ䂫�������v�i�u���n�l�������v13-36�j�Ɋ�Â��B�Ō�̔ӎ`�̐ȂŁA�y�e�����C�G�X�ɑ��Ĕ��������t�ł���B�y�e���̓C�G�X�ɐM�����ĂȂ��Ɛ������A�C�G�X�́u�{�����O�ɁA���Ȃ��͎O�x����m��Ȃ��ƌ������낤�v�Ɨ\������B
�@�u�N�H�E���@�f�B�X�v�i1952�N�j�́A���[�}�鍑�A�c��l���̃L���X�g���k���Q��`���B����̓w�����N�E�V�F���L�F���B�`�B���̐l���m�[�x�����w�܂��Ƃ��Ă���B�薼�̓��e����Łu���A�����ɂ䂫�������v�i�u���n�l�������v13-36�j�Ɋ�Â��B�Ō�̔ӎ`�̐ȂŁA�y�e�����C�G�X�ɑ��Ĕ��������t�ł���B�y�e���̓C�G�X�ɐM�����ĂȂ��Ɛ������A�C�G�X�́u�{�����O�ɁA���Ȃ��͎O�x����m��Ȃ��ƌ������낤�v�Ɨ\������B
�@�f��i����j�ł́A���Q��ă��[�}�����낤�Ƃ���y�e���̑O�ɃC�G�X���o������B�u���A�����ɂ䂫�������v�Ɩ₤�y�e���ɃC�G�X��������B�u���A�䂪�������̂ĂȂA��A���[�}�ɍs���č���x�\���˂ɂ�����ł��낤�v�B�C�������Ă����y�e���́A�N���オ��Ɩ������ƂȂ����̓������ǂ胍�[�}�������B�������A�����ɂ��̂悤�ȑ}�b�͂Ȃ��B
�@�ē̓}�[���B���E�����C�A�剉�̓��o�[�g�E�e�C���[�ƃf�{���E�J�[�B�c��l���̓s�[�^�[�E���X�e�B�m�t���������B���シ�郍�[�}��w�i�Ɏ����Ⴘ��Ȃlj�����������B�e���̋M���ɁA�u�T�e�����R���v�i�����g�V���A��g���Ɂj���������y�g���j�E�X���o�ꂷ��B���̉f����u���߁v���l�A�������������ɂ͊�����Ƃ܂ł͎���Ȃ������B
 �@�u�L���O�_���E�I�u�E�w�u���v�i2005�N�j�͏\���R�ƃC�X�����R�̐킢��`���B�ē��h���[�E�X�R�b�g�́u�O���f�B�G�[�^�[�v�ŃA�J�f�~�[�܂Ă���B��i�Ƃ��ẮA���̉f��̕�������ɏ㎿���Ǝv�����A�G���T�����ח���`���Ă��邹�����A�����J�ł͐l�C���o�Ȃ������B
�@�u�L���O�_���E�I�u�E�w�u���v�i2005�N�j�͏\���R�ƃC�X�����R�̐킢��`���B�ē��h���[�E�X�R�b�g�́u�O���f�B�G�[�^�[�v�ŃA�J�f�~�[�܂Ă���B��i�Ƃ��ẮA���̉f��̕�������ɏ㎿���Ǝv�����A�G���T�����ח���`���Ă��邹�����A�����J�ł͐l�C���o�Ȃ������B
�@�f��̏I�Ջ߂��A�G���T���������R��s���������A���u�R�̃��[�_�[�A�T���f�B��������ɓ���B�ނ́A���ɓ]�����Ă����\���˂��E���グ�A�Â��ɍՒd�ɒu���B
�@�@���͂����łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���Ƃ��Ⴄ�@���ł����Ă��A�݂��Ɍh�ӂ��A���d�������ׂ��ł���B���̂��Ƃ��A�ꌾ�������Ȃ����̏�ʂ��Y�قɌ�肩����B�@�@
������̂Ȃ�
�@�C�X���G���������O��`�����f�悪�u�h���ւ̒E�o�v�i1960�N�j�ł���B�ē̓I�b�g�[�E�v���~���W���[�B�����EXODUS�A�����́u�o�G�W�v�g�L�v�ƃ_�u���E�C���[�W�����Ă���B
�@�I���{���ݕ��D�ɏ�������_���l�������A�L�v���X�̍`����p���X�`�i�֏o�����悤�Ƃ���B�A���u�Ƃ��a瀂������C�M���X���{���A�R���o�������đ��~�߂���Ƃ��납��f��͎n�܂�B�n���X�g�Œ�R���郆�_���l�����B���_�ɔ��ꂽ�C�M���X�́A��ނȂ��o�q��F�߂�B
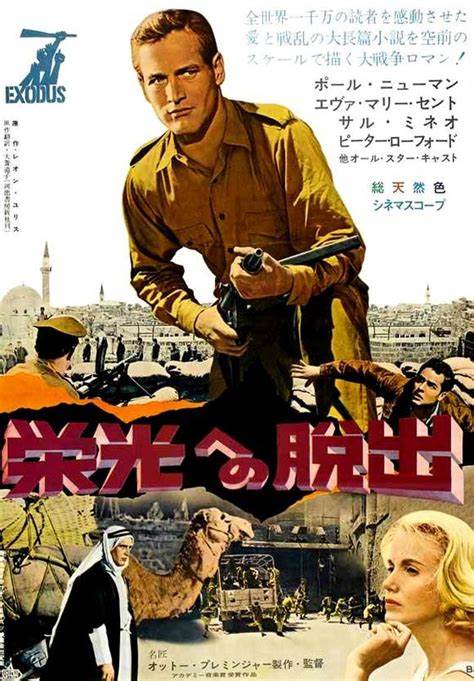 �@����E�ē����˂��I�b�g�[�E�v���~���W���[�̓��_���l�ł���B�f��͓O�ꂵ�ă��_�����ƂȂ�B�����A�����O�̃e�������A�Ȃ��ł��L���O�E�f�C���B�b�h�E�z�e�����j�����͏o�Ă�����̂́A�f�B���E���V�[�����p���X�`�i�Z���s�E�����͕`����Ȃ��B�C�X���G���̃e�������́A�~�ނ�����̂Ɛ��F�����B�f��̏o���h�����]�X����O�ɁA�s���������ڂɗ]��B�������A�f����J�����́A�A���u���̃j���[�X�͂قƂ�Ǔ����ė��Ă��Ȃ������B�قƂ�ǂ̐l�����̉f��ɐ��]���ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B�������̈�l�ł���B
�@����E�ē����˂��I�b�g�[�E�v���~���W���[�̓��_���l�ł���B�f��͓O�ꂵ�ă��_�����ƂȂ�B�����A�����O�̃e�������A�Ȃ��ł��L���O�E�f�C���B�b�h�E�z�e�����j�����͏o�Ă�����̂́A�f�B���E���V�[�����p���X�`�i�Z���s�E�����͕`����Ȃ��B�C�X���G���̃e�������́A�~�ނ�����̂Ɛ��F�����B�f��̏o���h�����]�X����O�ɁA�s���������ڂɗ]��B�������A�f����J�����́A�A���u���̃j���[�X�͂قƂ�Ǔ����ė��Ă��Ȃ������B�قƂ�ǂ̐l�����̉f��ɐ��]���ꂽ�̂ł͂Ȃ����낤���B�������̈�l�ł���B
�@���{�l�Ńf�B���E���V�[�����s�E�������f��ɂ����l������B�L�͗��ꂪ����E�ē����u�p���X�`�i1948�@�i�N�oNAKBA�v�i2008�N�j�́A���̑�S�����A�����̐l�X�̏،������Ƃɐo�����Ƃ����h�L�������^���[�ł���B
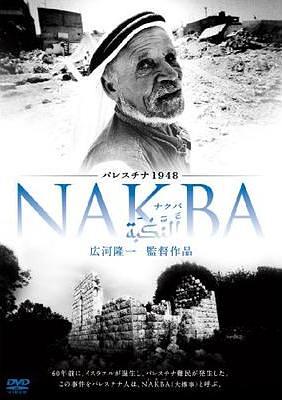 �@�L�͂́A���̉f������Ɏ������ߒ������̂悤�Ɍ��B�c�����C�X���G���ɒ������̂�1967�N5���B�Љ��`���������Ă���H�L�ȋ����̎Љ����ƕ����A�����ɗ����̂��B���E�������҂���������ăL�u�c�ɏW�܂��Ă����B��O�������푈�̎��ɂ́A���͂Ђ�����L�u�c�œ����Ă����B�͍����@�����̂��o���Ă���B�d���ΊD��ɂ�͂����e�������ċ�J�����B�����͖h�ɓ���A��������͂����C�X���G���̈��|�I�ȌR���I�����̃j���[�X����ŁA6���ԂŐ푈�͏I�������B
�@�L�͂́A���̉f������Ɏ������ߒ������̂悤�Ɍ��B�c�����C�X���G���ɒ������̂�1967�N5���B�Љ��`���������Ă���H�L�ȋ����̎Љ����ƕ����A�����ɗ����̂��B���E�������҂���������ăL�u�c�ɏW�܂��Ă����B��O�������푈�̎��ɂ́A���͂Ђ�����L�u�c�œ����Ă����B�͍����@�����̂��o���Ă���B�d���ΊD��ɂ�͂����e�������ċ�J�����B�����͖h�ɓ���A��������͂����C�X���G���̈��|�I�ȌR���I�����̃j���[�X����ŁA6���ԂŐ푈�͏I�������B
�@�L�u�c�͎��͘J���A�W�c�ӔC�A�g�������A�@��ϓ��������Ƃ���W�Y��`�I�����g���ł���B�\�A�̃R���z�[�Y�A�����̏W�c�_��ɋ߂��B���������A�C�X���G���͗��z�̍���������Ă���ƌ��`���A�L�u�c�����̈��Ƃ��Đ����Љ�̊S���W�߂Ă����B
�@�L�͂��A���̃v���p�K���_�ɖ������ăC�X���G���ɓn������҂̈�l�ł���B�ނ́A�q�}�������̂͂���ɔ������I��ڂɂ���B�c���̊��I�����Ď��́A�ŏ������̏��K�͂Ȉ�Ղ̐Ղ��Ǝv�����B���[�}���ォ�A�\���R���ォ�́B�������A�����q�˂��L�u�c�̃����o�[�́A�Ȃ����������͂��炩�����A�Ɣނ͋L���Ă���B
�@�^����������ނ́A�O�O�ɏ،������߂Đq�˕����A�ʐ^���B��A�uNAKBA��S���v�̎��̂�m��Ɏ���B�e�C�X���G���������ނ́A�K�R�I�ɐe�p���X�`�i�ւƕϖe����B�������A���̃h�L�������^���[�́A�����܂ł������ȗ�����ێ����悤�Ɠw�߂Ă���B��ƂƂ��Ă̗ǐS�������Ƃ��B
�@�L�u�c�͎p��ς��Ă��܂����݂��Ă���B�Ɨ����������̂ɋ߂��A�_�ƒ��S����A�H�ƁA�ό��Ƃ��c�ށB�����́A�\�����̕�V���[���i�����͖����ŕۏႳ���j���������A���݂͋��^���ɂȂ��Ă���B
�@�l���c���F�́u�p���X�`�i�E�i�E�v�̒��ŁA�����̃C�X���G���f��̓A�����J�̐������Ɏ��Ă����Ǝw�E���Ă���B�܂�A�p���X�`�i�l�̓l�C�e�B�u�E�A�����J���i�C���f�B�A���j���l�A�R�����Ȃ�ʃC�X���G���R�ɂ���ċ쒀�����̂ł���B�����c�O�Ȃ��ƂɁA���̏��ŏЉ���C�X���G�������̉f��́A���̂قƂ�ǂ����{�ł͏�f����Ă��Ȃ��B
�@���̂ق��A���{�l����������̂ł́A�u�e�����X�g�@�H�ҁv�i2006�N�j������B�ē͑��������B1972�N5���e���A�r�u��`���ˎ����̉��{���O�����f���ɂ��Ă���B�����������ē��A���{�̐S�ۂ�`�����Ƃ����h���}�ŁA�j���ɒ����Ȃ��̂ł͂Ȃ��B
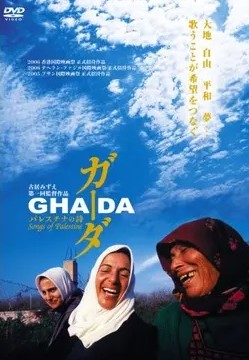 �@�u�K�[�_�@�p���X�`�i�̎��v�i2005�N�j�͌Ë��݂����̎�ɂȂ�h�L�������^���[�ł���B��l�̏����ɖ������A����23����35�܂ł́A�����A�o�Y�A�����ւ̒T����`���B���R�A�����̋��̗��j�����s����B�p���X�`�i�ł́A���q�̒a������ԂƂ����B�����Ȃ�ł͂̉\��������Ƃ����B���Ȃ��Ƃ��퓬���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B����͂���ŁA�߂��������ł���B
�@�u�K�[�_�@�p���X�`�i�̎��v�i2005�N�j�͌Ë��݂����̎�ɂȂ�h�L�������^���[�ł���B��l�̏����ɖ������A����23����35�܂ł́A�����A�o�Y�A�����ւ̒T����`���B���R�A�����̋��̗��j�����s����B�p���X�`�i�ł́A���q�̒a������ԂƂ����B�����Ȃ�ł͂̉\��������Ƃ����B���Ȃ��Ƃ��퓬���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B����͂���ŁA�߂��������ł���B
�@1972�N�~�����w���E�I�����s�b�N�ɂ�����e���������������f�悪�u�~�����w���v�i2005�N�j�ł���B�ē̓X�e�B�[�����E�X�s���o�[�O�B�p���X�`�i�����W�c�u�����㌎�v�ɂ��C�X���G���I��c�l���A��`�ł̎ˌ��̉��V���O���A�����c�����O�l���C�X���G���̔閧�g�D���ǂ��l�߂čs���ߒ����㔼�Ƃ����\���ł���B�X�e�B�[�����E�X�s���o�[�O�̓��_���l�ł���B���̉f��Ŕނ́A���_�����ł��邱�Ƃ��B�����Ƃ���B�����c�����e�����X�g�O�l�́A�ނ̉f��u�W���[�Y�v�Ɠ��l�E����Ă�����ׂ������ł���B���Q�̋N�_��I��c�P���ɒu���Γ��R�����Ȃ�B�e���W�c���Ȃ����܂ꂽ���ɂ��ẮA�Ӑ}�I�ɃX�s���o�[�O�͐G��Ȃ��B�f�B���E���V�[�����p���X�`�i�Z���s�E�����Q�̋N�_�ɂ��Ȃ���Ό����Ƃ͌����Ȃ��B
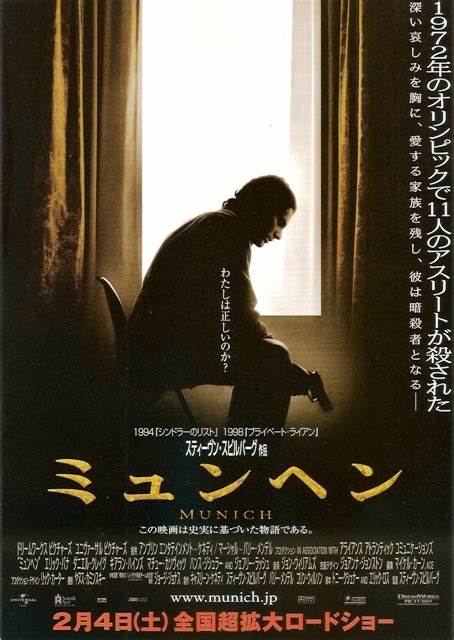
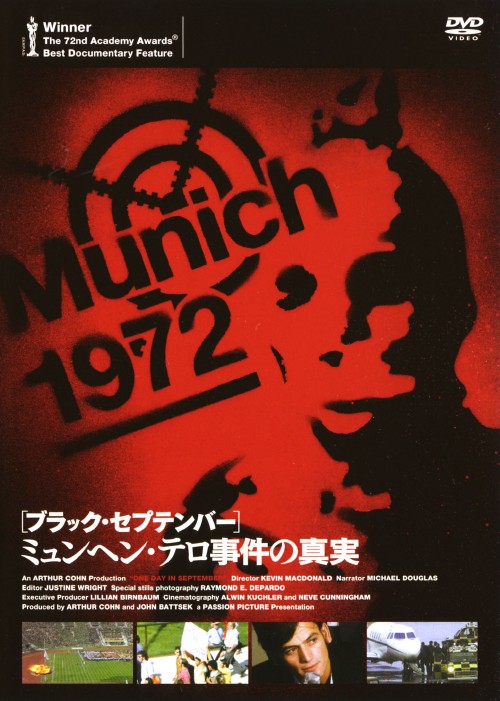 �@�X�e�B�[�����E�X�s���o�[�O�͏�����u���ˁI�v�i1972�N�j����r�B�҂Ȋē������B�X�����ƃT�X�y���X�Ƃ������ӂ̃e�N�j�b�N�ŁA�f��u�~�����w���v�̕Ό����B���Ă��܂��B�㖡�̈����f��ł���B
�@�X�e�B�[�����E�X�s���o�[�O�͏�����u���ˁI�v�i1972�N�j����r�B�҂Ȋē������B�X�����ƃT�X�y���X�Ƃ������ӂ̃e�N�j�b�N�ŁA�f��u�~�����w���v�̕Ό����B���Ă��܂��B�㖡�̈����f��ł���B
�@�u�u���b�N�E�Z�v�e���o�[�v�i1999�N�j�́A�����㌎�������ɕ`�����Ƃ����h�L�������^���[�f��ł���B����Ɋ֗^�������̓X�C�X���h�C�c���C�M���X�A�ēP���B���E�}�N�h�i���h�B�e���͐��F�ł��Ȃ����A�܂��v���ƂȂ���̂������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����҂����̈Ӑ}�������ɂ���B
�@�C�X���G����������f��ł́A
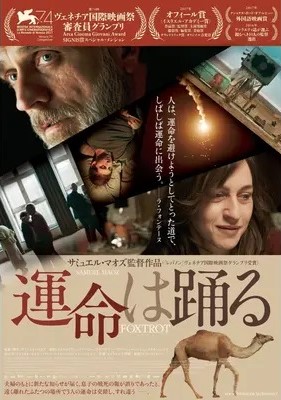
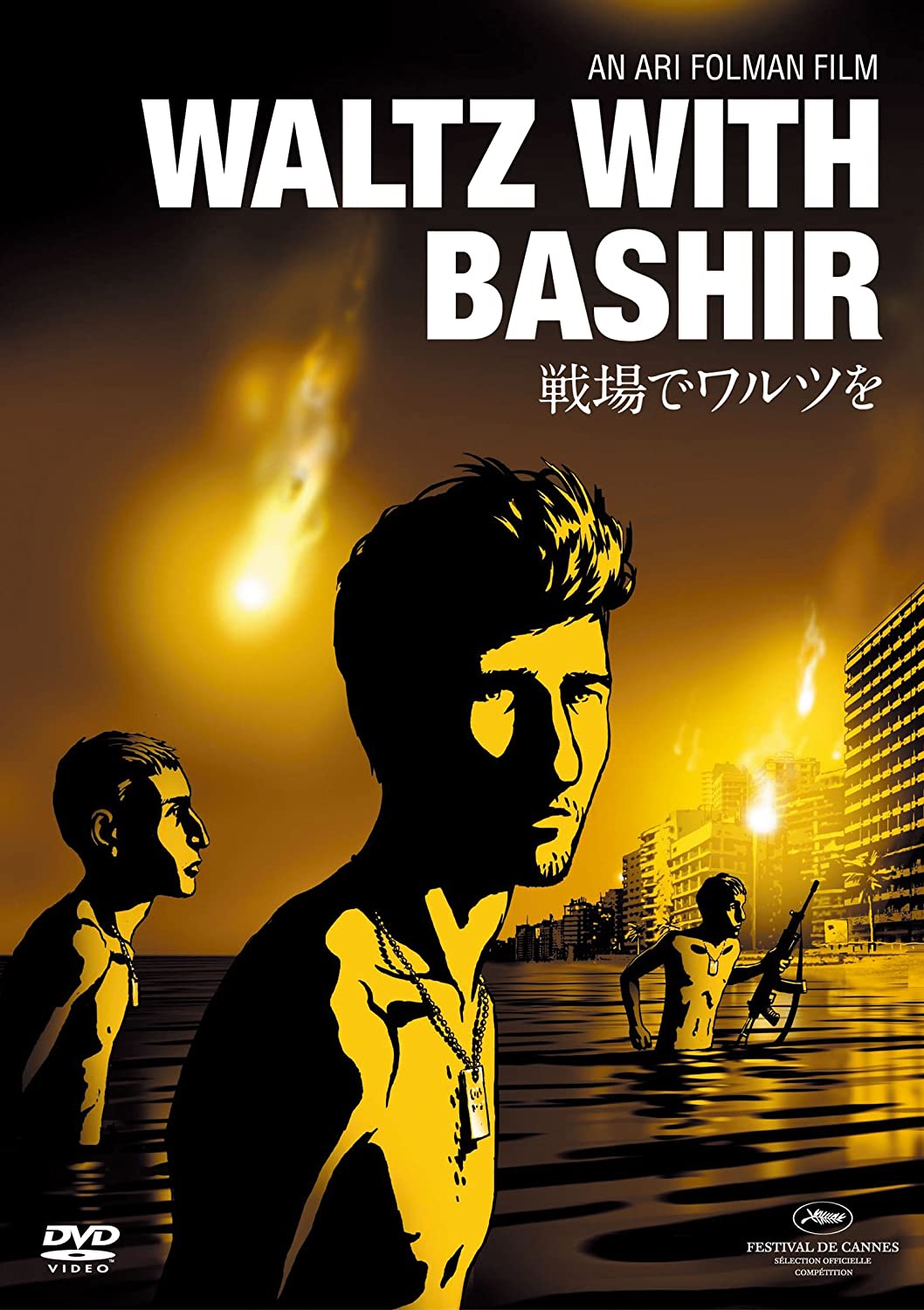 �@�u���Ń����c���v�i2008�N�j�́A1982�N�̃��o�m���푈�̃g���E�}�ɋꂵ�ސl�X��`���B�A�j���[�V�����Ɏ��ʂ��ꕔ�������Ă���B���썑�̓C�X���G�����h�C�c���t�����X���A�����J�A�ēA���E�t�H���}���B���X�g�́A��L�����v�A�p���X�`�i���������̋��Ԃ悤�Țe�������Ɏc��B�o�b�N�ɗ���鉹�y�A�V���[�x���g�̃s�A�m�E�\�i�^20�Ԃ���ۓI�B
�@�u���Ń����c���v�i2008�N�j�́A1982�N�̃��o�m���푈�̃g���E�}�ɋꂵ�ސl�X��`���B�A�j���[�V�����Ɏ��ʂ��ꕔ�������Ă���B���썑�̓C�X���G�����h�C�c���t�����X���A�����J�A�ēA���E�t�H���}���B���X�g�́A��L�����v�A�p���X�`�i���������̋��Ԃ悤�Țe�������Ɏc��B�o�b�N�ɗ���鉹�y�A�V���[�x���g�̃s�A�m�E�\�i�^20�Ԃ���ۓI�B
�@�u�^���͗x��v�i2017�N�j�̊ē̓T�~���G���E�}�I�Y�B�f��̑O���́A���m�ł��鑧�q�������e�́A���ɂ��߂��݂Ɠ{���`���B�㔼�͕��m�����ْ̋��Ƒދ������������T�X�Ƃ����C�����`�����B�����ċ����I�ɔߎS�Ȏ������N����c�B
�@���Ƃ��A�C�X���G���̗ǐS�I�ȍ�Ƃ����ɂ��㎿�ȉf��ł��邱�Ƃ͔F�߂�B�������A�ǂ���������߂������̂�������B�u�������Y��ł���̂ł��B�p���X�`�i�l��}�����Ă���킯�ł͂���܂���v�ƌ����Ă���悤�ɕ�������B
�@�u�n�b�s�[�G���h�̑I�ѕ��v�i2014�N�j�̊ē̓V�������E�}�C�����B�V�l�z�[����Ƃ������[�����X�Ȑl��B�����}�j�A�̓����҂��A���y���@�B��������̂������̌����B�����͈�؏o�Ă��Ȃ��̂ŋC�y�Ɋy���߂�B�������A�p���X�`�i���ɂ́A�V�l�z�[���ȂǍ��]�T�͂Ȃ��B
�@������̃C�X���G���̔Y�݂́A�������̃A���u�l�䗦�̍����ɂ������B�o�����������B���_���l�̔䗦�����߂�K�v�����邪�A�����㐔�\�N���o�ĂA�f�B���E���V�[�����s�E�̂悤�ȘI���Ȏ�i�͋�����Ȃ��B���[���b�p��V�A�ȂǂɏZ�ރ��_���l�����ɐϋɓI�ڏZ���Ăт��������̂́A���ꂾ���ł͑���Ȃ��B�C�X���G�����{�́A�G�`�I�s�A�ɏZ�ރ��_���l�������ڏZ������v��𗧂Ă��B�G�`�I�s�A�����_���l�́u�t�@���V���v�ƌĂ�A���Q�̑ΏۂɂȂ肪���������B�u�t�@���V���v�Ƃ́A���n��ŗ��Q���E�ٖM�l�̈Ӗ������B
�@�ڏZ���́A1984�N�́u���[�Z���v��1991�N�́u�\���������v��2��ɂ킯�čs��ꂽ�B���̌���U���I�ɈڏZ�͑����Ă���B�����̂Ȃ�������̈ڏZ�ŁA��A�������̂Ȃ����̏����B�閧���@�փ��T�h�ɂ��~�o��킾�����B���݁A�C�X���G���ɏZ�ޔ畆�̍����G�`�I�s�A�n���_���l��13���l����B�x�^�E�C�X���G���ƌĂ��ނ�́A�C�X���G���Љ�̍ʼn��w���\������B
�@�u�̗��H�v�i2005�N�j�̐��썑�t�����X�A�ē��f���E�~�w�C���A�j���B�����I�ȗ���ō��ꂽ�f��ƌ�����B���_���m���Ō�����������B
�@�f��́A1984�N�́u���[�Z���v����n�܂�B�X�[�_���̓�L�����v�ɁA�n������q�������B���_���l�ł͂Ȃ��B��e�́A�q���̏������v���A���q���ڏZ�o�^�̗�ɕ�����B�e�ȏ������킪�q�ƋU��A���N�͖����C�X���G���ֈڏZ����B�܂��Ȃ���e����̏����͕a�����A�ʂ̕v�w�̗{�q�ƂȂ�B�f��ɂ́A�����܂����܂ł́A���_���l�Љ�̍��ʂ��`�����B�ނ͍��ʂɔY�݂Ȃ�����������A�t�����X�ň�t�̎��i�����B���̂���A�C�X���G���ł̓��_���l�ƋU�����G�`�I�s�A�l���i�������ƂȂ��Ă����B�ނ͕n�����ւ̔h����t�̓���I�сA���̖T�琶�݂̕��T���n�߂�c�B
�@�ނɂ͎O�l�̕ꂪ�����B���݂̕�A�ڑ����������U�̕�A�����Ĉ�Ă̕�B���l�ƂȂ鏗���̌��t�u��������̂��ꂳ��Ɏ���Ă���̂ˁv�Ƃ������t������łB
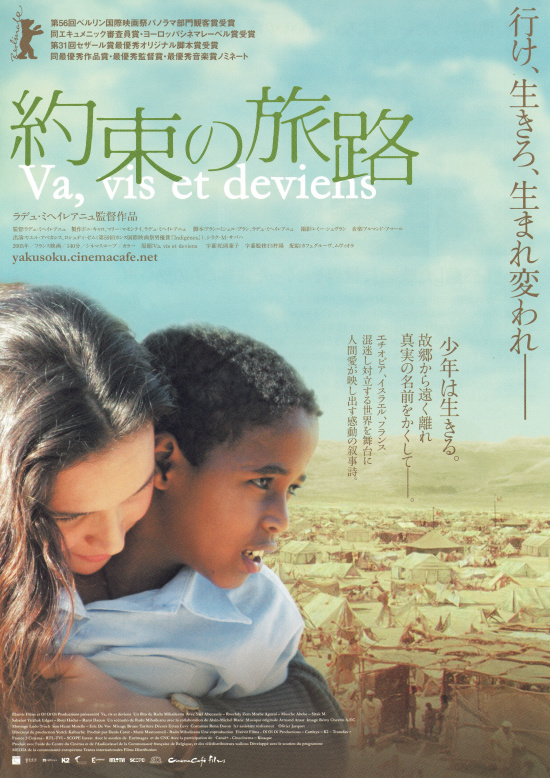
 �@�u�����ЂƂ�̑��q�v�i2012�N�j�̐��썑���t�����X�A�ē����[�k�E�����B�i���_���n�t�����X�l�j�B�C�X���G���l�Ƒ��ƃ����_�����ݒn��ɏZ�ރp���X�`�i�l�Ƒ��Ƃ̊Ԃ́A���Ⴆ�q�̖���`���B���{�ɂ��u�����ĕ��ɂȂ�v�i2013�N�A�ēE���}�T�a�j�Ƃ������삪���������A�ݒ�Ƃ��Ă͂��̉f��̕������[���ł���B18�ɂȂ���2�l���܂�6�l�����ꂼ��Y�݂Ȃ�����������o�����Ƃ���p���������B����ɂ��Ă����e�̓_���ł���B��`�ɂ������A���������͂��Ȃ��B��e�͎��Ԃɑ���������������o�����Ƃ���B�_��ł���B
�@�u�����ЂƂ�̑��q�v�i2012�N�j�̐��썑���t�����X�A�ē����[�k�E�����B�i���_���n�t�����X�l�j�B�C�X���G���l�Ƒ��ƃ����_�����ݒn��ɏZ�ރp���X�`�i�l�Ƒ��Ƃ̊Ԃ́A���Ⴆ�q�̖���`���B���{�ɂ��u�����ĕ��ɂȂ�v�i2013�N�A�ēE���}�T�a�j�Ƃ������삪���������A�ݒ�Ƃ��Ă͂��̉f��̕������[���ł���B18�ɂȂ���2�l���܂�6�l�����ꂼ��Y�݂Ȃ�����������o�����Ƃ���p���������B����ɂ��Ă����e�̓_���ł���B��`�ɂ������A���������͂��Ȃ��B��e�͎��Ԃɑ���������������o�����Ƃ���B�_��ł���B
�@���̓�̉f�悪�����悤�ɁA�t�����X�̓C�X���G���ɑ����������n�߂Ă���B�����ł��낤�Ƃ��Ă���B
�@�p���X�`�i�f��ɂ͊��͂�����B
�@���ڂ��ׂ��f��ē��n�j�E�A�u�E�A�T�h�ŁA�u�p���_�C�X�E�i�E�v�A�u�I�}�[���̕ǁv�A�u�̐��ɂ̂������N�v�Ƃ���3�{�̉f������Ă���B
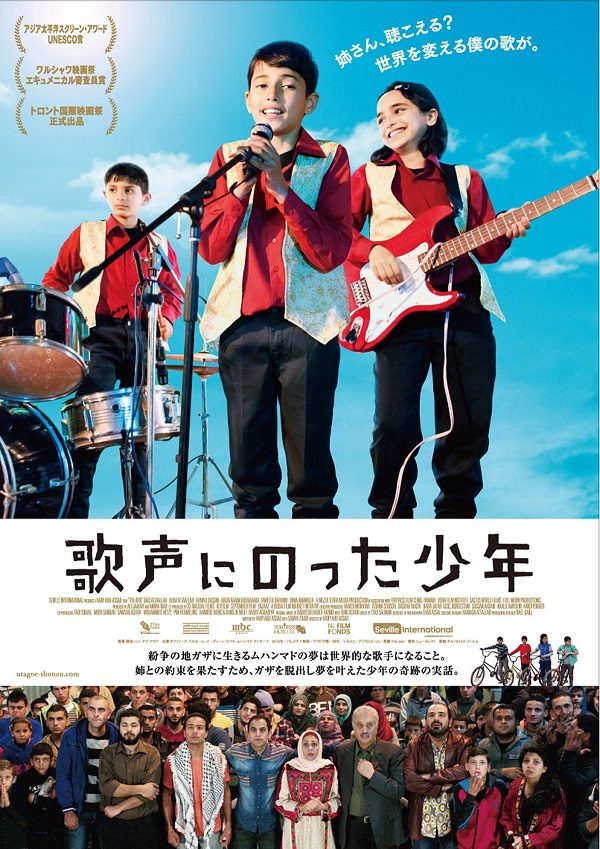
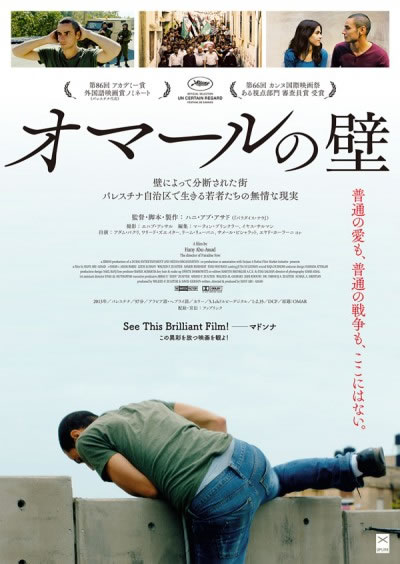
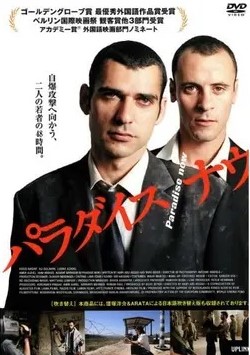 �@�u�p���_�C�X�E�i�E�v�i2005�N�j�̐��썑�̓t�����X���h�C�c���I�����_���p���X�`�i�B�e�����s�Ɏu�肵���N�����̔Y�݂����B���s�𖽂���҂̋U�P����������ƕ`���Ă���B���ʂȃA�����J�ł́A�e�����X�g�ɓ���I�Ə�f���Ή^�����N�����B
�@�u�p���_�C�X�E�i�E�v�i2005�N�j�̐��썑�̓t�����X���h�C�c���I�����_���p���X�`�i�B�e�����s�Ɏu�肵���N�����̔Y�݂����B���s�𖽂���҂̋U�P����������ƕ`���Ă���B���ʂȃA�����J�ł́A�e�����X�g�ɓ���I�Ə�f���Ή^�����N�����B
�@�u�I�}�[���̕ǁv�i2013�N�j�̓p���X�`�i�����݂̂̎����ō��ꂽ�B�����ǂ��z���ė��l�̂��Ƃ֒ʂ��N���A�C�X���G���R�ɕ߂炦���A�C���t�H�[�}�[�ɂȂ�悤���������B�ނ���������Q�̎�i������B�g�����v�哝�̂Ƃ����A�l�^�j���t�Ƃ����A�ǂ̌��݂ɗ]�O���Ȃ��B�����̒���͐��E��Y�Ŋό��q�𖣗����邪�A�����ǂ́A�����ł��X�����E��Y�ƂȂ邱�Ƃł��낤�B
�@�u�̐��ɂ̂������N�v�i2015�N�j�́A2013�N�́u�A���u�E�A�C�h���v�ŗD���������N�̎��b������̍��q�ł���B�W�J�͂悭����T�N�Z�X�E�X�g�[���[�����A�q�����������������ƕ`�����B���N�����z���Ȃ���Ȃ�Ȃ���Q���A�K�U�Ȃ�ł͂̌����������B
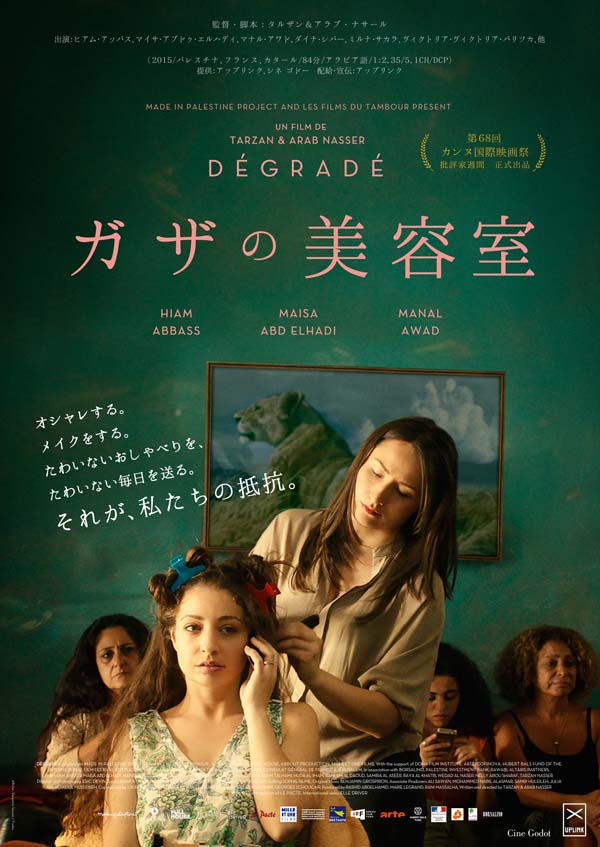
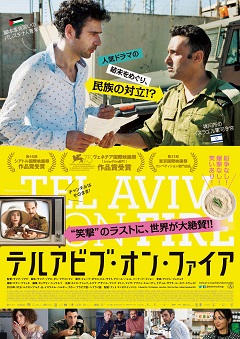 �@�u�K�U�̔��e���v�i2015�N�j�̐��썑�̓p���X�`�i���t�����X���J�^�[���A�ē^�[�U���E�i�T�[���B�V��̂Ȃ��S���ƌ�����K�U�ɂ��A���X�𑗂鐶��������B���e���ɏW�܂鏗������������B�ʂ�ł͏e���������B�u����������������A�O�̒j�����Ɠ�������Ȃ��v�ƈ�l�̏����������B���ł��푈������̂͒j�����B�I�V����������A���C�N����A�����Ȃ���������A�����Ȃ������𑗂�B���ꂱ�����ޏ������̒�R�Ȃ̂��c�Ƃ����e�[�}���d���B
�@�u�K�U�̔��e���v�i2015�N�j�̐��썑�̓p���X�`�i���t�����X���J�^�[���A�ē^�[�U���E�i�T�[���B�V��̂Ȃ��S���ƌ�����K�U�ɂ��A���X�𑗂鐶��������B���e���ɏW�܂鏗������������B�ʂ�ł͏e���������B�u����������������A�O�̒j�����Ɠ�������Ȃ��v�ƈ�l�̏����������B���ł��푈������̂͒j�����B�I�V����������A���C�N����A�����Ȃ���������A�����Ȃ������𑗂�B���ꂱ�����ޏ������̒�R�Ȃ̂��c�Ƃ����e�[�}���d���B
�@�u�e���A�r�u�E�I���E�t�@�C�A�v�i2018�N�j�̐��썑�̓��N�Z���u���N���t�����X���C�X���G�����x���M�[�A�ēT���t�E�]�A�r�B���̐l�́A�u�̐��ɂ̂������N�v�̋r�{�������Ă���B
�@�f��́A�p���X�`�i�̐l�X�̔S�苭���ƕ�����C�������Ă����B���⏊�́A�p���X�`�i�̐l�X�ɂƂ��āA���X���������̗͂̂Ȃ���g�ɐ��݂Ė������ꏊ�ł���B�����ł́A�e�ňЊd����C�X���G�����m�̂��@���Ȃ�ʂ悤�A����ɏo�Ēʂ蔲���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������C�X���G��������݂�A�e���U�����₷���őO���Ƃ������ƂɂȂ�̂����c�B
�@1967�N�̑�O�������푈�́A�A���u���ɂƂ��Ďv���o���������Ȃ���s��ł���B�f��́A���̌��⏊�Ɣs����R���f�B�ɂ��ď��̂߂��B�ɉ��ȏ������B
�@���썑�������悤�ɁA�p���X�`�i�̉f��l�́A�e�����玑�����W�߂ĉf�����葱����B�܂��Ƃɂ����܂����B�n�j�E�A�u�E�A�T�h��^�[�U���E�i�T�[���A�T���t�E�]�A�r�Ȃǂ��A���ꂩ����S�܂�邱�ƂȂ��A�f�����葱���Ă���邱�Ƃ�����Ă�܂Ȃ��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
2020�N6��6���A�L���B
���s�L�ē��ɖ߂�܂��B
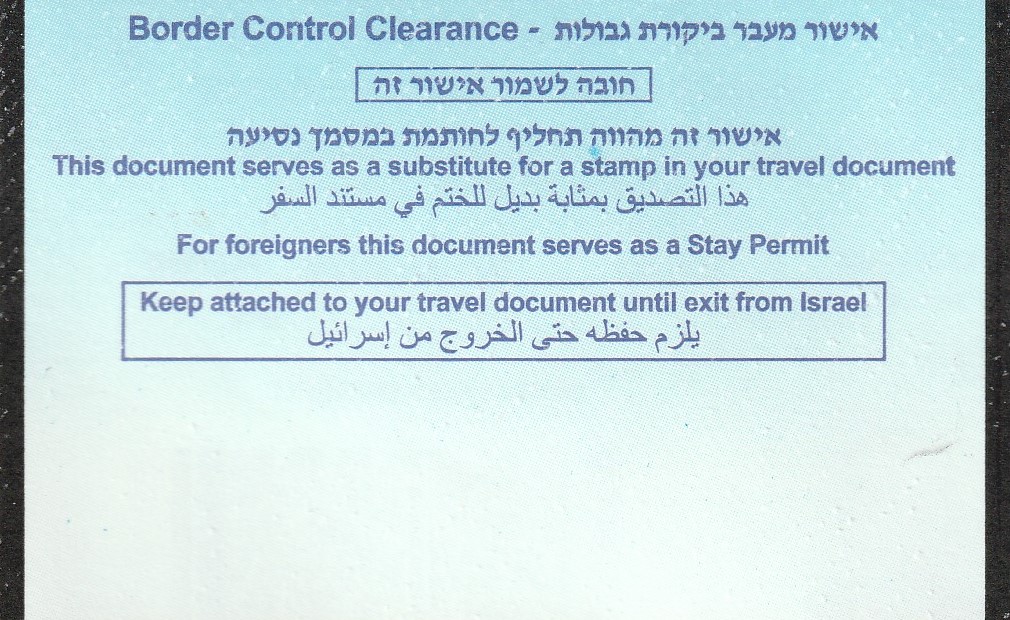
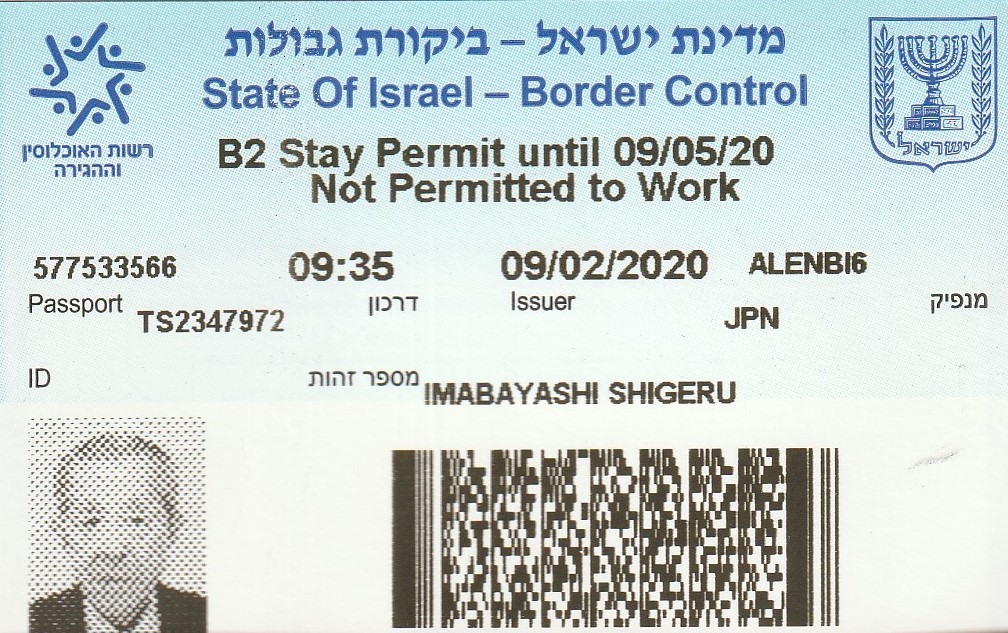 �@2020�N2��5������12���ɂ����āA�����_���ƃC�X���G���𗷂��܂����B��N���A���������s�Ŕ��������V�^�R���i�E�E�C���X���A�܂����E�I�Ɋg�U����ȑO�́A���b�N�_�E�����O�A���ˍۂ̂悤�Ȏ����ł��B�C�X���G�����痷�s�Ђɑ��A���N���ɒ����֗��s�����҂̓������֎~����A�Ƃ����ʒm���o����Ă����悤�ł��B�A����������A�C�X���G���͓��{���s�҂̓������֎~���܂����B���s����A��������A�V�^�E�C���X������قǂ̊����͂������Ă��悤�Ƃ́A�}�l�̎��ɂ͍l�����y�ʂ��Ƃł����B
�@2020�N2��5������12���ɂ����āA�����_���ƃC�X���G���𗷂��܂����B��N���A���������s�Ŕ��������V�^�R���i�E�E�C���X���A�܂����E�I�Ɋg�U����ȑO�́A���b�N�_�E�����O�A���ˍۂ̂悤�Ȏ����ł��B�C�X���G�����痷�s�Ђɑ��A���N���ɒ����֗��s�����҂̓������֎~����A�Ƃ����ʒm���o����Ă����悤�ł��B�A����������A�C�X���G���͓��{���s�҂̓������֎~���܂����B���s����A��������A�V�^�E�C���X������قǂ̊����͂������Ă��悤�Ƃ́A�}�l�̎��ɂ͍l�����y�ʂ��Ƃł����B