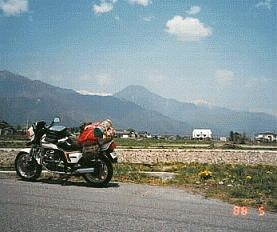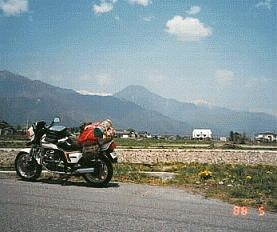82’ HONDA CX400E EURO
88年五月、CX400で長野県の白馬村に出かけたときの写真です。絵に描いたような快晴。雪の残る北アルプスに満開の桜。実はこの1枚の写真がこのバイクの運命を変えたのでした。(本文参照)
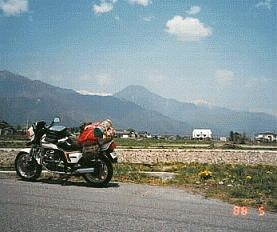
CX400ユーロ。たぶんほとんどの人が実車を見たことないのではないでしょうか。


フロントカウルはCB1100Fと共通(に見える)。外にひねったシリンダーがわかります?


前後のブレーキはCB750Fと同じらしい。ただ、TRAC(4段調整式のアンチノーズダイブ)は左にしか付かない。ホイルベースは1500mmもある。
シートの長さに注目。3人乗れる。塗装はパールホワイト。ホンダのマークはステッカーではなくバッジである。


くるまっぽいメーター周り。水温型と燃料計付き。キー周りのパッドは本来ハンドルバー全体を覆う。(調整用に切ってしまった)
マフラーの排気口は、リング状の部分に2センチぐらいの穴があいている。(真ん中のコーンはアルミだ)
シャフトドライブは汚れないのがいい。
特徴
-
縦置き水冷ツィステッドVツイン(なぜツィステッドというのかというと、クランク軸、この車の場合前後方向、にたいしてシリンダーヘッドが外向きにひねってあり、キャブからエキパイまでが扇形にセットしてあるんです。バルブを自由に配置できるOHVエンジンならではのくふうにより、キャブレターがフレーム内に収まり、モトグッツィと比較してもひざまわりがゆったりしています)。
-
熱膨張を考慮して採用された潜水艦の潜望鏡と同じ材料を採用した特殊ステンレスのバルブプッシュロッド。
-
OHVなのに4バルブを採用し10000回転も回るOHV(くどいようだがDOHC全盛の昨今、OHV!)
-
クランクと逆回転し、トルク反動(自動車のエンジンをよく見ると、回転をあげたときエンジン自体がクランク軸と反対方向に回転しようとするのがわかると思いますが、これがトルク反動です。昔のゼロ戦なんか、1000馬力のトルク反動のためまっすぐ飛ばず、パイロットが回転方向と逆に操縦桿を押さえつけて飛ばしていたと聞きました)を打ち消すヘビー級のクラッチ。
-
最新式のNSR等でよくつかわれている、しかし当時としては思い切りおごったカセットミッション。
-
CB750Fと同じアンチノーズダイブのTRAC装備のフロントエアサス。
-
これまたCB750Fゆずりの前後同径のツーポッドキャリパー装備のソリッドディスクブレーキ。
-
前後18インチのブーメランコムスターホイール。
-
プロリンクのリアエアサス。しかも分解整備可能。
-
油の飛ばないシャフトドライブ。
-
400km無給油を可能にした20リッターのタンク。
-
3人乗れる分厚いシート。
-
CX500ターボと同じスタイル(でもあっちは82馬力、こっちは40馬力・・・しくしく・・・)
- いまだ色あせないパールホワイトの塗装。
先代のGL400の欠点だった部分をほとんど解決した、ホンダGLシリーズの2代目です。(もっとも3代目はなかったけど)。このバイクの前に、VT250FEを乗っていて、山道ですれ違ったこいつに一目惚れし(二人乗りがかっこよかった)、バイクガイドで愛知県中を探し回ってやっと手に入れたのを思い出します。技術的には大変すばらしいバイクなのですが、思いっきり不人気車だったため、VT250を20万円で下取ってくれたうえ(当時の相場は15万円)、前後タイヤを新品にしてくれました。どうやら何年もここにあったようでした。ちなみにVTは数日もたたずに売れてしまいましたとさ。このバイク、買った当初は燃料計が動かず、ブレーキが利かず、4000回転以上ふけず、まっすぐ走らない、燃費は14KMしか走らず・・とひどい有様でした。燃料計はさびていたため分解掃除して復活。ブレーキはトリプルとは思えないほど利かなかったのが、オーバーホールして解決。なにせCB750とおなじですもの。利かないはずがない(当時としては)。エンジンが吹けなかったのはエアクリーナの取り付けミスでした。燃費も20KMに。まっすぐ走らなかったのはステア
リングヘッドのベアリング交換で見事解決。立派な長距離ランナーへ復活を果たしたのでした。さて、こんなにいいバイクなのに不人気の原因はどこにあるのでしょうか。友人たちの反応は・・・。
- くそ重い。乾燥重量で210KGもあるのに加えて重心が高いため、停車時には非常に不安定なんです。特にUターンはこわいですねー。何度も転がりました。
- シートが高く広く、足が着かない。178CMのわたしでやっとかかとがつきます。シートが厚いもんなあ。
- 非力。当時としては最強の40馬力エンジンも210KGの車重を引っ張りきれない。しかも高回転型の4バルブOHVエンジンは6000回転以下だととろい。本当にとろい。ただし1万回転も回るので最高速は160KMほどでますけど。
- でかい。ガソリンスタンドで何度もリッターバイクとまちがわれた。全長だけならアメリカン並だもんなー。特に20リッターのタンクがでかいためみんなびびってしまう。後ろを振り向くとテールまでの遠いこと。二人乗りでシートに荷物がのるもんね。
- エンジン音が許せないそうです。ころころした音がみなさんのお気に召さないようで。しかもOHVですよ。DOHCがあたりまえの時代に。
- 直進安定性がない。GL400の悪い癖はホンダの技術を持ってしても解決しなかったようで、重心の高さをもろに感じる。これをむかしは猫足セッティングと呼んでいました。常にふらふらしていて、どんな速度域からでも簡単にバンクする。私はそれを利用して狭い山道をレーサーレプリカとため張ってかっとばすんですけど、たいていの人はこの特性をいやがるみたい。あとでドカティに初めて乗ったとき、そのどっしりとした直進性に驚いたのは、このバイクと比較してしまったからです。イタリアじゃレーサーレプリカにさえ、あんな直進性を持たせるんだと。
- CX500(650)ターボとすれちがう、あるいは抜かれると、非常に悲しくなる。こいつはターボのレプリカだもんなー。
逆にいいところはというと
- クラッチが軽い。嘘のように軽い。みなさんワイヤーが切れてると思うようです。でも当時のホンダ得意のぺったんクラッチで半クラッチがきかないけど。
- 楽。この一言がこのバイクのすべてをあらわしてるといっていいでしょう。パワーがないのが幸いして、一定速で走る限り何の不満も感じません。けつも痛くならないし。1日700KM走ってもどこも痛くなりませんでした。
- (今になって)目立つ。外車と間違われたこともある。よく、どこのバイクですかときかれる。タンクにホンダって書いてあるだろうが。
- 整備しているとうれしくなってくる。もともとヨーロッパ向けに作られているため、つくりがいい。 フロントカウルなんか下をヒンジにして、ボンネットみたいに前に倒れるんですよ。しかもワイヤーストッパーで水平以上に倒れない。あけたところには、コネクターが整然と並んでる。サイドカバーの中も同じく、コネクターがきちっと並んでる。とにかく雑然としがちな電装類が、きれいに収まっているのをみるたび、何で国内仕様はあんなにいい加減なんだと怒りたくなります。
- 足が長い。400KM無給油で走れる。
- 壊れない。3万KM近く走っているが、バイク屋のお世話になったことがない。
とっても気にいっていまも持っているんですが、実は一度スクラップになりかけています。このバイクの次にVFR400Rプロアームを買ったんですが、そのとき下取りに出したんです。でもかなしい不人気車。珍しいからって高く下取ってもらえる訳じゃない。反対に廃車費用を請求される始末。とりあえず1万円で下取りしましょうといわれ、それでも貧乏だったため(それなら新しいバイクなんぞ買わなきゃいいのにとお思いのあなた。そこがバイク乗りの馬鹿なとこ。最新型に乗ってみたかったんだよう)泣く泣く手放しました。買い手がつかなかったらスクラップ行き。そこででてきた上にある写真。楽しかった思いでなんぞが走馬燈のように。翌日借金して作った一万円と引き替えに再び私の元へ出戻りしたのでした。
その時のバイク屋のほっとした表情を今も忘れられません。そんなに引き取るのがいやだったんかい。思い返すと、その後のバイクの無限増殖の引き金になったのはこのCX400だったような気がします。だってそれまでは必ず下取りに出してたから、ふえなかったもんなあ。
CX400ユーロ82年式
1986年11月 8000KM走行のを20万円で購入 現在15歳。今までの交換部品は
- Fフォークオイルシール 2組
- タイヤ前後2組
- バッテリー4個(レギュレーターがよくないようで過充電気味)
- ブレーキキャリパーOHキット 2セット
- ステアリングヘッドベアリング1セット(レース込み)
- ブレーキパッド1組 11年間でこれだけ・・・消耗品だけですねー。
GL系のバイクをいまも乗っている方(CXターボも含む、ただしツインのみ)クラブがありますので紹介しておきます。
GL−Vツイン−オーナーズクラブ
郵便番号242 神奈川県大和市中央林間3−19−22 大塚哲也さんまで
GL−CLUB会員のホームページ(個人)
http://www.linkclub.com/~f4-onota/
目次へもどる