<作例>

>作例<

> も <
スタディモデル,ダミーモデル,プロトタイプモデルがあります。
○スタディモデル … 構想段階で形を検討する際に粘土や石膏などで作ります。
○ダミーモデル … もう少し進んで,同じ様な材質や実際の形態に似せて作ります。依頼者に見せるのでプレゼンテーションモデルとも呼ばれます。
○プロトタイプモデル … ダミーモデルに実際の機能を組み込んで,動いたり走ったりします。
美術に関する用語集
このコーナーは基本的な美術の用語を集めています.。したがって全てを網羅するものではありません。主に生徒や初心者の活用を想定していますので,できるだけわかりやすく解説していくつもりです。より専門的な知識をお求めの方は図書館などで美術事典をご覧ください。
用語の解説
| マーブリング | モダンテクニックの技法のひとつ。 <作例>  |
| 蒔絵(まきえ) | 漆で絵を描き,金銀の粉を蒔きつけたもの。漆芸の器などで装飾表現のために用いられる技法。 |
| マスキング | 筆で着色する場合,境目をきれいに描くには限界があります。そこで紙テープやシートなどを使ってあらかじめ色のつけない部分を保護しておき,塗った後にはがします。スパッタリングをする際に型紙でブロックする方法もマスキングと呼ばれます。 |
| マチェール | 絵画の表面。絵の具の塗り方や筆の使い方によって表現される,材質的な効果のことを指す。 |
| 曼陀羅(曼茶羅) | 密教の教義を図式化したもの。平安,鎌倉時代に数多く製作された。 |
| 密陀絵 | 密陀僧(一酸化鉛と油と絵の具を混ぜてつくられるペンキ状のもの)を用いて描かれた絵のこと。法隆寺の玉虫厨子に描かれた絵が有名。 |
| 密教美術 | 弘法大師以降盛んになった,密教の教義や,曼陀羅を描いたものや,神秘的な彫刻像などの総称。密教は仏教とバラモン教などが融合して生まれた宗教といわれる。 |
| ミニテュアール | 細密画のこと。 |
| 未来派 | キュビスムの影響を受け,イタリアの青年芸術家たちの間からはじまる。急速に進歩する社会の中でダイナミックな表現活動を展開し,演劇や映画にまでも影響を与えた。伝統的な表現に反抗するかのように,芸術の中にスピード感と騒乱を含めようとし,さまざまな芸術の境界を取り除き,いろいろな感覚をめまぐるしく働かせることを目指した。 |
| 明朝体 | 中国の明の時代に筆で書いた形を様式化した字体です。横棒と縦棒の太さに違いがあり,横1に対して縦3.5から4ぐらいの割合で描くとメリハリのあるきれいな書体がかけます。また,「うろこ」とよばれる部分にも特徴があります。 |
| ムーブメント | 構成美の要素のひとつ。動勢とも呼ばれる。形や図形の組み合わせから大きな動きが感じられる構成。 >作例<  |
| 明度 | あかるさのこと。色の3要素の一つで,この要素は無彩色にも有彩色にも含まれる。白っぽいものは明度が高く,黒っぽいものは明度が低いと表現する。 |
| 雌型 | 粘土などでつくった原型に石膏などで型どりをしたもの。彫塑や金属工芸,陶芸など,様々な分野で同じ形のものを生産する際に利用されている。原型やそれと同じ形のものを雄型という。 |
| メゾチント | 銅版全体に均一な細かな傷をつけ,そこから小さな傷の粗密を作り出して濃淡を表現する技法。 |
| 面相筆 | 水彩絵の具で彩色する際に使われる細い筆。広い場所をぬる際には,平筆や彩色筆が用いられる。 |
| 目止め | 木材の作品で表面を塗装する際には,木目による凹凸を隠すためにとの粉を塗る。その作業を指す。 |
> も < |
|
| 木炭 | 柳・ぶどう・桑などの天然の材料を乾燥させて蒸し焼きにし,炭化させたものです。木炭デッサンに使われます。材質や焼き具合によって微妙に色合いや質感の表現に影響します。消し具として食パンが一般的に使われます。 |
| 木炭紙 | 木炭デッサン用に作られた紙です。表面は木炭の粉がつきやすくざらざらしていています。表裏を間違えやすいのですかしの文字を確認したり凹凸を確認してから使うようにしなくてはいけません。 |
| 裳階(もこし) | 建物の周囲につけられたひさしのことを指します。有名なところでは法隆寺の金堂や五重塔,薬師寺東塔についています。 |
| モザイク | 色ガラスや大理石などの石片を張り合わせて,絵や模様を作る技法のことです。キリスト教初期の教会は,この技法を用いた豪華なモザイク壁画によって飾られていました。残念ながらこの当時の教会装飾はほとんど現存していません。 |
| モダンテクニック | 新しい表現技法の総称。材料や可能性の追求,発見のために作り出されていきました。当時の新しい表現に使われています。デカルコマニー,シンメトリー,アクセント,グラデーション,リズム,マーブリングなどがこれです。 |
| モチーフ | 表現のための動機となる素材。 |
| 没骨法(もっこつほう) | 輪郭線を用いずに,面で直接表現する。墨や絵の具で濃淡を描く方法。 |
| モデリング | 可塑性のある素材(粘土や石こうなど)を用いて作品をつくる作業のこと。カービング(彫ったり削ったりする作業)に対する用語。 |
| モデルメイキング | 図面では表しにくい立体のものを粘土や石膏などを用いて作ることです。 スタディモデル,ダミーモデル,プロトタイプモデルがあります。 ○スタディモデル … 構想段階で形を検討する際に粘土や石膏などで作ります。 ○ダミーモデル … もう少し進んで,同じ様な材質や実際の形態に似せて作ります。依頼者に見せるのでプレゼンテーションモデルとも呼ばれます。 ○プロトタイプモデル … ダミーモデルに実際の機能を組み込んで,動いたり走ったりします。 |
| モビール | 動く彫刻といわれる。絶妙なバランス感覚で設計され,風や温度で自動的に動いたり,機械仕掛けになっていたりする抽象的な立体構成作品。カルダーが考案した。 |
| モノタイプ | 一枚だけしか刷れない版画のことです。ガラス板などの上に絵を描き,紙に刷りとります。 |
| 焼き入れ・焼きなまし | 刃物などの金属を赤熱させた後,水に入れて急速に冷やすと金属の硬度を高くすることができます。これを焼き入れといいます。逆にゆっくり冷やすと高度が低くなります。これは焼きなましをいいます。金属工芸(鍛金)で作品を制作する際には,この方法で柔らかくしてから成形していきます。 |
| 大和絵 | 平安時代から中国伝来の絵(唐絵)に対して,日本の風物を日本的な技法で描かれた絵のことを倭(やまと)絵と呼びました。これが後に大和(やまと)絵と呼ばれるようになっていきます。 |
| 弥生式土器 | 縄文時代の次の時代に作られた土器です。製作には専門の職人がいたらしく,形も洗練されてきました。器の厚みは均一で,焼成温度も上がっており,そこには技術が感じられます。 |
| 有彩色 | 無彩色(白,黒,灰)に対して,何らかの色味を帯びている色は全て有彩色という。 有彩色には色の3要素(明度,色相,彩度)があり,これらの微妙な変化によって無数の色彩が作り出される。 |
| 釉薬(ゆうやく) | 焼き物の表面を飾るガラス質のものです。成分によって発色が変わります。透明であったり,不透明であったり,釜の中で変化する変釉と呼ばれるものもあります。この釉薬の調合は陶芸家の腕の見せ所です。自分の気に入った色をつくるために何度も研究を重ねています。 |
| 釉(ゆ)がけ | 焼き物で,素焼きが終わった後に釉薬をかける作業のこと。 素焼きの状態は水分を非常に吸い込みやすいため,かけ方にはコツが必要。ひしゃくでかけるやり方と,釉薬の中につけるやり方がある。 |
| 俑(よう) | 土で作られた人形のことです。古代中国で数多く製作され,王などの墓に納められました。 |
| 陽刻 | 印の場合,文字の部分が飛び出している彫り方を言う。彫刻なら浮き彫り(レリーフ)のこと。 |
| 寄木造 | いくつかの木を組み合わせて一つの彫刻を作る技法です。藤原時代に仏師の定朝によって創案されたといわれています。 |
| 寄棟造 | 建築様式の一つです。四つの隅棟をもつ屋根の形式を指します。 |
| 来迎図 | 平安中期に浄土信仰によって生まれた仏画です。阿弥陀如来が西方浄土から衆生済度のために人間界に下ってくるという仏教思想を絵に表したものです。 |
| 楽焼き | 800℃ぐらいの低い温度で焼成する焼き物です。桃山時代から始まり,茶器が多く残されています。 |
| ラフスケッチ | アイデアを練る際に思いついたことを大ざっぱに紙に描きとめたスケッチのこと。 |
| 離型剤 | ※ はく離剤の項を参照のこと。 |
| リズム | 構成美の要素のひとつ。 形や色が規則的に変化(強弱や大小,明暗など)し,それが繰り返されることでそこに美しさが感じられる構成。 <作例> 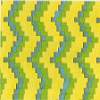 |
| リトグラフ | 平らな石版の面にインクのつく部分とつかない部分を作って刷る版画で,平版の一種です。水と油の反発する原理を利用しています。アルミニウム板や亜鉛版なども使われます。 |
| 量感 | 容積や重量の感じのことです。絵や彫刻では重視されます。 |
| 臨画 | 手本を見て,それを模写した絵のことです。明治初期の美術教育ではこれを盛んに行いました。 |
| 淋派 | 江戸時代の尾形光琳の様式を継承した人たちの絵を総称した言葉です。 |
| 類似色 | 色相で似ているもの同士や,色相環上においてある色を中心にその近くにある色の呼び名です。長所としてまとまりのある落ち着いて感じを作ることができますが,短所としてメリハリに欠けた感じになるために,明度や彩度を変えるなどの工夫をするとよいでしょう。 |
| レイアウト | 文字や挿し絵,写真などの配置のこと。ポスター制作などでは,見やすく印象的な方法を考える必要がある。 |
| レタリング | 代表的な字体は明朝体とゴシック体です。明朝体は明の時代に筆で書いた文字を様式化したものです。ゴシック体は刷毛で描いた文字を様式化したものです。それぞれに技法や用途に特徴があります。
|
| レリーフ | 浮き彫りのこと。 エジプトの彫刻は沈め彫りでつくられているのに対して,ギリシャの彫刻は絵の部分が膨らみを持つようにつくられている。 対象物の距離を圧縮して,凹凸を表現した技法。硬貨などにも表現されている。 |
| レンダリング | 完成予想図。商品などで,完成する前に想像して描いたもの。 |
| ろうけつ染め | |
| ロゼッタストーン | 1799年にナポレオンがエジプト遠征を行った際に発見したものです。ヒエログリフと呼ばれる象形文字に並んで,デモティックというエジプト文字とギリシャ文字が並んでいました。これは紀元前196年にプトレマイオス5世に捧げられた文章でしたが,3つの言葉で書き記されていたために,これによってヒエログリフの解読に成功しました。23年の後,解読を成功させたのはフランスの言語学者,シャンポリオンです。大英博物館に保存されています。 |
| ロマン主義 | |
| ロココ | 優美で官能的な絵画様式。 |
| ロマネスク様式 | 「ローマ風」という意味です。この頃に封建制度が確立していきます。この時代の教会建築は一般に重厚な石壁と暗い内部空間が特徴です。壁や柱が石で作られたために非常に重たくなり,窓を大きく開けることができませんでした。逆に薄暗くてたいまつを炊かなければならない空間が,祈りを捧げる場所にふさわしい雰囲気を作り出したのです。 |
> を・ん < |
|