| 第63話 そして伝説へ……
街を包む針葉樹林は、夜霧にうすぼんやりとその姿を浮かび上がらせていた。 「行くか」 勇者はそう言うと、昨日受け取ったばかりの剣を背中の鞘に戻し、荷物を持った。 いよいよだ。 若者たちの胸中には、いい知れない感慨と興奮と、そしてまだ見ぬ魔王への恐怖がせめぎ合っていた。それらが入り交じった、複雑かつ不可解な感情を抱いて、彼らはリムルダールの街を後にする。 「絶対に勝とうな」 「もちろんだ」 ともすれば無口になりそうな自分を励ますように、仲間に語りかける。 「オヤジか……」 勇者の父オルテガが、数日前に魔王の島へ向かったと言うことは判っている。ひょっとしたら追いつけるのではないか、父は自分を判ってくれるのだろうか、父は強いのだろうか……勇者は期待と不安でいっぱいの心を隠すことが出来ない。 「思えば長かったね」 戦士が、そんなことを言う。 「僕さ……この戦いが終わったら、僧侶にでもなって世界中に巡礼の旅をしようかと思うんだ」 「……テドンの件か」 「まあ、それもあるけど」 賢者の問いに答えながら、戦士は極めて明るく言った。 「魔王がいなくなっても、魔物が全ていなくなるわけじゃないと思うんだ。だからさ、人々が安全に旅できるように、残った魔物を退治しながら、その魔物も弔おうと思って」 「フフッ、お前らしいよ」 「ありがと」 「別に誉めたわけじゃないんだがね」 「判ってるよ」 賢者と戦士がそんなことを話しながら歩いているのを見て、武闘家も勇者に語りかける。 「なあ……」 「ん?」 「俺さ、色々考えたんだ」 「何を?」 「お前のオヤジさんのことさ」 「ふうん」 「……生きてるさ、絶対」 「そうかな、そうだといいな」 「だってさ、考えても見ろよ……オヤジさんは今まで、俺たちが通った道を、俺たちが4人がかりでやっとこ通った道を、たった一人でくぐり抜けてんだぜ?絶対大丈夫、逢えるって」 「ありがとよ……だがな、俺はそんなに楽観視してない」 心の底では期待しているくせに、勇者はわざと悲観的なことを口にする。楽観論で喋って、それを覆されるのが怖いのだ。 「オヤジは強いよ……会ったことはないが、それだけは判る。オヤジは世界一の勇者だ。だがな、オヤジにはいかんせん、共に旅をする仲間がいない……俺、みんなのこと頼りにしてるんだぜ」 「よせよ、照れくさい」 「……もし勇者サイモンが、オヤジと共に旅をしていたなら……俺はこんな風に、不安に思ったりはしなかったろう……オヤジには、背後を守ってくれる人がいないんだ……」 「おい……」 「とにかく、世界の平和だ。オヤジのことは後でいい」 無理をして、と武闘家は思う。これほどまでに思い詰めた顔をして、それでも平気な顔をしている勇者の決意がどれほどまでのものなのか、武闘家にも少し判ったような気がした。 歩いていくと針葉樹林が途切れ、岬に向かって砂浜が広がっていた。暗い空を受けて暗黒に沈む海の色は、まるで深淵を覗き込んでいるかのように深く、そして重かった。 「じゃあ、使うぞ」 岬の突端に立った賢者は、天高く【虹の滴】を掲げた。 「これで向こう側に渡れるようになるのか……」 一瞬の間をおいて、【虹の滴】から七色の光がほとばしった。荒れ狂う凶暴な七色の光は、空をそして水面を七色に染め、激しく揺れ動いた。 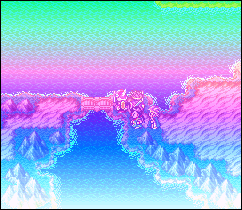
「見ろ、虹だ……」 武闘家が指さす方向、魔王の島側の海岸から、こちらへと伸びてくるのは間違いなく虹だった。だがその虹は通常の虹ではなく……文字通り虹の橋だった。明らかに質量を持っている虹が両岸を結び、その完成を待っていたかのように光は音もなく消え去った。 後に残されたのは虹の橋と暗い空と漆黒の海、そして呆然と佇む勇者たち。 「……い、行こうか」 「あ、ああ……」 少し不安に思いながらも、その質量を持った虹の上を歩き、遂に勇者たちは魔王の住む島へと到達した。 「……あれ、消えないね」 戦士が振り向きながら言う。 「馬鹿、消えられたらどうやって帰るんだよ」 「ルーラで帰ればいいじゃん」 武闘家の指摘を軽く受け流して、戦士は雷神の剣を鞘から抜きはなった。 「来る!敵だ!!」 魔王ゾーマの居城は、過去には人の住む城であったという痕跡がまだ多量に残されていた。壁に飾られている錆び付いた剣や盾には装飾が施され、血の染みで汚れたじゅうたんには豪華な刺繍がまだ残っていた。花壇には枯れた草木が無惨な姿を晒しており、シャンデリアには白骨死体が乗っている。 それらは全て、過去にこの城が反映した人間の城であったことを告げている。もしゾーマが自らの居城として建設したのなら、そのような極めて人間らしい装飾は元々存在するはずがないからだ。そして、そんな装飾をわざと無惨に放置しているのは、ゾーマが人々を憎んでいるからなのだ。 「フン、表の魔物と大して変わらないな」 軽口を叩きながら、ダースリカントの右腕を叩き折る武闘家。骨の砕ける嫌な音が、廃墟と化した玉座の間に響き渡る。 「魔法を使うまでもないな」 賢者もそう言いつつ、トロルキングの首をはねる。 「油断は禁物だよ、ここは嫌な感じがする」 戦士は眉をひそめ、反撃に転じようとしたダースリカントを袈裟懸けに斬った。悲痛な叫びを残して、ダースリカントは床に倒れ込む。 「とどめをお願い」 「あいよ」 勇者はダースリカントの頭を踏み抜いた。脳髄と血が飛び散り、ダースリカントは動きを止める。 「玉座にゾーマはいない、か。まぁ予想通りだな」 勇者は口笛を吹いた。 「こっちだ!玉座の裏に、隠し通路がある!情報通りだよ」 「全く」 賢者は笑って、肩をすくめた。つられて勇者も笑う。 「馬鹿と煙は高いところが好きだって言うが……どうしてこう悪人ってのは穴のどん詰まりが好きなんだろうな?」 「連中は、早く自分をブッ殺して欲しいのさ……だからわざわざ袋の鼠になりたがる」 「うし、行くか」 隠し通路のフタを取り除いて、勇者たちは地下へと潜っていく。元々この城には地下迷宮があったらしく、整然と石で組まれた通路に勇者たちは驚いた。 「どういうことだろうな?」 「さあ……だが、魔物にこんな芸当はできないはずだ」 幾階層かを降りて行くが、それでも緻密な石の通路は続いた。 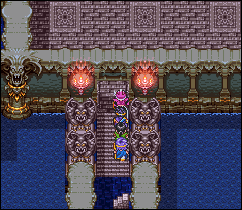
「見ろよ、このフロアには川まである……橋もかかってる」 階段を降りてきたその前には、まるで地底世界のように……アレフガルドのように、石積みで再現された庭園があった。川があり、中州とおぼしき島があり、そして通路は橋が用意されている…… 「こいつは妙だと思ってたが、どうもホビットかドワーフの細工だな」 賢者が床を調べながらそう言う。 「なるほどね……大地の精霊なら、地下にこんな空間を作るのも判るよ」 「城の上の階には階段を壊されてて行けなかったが、上もかなりの階数があった……ということは、この城は天と地の両方にそびえていることになる」 「つまり、精霊や妖精たちの城ってことか……」 武闘家は床に落ちていたペンダントを拾って、埃を払いのけた。 「ああ、精霊王の城かもしくは、ルビス様の城だったかも知れない……」 武闘家は拾ったペンダントを物陰に投げつけた。グウ、と声がして、数匹のトロルキングが姿を現す。 「ンググ、気付かれちまっただぁ……」 「あいにく、手前らは臭くってな!隠れてたってモロバレだよ!」 「グフォフォ、臭いって言ったなぁ、言ったなぁ!?」 「本当のことを言ったまでだ!」 「ゆ、ゆゆ許さない!」 武闘家はニヤリと笑って、中指を立てる。 「へっ、だったらどうする?どうもしないならこっちから行くぜ!」 「グフフ、消えろ!バ・シ・ル・ー・ラ!!」 「な!!」 武闘家の体が淡い紫色の光に包まれ、そして消えた。 「なんだ!?」 「グフフ、お前も、だ、バ・シ・ル・ー・ラ!!」 「くそっ、ここまで来て……」 戦士の体も武闘家と同じように、消え去った。 「グフォ、これで、お前たちは2匹、オラたちは3人……ゆ、有利になった」 「畜生、こいつらを倒したとしても2人だけかよ……」 唇を咬む勇者。周りを囲まれ、賢者と背中を合わせて絶体絶命だ。 「なぁ、提案があるんだが」 「なんだ」 「こいつらから逃げ回っていられるか?」 「は?」 賢者はそっと勇者に耳打ちする。 「幸い俺はバシルーラを使える。バシルーラを受けた者は、アリアハンの酒場に戻るって寸法だ」 「なんで判る?」 「ルイーダから酒場の登録証を貰ったはずだ……アレには、そういう対抗呪文が施してある」 「知らなかったな……さすが賢者だ」 「俺はお前ほど体力に自信がない……だから、俺がバシルーラで酒場に戻って、連中を引き連れてもう一度戻ってくる」 「……1時間も耐えきれないぞ」 「30分で戻る」 勇者は右手に持った王者の剣を振りかざした。剣から突風が吹き出し、トロルキングたちは慌てて目を押さえた。 「よし、乗った!!」 「すぐ戻る!バシルーラ!!」 賢者の体が消え、勇者はまだ目を押さえているトロルキングの脇を通り抜けて、小学校の体育館ほどの広さがある広間へと出た。 「グググ、ま、待てぇ!」 走って追いかけてくるトロルキングが縦一列になったのを確認して、勇者は印を結んだ。 「ライデイン!」 稲妻の魔法が戦闘のトロルキングの右膝を直撃し、そのトロルキングは衝撃でつんのめった。後ろから走ってきていたトロルキングたちに、そのとっさの出来事を理解する余裕はなく、仲間の体につまづいて大げさに倒れた。 「ハッ、その程度か!」 トロルキングの山に駆け寄って、勇者は王者の剣を振り下ろす。一番上のトロルキングが右腕を失い、大きな悲鳴を上げる。 「よ、よくもやったな!!」 「痛いよ、痛いよ!」 「ううう、うるさーい!上からどけ!」 「痛いよー!」 「重たい!どけ!」 腕を斬られたトロルキングは、怒りと憎しみで自分の下のほうにいるトロルキングを睨んだかと思うと、いきなり棍棒で一番下のトロルキングの頭を殴りつけた。 「ぎゃ!!」 びしゃ、と血が飛び散り、一番下になっていたトロルキングの四肢がビクビクと痙攣を始める。怪力で叩き付けられた棍棒に、頭蓋骨は完全に粉砕されたらしく、一番下にいたトロルキングの頭は完全なのしイカ状態になってしまう。 「ひひひ人の痛みを判ってあげられない、そんなのは間違ってる!!」 肩で息をしながら立ち上がったトロルキングはそう吐き捨てるように言うと、憎々しげに勇者を睨んだ。 「お前にもお返ししてやる、叩きつぶしてやる!!」 いくら勇者でも、2匹のトロルキングを一人で相手はできない。勇者は再び様子をうかがうと、今度は中州へと繋がる橋の方へと逃げ出した。 「ほら、相手をして欲しかったらこっちに来い!」 トロルキングたちが追いかけてくるのを確認して、勇者は笑った。この調子で時間を稼げば、仲間たちも戻ってくる……!! 勇者がほくそ笑んで前を向くと……その向こうでは、初老の戦士が1人、ヒドラを相手に奮闘しているのが見えた。 「まさか……オヤジ!?」 「おー、お前も飛ばされたのか?」 落ち着かない様子でうろうろしていた武闘家は、見事な着地を決めて見せた賢者にそう冗談めかして言った。 「馬鹿言え、わざわざ迎えに来てやったんだよ」 「勇者は!?」 「まだゾーマの城にいる。今すぐ戻るんだ、さあ来い!」 戦士はコーヒーカップをテーブルに置いて、溜息をひとつついた。 「良かったよ、迎えに来てくれて……僕たちはルーラ使えないからさ、どうやって戻ろうか悩んでいたんだ」 「誰か魔法使い捕まえて、ルーラ覚えさせて行こうかとまで思ったんだぜ」 「くだらない冗談言ってるヒマがあんならさっさと来い!勇者は1人で待ってんだ!」 賢者のただならぬ形相に驚いた武闘家と戦士は、小走りに酒場の外へと出ていった。一部始終を見ていたルイーダは、ふっと笑ってタバコに火をつけた。 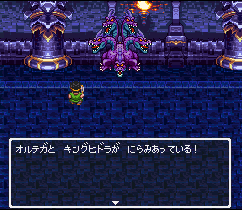
「よく似てるって言われるぜ!」 「男の子は女親に似るって言うがな、俺の遺伝子の勝ちってわけだ!」 父と子は、互いに戦いを続けながらも、声を張り上げて会話をする。 「だからオヤジ、俺も来たぜ!オヤジの歩いた道を通って、ここまで来たぜ!」 トロルキングが振り下ろす棍棒を避け、キングヒドラの吐く炎を受け流しながら、勇者とオルテガは親子の会話を続けていた。その距離約40メートル。 「おうよ!わざわざアイテムもヒントも残してきてやったんだ、来られなくてどうする!」 結婚の遅かった勇者オルテガは、もう50を過ぎる壮年になっていた。戦いはそんな体には過酷だったが、息子がすぐそばにいるという事実が、彼の体を今まで以上に動かす原動力となっていた。 「だがな、なんでお前まで1人で来た!?そこまで真似る必要はないんだぜ?」 「へっ、仲間はいるよ!今ここに向かってる!」 「そうか、仲間がいるか!そいつはいい!1人で戦うより、よっぽどいい!」 キングヒドラの尾がオルテガを襲った。ビシイ、と乾いた音がして、オルテガは片膝をついた。 「ククク、勇者オルテガよ……寄る年波には勝てないな?」 「ふ、少しはハンデをやらないとな」 「減らず口を!」 キングヒドラの攻撃が激しさを増していくように見える。だが、実はキングヒドラの攻撃自体は、さほど変わってはいないのだ。それを受け流し、避け、反撃するオルテガのスピードがみるみるうちに衰えて行っているのである。 「ふ、ふはははは、勇者オルテガその程度か!跡継ぎが現れて安心したか、しからば安らかにあの世へ行けいっ!」 「オヤジ!?」 思わず振り返る勇者。しかし、そのボディへ容赦ない棍棒が叩き込まれる。 「グフォフォ、おおお前の相手はこの俺だ!」 「畜生……!!」 トロルキングが憎々しげに笑い、勇者は口の端から流れた血を拭って、王者の剣を構え直した。 「大丈夫だほだか、安心しろ!この程度で俺がくたばるもんかよ!」 だが、勇者にも、そしてオルテガにもそれが強がりであることが判っていた。 「こンの、くたばれェッッッ!!」 ジパングの名工によって鍛えられし名刀【王者の剣】が一閃し、トロルキングの腹腔を切り裂いた。 「あぐぐぐぅ……」 信じられないものでも目撃したかのように目を大きく見開いて、トロルキングは自分から離れていく臓物を悲しげに眺め、引き留めようと手を伸ばしながら絶命する。 会心の一撃。 「ぐぬぬう、よよよくも兄者を!!」 最後まで残ったのは、さきほど右腕を切り落とされたトロルキングであったが、そのモンスターが3匹の中で一番の手練れだったらしく、ダメージを感じさせない攻撃の嵐は勇者の焦りをさらに増幅させる。オルテガはさっきから完全に黙って、キングヒドラの攻撃になんとか耐えているといった状態になりつつあるからだ。 「こいつ、しつこい!」 「ふははははあっ、勇者オルテガよどうした、そらそらそらっ!!」 「ぐうっ!」 背後でどさり、と倒れる音がする。勇者は振り向きたい衝動に駆られるが、俊敏に打ち込まれる棍棒のために振り向けない。 「かはははは、勇者オルテガ打ち取ったりィ!!ゾーマ様、このキングヒドラめが勇者オルテガを打ち取りましたぞ!!」 「お、オヤジぃ!?」 「オルテガが息子よ、貴様はゾーマ様直々に相手をなさると仰っておる……今ここで命を絶って貰えぬ不幸をとくと味わうが良い!」 「勝手なことをっ!!」 勇者は体の中の力を爆発させ、一気にトロルキングの上空へと飛び上がる。そして、防御しようとした棍棒ごと、トロルキングをまっぷたつに斬った。 「がぅぷっ!?」 「オヤジ!!」 着地した勇者はそのままオルテガの方へと走り出す。不敵に笑うキングヒドラの姿がゆらめき、次第に薄くなっていく…… 「逃がすかよッ!!」 「ふはは、父の死に目に出会えて幸せだな?」 駆け寄りながら【王者の剣】を振り下ろす。しかし、キングヒドラは一瞬早く消え、剣は虚しく空を斬った。 「くっ……オヤジ!」 子は父に駆け寄った。そこに横たわっている白髪混じりの男は、確かに子が思っていた通りの父親だったが、その命の炎は今にも消えようとしていた。 「ふ、強く……なったじゃねえか……」 「喋るな、今傷を調べるから」 勇者は父の体を調べて驚いた。灼熱の炎に焼かれ、鋼の鱗に切り裂かれ、重い尾に打ちのめされ、父の体は既にボロ雑巾そのものとしか言い様のない程にまで痛めつけられていたからだ。 「た……確かに似ていやがる……俺の若い頃にそっくりだ……」 「当たり前だろ?……ちょっと待て、今鎧を脱がせてやる」 オルテガは満足そうに笑い、鎧を脱がせて手当てをしようという勇者を手で制した。 「ん?なんだよオヤジ、早いとこ手当てを……間に合わない!」 「どうやら……あとはお前たち……若い世代に託す……ことになるな……」 「オヤジ!いいから喋るな!ベホマ!……どうしてだ、どうして魔法が効かない!?ベホマ、ベホマ!」 「魔法は生命力を高め……自主的な治癒を促すに過ぎん……無理をしたせいか、俺の体はもう……ゲフッ!!」 肺に血が入ったのか、咳と共に血の泡がオルテガの口からこぼれる。 「畜生、やっと!やっと逢えたんだぞ!俺がまだガキの頃に旅に出たまま帰ってこなかったオヤジに!ここまで来て、何年もかかって!」 「いいか息子よ……ゾーマの弱点は……奴が昔【光の賢者】だったことだ……」 「何言ってんだ、それは後で、ゾーマと戦うときに教えてくれ!」 「奴は光の宝珠に吸い込んだ闇に取りつかれているに過ぎん……その本質は未だ光……だから、わざわざ闇の衣を……着込んでいる……それを剥ぐことが……光の珠……」 「オヤジ、しっかりしろ!すぐに連中が来る、アリアハンに送ってやる!……かあさんが、かあさんが待ってんだよ!!」 勇者の瞳から涙が溢れ出し、その滴がオルテガの血と煤で汚れた横顔を洗った。 「光の……珠で、闇の衣を……うははは、俺の意志は息子が……悔いはない……」 「喋るなって言ってんだろーが!!くそっ、幸せそうに死のうとしてんじゃねぇよ!!この糞オヤジ!!」 「行け、我が息子よ……仲間たちが……お前を……」 オルテガの震える手が勇者の背後を指し示す。勇者がゆっくり振り向くと、そこには走ってきたのか肩で息をしている仲間たちが、呆然とこちらを見つめていた。 「マリア……俺たちの子は……強く……」 オルテガの手が、力無く床に落ちた。 勇者は、号泣した。 「あら」 洗濯物を取り込む手を休ませて、彼女は夕焼けの空のある一点を見つめた。 「どうしたんじゃね」 同居している義父はそう言って、息子の嫁が見る視線の先を追った。 「流れ星……きれい」 「……ほう」 東の空、既に暗くなりつつある空に幾筋ものほうき星の軌跡が描かれていく。 「……あの子は、あの子たちは元気にやってるでしょうか?」 「ふほほ、大丈夫じゃよ。あの子はワシの息子オルテガの子、この爺の孫じゃ!元気にやっとるに決まってるわい!」 老義父はそう言って胸を反らした。 「……さてマリアさん、今日の晩飯は何じゃろか?」 「今日は特製シチューと焼き魚ですわ」 「ふほっ、そりゃ楽しみじゃわい!」 「じゃあな、オヤジ」 石畳をはがして土を露出させ、オルテガの亡骸を埋めると勇者は初めて口を開いた。 遺骸をそのまま放置すれば、この城にうごめく訳の分からない者共にオルテガの体を荒らされることになる。ならば、せめて土中に埋葬すれば、その心配も減ろうというものだ。 「あ、あのさ……俺、何て言っていいかよく判らないんだけどさ……」 武闘家がうろたえながら話しかける。 「すまんな、みんな」 そんな武闘家を制して、勇者は仲間の方に向き直った。 「俺のワガママで時間を取っちゃって申し訳ない」 「いや、俺は……」 「俺たちがここに来た目的は、あくまでも魔王征伐だ。私的な感情で動いてすまない」 「いいんだ」 賢者は目を閉じて、静かに言う。 「勇者オルテガは俺たちにとっても大きな存在だった……その死を弔うのは、私的な感情でもなんでもないさ」 賢者は静かに印を結び、浮かび上がった光をオルテガが埋められた地面に向かって放つ。 「……ニフラーヤ」 それは既に失われた古代の魔法……死者の魂を遠くヴァルハラへといざない、平穏な死後を約束する魔法。 「よし、行こう」 戦士が静かに、そして力強く言う。 戦う集団が、ゆっくりと動き出した。 「ゾ、ゾーマ様!!勇者たちが、ぐはあっ!!」 そのアークマージは、報告を最後まで出来ぬまま【雷神の剣】に斬られて死んだ。 「ふふん?来たか……」 玉座の上のゾーマは、肘をつきながら傲慢に嘲笑う。 
「全くで御座います」 柱の影からのっそりと現れた三体の影……バラモスそっくりの魔物、キングヒドラ、そしてバラモスと同等の大きさに見える骨だけのアンデッド・モンスター。 「我々にお任せ頂けますかな?」 「ふふふ、お前たちに相手が務まるとは思えぬが……やってみるが良い」 「有り難き幸せ」 そのバラモスそっくりの魔物はうやうやしくゾーマにお辞儀をすると、不敵な笑みを浮かべて飛びかかってきた。 「ギギギ、たかが人間ごときに敗れ去った我が弟のように、私は甘くはない!」 「弟!?」 バラモスよりは俊敏な、それでも緩慢な攻撃を余裕で回避して、武闘家は首を捻る。 「ってことは、だ。手前はバラモスの兄ちゃんか何かか?まさか姉ちゃんってことはないだろうがよ、そのツラで!」 武闘家の右腕に装着された【黄金の爪】が一閃し、バラモスに似た魔物の顔に数本の傷が付く。 「フン、お前によく似た奴を見たことがあるな?……ロマリア近くの公園の池で、ゲロゲロ鳴いてたアマガエルだ!」 「グギギギギ……このバラモスブロス様を怒らせて……グギギ、無事に生きて帰れると思うなよ小僧が!!」 「へっ、たかがバラモスの兄弟が俺たちに勝てると思ってんのか!?お前こそ生きてここから帰れると思うなよ……お前に素敵なマイホームがあるとは思えないけどな!!」 そのやりとりを聞いて嬉しそうにしているキングヒドラ。 「これは面白いことを言う……バラモスゾンビよ、我等も行こうぞ」 骨はカタカタと関節を鳴らして、バラモスブロスの加勢に走り出した。 「記憶も感情もないスケルトン・アンデッドに成り果てたバラモスだが……貴様たちへの恨みは骨髄みたいだな!」 4対3で、数の上は勇者たちが有利だとは言え、体格差はあまりにも大きい。囲まれてしまえば袋叩きに遭うことは必至で、かと言って分散しての攻撃では薄紙を剥がすような攻撃しかできない。 「くはは、まずはお前だ!」 戦士に狙いを定めたキングヒドラは、灼熱の炎を吐く。 「さっそくかい……全く、しつけの悪いペットだね」 「ペットだと?ふはははは、これは面白い冗談だ!」 「冗談だって?ははははは、これは面白いジョークだよ!自分の顔を鏡でよく見なよ、下品なトカゲが利口なフリしてんじゃないよ!」 「くくく、命知らずな人間だ!!さっきのオルテガとか言う馬鹿同様、たっぷり痛めつけてなぶり殺しにしてくれる!!」 それを聞いて、戦士はフッと笑った。 「よし、こいつを使ってみるか」 戦士は何やら剣を持ち替えて、キングヒドラに突撃する。 「ふん、この私の鱗にはどのような武器も無効!」 「どうかな」 短く言って、戦士はキングヒドラのシッポに思いきり剣を振り下ろした。 さくっ。カチイン! よく熱したナイフをバターに突き立てたように、その刃はシッポを切り裂いて床にぶつかった。 「ぐ、ぐきゃあっ!?」 返す刀で、首をひとつ切り落とす。 「ふむ、買っておいて正解だったな」 「なっ、ななななんだその剣は!?我が鱗の鎧を苦にもせず斬るとは!?」 戦士はにっこりと笑って、剣を正眼に構える。 「これは【ドラゴンキラー】さ。トカゲやドラゴンなんかに有効な意匠を込めてある魔剣だね……君の防御はもう怖くない、僕1人でお相手できそうだ」 「そうか!」 賢者も何か得心したように手を叩き、持っていた【理力の杖】を【ゾンビキラー】に持ち替えた。バラモスゾンビはその様子を見て後ずさりする。 「ふふふ、やっぱりそうか……勇者、武闘家!このホネホネロックは俺1人でなんとかなる!バラモスのアニキをなんとかしてくれよ!」 「OK!」 勇者はそう言って、【王者の剣】を振りかざす。剣から生まれた突風がバラモスブロスを襲い、思わず顔を伏せたバラモスブロスに武闘家が接近して攻撃の嵐を加える。 「グギギィ、たかが、たかが人間共にぃ!!」 「畜生、人間共がぁっ!!」 キングヒドラは完全に追いつめられていた。残る首は後一本、もはや灼熱の息を吐くほどの余裕も残されていない。 「あんたが勇者オルテガを殺したそうだね……僕はオルテガさんを直接知らないけどさ、アリアハンの人はみんなオルテガさんを知っているようなものなんだ。いろんな武勇伝を、人柄を、聞かされて育ってきたからね……」 戦士の瞳に殺意がみなぎっているのが、キングヒドラにも判った。 「僕は、人間・魔物に関わらず、死んでしまった魂を弔いたいと思っている。でも、お前とゾーマだけは別だっ!!」 戦士は跳んだ。【ドラゴンキラー】がキングヒドラの頭蓋をあっさりと二枚に下ろし、そしてその龍族最強の魔物は絶命した。 「ん?じゃ、そろそろ俺も本気で行くか」 スケルトン・アンデッドモンスターは、その体が骨格のみで構成されているので、視覚でダメージを類推しにくい。砕け散った骨の量のみでそれを判断するのは至難の業だが、基本的にそのかりそめの命を維持しているパーツは頭蓋骨であるため、そこを破壊すればたいていのスケルトン・アンデッドは生命活動を停止する。 賢者は大きく振りかぶり、そして【ゾンビキラー】を投げた。狙い過たず眉間に【ゾンビキラー】は命中し、次の瞬間、【ゾンビキラー】から放たれた淡い緑色の光に包まれて、バラモスゾンビはただの骨の山と化した。 「ほい、いっちょ上がり!」 その様子を横目で見て、バラモスブロスは驚愕する。 「グギギ……馬鹿な、我々ゾーマ親衛隊が、これほどまでに……」 「だから言ったであろう、お前たちに相手が務まるかどうか……とな」 ゾーマは興味が削がれたように言うと、首を横に振った。 「ゾ、ゾーマ様、お助け下さい……ゾーマ様のお力で……」 勇者の太刀を浴びたバラモスブロスは、ゾーマの玉座の前ににじり寄って救いを求める。 「ふむ」 ゾーマの掌から発した暗黒の光がバラモスブロスを包む。 「あ、有り難き……って、こ、これは……ゾーマ様!?」 光に包まれたバラモスブロスは、その光が集約されていくのと同時に、次第に圧縮されていく。まるで見えない巨大な万力に絞め潰されていくようにじりじりとその体積を減らしていくバラモスブロス。 「ゾゾゾゾーマ様ッ!?」 ゾーマは興味なさげに指をパチン、と鳴らした。その瞬間、光は縦一線に変化し、鋭い悲鳴を残してバラモスブロスは二次元に近い死体となり吹き飛んだ。 「若者たちよ……このような闇の力を見せつけられて尚、我と戦うと言うか?」 「もちろんだ……俺たちはそのために旅をしてきた」 勇者が一歩、前に出る。 「悪いけど、その程度でビビってる場合じゃないんだよな……人が殺されるのを、俺はもうこれ以上見たくはないんでね」 「人々の魂を鎮めるためにも、あんたには消えて貰う。後に続く悲劇を消すためにもね」 武闘家と戦士が、己の内に芽生える恐怖心を打ち消して、勇者に続く。 「ま、そういうことだ……かつて【聖者ゾーマ】と呼ばれし神官、今や大魔王として君臨する男……俺たちは、あんたを倒すために戦ってきた。その目標が目の前にいて、諦める馬鹿がどこの世界にいるかって」 賢者が【ゾンビキラー】を構え直す。 「くふふふふ、【聖者ゾーマ】か……懐かしい名を知っているものだな……あの頃の儂は確かにそう呼ばれておったな……矛盾だらけの人の世で光と崇められる聖者と今の儂、何も変わってはおらぬのだがな!」 ゾーマの両手から吹雪が吹き出す。 「否!儂は変わったのかも知れぬ!自分に正直に、率直になった!!気に入らぬ者を滅ぼし、欲しい物は無理矢理にでも奪う!正直が、率直が美徳というなら儂は未だ聖者のままよ!」 次いで灼熱が勇者たちを襲った。賢者は慌てて結界を張る。 「フバーハ!!」 三角錐のバリヤーが、勇者たちを灼熱地獄から守り始める。 「それはただの独善だ!独りよがりな欲望で、世界を意のままにできると思うな!」 勇者はふと父の言葉を思い出し、道具袋から【光の珠】を取りだして高く掲げた。 「馬鹿な!それは【光の珠】!闇を吸いきれず壊れたはずの光の珠!?」 「あんたのその猛攻は全て、あんたが着込んでいる闇の衣のおかげなんだろ?俺はこの【光の珠】に、その闇の衣だけを吸い取る!」 ゾーマの表面から、黒いタールのような液体が剥がれ始め、勇者の掲げる光の珠に吸い込まれていく。 「なんだと!この鉄壁を誇る闇の衣が!?」 「あんたは欲深すぎたんだ……世界の全ての闇を吸い取ろうとして、結果光の珠を壊しちまった……聖者として崇め奉られたかったあんたの欲深さが、闇に身を置いてまで世界に君臨しようとさせたんだ!」 ゾーマの体が、次第に貧相な人間のものへと変わっていく。いや、戻っていくのだろう、闇の力を失って、そこにいるのはただの邪悪な心を持った人間だ。 勇者は光の珠を道具袋に戻して、剣を構えた。 「くくく、小僧共が勝手な評論を!死ね!!」 ゾーマが唱えたのはイオナズンだったが、実際に放たれた衝撃は良くてイオラ程度のものだった。既にゾーマの力は半減していたのだ。 「悪いが、あんたを殺すことだけにはためらいはない!」 勇者はゾーマに駆け寄って、その貧相な老人の体を、袈裟懸けに斬った。 「……終わったようです」 精霊ルビスは、その美しい横顔を曇らせて、切なそうに言った。 「かつて崇高な意志の元に、光の世界を創るべく奔走していた聖者ゾーマ……彼は自分の心に闇があることを許せなかったのでしょう……」 「ルビス様……」 そのエルフが差し出したハンカチで涙を拭い、ルビスは溜息をついた。 「光があるから闇もある……それでも、その光を信じていれば、闇に心を飲まれることもなかったでしょうに……この私にだって、心に闇はあるというのに……」 ルビスは静かに頭を垂れた。ゾーマの救われぬ魂が、せめて迷わぬように祈ったのだ。 「お前の敗因はたったひとつ……信頼できる仲間がいなかった、ということさ」 賢者は、あおむけに倒れるゾーマの前にかがみ込んで、そう言った。 「……ククク、だがな……光ある限り闇もまた生まれる……いつか必ず、再び世界を暗黒に包む者が現れよう……」 
「ああ、理解できんよ……するつもりもない……」 「じゃ、安らかに眠りな」 賢者は、ゾーマの体を炎の魔法で焼き尽くした。その魔法が【メラゾーマ】だったというのは何かの皮肉だろうか。 「……終わった、な」 「ああ、終わった」 勇者たちが城の外に出ると、突如として大地震が起きた。篭もったような音がして、次いで勇者の道具袋から光の珠が飛び出し、空を明るく照らし始める。 「ふ、闇の世界に朝が来たってわけか」 世界は今や光に満ちあふれていた。朝日に似た光に照らされた樹木はいきいきと輝き、水面もまた生命に溢れる場所へと変貌していた。 エンディング ラダトームの城は、お祭り騒ぎになっていた。空を覆っていた闇が消え、柔らかな光が空を満たしたとき、人々は自ずと大魔王が倒されたことを悟ったのだ。 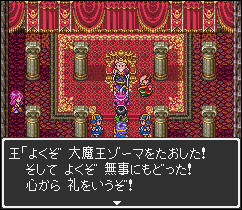 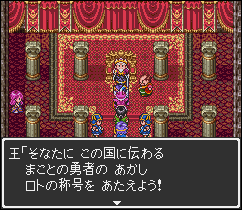
城に戻った勇者たちを待っていたのは、大歓迎で迎えた人々と、上の世界へと通じるトンネルが今にも塞がれそうな状態であるというニュースであった。 「仕方ない、宴はそこそこに楽しんでおいて、穴が閉じないうちに帰ろう。アリアハンでもごちそうは食べ放題だろうしね」 戦士のその言葉に苦笑して、武闘家はワインをラッパ飲みし始めた。賢者はさっそく肉にかぶりつき、勇者は戦いの様子をわざと大げさに、身振り手振りを交えながら話す。 宴が1時間を過ぎた頃、一行は座を辞することに決め、城下町へと歩いていった。 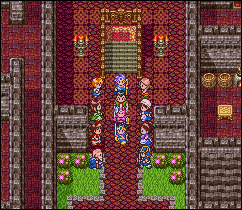 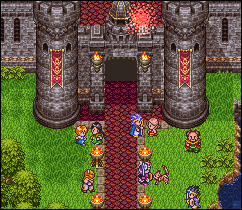
町を出て、上へのトンネルに向かうべくしばらく行ったあたりで、べろべろに酔っぱらった武闘家が異変に気付いた。 「おや?ゆーしゃはどこいったのら?」 「おう、さっき小便してくるっつってたな、ギャハハハハ!」 同じく酔っぱらった賢者が、戦士の背中をばしばし叩きながら笑う。 「もう、飲み過ぎだよ2人とも……ま、先に上の世界に戻って待っていようよ」 酒が苦手な戦士だけは素面のまま、酔っぱらった2人を連れて歩いていく。ふと、何か不安感のような不吉なものが胸をよぎったが……大魔王を倒したという達成感、そしていよいよ自分の思う旅に出られる嬉しさで、自然と足が早まった。 鳥は歌い、花は咲き、まさに彼らとこのアレフガルドの大地の前途を祝しているように思えて、戦士は自然にほころぶ顔を我慢できなかった。 エピローグ 「お前の仲間たちは、先に地上に帰ったぞ」 「ああ、ありがとな」 「上への通路はもう使えなくなる、お前も上に戻るなら早くした方がいい」 青年はフッと笑って、エルフの少女の髪を撫でた。 「……俺さ、この世界に残ろうかと思う」 「どうして?」 「……上の世界は、もうほとんど冒険しつくしたからね。下の世界はまだ広い、未知の大陸がまだまだある!そんな場所を、旅してみたいのさ」 「そうか……」 少女は少し切なげな顔をして、視線を伏せた。 「……一緒に、来るかい?」 その問いに、少女は笑顔で答えた。 「うん!」  かくして ロトの称号をうけたほだかは ここアレフガルドの英雄となる。 だが 祝いの うたげが 終わった時 ほだかの姿は もはや どこにもなかったという。 そして 彼が 残していった武器 防具は ロトのつるぎ ロトのよろい として せいなる守りは ロトのしるしとして 後の世に 伝えられたという。 
to be Continued to DRAGONQUEST I & II あとがき 「DQ3-Replay」トップに戻る |