| 第10話 悲恋
前回までのあらすじ 村全体が奇妙な眠りに包まれた村、ノアニール。その背後にエルフの存在を知った勇者たちは、村の西にあるというエルフの里を目指した…… 「方向感覚がなくなりそうだな」 武闘家がポツリと漏らす。鬱蒼と茂る針葉樹林は、太陽の光すら拒絶してまるで夜のようだった。微かに続く獣道を辿る一行は、今が昼なのか夜なのか、それとも朝なのかすらも判らなくなっていた。 「方向はこっちで間違いないんだろ?」 苛ついた風に、戦士が問う。魔法使いは地図とコンパスを片手に、僅かに頷く。 魔物の姿さえ見あたらない。コケとシダが一面を埋め尽くし、朽ち倒れた巨木が森の雰囲気を一層沈鬱なものにしていた。 「もうすぐのはずだ」 魔法使いは、感情を押し殺した声でそう言う。森に入って何日目になるのか、それすらもう判らない。彼の持つコンパスは、それでも方向を見失ってはいなかった。 しばらく歩いた後……勇者がふと立ち止まった。 「どうした?」 「あの幹……ここ、さっき通ったぞ」 「馬鹿な!方向は間違ってないし、だいたい迷うような道じゃないだろ?」 しかし、勇者が指し示す幹には全員が見覚えのある傷跡がついていた。熊が爪を研いだような傷跡…… 「知らず知らずのうちに、ぐるっと回っちゃったのか?」 「それはない」 魔法使いが反論する。 「俺はずっとコンパスを持っているんだ。針がふれたことなんて一度もない。ただ……」 「ただ?」 魔法使いは躊躇していたが、思い切ったように右手を差しだし、呪文を唱える。 「メラ」 武闘家は思わず飛び退き、戦士は盾で身を隠した。だが、勇者は腰に手を当てたまま辛そうに首を振った。魔法使いの手から、火の玉は出なかったのだ。ただ、火の粉が微かに飛んだだけだった。 「……どうもこの森はおかしい。精霊たちが、俺の言うことを聞きたがらないんだ」 「僕も感じていたさ……何か、厳かな魔力がこの森を支配している。そして、僕たちを拒絶しようとしているんだ」 勇者も手を出して、呪文を唱えた。 「ホイミ」 しかし、いつもなら暖かな光が傷を癒やすはずのその呪文は、ただ虚しくこだまして、勇者の手が僅かに輝いただけだった。 「ほら、神への祈りすら通じない。だからモンスターもほとんどいない。魔力が通用しないんだ」 「俺にはあんまり関係ないけどな」 武闘家はそう言うと、背中の荷物を降ろした。 「とにかく、このまま歩いても無駄だろう。今日はここでキャンプにしよう」 食事の後、たき火の回りで思い思いの行動をとる一行。戦士は武器の手入れをし、武闘家は腹ごなしに型を復習する。魔法使いは杖の先の宝玉を磨き、勇者は横になって鼻歌を歌い始めた。 「しかしなんだね、こうやっていると、バラモスが世界を征服しようとしている……なんて、嘘みたいだよな」 「でもさ、僕たちがこうして旅をしている……その原因はバラモスなわけだから」 武器は戦士の命、というだけあって毎日しっかりと手入れをする戦士。ここ数日は魔物に会うこともほとんどなく、ただ磨くだけの日々だ。 「街ではもうすぐお祭りなんだよな……お前、ルーラ覚えたんだからさ、今度帰らないか?」 「駄目だ、手がかりだって掴んでいないのに帰れるわけないだろ?俺たちは期待されてるっていうこと、忘れるんじゃない」 武闘家の意見をあっさりと魔法使いは却下して、宝玉に息を吹きかけた。 「せめて、オルテガさんの消息でも掴まなきゃ、帰れないよ……」 「親父のことなんて、どうだっていいよ」 勇者は寝返りを打って、たき火に背を向けた。 「前に進む……僕たちにできるのは、それだけさ」 ポケットからハーモニカを取りだして、勇者はそっと吹き始めた。辺りにハモニカの調べがしみ通る……あまり上手くないが、誰も文句は言わない。言ったところで腕が上がるわけでもないし。 
木陰から唐突に声が響き、一行は飛び退いて身構える! 「誰だ!」 「ヘタなものをヘタと言って何が悪い?」 木陰から姿を現したのは……まだ幼いエルフだった。 「お前の調べは耳に響き心を打つ。が、稚拙だ。技術がなってないな」 勇者はエルフに近づき、しゃがんで目線を合わせた。 「あのな、僕は別にこれで食べていくつもりはないんだ。お子さまは文句言わないの!」 勇者がエルフの頭を撫でようとして出した手を、エルフは打ち払った。 「うつけ者!あたしは貴様ら人間などよりも長く生きておるぞ、この無礼者!」 「ええ?エルフって、成人までは人間と同じくらいの速度で成長すると思ったけど?」 「ほう、精霊使いか。主らの知識ではそんなものだ、人と交わったエルフしか知らぬ。純粋な森エルフはその限りではないのだ!」 「そうだったのか……知らなかった」 魔法使いは懐から手帳を取りだしてメモを取る。 「あたしはもう百二十年も生きておる。お主らはどう見ても二十年も生きておらぬではないか」 「げっ、うちのじいちゃんより年上か……」 「そんなことより、お主らなぜこの森に入ってきた?ここがエルフの聖地と知った上での狼藉か?」 「狼藉……」 時代がかった科白に、武闘家は苦笑する。 「僕たちはエルフの里を探しているんだ。ノアニールの村の呪いを解いてもらうために」 「ほう、主は戦士か。またショボい鎧だな」 「仕方ないじゃないか、貧乏なんだから」 「ノアニールの村の呪いは解けぬぞ。諦めて早々に立ち去るがいい」 「どうして?」 エルフはふっと笑う。 「エルフの女王は人間が嫌いだ。せっかく呪いをかけて動かなくしたのに、どうしてわざわざ動かしてやる必要があるというのだ、ん?」 「それは……」 戦士が言葉に詰まった。それを見て、勇者は静かに口を開く。 「僕の父……勇者オルテガが北へ向かったという話がある。もう十何年も昔の話だけど……父が辿った足跡を追いかければ、魔王バラモスを倒すための手がかりになる、そう思っているんだ」 「ほう、お主オルテガの子息か。あんまり似てないな」 「聞けばノアニールの村人が眠った時と、父がノアニールに立ち寄った時期はほぼ重なる……だから、どうしてもノアニールの人を起こしたいんだ」 「バラモスを倒す?人間はまた酔狂なことを考えるな」 「奴は世界を滅ぼそうとしているんだぞ!」 「我々は平気だ、この森を見るがよい。魔物もおらぬ、邪な気も入り込めぬ……エルフの神々、そして精霊ルビスの加護は厚いからな」 「自分だけ良ければいいのか?」 逆上する武闘家に、エルフは鋭い視線を向けた。 「黙れ人間!お主らがこの大地にどれだけひどいことをしてきたか、忘れたのか?森を切り開き大地を汚し、自然に対して取り返しのつかぬ大罪を犯したではないか!そんな貴様らが、そんな大口を叩く資格があるとでも思っているのか?」 「そ、それは……」 「ちょっと待てよ」 戦士が立ち上がった。 「ここには、魔物はいないのかい?」 「当たり前のことを聞くな。この森は神聖な森、バラモスの息がかかった邪な者は、入り込むことすらできぬ」 「いや、僕たちはここに入って何回か、敵と戦っている。魔物が入り込んでいる」 「そんなはずはないわ」 「嘘なんかついてない。バラモスの魔力は、それほどまでに増大しているんだ」 魔法使いは、宝玉の杖を振りかざして呪文を唱えた。 「メラ!」 宝玉によって増幅された魔法は、通常の半分程度の火の玉となってたき火にぶつかり、弾けた。 「ほら、精霊の力が強くなっている。この森にかけられた結界を、バラモスの魔力が凌駕しかけているんだ。だから、人間程度の魔力でも、魔法が使える」 「馬鹿な、この百年間森に魔物が入り込んだことなど一度もない!」 「う〜ん、ドラマ的に盛り上げるなら、ここら辺で魔物が出てくるんだけどね」 勇者が笑顔で言う。しかし森はあくまで静かだ…… 「……これ、オルテガの息子よ」 「なんだい?」 「……嘘を言っている目ではないな。よし、お主らを明日、エルフの女王に会わせてやろう」 「本当かい?」 「だが、一つ条件がある」 「なに?」 エルフは無邪気に笑って、勇者の首に抱きついた。 「お主はあたしの部下になるのだ!」 「え?」 翌日、迷いの結界からエルフの少女の手引きで出た勇者たちは、エルフの里へと案内された。鬱蒼と茂っていた迷いの森とは違い、木の間にありながらも太陽の存在がまぶしい、のどかな里というのが第一印象だった。 「あんなにうろうろ迷ってたのが馬鹿みたいだ」 「ほら、しっかり歩かないか!」 少女を肩車して歩く勇者。足下が心許なく、ふらふらするたびに少女は髪の毛を引っ張る。 「痛いってば!」 「黙れ、ハーモニカもまともに吹けぬ輩が何を言うか!」 「関係ないでしょうが、それは……」 里のエルフたちは、勇者一行を見て眉をしかめて遠巻きに見つめる。 「人間よ、ほら!」 「馬鹿、早く家に入りなさい!さらわれてしまうわよ!」 小さな声で、それでも聞こえるように喋り合うエルフたち。武闘家は苦笑する。 「もの凄い歓迎ぶりだな、こりゃ」 「仕方なかろう、人間などは我らの出来損ないだ」 「何だそりゃ」 エルフ少女は、勇者の肩の上で胸を張る。 「我々エルフは精霊ルビスのしもべとして生を受けた、光の元でしか生きられぬ種族よ。そちたちは、魔物や雑多な生物の影響を受けて汚れた種族。だから寿命も短い」 「でも、人間の方が数が多いぞ。繁栄している」 「ふん、雑種は数多くなるものよ。住む地を選ぶ事なき民が増えるのは当然であろう」 少女は言いながら勇者の髪を抜いて、ふっと息で飛ばした。 「こら、抜くな!」 「ケチケチするな」 木立の間を抜け、道なりに歩いていくと池があった。そのほとりに老人がたたずんでいる…… 「あれ、人間がいるじゃないか」 「あれは呪いの原因の親族だ。構うな、先に進め」 老人は、水に映る自分の姿を眺めてため息をついている。戦士は思い切って、老人に話しかけた。 「ご老人、どうしました?」 「ノアニールの村の皆が眠らされたのは、わしの息子のせいじゃ……」 「え?」 「あいつがエルフのお姫さまと駆け落ちなんかしたから……だから息子に代わって、こうして謝りに来ているのに話さえ聞いてもらえぬ。ああ、わしはどうすればええんじゃ!」 「ほら、先を急ぐぞ。これ爺、いくら待っても女王は会わぬぞ。さっさと帰るがいい」 「おおお……」 泣き崩れる老人。エルフ少女はその様子を冷ややかに眺めると、勇者の髪を引っ張った。 「ほれ、行くぞ。女王陛下は、機嫌を損ねると大変だからな」 
エルフの女王は、開口一番そう言った。玉座から、威圧的に勇者たちを見下ろしながら。 「ノアニールの村で聞いたんだ。あなたが村人に呪いをかけた、夢見るルビーを返せば元に戻してくれるって……」 「ノアニールの村の……そう、そんなこともありましたね」 「どういうことなんです?だいたいその『夢見るルビー』って、何なんですか?」 「その昔、私の娘アンはひとりの……人間の男を愛してしまったのです」 「あたしの姉上だ」 勇者の肩から降りながら、そっとエルフの娘は勇者に耳打ちした。 「そしてエルフの宝、夢見るルビーを持って男の所にいったまま帰りません」 「駆け落ちか……」 「しょせんエルフと人間。アンは騙されたのに決まっています。たぶん夢見るルビーもその男に奪われ、この里へも帰れずにつらい思いをしたのでしょう」 「ち、ちょっと待ってよ奥さん!」 武闘家がたまらず声を上げた。 「そんな理由で村人に呪いをかけたの?」 「そんな理由?」 女王の眉毛がピクリ、と動いた。 「そんな理由とはなんですか!あんた、見たところまだ結婚もしていないようだけど、娘を持つ親の心っていうものが判るつもりなの!?」 「ま、まぁまぁ落ち着いて……ではこうしましょう。私たちが娘さんを捜す、そしたら呪いを解く。ギブ&テイクでどうです?」 魔法使いが間に入るが、女王の鼻息は荒い。 「夢見るルビーを持ってくるのです!どうせ、あのロクでもない男がとうに売り払ってしまったでしょうからね……それを見つけて持ってこられたら、その時に考えてあげましょう」 「な……めっちゃ不利な条件だ」 「あたしの母上、怒らせると怖いぞ」 「シンシア!お前も人間なんかにくっついていないで、魔法の修行でもしなさい!」 「へへーん、この人間はあたしの部下にしたの!文句は一切受け付けないよ〜だ」 女王は顔を真っ赤にして何かを言おうとしていたが、大きくため息をついて目を閉じた。 「ああ、人間など見たくもありません。立ち去りなさい!」 「あたし、お姉さまがどちらに向かったのか知っているぞ」 「ええ?」 店で買った木の実入りのクッキーをかじりながら、シンシア(エルフ少女のことだ)はぽつりと言った。 「固く口止めされてたから母上には申し上げなかったが……」 「教えて、教えて!」 武闘家が水筒を差し出して、目を輝かせた。 「う〜む……しかし、姉上との約束を破るわけにはいかんからな……」 「そこをなんとか!」 戦士も加わって拝み倒す。シンシアはその様子を横目で眺め、にやっと笑った。 「なら、一つだけ言うことを聞いたら教えてやろう」 「一つだけ……う〜ん、あんまり無理なことでなければ……」 しぶしぶ答える勇者。 「そうか!ではオルテガの息子、お前はエルフになって、あたしと一緒にここで暮らせ!」 「は?エルフになんか、なれるわけないじゃないか!」 勇者は『お話にならないよ』といった風に首を振る。種族の壁というものは決して越えられない高い壁、そもそも人間が簡単にエルフになれるのなら『夢見るルビー』をめぐる一連の駆け落ち騒ぎだって起きるはずがないのだ。 「ふふん、お主物を知らぬのう。この世界には、精霊ルビス様に付き従う全知全能の神、神竜がいるのだ!お主ら人間は戦って勝たねば願いを叶えて貰えぬが、我々森エルフの頼みは代償無しで聞いて貰える。そして、そのためのキーが『夢見るルビー』なのだ」 「よし、それで行こう!」 「こ、こら!勝手に話を進めるな!」 「勇者ひとりの犠牲で全てが丸く収まるのなら、それもいいだろう」 困惑する勇者をよそに、戦士が言った。 「おいおい、そもそもの目的を忘れるなよ……バラモスを倒すことが目的だったんだぞ」 「どうせ回復役も勇者じゃ不足だったし、これを機会に教会のミヨちゃんをパーティーに入れよう」 魔法使いも乗り気になっている。 「そうそう、それが良かろう。たまには会いに来てやれよ、お主たち」 「話を勝手に進めるな〜!」 「しめっぽい洞窟だな」 たいまつを掲げて、戦士がぽつりと呟く。その声が洞窟の奥で反響して、奇妙な生き物の鳴き声のように響いた。 「この洞窟は我がエルフの支配下にありながらも邪気を発している。その昔、この洞窟はアガルタへの通り道だったと言うが……」 「アガルタ?地下の千年王国、エルフにも伝承されていたのか……」 「そこの精霊使い、そこそこの知識はあるようだから教えてやる。遙か昔に精霊ルビス様が、我々妖精族と動物たちのために地下世界をお作りになったのだ。そこがアガルタ、平穏の地よ。始まりの地、アレフガルドとも言うがな」 「なるほど……」 魔法使いはメモを取る。普段いるようなエルフたちの間には、漠然としたことしか伝わっていない。『始まりの地、アレフガルド』という単語は初めて聞いたものだ。 「元々地下世界には幾人もの魔王や数限りない魔物がいた……そこをルビス様が平定したのだ。しかし長年染みついた邪気は消えぬ。それが、洞窟に染み出してくるこの邪気だ」 洞窟の壁は結露してぬめっている。歩いていく先に、人の気配を感じた戦士は立ち止まって、たいまつを揺らす。 「誰か、いらっしゃるのですか?」 「私は旅の神父です」 返事に安心した一行は、先へと進んでいった。泉の脇には確かに旅姿の神父がたたずんでおり、彼はにこやかに微笑んでいた。 「おや、あなたがたは?」 「アリアハンの勇者オルテガの息子です。父を捜し、魔王バラモスを倒すために旅をしています」 「そうですか……ささ、ちょうど湯が沸きました。お茶にしますが、ご一緒にいかがですか?」 「ご迷惑ではないのですか?」 魔法使いの遠慮がちな声に、神父はまた笑った。 「喜んでご招待いたしますよ」 「うむ、では相伴に預かろうではないか」 シンシアは勇者の背中から降りて、神父の前にぺたんと座った。 「これお主ら何をボケッとしておる、早く座らぬか」 「あ、ああ」 神父は銀製のポットから手際よくカップに紅茶を注ぐと、取るように目配せをした。 「では、いただきます」 辺りの空気が和らぐ。洞窟の中にも関わらず、リラックスする一同。 「しかし、勇者さまがたは少し怪我をなさっているようですな」 「あ、これくらいは平気です。薬草も無駄遣いしたくないし、回復役が僕しかいませんので」 「ああ、それだったら……」 神父はカップを置き、勇者に向き直った。 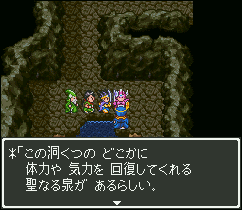
「本当ですか?いや、本当の事を言うと、もうホイミの使い過ぎでMPが残り5ポイントしか残ってなかったんです」 神父はにっこりと笑ってから、表情を曇らせた。 「しかし、こんな所にどうしてそんな泉が湧いたのか……私には悲しげな呼び声が聞こえますぞ」 「もしかして姉上……」 「ん?どうしたんだ?」 うつむくシンシアを見て、武闘家が声をかける。 「うん……まだ確信は持てないが……ひょっとしたら……」 その疑念が確信に変わったとき。それは、神父と別れ洞窟をさらに深く、深くへと進んで行った先に待ち受けていた。 
シンシアが血相を変えた。四本の石柱に囲まれた真ん中に描かれた魔法陣。淡く輝くその魔法陣を見て、シンシアはその場にへたりこんだ。 「どうしたんだ、あれ、何なの?」 「あれは……姉上の……」 シンシアの瞳が涙に濡れている、と勇者が気づいたとき、シンシアは絶叫した。 「あれは姉上の命の証だ!」 「これ、お前。あたしを背負え」 ため息をついて、勇者はシンシアをおんぶした。 「森エルフは、自分の輝きを削って他者に命を与えることが出来る。かつて森エルフが他の土地に移住したとき、誰かが自らの命を犠牲にして仲間を助けていたという……」 鼻をすすりながら、シンシアは続ける。 「あの魔法陣は、自分の生命力の半分を削るものだ……だが、あの程度の魔法陣でも、森エルフとしての輝きは完全に失う。だから、姉上は里に戻ることができなかったのだ……」 背中に涙の暖かさを感じる。勇者は声をかけていいものかどうか、思案に暮れた。 「姉上……」 ふと、背中でしゃくりあげる少女が愛しく思えそうになったその瞬間、当の少女がいきなり勇者の肩に噛みついた。 「痛ててててててて、な、何するんだ!」 「うるさい、お前たち人間のためにどうして姉上が森エルフの誇りを捨てなければならないんだ!気に入らぬ、あたしは気に入らないぞっ!」 「だからといって僕に噛みつくなっての!」 「黙れ、お前はもうあたしのものだ!お前をどう扱おうがあたしの勝手だ!」 「痛てててて、跡が残ったらどうするんだ!痛いってば!」 「うるさい、黙って噛まれろ!噛まれることを光栄に思え!」 「そんな無茶な……」 地底湖に浮かぶ島で、一行は夢見るルビーを見つけた…… 「手紙だ」 戦士が乾いた声で言った。 「読んでみる、か」 誰にいうでもなく、ぼそっとそう言うと戦士は黄色く変色した便せんを広げた。 「えー、『お母様、先立つ不孝をお許し下さい。私たちはエルフと人間、この世で許されぬ愛なら……せめて天国で一緒になります。アン』、か……」 「馬鹿だ」 シンシアは足下の小石を拾って、湖面めがけて放り投げた。 「死んだら何にもならないのにな。どうして、こんな所に逃げ込んだのだ、姉上は」 「さ、戻ろう」 肩に置かれた勇者の手を振り払って、シンシアは叫ぶ。 「冗談じゃないぞ!どうして死ぬ必要があった?ここまでせねば、エルフと人間は一緒になれないとでも言うのか?どうしてだ、お前答えなさい!」 「そりゃ」 武闘家が、横から口を挟む。 「あんたたち森エルフが高貴な一族で、人間はどうしようもない低級な生き物だからだろ?そういう価値観が、こういう結末を産んだってことさ。それだけだ」 「お前には訊いていない、黙れ!……オルテガの息子、お前はどちらかと言えば人間よりも妖精に近い血筋だ……お前の意見を聞かせろ」 勇者は目を閉じた。 「僕には判らないよ……何が正しくて何が間違っているかなんて、僕には判らない。子を思わない親なんかいないんだ、だから女王がアンたちを死なせるために追い込んだなんてことは絶対にない。ただ……不運だったんだよ……」 「なん……だと?」 「君は言ったね。『エルフは自分の輝きを削って、他者に命を与えることが出来る』って。きっと相手の男がケガをして、アンは静止も聞かずに魔法陣を描いたんだ。そのお陰で里に帰るわけにもいかなくなったし、せっかく持ってきた『夢見るルビー』で神竜に願いを叶えてもらうわけにもいかなくなった……たぶんそんな所だろう。森に入ればすぐに見つかるし、アガルタへの道も見つからない。食料がなければ、もう後は……」 シンシアは、勇者の言葉が終わりきらないうちに、大声で泣き出した。勇者たちは、黙って泣くシンシアを眺めていたが、いたたまれなくなった勇者はシンシアの傍らにひざまづき、その髪を優しく撫で始めた。 武闘家は黙って湖面に石を投げ続け、戦士は幾度も手紙を読み返して涙を流した。魔法使いは夢見るルビーを掲げて、始終ため息をついていた。 「じゃ、そろそろ行こうか」 泣き疲れて眠ってしまったシンシアを背負い、勇者が仲間たちに声をかけた。 「歩いて帰るのもしんどいだろう。俺が魔法を使うよ」 魔法使いが杖でなにやら地面に描く。円形の文様の中に全員がいることを確認し、魔法使いは呪文を唱えた。 「リレミト!」 
エルフの里へ戻り、女王に謁見を求めると、女王は魔法使いの持つルビーを目ざとく見つけた。 「ええ、そうです……これは、お返しします」 魔法使いは女王に『夢見るルビー』を渡すと、そっぽを向いた。 「それで?娘は、アンはどこです?」 武闘家も横を向く。戦士はくるっと後ろを向いて肩を落とした。 勇者の背中の上から、シンシアが鼻をすすりながら重い口を開く。 「母上様……姉上は、姉上は涅槃へと旅立たれました……男と共に、湖に入られて……」 「なんと!アンと男は地底の湖に身を投げた、というのですか?」 「これを読んでください」 戦士が黄色い便せんを女王に渡す。女王は震える手で便せんを受け取り、目を通す。その頬を涙が伝い、こぼれた涙はルビーに変わる…… 「おお!私がふたりを許さなかったばっかりに……」 女王はしばらくうつむいていたが、意を決したように立ち上がり、玉座の裏から小さな包みを取りだして、戦士の手に置いた。 「わかりました。さぁ、この目覚めの粉を持って村にお戻りなさい。そして呪いを解きなさい。アンも、きっとそれを願っているでしょう……」 勇者たちは目を伏せた。ほんの少しの行き違いが悲劇を産む……ほんの少しの不運が、大きな不幸へと繋がっていく…… シンシアは勇者の背中からおりて、母親に抱きついた。 「母上……姉上は恐らく、ケガをした男を救うために自ら森エルフとしての輝きを捨てたのです……だから里にも戻れず、洞窟の外にも出られず……」 「そんな……そんなにまで、あの人間を愛していたというの?アン……」 女王とシンシアの瞳からこぼれた涙は「夢見るルビー」に滴り、ルビーへと変化した涙は「夢見るルビー」と同化していく……その深紅の輝きは血の色にも似て、見るものを深い悲しみへと誘っていた…… 「お前をエルフにするのは、しばらく待とうと思う。母上もあんなに気落ちされているし、そもそも魔王バラモスを倒すという大願があるのだろう?」 「あれ、森エルフには関係ないんじゃなかったっけ?」 武闘家が冗談めかして言うと、シンシアは照れ笑いを浮かべた。 「それを言うな。しつこい男はモテぬぞ?」 皆、腹を抱えて大笑いをする。笑いが収まると、シンシアは真剣なまなざしを勇者に向けた。 「オルテガの息子よ、必ず生きて戻れ……あたしとの約束を忘れるな、お前はあたしのものだ。勝手に死ぬことは許さん」 「はいはい」 「返事は一度でいい!……それから……洞窟の邪気が、どうも増しているような気がする。バラモスの邪気が膨れ上がっているのか、それとも他にも強敵がいるのか判らぬが……心して当たるのだぞ、よいな?」 「判りましたよ、姫さま」 「それを言うな」 勇者はふっと笑うと、荷物を手に取った。 「じゃ、お元気で」 二、三歩進んだところで、シンシアは勇者を呼び止めた。 「オルテガの息子よ!」 「はい?」 「その……なんだ……」 もじもじしているシンシア。勇気を振り絞って、シンシアは勇者に言葉をかけた。 
勇者はきょとんとしてから、また笑顔をシンシアに向けた。 「僕はほだか……アリアハンの勇者、ほだかだ!」
一部ゲーム画面のように見えるものは合成画像です。実際にこんなイベントはありませんのでご注意下さい(笑)。
次回予告 古代の遺跡を発掘していた学者が、とんでもないものを掘り出した。生き物の進化を促進し、あらゆる環境に適応した超生命体を創り上げる秘宝……しかし、持ち馴れない力はやがて暴走し、持ち主を破滅の闇へと導いていく…… ほだ「なんだ、このナメクジ……塩が、平気みたいだ」 学者「うむ、塩に対する耐性を付加してみたのだ。そのうち、ウサギよりも早く走る亀も作って見せるぞ」 ほだ「なんだかアホくさ……」 まさ「チッ、なんだこいつは!」 ???「やめてください、あれは、うちの人なんです!」 ???「お父ちゃんが、お父ちゃんがあんなになっちゃった!」 ひで「進化の終着点は、死なんだ。究極的には個体の意味はなくなった、と細胞が認識して壊死していく。判るかい、進むことに行き詰まれば、後戻りはできないんだ!」 ???「コの人間どモガ……わタシは最強ノパわーをTEニ入レタ、カん璧ナ生命体ニナッタ!」 とも「やばい、背骨が体重を支えきれてない!下敷きになるぞ、みんな逃げろ!」 悲嘆に暮れる家族を残し、消えゆく学者。それは、自然界の自浄作用と呼ぶにはあまりにも無造作で、あまりにも悲しい光景だった。進化の秘宝はその鈍い輝きに憎しみと怒りを受け、深い海の底へと沈む…… 次回、ドラゴンクエストIII「進化の秘宝」、ご期待下さい! (内容及びサブタイトルは変更になる場合があります。ご了承ください) 第11話へ 「DQ3-Replay」トップに戻る |