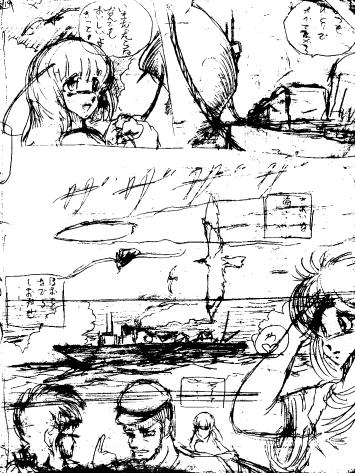 |
 |
さんごの住む町 第3話
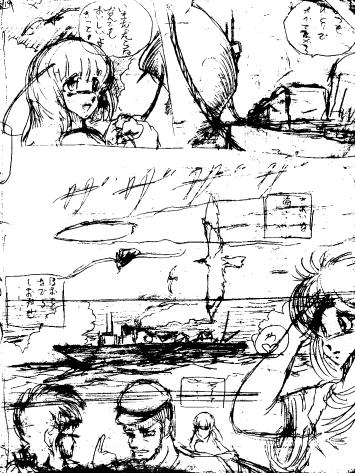 |
 |
(この辺から絵コンテと小説ではストーリーが変わっていきます。右ページはさんごがはじめてハンバーガーを食べるシーン。小説ではカットしました。せりふが恥ずかしかったから。「いつもね、一人で食べてるから。今だったらなんでもおいしいよ。きっと。」このシーンはさんごと真島がお屋敷で食事するシーンで代弁しました。)
1
まず、冷たいパンプキンスープ。
前菜は薄くスライスされた生ハムにオレンジソース。
そして温野菜のサラダ。
さんごが未成年ということで、ワインはグレープ100パーセントのジュースにかわっているものの、一流のフランス料理店にひけをとらない味だと断言していいだろう。
パンは3種類。
ライ麦パンとバケット、それにオレンジのピールを練り込んだ全粒パンが、籐のバスケットに山盛りにしてある。
今焼いたばっかりらしく、柔らかく、暖かい。
メインディッシュには飛騨牛を網焼きにして油を落としたものに、近くの牧場で作ってもらっているバターを使用した和風ソースをかけたステーキ。
真島はなれないナイフとフォークを駆使してかたっぱしからたいらげていった。
毎日、コンビニの弁当を電子レンジで温めて食べている身分にとって、こんな豪華な食事は卒業式の謝恩会以来である。
目の前のごちそう以外、真島の視野から消え去っていた。
デザートのメロンのシャーベットを本物の金のスプーンで口に運ぶ頃になって、真島は、さんごと源じいがじっとこちらを見ているのに気づいた。
さんごも源じいもこの青年のたべっぷりに感動していたのである。
さんごは、自分の目の前で他人がこんな風に豪快に食べる光景を見るのは初めてだったから。
源じいは執事として当然のこととして、さんごといっしょに食べることはしなかったのである。
源じいは源じいで、作ったものがかたっぱしからすべて消えていくのに満足していた。
お客が男ということで、さんごの食べる量の倍を用意していたのに、目の前で見る見る片付いて行くのだ。
「あ、いやあ、こんなおいしいもの、めったに食べられないから。ほんとにおいしかったです。」
まるで自分が悪いことでもしているかのように、真島は思わずいいわけをしてしまった。
「ほんとにおいしいわ。今日のお料理。なにか特別な材料使っているんでしょう。ねっ、源じい?」
真島のたべっぷりに気を取られていたが、源じいはさんごの料理もみごとにたいらげられているのにその時はじめて気づいた。
最近、食の細いさんごにしてはめずらしいことだった。
「材料は有り合わせのものを使っております。特別なものはなにもありませんが。」
源じいにはわかっていた。料理がおいしいのは材料や調理法のせいじゃないこと。
今だったら、どんなまずいものをだしても、おいしいと言ってもらえるだろう。
「ごちそうさまでした。」
真島は両手を合わせ目を閉じつぶやいた。
食器にはソースのしずくさえ残っていなかった。
もうそろそろ、ひぐらしが鳴いてもいい季節なのに、いまだにみんみんぜみが大音響を発している。
昼を過ぎてさらに気温があがったようだ。
しかしこの屋敷の広大な庭には、広葉樹の大木が森といっても差し支えないほど繁っているので当然日陰も多い。
そのなかでも特に大きなけやきの下。
大木を背にしてさんごの車椅子がある。
さんごの前の芝生に真島はじかに座り込んで自分の仕事のことを話しはじめた。
海底調査支援船「とおあさ」は、予定通り自船位置測定用のトランスポンダ3基を海底に沈めると、現在位置を測定し始めた。
船上では物音ひとつしない。超音波測定を行っているため、雑音を出すことができないからだ。
今さんごの耳に聞こえてくるのは、おだやかな波が船にぶつかってくだける音と、かもめの鳴き声、そして麦わら帽子をかすめていく風の音だけ。
そう、今、さんごは船の上にいる。
真を屋敷に招いてから1週間たった。
真の話すことは、すべてが新鮮で光り輝いていた。
学生時代に1冊の本に導かれ、海洋調査の仕事に就いたこと。
3年間の訓練を経て、深海調査船「あさせ」のパイロットになったこと。
はじめて大陸棚の調査へ繰り出したときのこと。
あっという間に時間が過ぎ、さんごが我に返ったときには、もう太陽が沈みかけていた。
楽しかった1日がもうすぐ終わってしまう。
帰る真島を送るために玄関にでていたさんごは、できるだけ明るく「さよなら」を言おうとした。
しかし唇からは嗚咽が漏れただけだった。
涙があふれてとまらない。
なすすべもなく立ちつくす真島はしばらく考えてからさんごにいった。
「お嬢さん、来週の月曜日、豪華クルーズにご招待したいのですが・・・・」
胸に手をあて、ミュージカルよろしく節を付けて、おじぎをしながらおどけて言うと、真島はさんごの反応を待った。
しかし、さんごはうつむいたまま。
「歩かなくてもいいんだけど・・・・だめ?」
さんごは、いやいやをするように首を振ると、鼻水をすすりながら顔を上げ、源じいにすがりつくような目をむけた。
もう泣いてない。
しばらく膠着状態がつづいたのち、源じいが根負けした。
「一度だけですぞ。」
それから1週間、いろんな手続きをへて、さんごははれて「とおあさ」初の女性客となった。
ま、手続きそのものは非常に簡単にすんだ。
なぜなら船長以下、乗組員全員が、女っ気がいっさいなかった真島の「恋人」を見たがったからである。
自船の位置の特定がすんだらしく、甲板上が騒がしくなってきた。
潜水艇を覆っていたカバーがめくられ、専用のガントリークレーンにつるされた深海調査艇「あさせ」が顔を出した。
直径2メーターたらずのチタン合金のボールに、カーボンファイバーの殻を張り付けただけのこの船は、いわゆる最新式ではなく、3年前、新型の1万メーター級の深海調査船の誕生とともに、公的機関から民間に払い下げられた中古品である。
製造当初は、6000メーターまで潜れる調査艇としてもてはやされたが、現在では老朽化も進み、保証深度は1000メーター程度に落ちている。
しかし大陸棚を含む近海の調査には十分すぎる性能を発揮していた。
あちこち塗装の剥げたチタンのボールに1カ所だけあいた穴から、白いつなぎのお尻がみえている。
上半身をコックピットに乗りいれて、真島が最終チェックをしているところだ。
「いいなー」
1日話をして、さんごが真島に抱いた印象は「そそっかしそうな人」だった。
でも今目の前で働いている真島はちがう。目つきが鋭い。
真島だけではない。
さんごの乗船を歓迎してくれた乗組員たちも最初とはずいぶん印象が違う。
そりゃそうである。
真島が今から潜る海域はたかだか水深300メーターぐらいだが、そこですら太陽の光が届かない、超高圧の世界なのだ。
この内径2メートルの小さなチタンのボールだけが真島の命を守る唯一の鎧となる。
購入当初は一応パイロットと調査員の2名が乗れるようにはなっていたが、払い下げられた段階で最新式の超音波デジタル通信装置を搭載したため、完全な一人乗りになってしまった。
たよれるものが誰もいない、たった一人の仕事場だから、徹底的な安全チェックをおこなっているのだ。
突然日が陰った。
日傘が差し出されたのである。
「日焼けは体に悪うございます。お嬢様。」
そう、この、さんごにとって大事な大事な初デートに、源じいもついてきてしまった。
それがさんごをこの船に乗せるに当たっての、源じいの要望だった。
源じいにとって、さんごは世間知らずの、なにをやらかすかわからない赤ん坊だ。
目を離すと彼女自身の秘密を真島にしゃべってしまいそうで心配なのである。
源じいは、先週真島が帰った後のことを思いだしていた。
あの日、真島が見えなくなるまでずっと見送っていたさんごの肩ごしに、源じいがさとすように忠告した。
「お嬢様、深入りはいけませんぞ。しかもあの方は海洋学者。いつお嬢様のことに・・・」
さんごはうつむき、つぶやくように返事をした.
「わかってる。わかってるわ。・・でも・・これからもずっと・・ひとりぼっちで生きてくのよ・・。お願い、もうわがまま言わない。一度だけ、今度だけでいいの。夢をみたい。そしたらもう・・・」
「お嬢サン、どうですか、真島は。」
振り返るとデンマーク人だと紹介された船長がたっていた。
「ミス・・さんご、だったよネ。いい名前。ミス.リーフだネ」
まるでポパイにでてくるブルートのような風貌を持った、長身のと言うよりは、ばかでかいと言う印象の船長は、腰をかがめ目線をさんごと同じ高さにすると、陽気に話を続けた。
「びっくりしたネ。みんな。アノ真島にこんなにかわいい恋人がいたなんてネー。」
「はああ?」
すごくまぬけな反応をしてしまったことに気づくのに、たっぷり1分はかかったろう。船長の言ったことを理解できたとき、さんごは真っ赤になって弁解した。
「ち、ちがいますう。わたし達、まっ、まだ一度しかあったことありません。」
そんなやりとりが進行しているとはつゆ知らず。
真島はコックピットに収まって、チェックリストを読み上げていた。
「メインスイッチオン。酸素バルブオン。ボンベ残量100パーセント。流量チェック。圧力15キロ。バルブオフ。漏出チェック。」
「ジャア、一目惚れってやつだネ、ミスさんご。」
「バッテリー残量チェック。予備燃料電池チェック。バルブオン。発電量5.6.7アンペア・・・。バルブオフ。」
「真島はおっちょこちょいだけど、しっかりしたやつだヨ。あれ、日本語になっていないナ。デモそうとしかいえないネ。さんごは嫌いかい。そういうのは。」
コックピットでのチェックをひととおりし終わると、真島は船外の点検をはじめた。
「真島は前に1回、死に損なったネ。はじめての潜水で、海底の潮流にまきこまれて、大陸棚から海溝に落っこちたネ。本人は気を失ったまま、1000メーターの深さまで。そんときは安全装置が働いて無事に浮上してきたけど、みんなもう真島はやめると思ってた。そしたら次の調査も志願したネ。」
真島は球形のコックピットにいくつかはめ込んである、アクリル製の丸窓に超音波探傷機のプローブをおしあて、入念に傷をチェックした。
厚さ60ミリの円錐型をしたアクリルガラスは、簡単に割れることはないのだが、念には念を入れるのに越したことはない。
真島は過去の事故で、それを学んだ。
5
ガントリークレーンが「あさせ」を待機位置から持ち上げ、「とおあさ」の船体後尾に口を開けた着水位置まで移動させた。すでに真島は乗り込んでいる。
クレーンアームがロックされ、潜水艇をつり下げているワイヤーが繰り出されてゆく。
「マイナス3、2,1,着水」。
海面を割り、「あさせ」が水深0メーターを宣言した。これから水深300メーターの海底へ、片道約30分間の旅が始まるのだ。
「ワイヤー切り離します。」
ガントリークレーンからのびるワイヤーを「あさせ」に固定していたフックが開き、ワイヤーを22トンの張力から解放した。
と同時に、「あさせ」は20トンの自重と、浮力相殺のためにつまれた2トンのおもりにひきずられ、ゆっくりと潜水をはじめた。
デッキから船長と一緒にそれを見送ったさんごは、なぜか背中に悪寒を感じていた。