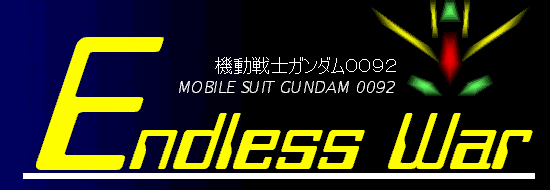 メカニック解説 RGM−79G/S17F ハセガワ中尉の専用機で主役マシン。番号で判るように、ベースとなった機体は宇宙用のジムコマンドGS型ではなく、コロニー内防衛用のジムコマンドG型である。 もっとも、一年戦争時にごく少数が存在したジムコマンドG型は、大戦後にその装備をGS型と同等に改められているため大きな違いはなくなっている。改修後、GS型に改番・編入された機体もあるが、U.C.0080年度五次債発注以降の機体においてはそのままのG型番を名乗っている。 なおスラッシュ以降の文字列に関しては、Sはスペシャル・カスタム機であることを、17は大規模な機体改修の回数を、そしてFはファンネル・システム対応準備工事がなされていることを意味する。 外部塗色はガンダム・タイプを模したデザインに変更されており、ニュータイプ用の実験機としての本機の性質を象徴しているかに見える。 ムーバブル・フレームへの置換もリニアシートの採用も済んでいる高性能機。外装材質にはガンダリウムγを使用。 RGM−79GS/S5RC リルル・リーフレット少尉が使用するジムコマンド。この機体型番もやはりベースはコロニー内防衛用のG型である。が、前期量産タイプであるための機体の老朽化と、連邦軍の補給・整備の簡略化によって運用上不都合が生じ、それに対応するための改造部分が多岐に渡るため、改修後区別するためにGS型番に編入された。 よって機体はほぼ新製され、エンジン部分とコンピュータなどの電子機器のみを流用するという手法で更新作業は行われた。 リルル少尉の専用機になる前の型番はRGM−79GS/5R。スラッシュ以降の文字は、Sはハセガワ機と同じくスペシャル・カスタムを、数字は同じく大規模改修回数を、そしてRはリファインを、Cは新たにコンピュータによる支援システムを実験的に搭載したことを意味する。 外部塗色は黄色を基調としてペイントされ、装甲にはチタン合金セラミック複合材が使用されている(ガンダムマーク2のものの改良型)。 基本的には余剰となったジムコマンドを戦後GM2なみに改造し、それをまたGM3なみに改造したという機体のため、新量産型であるジェガンとの置き換えが検討される機体である。 RGM−86/M7D2 マサ・ヤマモト少尉専用のジムコマンド。外見はジムコマンド、中身はジム3相当の機体。 グリプス戦時にカラバが接収、ジム3開発のテストベッドとして使われたジムコマンドが20機ほどあったが、この機体はそのデータを元に新製された機体である。外見がジムコマンドと同等なのは、その時点でデザインワークが済んでいなかったということと、試作機という性質上、外装甲のメンテナンスを容易にする必要があったため。ちなみに量産されたGM3は型番にリファレンスのRがつき、RGM−86Rを名乗っている。 スラッシュ以降の文字は……Mはマイノリティーすなわち少数のみが存在する機体であるということを、数字は大規模改修の回数を、そしてD2はコア・ブロック・システムによるドッキング機構を保有していることを意味する。 これは余談になるが、純正RGM−79GS型番の中にも一部エース・パイロット用にコア・ブロック・システムを採用していた機体も存在した。 装甲材質はリルル機と同様、チタン合金セラミック複合材である。 イサリビ・システムを使用することを前提に再設計されたゼータ・ガンダム。基本的な能力じたいはプロトタイプのゼータと変わっておらず、その真価はイサリビ・システム本体とのドッキング時に発揮される。 機体の各所にイサリビ・システムとのドッキング・スポットが設けられているが、それによって外観に変化は生じていない。ゼータ・ガンダムの後継機はこの機体の他にあと二機種開発されており、そのうちの一機種は変形機構を簡略化して低価格化を図ったRGZ−91リ・ガズィであり、もう一機種はサイコミュを搭載したニュータイプ用のRGZ−006Fである。 外部塗色は濃紺を基調にしており、ティターンズ・カラーのガンダムマーク2を彷彿とさせる。 変形機構はプロトタイプから変更はないが、シールド形状が若干変更になっているために大気圏への単独突入は不可能になっている。これはこの時代の変形モビルスーツ全てに言えることだが、連邦政府の首脳は宇宙からのモビルスーツによる直接攻撃を恐れているのだ。 ZMS−010IS 同じくイサリビ・システム対応のダブルゼータ・ガンダムである。再設計にあたって、ダブルビーム・ライフルのコクピットは廃止されており、コア・トップ形態でも操縦はコア・ファイターの乗員が行うことになっていて、コア・ベースは無線誘導に改められている。 そのためにコア・ファイターの存在意義がまさに脱出ポッドとしてのみに絞られ、その結果分離・合体は全て母艦のデッキにおいて行われるようになっている(Gフォートレスへの変形はその限りでない)。 真紅を基調にペイントされており、濃紺のゼータと対であることをアピールしている。 ダブルゼータのように、対費用効果があまり期待できないモビルスーツは後継機の開発もほとんどなく、この機体が唯一ダブルゼータの血を受け継ぐ機体である。 頭部のハイメガ粒子砲はゼータプラスA2程度の出力に押さえられてはいるが、大気によるビームの減退を心配しなくてよい宇宙空間での使用であれば、戦艦の一隻や二隻は楽に落とせる。 ZMA−IS11 巨大モビルアーマー・システム、イサリビの本体。拡散ハイメガ粒子砲、ミサイルポッドなどをその巨体にあます所なく詰め込んだ攻城戦用兵器。 サイコ・ガンダムからクイン・マンサまでの巨大兵器のデータ全てを参考にして作られていて、現時点ではほぼ無敵。 ただ唯一の弱点は、その巨体ゆえの機動性、白兵戦に対応できない、至近距離での爆発には弱いという巨大兵器にはありがちな弱点。 イージー・ファンネル・システムという、プログラムによってあたかもファンネルのようにふるまう随伴攻撃機の試作版を装備しているが、後年のモビルスーツ・モビルアーマーに採用されていないのを見る限りでは失敗に終わったのだろう。 データはネオ・ジオンに渡り、α・アジールの基礎となった。 MSA−003 RGM−79R(GM2)の発展量産型としてアナハイム・エレクトロニクスが開発した機体。装甲にはガンダリウム合金が使われており、防御力は高い。 ムーバブル・フレームの設計が甘く、被弾した際に予想以上の破砕効果が出てしまうというデータが前線から届けられたため、エゥーゴとカラバはこのネモに対して早々に見切りをつけてGM3の開発に着手した。 それ以外の性能は良かったために残念な機体である。 MSN−00100 「Z計画」において、変形のテストベッドとして開発された機体である。しかし、当初計画されていた変形機構があまりに複雑であったために、変形は実現されなかった。 金色の機体に肩の漢字でかなり有名になったモビルスーツ。出力自体はガンダムマーク2と同程度で、グリプス戦後半はさすがに第一線というわけにはいかなくなった。 エゥーゴには二機、供与されている。 RMS−099 シャア・アズナブルがアステロイド・ベルトより持ち帰ったガンダリウムγを初めて装甲材質に使用したモビルスーツ。探検家バーソロミュー・ディアスの名前からリック・ディアスと名付けられる。 型番を見れば判るように、機体のベースはリックドムであり、機体から受けるイメージも同様のものである。 当初はシャアの乗機のみ赤の塗装だったが、百式到着以後は全てのリック・ディアスが赤系統に塗色を変更している。 推進系を改良したシュツルム・ディアスという後継機が開発されたが、それはアナハイム・エレクトロニクスの手によってハマーンのアクシズ軍に提供されている。 RGM−89 連邦軍の新量産型モビルスーツ。装甲、出力ともに及第点以上の量産機で、その後長きに渡って使用される機体。GM系の決定版である。 従来のGMと部品レベルでの互換性があるため、整備はしやすい。整備・補給のしやすさは巨大組織となった連邦軍において最重要視されるため、ジェガンを支持するメカマンは多い。 パーツはそこそこのものでも、設計次第でモビルスーツの性能は変わるということを証明して見せた機体。 RX−178 もともとはティターンズで開発されたモビルスーツ。ティターンズ内ではあまり評価されてはいなかったのだが、エゥーゴに奪取されてからは予想以上の働きを見せる。それはベースになっているRX−78ガンダムの性能にも一因があるだろう。 装甲はチタン合金セラミック複合材だったが、エゥーゴの手によってガンダリウムγに換装されている。後年は出力不足に悩む。 RGM−86R カラバによって開発されたGMの直系後継機。仕様としてはガンダムマーク2に近いが、ミサイルポッドを装備しての支援任務に使われることが多かった。 本文で「GM」と言った場合、特に指定がなければこのGM3を指します。 RGM−79R リファインされたGMは、地球連邦軍・エゥーゴではGM2と呼称された。リニアシートは組み込まれたもののムーバブル・フレームは採用されていない。それは、フレームを交換するということは、機体の再設計に近い作業になるため、大量に在籍しているGMを改造するには膨大な資金が必要になるとの試算結果を受けての決定である。 そのために、性能的には満足いくレベルにはほど遠く、新たな量産型を待つことになる。 AMX−004 サイコミュを搭載したニュータイプ専用モビルスーツ。ハマーン・カーンの白いキュベレイ、エルピー・プルのキュベレイマーク2は有名。 腰背部のファンネル・ポッドには多数のファンネルが格納されており、オールレンジ攻撃は連邦軍・エゥーゴを苦しめた。 エミリア・カーンのキュベレイは姉ハマーンのものと同じく純白のキュベレイであった。 AMX−006 ガザシリーズ第四弾。あまりにも戦闘耐久性のなかったガザCを改修したのがこの機体、ガザDである。生産性は大して変わらなかったが、対弾性と火力を大幅に引き上げることに成功した。が、それでようやく他のモビルスーツ並である。 可変モビルスーツなので行動範囲は広い。嵐隊が使用したのは、このガザDの試作機である。 AMX−008 ガザシリーズの決定版。本来はガザEと呼ばれるべき機体だったが、あまりの完成度の高さに、ガザシリーズの一員としてでなく開発コードのガ・ゾウムと呼ばれる。 ガザDと外観はかなり違うが、それでも部品の大多数を流用可能なために生産性は高い。 AMX−011 「ジオンのモビルスーツを今の技術で」というコンセプトで新設計されたザク。ザク3と名乗ってはいるが、そのデザイン以外に直接関係のある部分はない。 ザク2の汎用性を再現すべく設計されており、バックパックや装甲は戦況によって換装できるようになっている。 基本性能は高かったが生産性が低かったので、一部のエリート・パイロットに配られただけで量産化は見送りとなった。 AMX−102 爆撃仕様の重モビルスーツ。このズサは、ジェネレーター自体の出力はそう高くないために主武装はミサイルや実体弾である。 ミサイル・ポッドを排除すれば飛行形態にトランスフォームできるが、速度が出ないために狙い撃ちにされやすく後期量産型からはミサイルポッドは固定式になり変形機能は排除された。 MS−06F ジオン公国軍主力モビルスーツであるザク2のうち、もっとも多く生産されたF型。非常にバランスと汎用性にすぐれた機体で、後々多彩なバリエーションを生み出す。 弱点は出力の弱さと装甲の薄さだが、使いやすさと安定性のおかげで大戦後期まで生産・改修されて使われ続けた。 MS−09R 地球上での行動範囲を広げるために熱核ジェットによるホバー走行を実現したドムを、宇宙用に改修した機体。リック・ドムと呼ばれる。 その装甲の厚さとバズーカの破壊力は連邦軍艦の間で恐れられたが、対モビルスーツ戦では期待されたほどの戦果をあげられなかった。 後にリック・ディアスのベースとなる。 MS−14A ジオン公国軍最後の量産型モビルスーツ、ゲルググ。ジオン軍としては初めてビーム兵器の携行を果たした高性能機で、その実力はガンダムをも凌ぐとまで言われている。が、いかんせん登場時期が遅すぎたことと搭乗パイロットのほとんどが学徒兵ということで、性能をいかんなく発揮できたとはとても言い難い。 後にリファインされた機体がリゲルグを名乗り、アクシズで使われた。 「ガンダムシアター」メインページに戻る |