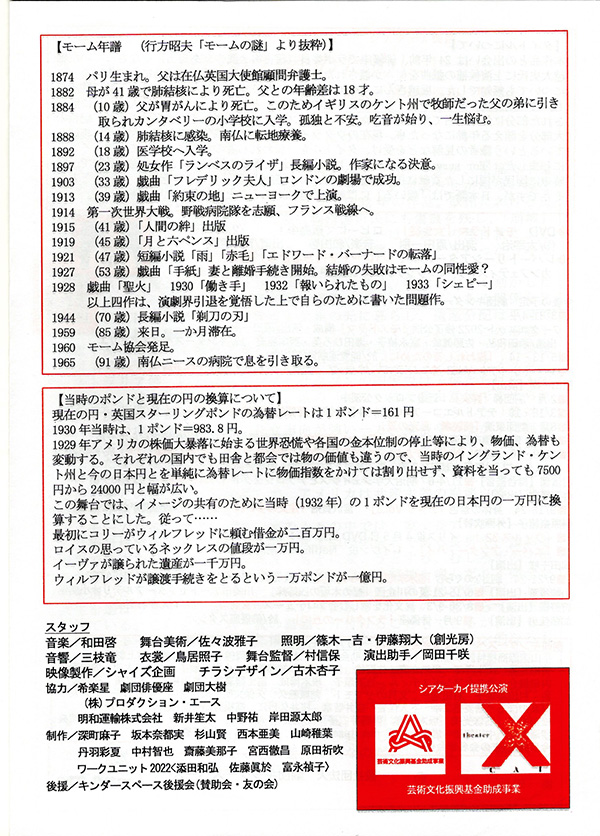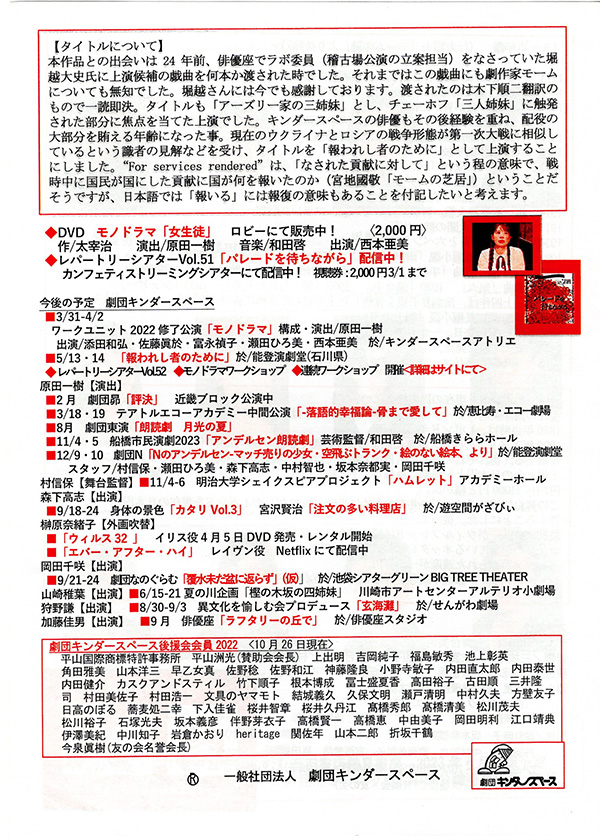103 見えない希望へ──劇団キンダースペースの「報われし者のために」(サマセット・モーム)を観て
2023.2.23
見えないものを見えるようにするのが演劇だと原田一樹は言う。矛盾した言葉だ。「見える」ようにしてしまったら、「見えないもの」ではなくなってしまう。「見えないもの」は、「見えるもの」の後ろに隠れてしまう。
しかし、それを矛盾した言葉ではなくて、ごく正当な言葉だと考えるには、「見る」ものが、「見えるもの」の背後に、或いは奥に「見えないもの」を見なければ、いや、感じなければならないのだ。
舞台に繰り広げられる役者の肉体や、そこから発せられる言葉の「表面」にとらわれることなく、その向こうに、その奥に「ある」もの、そこをこそ見つめ、耳を澄ませ、全身で感じ取らねばならない。
この舞台に登場するすべての人間が、大きな問題をどうしようもなく抱え込んでいて、そこから逃れるすべがない姿に、絶望しか感じないとしたら、やはりまだこの芝居を「見た」とは言えないのだろう。だからといって、安易に希望を感じようとしても仕方がない。舞台がそれを許さないからだ。それほど、キンダースペースが作り上げる舞台は、濃密・緊密で容赦のないリアリズムで貫かれている。感嘆の他はない。
すべての登場人物が「どんづまり」にいて、そこであがきながら生きている。イギリスの田舎町。弁護士の父(レナード・アーズレイ)が君臨する裕福な一家。長男(シドニー)は、戦争(第一次世界大戦)で負傷、失明し、親の家で暮らしている。
長女(イーヴァ)は、婚約者が戦死し、長男の面倒を献身的にしながら親の家で暮らしているが、実は失明した兄が自分の時間を奪っていると感じている。家に出入りしている元軍人で今は自動車工場を経営し、破綻に追い込まれている男(コリー)に恋をするが、その恋は実らず、そればかりか、その男は自殺してしまい、絶望して長女は発狂してしまう。
次女(エセル・バートレット)は、親の反対を押し切って農家に嫁入りしたが、夫(ハワード・バートレット)の野卑な言動や酒乱という現実を前にしても自分の結婚が間違っていたとは言えず、親きょうだいの前では、偽りの幸福を演じざるを得ない。
三女(ロイス)は、そういう兄や姉たちを見て、自分もこの田舎で平凡な人生を終えるのかと思うといたたまれずに、家を出たいと思う。そこへ、この村にやってきてこの一家の者とテニスを楽しんでいる親子ほど年の違う道楽者(ウィルフレッド・シダー)に誘惑されて、出奔することを決意するが、男の妻(グエン・シダー)はそれを許さず、ぜったいに離婚なんてしないと言い張る。
そのすべてを受け入れ、子どもたちを暖かく見守ってきた母(シャーロット・アーズレイ)は、病を得て、余命いくばくもないと宣告される。死を自覚した母は、すべてから解放されたような気分になり、すべてのことは「他人事」と感じるようになってしまう。
何事もないのはただ一人、父である。弁護士の父は、何が起きても、それを我が事とは捉えず、家の安泰だけを願い、願っていればかなうと思っているらしい。
すべては戦争がいけないのだ、ということではない。戦争がなくても、田舎の名家をこうした悲劇が襲うことはある。いや、多かれ少なかれ、生きていくということは、こうした悲劇を体験することだ。ただ、戦争はその悲劇を増幅するだけだ。
問題は、長女においてくっきりと表現されている。婚約者の戦死という悲劇を、失明した兄への奉仕という行為で乗り越えようとするわけだが、心の中に、兄への憎悪が蓄積していく。それは、「自分の時間を奪われる」というエゴイズムだ。これは正当なエゴイズムであって、誰もそれを非難することはできない。ボランティアにしろ、介護にしろ、こうしたエゴイズムから自由な人間はいない。それでも、そのエゴイズムとどこかで折り合いをつけていくことで、生きて行くしかないのだ。
けれども、長女には、限界がくる。新たな恋は、新しい献身としての生き方への希望だったが、それもかなわなかったとき、怒りは父へと向かう。男が破産することを知っていながら、なんの支援もしようとしなかった金持ちの父への憎悪。お父さんがあの人を殺したんだと叫んで、狂っていく長女は痛ましい。
この長女の悲劇をどうしたら防ぐことができたか。もちろん戦争がなかったら、悲劇の出発点はなかった。けれども、婚約者との結婚が、悲劇の出発点ではなかったとは誰にも言えない。次女の悲劇は、まさにその結婚だったわけだ。
次女についても、三女についても、事態は同じことで、人生は悲劇なのだ、「幸福」なんてものは、人生の中には「ない」のだ。そうモームは言ってるように思える。
戦争については、直接の被害者である失明した長男によって、するどく抉られる。国家のために犠牲になることを当然のように考える父や国の支配者に対して「彼らは学ばないんだ。」という切実な声は、リアルに観客の心に突き刺さった。この芝居が、単なる家庭劇ではない所以であるし、あえて、この時期にこの芝居を上演するキンダースペースの意図でもあったろう。
この芝居を見ている観客の心の中には、「ではどうすれば?」の疑問が渦巻くだろう。その解決が「やっぱり戦争はいけないんだ。」でないことは確かだ。戦争はいけないけれど、その戦争はどうしたらなくせるだろう、と考えたとき、結局は人間のエゴイズムという現実に直面する。国家のエゴイズムだけではなくて、人間一人一人のエゴイズムに直面する。そして、こう呟かざるを得ない。「解決は、ない。」
そう、解決なんてないのだ。けれども、死ぬまでは、生きていかねばならない。そのおおむねは辛く厳しい人生の途上で、たまに出会う安らぎとか感動とかが、「幸福」であろう。だから「幸福」は、懸命に求めるものではなくて、僥倖として降ってくるものだ。だから、それを素直に受け止め、素直に手放さなければならないのだ、きっと。
この芝居の本質は、おそらく、ラストシーンにある。すべてに解決も見えない崩壊寸前の家族を前に、今までただただ忠実に黙々と働いてきた召使い(ガートルート)が、すっかり旅支度をして、「これでおいとまします。」と言って去って行く。父は、事態をまったく把握できずに、きょとんとするところで終幕となる。
これは、まるで、舞台全体を、大きな風呂敷でまるごと包んで放り投げるような印象があって、見事だった。ここで、初めて、この舞台全体の出来事が、召使いという「部外者」の目を通して冷たく見つめられていたことに気づく。そして、「いったいこの人たちときたら、何やってんだか。さ、おしまい、おしまい。」という作者モームの肉声を聞く気がした。このやっかいな人生を「外側」から俯瞰する視点の獲得といってもいい。
モームは、召使いとともに、さっさといなくなってしまうが、風呂敷の中に取り残された人たちは、これからも、実にメンドクサイ人生を生きていくだろうし、その風呂敷の中の人たちと同類である観客も、やれやれと思って、帰途につくこととなる。
その帰途で、ずっしり重い「人生の問題」を抱えつつも、「やれやれ」というため息が、どこかで、「見えない」人生の秘密に通じていることもまた実感するのだ。
個々の俳優の好演については、いちいち書かないが、客演は言うまでもなく、キンダースペースの俳優の演技力には、ますます磨きがかかっていて、嬉しい限りだ。俳優だけではなく、音楽、舞台美術、照明、音響、衣装のどれをとっても、繊細で神経の行き届いた素晴らしい舞台だったことは特筆しておきたい。演出のすごさは、今更言うまでもないが、やっぱり原田一樹は、稀有の演出家だと実感した。


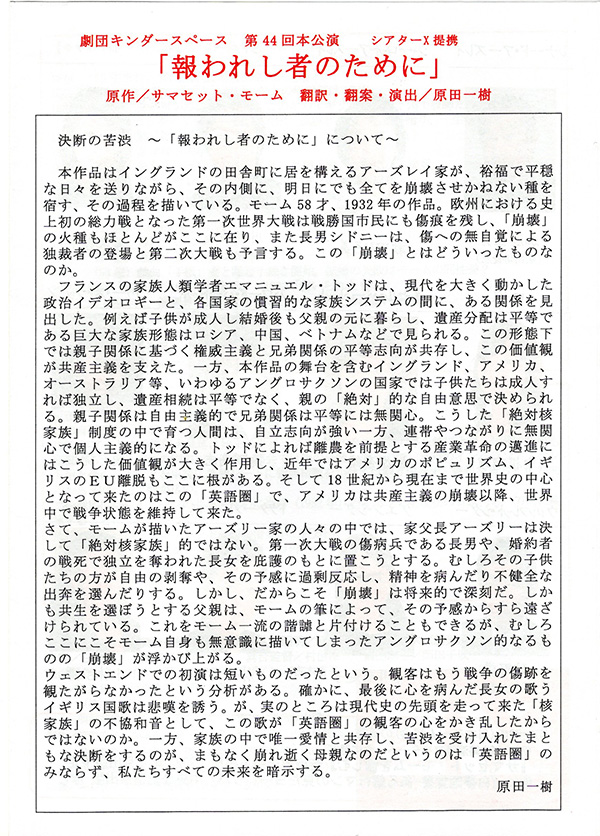
決断の苦渋〜「報われし者のために」について〜
本作品はイングランドの田舎町に居を構えるアーズレイ家が、裕福で平穏な日々を送りながら、その内側に、明日にでも全てを崩壊させかねない種を宿す、その過程を描いている。モーム 58才、1932年の作品。欧州における史上初の総力戦となった第一改世界大戦は戦勝国市民にも傷痕を残し、「崩壊」の火種もほとんどがここに在り、また長男シドニーは、傷への無自覚による独裁者の登場と第二大戦も予言する。この「崩壊」とはどういったものなのか。
フランスの家族人類学者エマニュエル・トッドは、現代を大きく動かした政治イデオロギーと、各国家の習慣的な家族のシステムの間にある関係を見出した。例えば子供が成人し結婚後も父親の元に暮らし、遺産分配は平等である巨大な家族形態はロシア、中国、ベトナムなどで見られる。この形態下では親子関係に基づく権威主義と兄弟関係の平等志向が共存し、この価値観が共産主義を支えた。一方、本作品の舞台を含むイングランド、アメリカ、オーストラリア等、いわゆるアングロサクソンの国家では子供たちは成人すれば独立し、遺産相続は平等でなく、親の「絶対」的な自由意思で決められる。親子関係は自由主義的で兄弟関係は平等には無関心。こうした「絶対核家族」制度の中で育つ人間は、自立志向が強い一方、連帯やつながりに無関心で個人主義的になる。トッドによれば離農を前提とする産業革命の邁進にはこうした価値観が大きく作用し、近年ではアメリカのポピュリズム、イギリスのEU離脱もここに根がある。そして 18世紀から現在まで世界史の中心となって来たのはこの「英語圏」で、アメリカは共産主義の崩壊以降、世界中で戦争状態を維持して来た。
さて、モームが描いたアーズリー家の人々の中では、家父長アーズリーは決して「絶対核家族」的ではない。第一改大戦の傷病兵である長男や、婚約者の戦死で独立を奪われた長女を庇護のもとに置こうとする。むしろその子供たちの方が自由の剥奪や、その予感に過剰反応し、精神を病んだり不健全な出奔を選んだりする。しかし、だからこそ「崩壊」は将来的で深刻だ。しかも共生を選ぼうとする父親は、モームの筆によって、その予感からすら遠ざけられている。これをモーム一流の諧謔と片付けることもできるが、むしろここにこそモーム自身も無意識に描いてしまったアングロサクソン的なるものの「崩壊」が浮かび上がる。
ウェストエンドでの初演は短いものだったという。観客はもう戦争の傷跡を観たがらなかったという分析がある。確かに、最後に心を病んだ長女の歌うイギリス国歌は悲嘆を誘う。が、実のところは現代史の先頭を走って来た「核家族」の不協和音として、このが「英語圏」の観客の心をかき乱したからではないのか。一方、家族の中で唯一愛情と共存し、苦渋を受け入れたまともな決断をするのが、まもなく崩れ逝く母親なのだというのは「英語圏」のみならず、私たちすべての未来を暗示する。
原田一樹